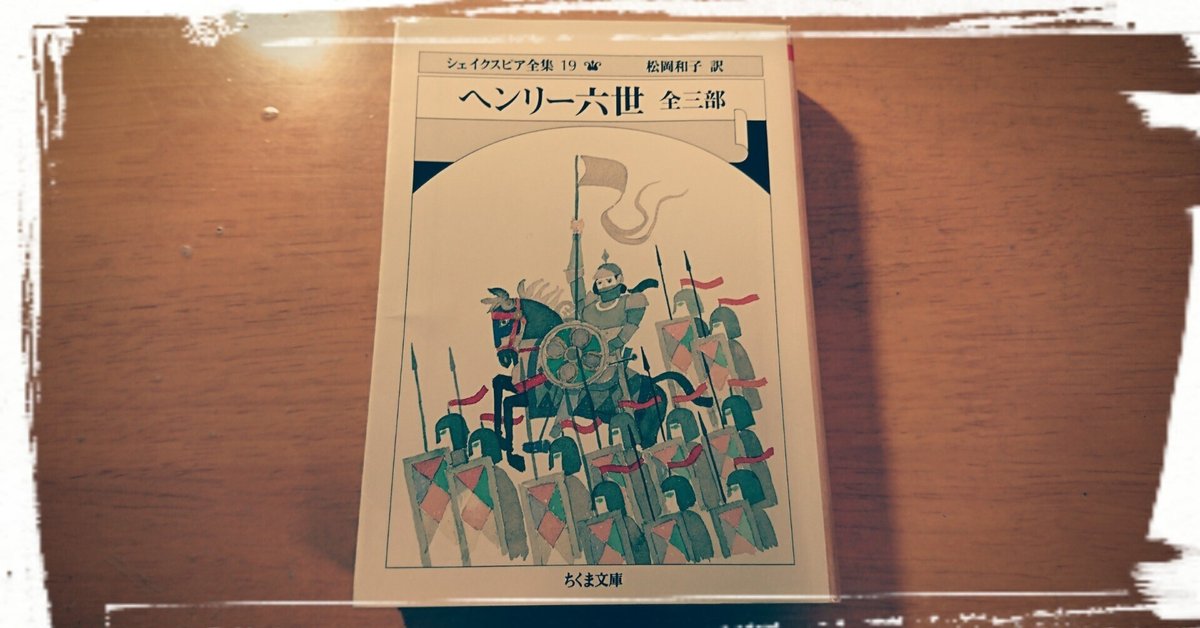
シェイクスピア『ヘンリー六世』読了
[アップグレード]薔薇とヘンリー六世の受難
シェイクスピア(作)『ヘンリー六世』を読了した。
本作を手に取った理由は『リチャード三世』同様、漫画家・菅野文(作)『薔薇王の葬列』にハマったことがきっかけ。
副題に「アップグレード」とつけたのは、シェイクスピアを読んだうえで、『薔薇王』についての感想も含めて述べるためである。
🌹関連記事👑
百年戦争とそれに続く薔薇戦争により疲弊したイングランドで、歴史に翻弄される王ヘンリー六世と王を取り巻く人々を描く長編史劇三部作。
敵国フランスを救う魔女ジャンヌ・ダルク、謀略に次ぐ謀略、幾度とない敵味方の寝返り、王妃の不貞――王位をめぐる戦いで、策略に満ちた人々は悪意のかぎりをつくし、王侯貴族から庶民まで血で血を洗う骨肉の争いを繰り広げる。
大まかなストーリーの流れは、あらすじに示された通りである。

ちくま文庫/シェイクスピア全集19/訳:松岡和子
本作を読んだことで発見したのは、『薔薇王の葬列』での描写や台詞の大半が、極めて忠実に存在していたことである。勿論、原案として明記されている以上、想定されることかもしれない。
だが、驚くべきは、翻訳とは言え、極めて現代にも通ずる語彙・内容が、既にシェイクスピアによって、登場していた点である。
マーガレット王妃の感情や所業は、2022年10月から、新たに新作外伝として、『薔薇王の葬列 王妃と薔薇の騎士』が出版を開始しているが、それらも丹念に筆者が読み込んだ上での、漫画表現であることが分かる。
これは当然、漫画へのマイナスポイントにはならない。
かつて史劇として書かれ、史劇(演劇)として表現されたものが、今日、時代・文化のうつりに伴って、漫画へと至ったとみるのが無難だろう。
なお、『薔薇王の葬列』としても舞台化されているなど、表現媒体において、相互性のあることが認められる。
そのため、古典作品を漫画化した諸作品同様、シェイクスピア作品を理解度を深めるという役割も期待できる。
そういった原案忠実度で言えば、先に記載したシェイクスピア『リチャード三世』よりも、この『ヘンリー六世』の方が高いと言える。
という訳で購入しました!
— 綾波 宗水 (@Ayanami55461929) October 19, 2022
菅野文先生(作)『薔薇王の葬列 王妃と薔薇の騎士』第1巻。 pic.twitter.com/suQ83tm6Se
西欧における語彙を飛躍的に向上させたのがシェイクスピアであると聞いたことがある。
ところで、人は感動したとき、あるいは驚愕したとき、「言葉を失う」ことがある。
一方で、語彙を総動員するかのようにまくしたてることもある。本書でいうところの「悪口雑言」がその代表である。
『リチャード三世』では謀略シーンが多々あったが、長編三部作『ヘンリー六世』では、戦闘中であったり、宮廷、あるいは庶民の間、その場面や身分の上中下を問わず、かなりの罵詈雑言の応酬が描かれているのだ。
売り言葉に買い言葉、というが、バーゲンセールよろしく、貴族は己の野心・名誉にかけてひたすら「(政)敵」を罵る。
貴族らしく度々古典を引用してはいるものの、わざと嘆くような場面でも、ひたすらに言葉が飛び交う。
そのため、「傍白」と呼ばれる語り手と観客(読者)しか知り得ない独り言も、『リチャード三世』より少ないように思われる。その意味で、本書は会話劇であり、それこそが「動乱」なのである。
さて、アップグレード考察にすすむ。
以前、『薔薇王の葬列』での描写から、ヘンリー六世はその敬虔さに注目した。それ故に、王妃からは「王」ではなく「(ローマ)法王」になるべき人物だったと批判的に思われる。
『ヘンリー六世』でもそういった描写は多々ある訳だが、それとセットで、彼・ヘンリー六世には、頼りとなる、あるいは頼るべき相手が宮廷内で存在していた。
その代表は、ヘンリー六世の叔父たちである。彼らは「摂政」や「枢機卿」として大きな派閥抗争を展開する。ヘンリー六世は幼帝として即位したため、当初からその血筋・王権の象徴でしかなく、ながらく王としての実務はなかったものとみられる。
彼は、父なる神、そしてフランスでもしられる先帝の権威、そして摂政たちの専制的な支配に己の進退を委ねていたのである。それをして彼は運命や政権中枢の移ろいを「神の御心」と感じていたのだ。
なお、『薔薇王の葬列』よりもシェイクスピア作の方が、ヘンリー六世は比較的意思がハッキリしている。王妃やヨーク公リチャードへの反感を示すこともある。
だが、摂政からそのポジションが王妃へと代わったように、ヘンリー六世として断行的な勅令を発するなどはやはりない。
また、訳者もあとがきで述べているように、『ヘンリー六世』は対立を描いている。強いて言えば対称的でもある。
イギリスVS.フランス
イングランド宮廷内の各派閥
貴族と庶民、王候と僭主
ヨークVS.ランカスター、薔薇戦争(白ばらと紅ばら)
I(私)と君主のwe(余/朕) etc.
聖人的ヘンリー六世と、女好きのエドワード四世や、悪魔的な片鱗をみせる後のリチャード三世という風に、ある種の属性(キャラ)としてもコントラストが存在している。
複雑な貴族の血筋のなかで、これらの対称が文脈をより豊かにしている。より効果的に発揮するため、シェイクスピアもまた、史実を変更してもいる。
幸いにして、ちくま文庫版は注釈が丁寧であり、また三部作を一冊にまとめられている。
退屈する箇所のない名作でもあり、是非ともオススメしたい、特に『薔薇王の葬列』が好きならば。
いいなと思ったら応援しよう!

