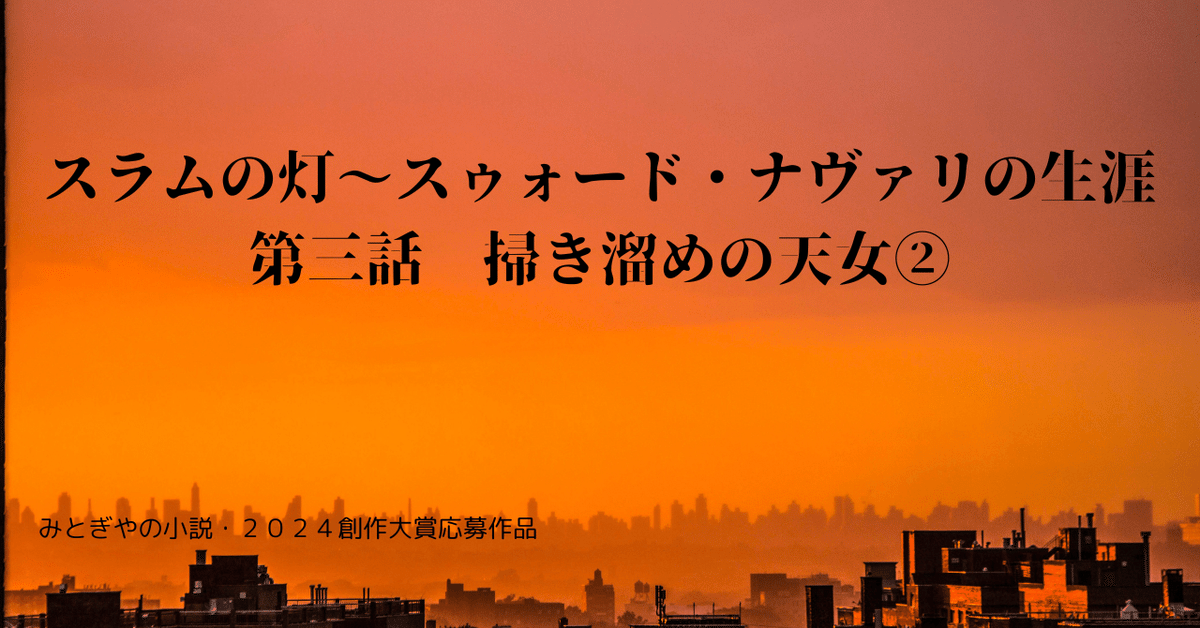
スラムの灯~スゥォード・ナヴァリの生涯 第三話「掃き溜めの天女②」
「そうか、皆、5年前の大戦の後、遺された子どもたちだったのか」
「そう。私もね」
「私の名前、知ってたのは、太刀に聞いたのかしら?」
「ああ、あの上の子、太刀っていうのか」
「そう。私が沙夜で、太刀、棟、ふくら」
「なんか、聞いたことがあるな・・・」
「一人にされた時にね、名前が解らない子もいるんだよ。ここの子たちって。だから、強く育つようにね、この区画の纏め役のお爺さんがつけてくれたの」
「俺の名前、こう書くんだ」
メモを取り出して、「御剣」と書いて見せた。
「ああ、太刀と同じだわ。でも、いい刃物のことよね」
「ミツルギって読むんだ」
「うわあ、すごい、カッコいい」
「ふふふ、名前負け。顔だけ見ると、女みたいだろ?」
「うふふ、私より、美人さんかなあ、見ると」
「そんなことない、沙夜だって、口紅しなくても、いいぐらいじゃないか?」
「うん、・・・昨日も、そう言われた」
そうか。
「子どもたち、寝たね」
「そうだな、じゃ、そろそろ、俺、帰る」
「夜中に、層越えするとね、陸軍の見回りに怪しまれるの、知ってるよね?」
「あー、そんなの、大丈夫だよ」
「だめだよ・・・隣ね、空き家なの」
「え?」
「帰らないで。頂いた分、返せてないから」
「・・・そんな、じゃないから、連れ出したのに」
「昨日は、散々だった。でも、泣いてても、仕方ないからって、お客さんに慰めてもらったの」
「そうだったのか・・・」
「顔見知りが多くて、恥ずかしかったけど、複雑な感じで・・・」「・・・」
「ミツルギに出会えて良かった。やっぱり、優しい人だった。ねえ、私、いいんだって」
「え?」
央樹の顔が浮かんだ。きっと、沙夜の水揚げの相手は、央樹だ。店の人間が慣らして、仕込むっていうらしいから。それにしても、泣いていたのが、嘘のようだ。
「確かに、お店に出てしまったけど・・・最初のお金は、ミツルギのものだし、今日の分も、ミツルギのものでしょ。私、色々とこれからもあるけど、ミツルギがいたら、頑張れる気がして・・・」
「そうか、だったら、良かった。いつも、というわけにはいかないが、仕事の儲けが入った時に来るよ。また、連れ出して、こいつらに食べるもの買ってやろう」
「隣に行こう」
「いや・・・それは」
「嫌なの?恋人がいるから?・・・いるよね?」
いないよ。愛人紛いのことはしてるけど。君と似てるんだよ。俺も。動機は違うけど。今日の金だって、三層の奥様や、宝石商の社長から、頂いたものだからね。
「恋人には、内緒にして。学校に行って、頭が良くて、お上品なお嬢様でしょ?」
三層の暮し、良い人はそんな人もいるかな。学校にも行ったけどね。俺は普通だし、写真ばっかで、齢の近い恋人なんて、持とうともしなかった。なんとなく、興味なかったしね。
「本当は、こんなの、嫌なんじゃないか?」
「嫌だよ。でも、優しい人、ミツルギだから」
沙夜は、もう一度、子どもたちが寝静まったのを見てから、来た時のように、部屋を出て、鍵をかけた。裏に回り、階段を上ると、もう一つ部屋があった。また、鍵を開ける。同じ鍵で開け閉めできるらしい。ドアを開け、灯りをつけると、ベッドがあった。
「さっき、向こうで、お湯使ったから、身体は綺麗だから、流石に、店では川で、ってわけにはいかないから」
意外だった。泣いていた彼女が、こんな風に。
★・📷・★
大人との交わしとは違った。抱き締めると、若い彼女は、俺より、小さかった。
「恋物、って知ってる?」
「ああ、なんか、女の子の読み物だろう?」
「うん、宿にあるの、皆で、回し読みするんだけど」
「そうなのか」
「読んだことある?」
「ない」
「紫は、書いてあるらしいの。色んなこと」
「何?」
「色々と例えるの。こういうことするの。・・・思いついちゃった」
「何々?」
「結局、こういう事するの、同じなのにね。翡翠だって、言葉は綺麗だけど、男同士のことでしょ?」
「翡翠のことも書いてあるのか?」
「多分、ないけど・・・沙夜がミツルギを包む」
なんだ?これ。・・・ああ、そうか、言葉遊びだな。
「これからすること」
鞘が剣を・・・
「あー・・・そゆ意味か・・・」
「そお・・・うふふ」
二人でなんか、どちらからともなく、ニヤニヤして、そして、声を立てて笑った。
「あんまり、心配しなくても、良さそうだな」
「ううん、沙夜は、ミツルギがいないとダメ。いれば、大丈夫」
どちらからともなく、口づけた。そこからは、もう会話もなく・・・。
惹き合っていた。痺れ捲って、何度も惹き上がった。きっと、俺たちは、そうなんだ。お互いに、相手を満たす天才らしい。俺も「天使」と、奥様に絶賛されたが、彼女は、央樹の言う通りの「天女」だった。
★・📷・★
その後、コンテストに出した、俺の写真は、スメラギ大臣賞を頂き、名実ともに、写真家となった。ランサムの写真館にも、いくらか、飾ってもらうことになった。その時に、俺をプロデュースしたいと言った、画廊の経営者が、それ用の名前にしようと、俺のスメラギ表記の名前「隠 御剣」に「スゥォード・ナヴァリ」と読み方をつけた。俺は、そんなランサム人みたいな名前は嫌だ、と言ったが、その時にはもう遅かった。お蔭様で、撮る写真に価値が付き、撮影の依頼も増えていった。
そして、俺は、沙夜を買い上げた。しかし、階層の違うものが、一緒に暮すのは難しかった。つまりは、結婚することはできなかった。なので、生活の支援をしながら、通う形となった。それでもいいと、沙夜は言った。その後、間もなく、残念なことに、ふくらが、流行りの黒墨の病に罹り、亡くなってしまった。太刀と棟は、亡くなった屋台の老夫婦を継いで、雑穀スープを売る仕事に就いた。その頃だった。沙夜が妊娠したのは。そして、俺たち二人の間に、娘が生まれた。娘は大きくなり、美しく育った。
この頃、スメラギの法律が、更に厳しくなった。各階層での行き来が制限されることになった。商業的事由以外では、出入りを禁じるようになった。どうしても、ということであれば、居留権を降格して降りるしかなかった。
写真家としての俺は、色々と仕事に呼ばれていた。ランサムにも一度、何かの写真の表彰で行った。その時に、初めて、若い頃の自分に似たと言われた、ランサム礼拝堂の天井のフレスコ画を見た。その頃には、もう、俺は、四十歳を過ぎていたから、そうは似てはいないと思った。思えば、人や風景写真ばかり撮って、自分の写真など、遺してはいなかったことに気づいた。
ランサムから戻ると、写真館の中から、色々なものが無くなっていた。プロデューサーが姿を消していた。俺の写真の版権、写真の販売の権利の契約の書類を持ったまま、一緒に、スメラギに帰るフリをして、ランサムへ逃げたのだ。戦後、ランサムからの自由の風潮が、人々の労働意欲を割く原因となるとし、スメラギでの芸術・文化的活動は、更に締め付けられてきた頃だった。商業的な活動を止められる前に、そのようにしたのだと思われた。
俺は、ならば、丁度良いと思った。五層への降格の手続きをした。役人は、いぶかし気に、俺を見た。そんな奴はいない。身分を下げるなど。このまま、三層に居れば、元のガラス工芸職人の工場を再開できると。しかし、もう、その頃の職人は亡くなっていたし、現場から離れていた俺には、その手仕事の技術はなかった。その工場の土地も、写真館も売り払った。そうして作った、手持ちの金を持って、五層に降りた。
しばらくは、その持ち金を切り崩し、沙夜と娘の慈いつくと、そのスラムの家で暮した。太刀は町の娘と結婚して、離れた地区に移った。そもそもが、節約して暮すようなスラムだ。家族で、屋台や拾い仕事をしながらやっていけば、十数年はやっていけるだろうという目算でいた。そのうちに、その実、他人であり、家族の戸籍ではなかった、もう一人の弟分の棟と、娘の慈は結ばれた。そして、子どもが生まれた。俺は、五十代だったが、孫を持つ身となった。男の子だった。
「可愛い。ミツルギ、貴方と出会った時のこと、思い出す。大きな瞳で、そっくり」
そもそもが、皆、剣を司る名前でもないと思い、娘には、優しい子にと、慈と名付けていた。その娘に、孫の名づけを頼まれた。祖父母の私たちは、この子を、慈の文字を使い、慈朗と名付けた。この時、記念に、この天使の写真を撮った。スラムに於いて、人の写真を撮ること自体、危険なのだが・・・。
この後、沙夜と慈が、例の黒墨の病に罹った。医者に診てもらおうと、上の層の人間に金を渡したが、それは叶わず、・・・法律的に無理だったこともさることながら、つまりは、また、金だけ騙し取られてしまった。手を尽くしたが、妻と娘は、間もなく、亡くなった。遺されたのは、男たちだけとなった。婿の棟と、その子、当時まだ、赤子だった慈朗と、三人となった。
金は、僅かになっていた。
つづく
いいなと思ったら応援しよう!

