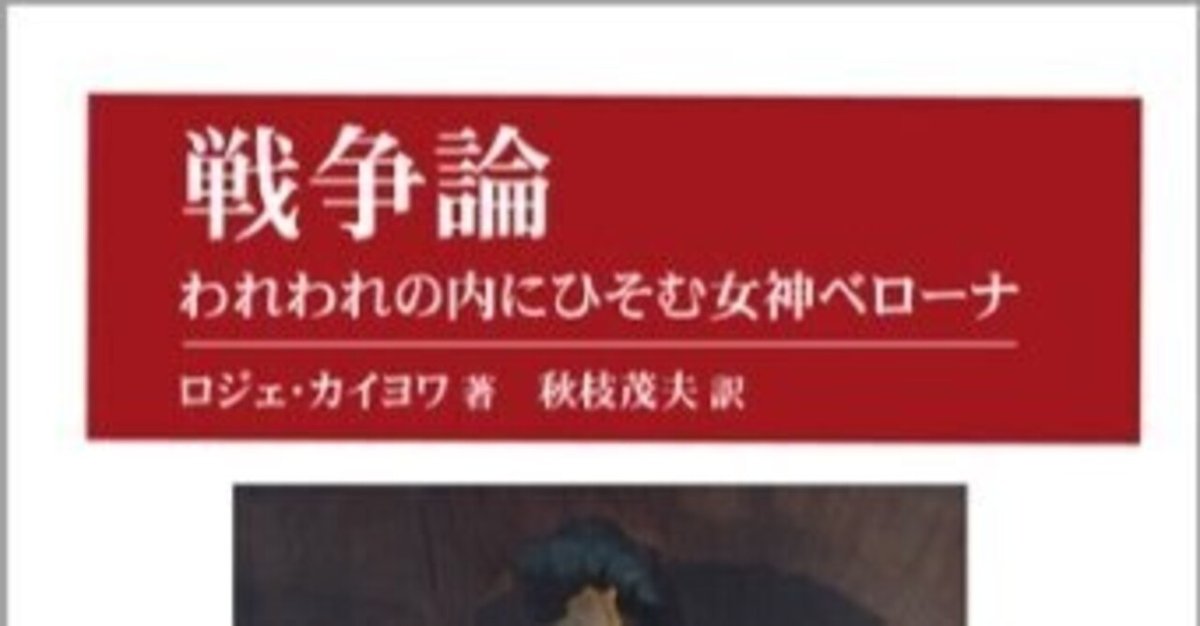
書籍『戦争論 われわれの内にひそむ女神ベローナ』
ロジェ カイヨワ (著), Roger Caillois (原名), 秋枝 茂夫 (翻訳)
出版社 法政大学出版局 新装版
発売日 2013/8/9
単行本 294ページ
目次
序
第一部 戦争と国家の発達
第一章 戦争の原形態と小規模戦争
一 原始的戦争
二 戦争と国家の発生
三 帝国戦争
四 貴族戦争
第二章 古代中国の戦争法
一 戦争は災厄である
二 戦争の倫理
三 名誉の規則
四 暴力の萌芽
第三章 鉄砲 歩兵 民主主義
一 槍から火縄銃へ
二 歩兵と民主主義
三 貴族歩兵創設の試み
四 上流社会の戦争
五 変革の徴候
第四章 イポリット・ド・ギベールと共和国戦争の観念
一 アンシャン・レジームの理論家
二 革命主義者
三 国民総武装の予見
第五章 国民戦争の到来
一 市民兵
二 戦争の激化
三 戦争と民主主義
第六章 ジャン・ジョレスと社会主義的軍隊の理念
一 人民の軍隊
二 全体主義への趣向
第二部 戦争の眩暈
序
第一章 近代戦争の諸条件
一 極端への飛躍
二 戦争の形而上学
第二章 戦争の予言者たち
一 プルードン
二 ラスキン
三 ドストィエフスキー
第三章 全体戦争
一 戦争の新次元
二 全体戦争の倫理
第四章 戦争への信仰
一 ルネ・カントン
二 エルンスト・ユンガー
第五章 戦争 国民の宿命
一 戦争のための政治
二 戦争のための経済
第六章 無秩序への回帰
一 根底にある真実
二 兵士の本性
三 兵士の陶酔
四 きびしさと熱狂
第七章 社会が沸点に達するとき
一 戦争と祭りはともに社会の痙攣である
二 聖なるものの顕現
三 祭りから戦争へ
結び
原注
訳注
訳者あとがき
内容紹介
人類が経てきた「戦争形態の変遷」を、主に4つ(「原始的戦争」「帝国戦争」「貴族戦争」「国民戦争」)に区分し、「人間にとって戦争とは何か」という問いに、フランスの良心ロジェ・カイヨワが真っ向から挑む。
レビュー
原題は『Bellone oula pente de la guerre (「ベローヌ、あるいは戦争への傾き」)』。
「ベローヌ」とはローマ神話の戦争の女神の名前。
第二次世界大戦までの戦争に関する西洋視点からの解析が展開される、現在から約70年前の著作ですけれども、カイヨワの圧倒的な素養が功を奏し、訳文はその言い回しに多少の時代を感じるものの、興味深く面白い1冊となっております。
というか約70年も前に本書の結論に至っていたというのが、凄過ぎると思いました。
※現在の戦争の形態は、カイヨワの指摘した4つには収まらず、5つ目のカテゴリーが必要となる状況となっており、それを考えながら読んだのですけれども、色々とインスピレーションを与えてもらいました
カイヨワは言います。「戦争というものは単なる武力闘争ではなく、破壊のための人間集団間の組織的な企て」であり、「その定義を前提としてこそ、はじめて戦争というものを理解することが出来るのである」と。
特に心に残った箇所を3つ厳選すると、
① 戦争は文明とは逆のものであると言われるがその指摘は正確なものではない。戦争は文明の影のようなものであり、文明と共に成長する(いわばコインの裏と表のような表皮一体の)ものである。しかし多くの人々が言うように、戦争は文明そのものであり、戦争がなんらかの形で文明を生むのだというのも、同じく正確性を欠いた指摘である。文明は平和の産物であるのだから。とはいえ、戦争は文明を表出している。
② 戦争は祭りに類似しており、祭りと同じようにひとつの絶対(絶頂)として現れ、ついには祭りと同じ眩暈と神話を生むのである。
③
(中略)
機械そのものは決して危険なものではない。私が恐れているのは、機械の組み立てのために必要とされる、あらゆる種類の数限りない機構、構造、関係、作業なのである。これらは重みをもってのしかかり、社会のバランスを崩す恐れのある惰力である。現代社会の複雑性は、人間の知的能力を凌駕するものとなった。しかも人間は、類別し、分配し、管理し、予見するために、人間よりもより良く、そして早く計算することのできる機械を、ますます多く使用しなければならなくなってきている。
同時にまた、公的な職責に付随する種々の特権がますます大きなものとなりつつある今日、道徳的良心だけでは、これらの特権に対しての誘惑を押さえるには、あまりにも不十分のようにみえる。すべてが公的に管理されている国においては、ことにこの傾向が強い。大衆の利益といっても不明瞭なものであり、イデオロギーの勝利もはるかに遠いものである。それにひきかえ、政界人や党派指導者の得る個人的な利益は、間近なものであり、またはっきりしている。このはるかに遠い善と間近な利とを分かち難いものとする狡猾な全体性のあることを、忘れてはならない。国家の掲げる原理は、現実のものにせよ想定されたものにせよ、最高の法でありまた都合の良い口実である。このような国家の原理が、至高のものとされるようになったときには、これを掣肘できるような原則や尊厳はもはや何もない。国家原理の猛威を免れ得るような場は、もはやあり得ないのである。
そのほかにも、人間に奉仕するこの巨大な機構は、目に見えない色々な方法により、人間に奉仕しながら人間を服従させている。いまはもう、関心のある者はこの問題について考え、どこにその悪が潜んでいるのかを知らなければならぬときである。ところでこれに対処する方法となると、これまた微妙なそして限りを知らぬ問題である。が、それには物事をその基本においてとらえること、すなわち、人間の問題として、いいかえれば人間の教育から始めることが必要である。たとえ永い年月がかかろうとも、危険なまでに教育の欠如したこのような世界に、本来の働きを回復させる方法としては、わたくしにはこれしか見あたらないのである。とはいうものの、このような遅々とした歩みにより、あの急速に進んでゆく絶対戦争を追い越さねばならぬのかと思うと、わたくしは恐怖から抜け出すことができないのだ。
といった感じです。
※①、②は勝手に要約したものであり、③は本文からの引用となっております
①、②に関しては、視野を大きく広げてもらい、③に関してはほぼ同じ考えのため、正直身につまされました(カイヨワなら何か驚くような秘策を伝授てくれるのではないかしらと期待していたのですけれども、やっぱりそれしかないよね……と)。
ちなみに私の脳味噌は③を、以下のように理解しております。
便利な機械を効率的に生産する工程のような、「効率をどこまでも追求する」社会システムを採用し今後も邁進した場合、その社会は人々の生活をさらに圧迫し「多くの人々の生活(人生)のバランスを崩す」無益なものとなるに違いない。
現代社会の複雑性は、個々の人間が把握できる範囲をすでに凌駕しており、人間は類別し、分配し、管理し、予見するために、人間よりも正確に、そしてより早く計算することの出来る機械を、今後ますます多用しなければならない状況に追い込まれている。
同時に国家権力は増し、上位の公職に就く者たちの様々な特権はますます力を増しており、そのような者たちの特権(職権)乱用の誘惑を押さえるためには、道徳的良心に訴えるだけでは余りにも不十分であるようにみえる。
全てが公的なシステムにより管理されている国においては、特にその傾向は強い(公職上位の人間は汚職しまくりとなる)。
「多くの人々の幸福」と言ってみてもそれは不明瞭な概念に過ぎず、イデオロギーの勝利(まともで論理的な社会的、政治的な思想が実行される日)もいつになるやらわからない。それに比べて、政財界や党派指導者(政治家)の得る個人的な利益(汚いことをして稼いだ「金」)は、目の前に既に存在しているはっきりとした物である。ゆえに私たちは、遥か遠くに見えている人々を幸福にする社会システムの実現を妨げ、目先の利益のみを追求することを良しとする狡猾な(全世界規模に及ぶ)全体的なシステムが存在することを、決して忘れてはいけない。
国家の掲げる原理は、それが現実のものであるにせよ想定されたものであるにせよ、人々の自由を縛り権力者の利益を追求して守るために用いられる強力な法(法律&方法)であり、また都合の良い口実である。
だからもしそのような国家の原理が至高のものとして実行されるようになってしまったときには、そのような原理を退けることが出来るような原則や尊厳は、もはや人々(ディストピア国家の国民)には残されてはいない。
国家という強大なシステムは、その他の目に見えない色々な方法で(マスコミ等を利用することにより)、人々(国民)にある程度奉仕しつつも、裏では狡猾に立ち回り、欺き、服従させている。
だから今、そういった政治システムの欺瞞に気づき、関心を持っている者たちは、その問題について考え、そのシステムのどこに悪が潜んでいるかについて学び、知るべきだ。
しかしそれを知り、変革にむけてどのようにそのシステムを構築し直してゆくかということになると、とても繊細でどこまでも難しい難題だ。
が、難しく考えずに、まずは最もシンプル且つ普遍的な方法、子どもたちの教育から始めることが必要であると思う。たとえ永い年月を要しても、危険なまでに教育の欠如したこのような世界に、本来の働きを回復させる方法は、私にはそれしか見当たらない。
とはいうものの、子どもたちに丁寧な教育を時間をかけて施してゆくという方法で、日々恐ろしいほど加速度的に、安易に開戦することが可能となってゆく戦争を起こさないよう戦ってゆかなければならぬのかと思うと、不可能なのではないかと慄いてしまい、私はその恐怖から抜け出すことができないのだ。
③の最後の一文は、本書の大切な〆であるのに、カイヨワの名前には「ヨワ」という響きが入っているからなのか、かなり「ヘタレな発言」で〆られていて(まぁ現実的といえば現実的ですけれども……)、読み終えた瞬間に「ヨワいんカイ! 」と、なじってしまいました。
たとえ思ってなくとも、ドフトエフスキー流に「ゼロだよ、ゼロにかけるんだ!」くらいのハッタリをかまし、「鼓舞」してほしかったなぁ。
ほぼ全編が最高にカッコイイのに、最後の最後にズッコケさせてくれる、稀代の名著でございました。
