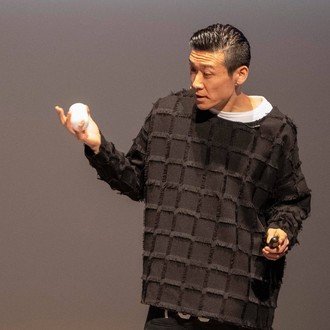2019年8月の記事一覧
ハッタリと嘘の狭間で(第18話)
こちらとしては、いいモノができる!これを作ってくれる協力してくれる企業はたくさんあるはずだ!というというテンションである。
ただ、現実はテンションとは甚だしい乖離があった。
「最低ロットは20万台からですね」
「予算はザッと4億円からといったところでしょうか」
「量産できるようになるのは2年後くらいだと思った方がいいですよ」
こんな答えがあらゆるところで返ってきた。
夢とか商品に対する
ハッタリと嘘の狭間で(第17話)
要するに、また考えが甘かったところが露呈するのだが、プロトタイプができてからのコストがどれくらいかかるのかが未知数だったのである。
くり返しになるが、ときは2017年12月。
年の瀬である。
ちょうどこの頃、ある程度のプロトタイプが完成した。
ただ、これだけでは商品として世の中に出すわけにはいかない。
回路図は専門知識のない状況での試作なので安全設計等は皆無だし、外側は3Dプリンタで出力
ハッタリと嘘の狭間で(第16話)
2017年10月以降の開発は、とにかく動くものを作るということだ。
kickstarterでプロジェクト申請をしたときのプロトタイプはライトは点いたが、リモコンモジュールはハリボテだった。
実際のソフトウェア側もできていなかったので、アプリもイメージUIを載せたり、動画もイメージに近い形で撮影をしていた。
もちろん、実際にできるよう設計は考えていたし、時間さえあればほぼ間違いなくできる自信も
ハッタリと嘘の狭間で(第15話)
kickstarterでのプロジェクト申請はとりあえずは諦めたものの、開発を止めるわけにはいかない。
次の作戦は、国内のクラウドファンディングを視野に立て直しを図るというものだ。
kickstarterで最も大変だと思ったことの1つは英語だ。
英語ができる人がいないと正直プロジェクト制作や担当者とのコミュニケーションは本当に大変だ。
このあたり、実際にプロジェクトを実行してサクセスして、ア
ハッタリと嘘の狭間で(第14話)
いろいろと準備してきた渾身のプロジェクトをkickstarterに申請した。
でも、あっさりとリジェクト(申請拒否)されるという結果に終わった。
その理由は、レンダリング画像(CG画像)等が多すぎて、このプロジェクトには信憑性がないという判断をされたのである。
はっきり言って心外だった。
kickstarterのプロジェクトの中には、明らかにレンダリング画像を使っただけの実現不可能に思える
ハッタリと嘘の狭間で(第13話)
そして、kickstarterへのプロジェクト掲載に向けて全体を構成を俺が考えて、メンバーへの割り振りを決めていく。
このように当時の完成イメージ画像もどんどん作成されていく。
もちろん、機能が拡張していくこと、モジュール構造になっていることもしっかりと記載していく。
とにかく機能性とデザイン性を推すことを重視して、実際にできるかどうかというギリギリのところを攻めた。
まさにハッタリと嘘の
ハッタリと嘘の狭間で(第12話)
とにかく、開発まで時間とお金をかけていた俺は焦っていた。
kickstarterでクラウドファンディングして、世界に注目されれば一気にいける!と本気で考えていた。
実際に数億円単位で資金調達できてるプロジェクトも目立っていた時期なのも気持ちを高ぶらせていた。
後々、kickstarterのコンサルをしているフランスに拠点を置いている会社から聞いて知るのだが、10万ドル(約1,100万円)以上
ハッタリと嘘の狭間で(第11話)
電気回路のことやデザインのところも一手に引き受けてくれた上本が完成させてくれた記念すべきstakのプロトタイプがこちら。
一番右にあるのが、stakの頭脳となる本体の部分である。
真ん中がLED照明モジュール、一番左がリモコンモジュールである。
いずれもマグネットで取り付け取り外しができて、LED照明モジュールは実際に光らせることもできる。
このプロトタイプをelephantのときのように
ハッタリと嘘の狭間で(第10話)
stakの開発までにしてきた「モノづくり」は今思えば、本当にレベルの低いものだった。
というのも、stakは機能拡張型・モジュール型という特徴から、モノづくりといっても実質3つのパーツを作らなければならない。
1つは頭脳の部分になるstak本体。
この中にはWi-FiチップやBluetoothが内蔵されていて、まさにstakの司令塔になる部分だ。
2つ目は、今や認知度も上がってきたスマート
ハッタリと嘘の狭間で(第9話)
第3弾の「モノづくり」の際にプロトタイプの依頼をした。
その際に3Dプリンタで外注したのだが、4つで20万円というもの。
今思えばとんでもなくボッタクられていた。
なぜなら、stakの構想に至ってから3Dプリンタを購入したのだが、1台は50万円。
もう1台はクラウドファンディングの商品だったので20万円以下で購入ができた。
そこで何度も試作品を作ることになるのだが、フィラメントと呼ばれる
ハッタリと嘘の狭間で(第8話)
「モノづくり」のハードルが下がった。
この言い回しを近年耳にしたことがある人もいるのではないだろうか。
その理由の1つに挙げられるのがクラウドファンディングの登場にあるだろう。
確かにそのとおりなのかもしれない。
でも、この言葉には裏側があることを忠告しておこう。
モノは簡単に作れても、売れるということとは全く別次元であるということ。
いくら入念に計画を立てたとしても、そのとおりにいく
ハッタリと嘘の狭間で(第7話)
stakの構想は当初からほとんどブレることなく進んでいる。
機能拡張型・モジュール型IoTデバイスと称している。
最大の特徴は3つある。
1. ソフトウェアとハードウェアのいずれも機能が拡張していくこと。
2. マグネットで簡単に取り付け取り外しができること。
3. 他のIoTデバイスとの連携が容易にできる仕様になっていること。
キャッチコピーは「あなたのお家をぷちスマート化」。
ま
ハッタリと嘘の狭間で(第6話)
俺はクラウドファンディングを開始することにイケイケだった。
とにかく世間にアピールして、注目を集めて一気に一気に高みへ昇ってやるんだ!
プロジェクトの内容も少しずつ決めていく中、エンジニアの上本から話があると連絡があった。
その内容はelephantを全否定するものだった。
開発の部分は上本に任せており、ずっとやってきた本人から、このタイミングでelephantを止めましょうと言われたこと
ハッタリと嘘の狭間で(第5話)
くり返しになるが、今までのなんとなくの「モノづくり」だったが、このelephantは力が入っていた。
この1枚からも、その本気度が少しでも伝わればと思う。
今見返すと稚拙で甘すぎる事業計画だが、いろいろと考えて行動し始めた。
この事業計画の期首は2017年6月となっていることから、2016年9月にモノづくりを始めてから、1年足らずで形にしていったことになる。
少なからずの自信とワクワクが止