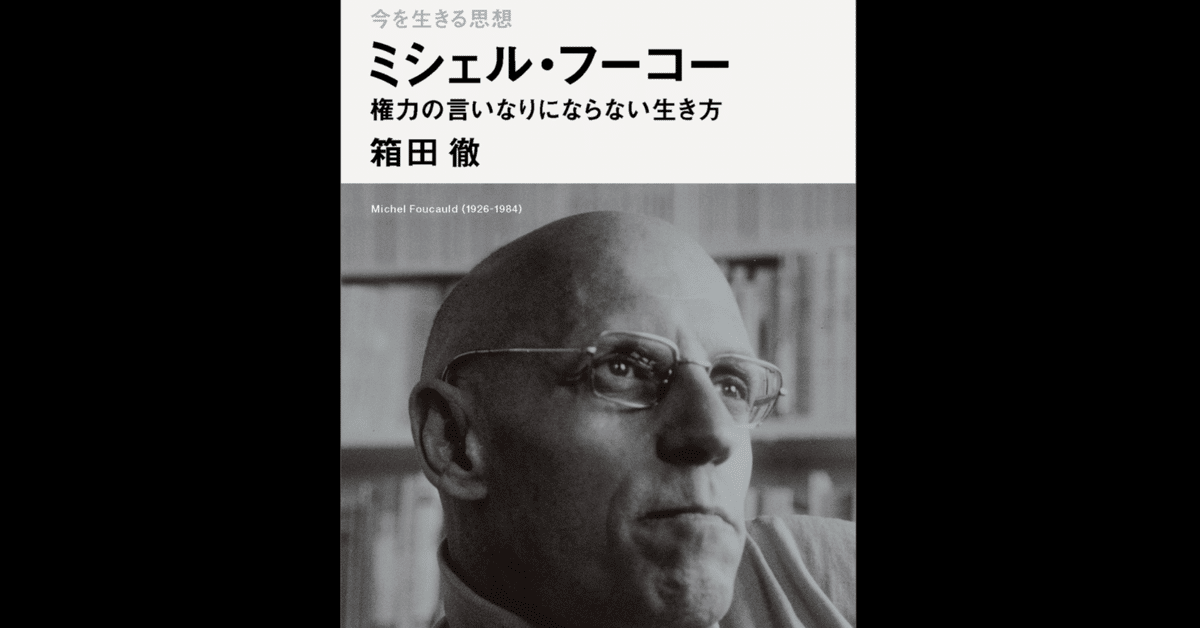
「対抗導き(コントル・コンデュイット)」としての「啓蒙」——ミシェル・フーコーの統治論
フーコーはこの議論を足がかりとして、啓蒙に「意志と権威、理性の使用との間の既存の関係の変更」という定義を与える。
すなわち、統治論から見た「啓蒙」とは、自己の導きと他者の導きの関係によって構成される自己が、みずからの振る舞いのありようを問題化することで、いまみずからが置かれている統治の関係を変えることだ。人は啓蒙を意志し、勇気を出して、これをあえて引き受けることによって、啓蒙という集合的なプロセスに個人として主体的に加わるのである。この議論は、一九八二/八三年度コレージュ・ド・フランス講義『自己と他者の統治』の初回講義でコンテクストを含めて改めて詳細に取り上げられている。
現在が啓蒙の時代であるという感覚は、いまここを固有の時点として捉えるという近代に固有のものである。こうした時代感覚を、フーコーは、一九八三年に米国で行った同名の講演を元にしたとされるテキスト「啓蒙とは何か」(一九八四年)で、一九世紀の詩人ボードレールのダンディズムや「現代性(モデルニテ)」と重ね合わせる。
ここで「ダンディズム」とは、近代における自己への配慮の実践、ひとつの修練である。(中略)それは「みずからの身体、振る舞い、感情と情熱、そして生を芸術作品にする」修練としての自己の主体化である。
この修練としてのダンディズムとは、移りゆく時代の流行を追うのとは反対に、いまという瞬間的な時のなかにあって核となる永遠なもの、ボードレールによれば「英雄的なもの」を捉えることである。いまここを歴史上の一時点としてではなく、固有の時点と見なし、その特徴を探すことは選択に基づく「態度」なのだとフーコーは言う。
ミシェル・フーコー(Michel Foucault、1926 - 1984)は、フランスの哲学者、思想史家、作家、政治活動家、文芸評論家。フーコーの理論は、主に権力と知識の関係、そしてそれらが社会制度を通じた社会統制の形としてどのように使われるかを論じている。フーコーの思想は、特にコミュニケーション学、人類学、心理学、社会学、犯罪学、カルチュラル・スタディーズ、文学理論、フェミニズム、マルクス主義、批判理論などの研究者に影響を与えている。
本書『今を生きる思想 ミシェル・フーコー:権力の言いなりにならない生き方』は、社会哲学者の箱田徹氏(神戸大学大学院国際文化学研究科グローバル文化専攻准教授)による解説書である。本書の特徴は、フーコー前期思想の「権力論」だけではなく、後期の思想である「統治論」にも大きく焦点を当てて、現代の新自由主義経済との関連などにおいても論じていることである。
1970年代から1980年代にかけてフーコーの思想は権力論から統治論へと大きく展開した。権力論において、パノプティコン、規律権力、生権力、生政治といったキーワードとともに、フーコーの思想は広く知られていることだろう。しかしながら、フーコーにとって、権力論は「統治」と「主体」という概念と一体のものであり、統治論において、主体がいかに作られているのかという問いは、主体がいかにみずからを変えるのかという問いと一体不可分のものとして考察されている。社会と自己を説明することと、それを変えることとはどういう関係にあるのか?この古典的な問いに改めて取り組むことで、フーコーの統治論は私たちが現代社会を考えるにあたって大きな示唆を与えてくれる、と箱田氏は述べる。
フーコーが権力論を「統治」という大きなスケールで展開するようになったのは「司牧権力」という概念である。これは西洋近代に特徴的な権力のあり方をキリスト教の「導き」の「世俗化」として捉えたことにある。この統治という概念は、古代ギリシア・ローマの「自己への配慮」の問いへとつながり、さらには「自己と他者の統治」という統治論の大きな枠組みをかたちづくる。
1970年代後半のフーコーは、西側先進諸国の社会統制のあり方が大きく変わっているという感覚のもと、権力論の手法を西洋近代国家の統治技術=統治性の分析に適用した。そこでは、戦間期に登場した新自由主義(ニューリベラリズム)は、個人を「ひとり企業家」にしたうえで、完全競争市場というフィクションを原理として社会に介入させていることをフーコーは指摘する。
そうした社会の大きな統治の動きに対して主体は別の道を探ることができるのであろうか。フーコーは、統治論における「対抗導き」という着想をもとにして、オルタナティブを求める自己の統治の可能性があることを指摘する。この対抗導きとは、権力関係のなかでの「抵抗」を超えた、既存のシステムへの反乱であり、新たな導きの模索を通して、未来を形づくろうとする主体的な試みなのである。
統治とは、自己の統治と他者の統治のあいだの「補い合う関係と争い」をはらむ、決して安定しない状態とフーコーは言う。このような権力論と統治論の交点にあって、導かれる側がみずからを別のかたちで導くことを「対抗導き(コントル・コンデュイット)」と名づけた(『安全・領土・人口』)。ちなみにこの言葉は「反操行」とも訳される。統治としての導きには、このようなオルタナティブな導きとしての「対抗導き」が原理的に備わっているのである。
フーコーは中世から近代に至る「導かれる側の反乱」として、修道会の設立や信仰革新運動、16世紀の宗教改革の先触れとものあった14〜15世紀のフスやウィクリフなどの教会批判、キリスト教の成立時点から連綿と存在する神秘主義、聖書への回帰、終末論などを例として挙げている。
宗教以外に世俗の歴史にはどのような対抗導きの主体が見られるのか?フーコーは、それは国家への従属を拒否し、国家が提示する真理とは異なる真理によってみずからを集団として導く市民社会、住民(ポピュラシオン)、民族=国民(ナシオン)であると述べる。つまり国家理性に抗する政治的自由主義、自由主義に抗する民衆蜂起と革命運動、帝国主義や植民地主義に抗するナショナリズムと革命運動が対応すると考えられる。
それは「このようには統治されない技術」である。この言葉をフーコーは、カントの小論『啓蒙とは何か』(1784年)を参照しながら、「批判」さらには「啓蒙」という概念と結びつける。「批判」とは、一切の統治を望まない技術ではなく、いまあるようなかたちで統治されないためにはどうすればよいのか、という問いをめぐる考察と技術のことである。そしてこれは「啓蒙」でもある。啓蒙とは、自己が他人の導きに身を委ねてみずからの力で考えようとしない未成年状態から決別すること、自分の悟性を使って自由に考えるという責任を、勇気をもって引き受けると決断することだと、カントは論じていた。一定のリスクを引き受けて実践される理性の公的使用が「啓蒙」の実践であるからである。
フーコーはこれを足がかりにして、「啓蒙」に「意志と権威、理性の使用との間の既存の関係の変更」という定義を与える。つまり、統治論から見た「啓蒙」とは、自己の導きと他者の導きの関係によって構成される自己が、みずからの振る舞いのありようを問題化することで、いまみずからが置かれている統治の関係を変えることである。人は啓蒙を意志し、勇気を出して、これをあえて引き受けることによって、「啓蒙」とい集合的なプロセスに、個人として主体的に加わることができるのである。
