
#10「例外」の中にヒントがある - 解決志向アプローチ -
この記事では「解決志向アプローチ」の考え方について、一緒に学んでいきたいと思います。この考え方を身につけるには、3つの力が必要であり、前回は2つ目の力、「自分の強みやリソースに気づき、それを活かす力 (Resource Activation)」について、「こころの力に目を向けること」の大切さを一緒に学んできました。
今回は「原因を追及して、悪い部分を直す」という従来の問題解決のやり方ではなく、「過去に使っていた自分のリソースを活かして、解決に結びつけていく」というやり方について、一緒に学んでいきたいと思います。キーワードは「例外探し」です。
原因追及のプロセスで自信を失うことがある
僕たちは、多くの場合、問題を抱えているとき、「なんでこうなったんだろう?」と問題の原因を追及して、特定できた悪い部分や欠点を直していこうとします。勿論、それで問題が解決するのであればよいのですが、多くの場合、問題の原因が一つに特定できなかったり、その原因を追及するプロセスで「ここが悪いから、あそこも悪いから」と弱みや欠点ばかりに目が行き、自信を失ってしまうことがよくあります。特に、フィリピンに移る前に関わっていた発達特性が高い青年たちがよくこの状態に陥っていて、せっかく「問題を解決しよう」という意欲があったのに、そのプロセスで自信を失ってしまい、本当に勿体ないって思うことがよくありました。
皆さん、このこと、本当に知っておいてほしいんですが、実は僕たちが当たり前のようにやっている「原因を追及して、悪い部分を直す」という「問題解決」のやり方以外にも「解決に繋がる糸口」はあるんです。
それは、例外的にもよかったときやマシだったときのことを思い出し、「そのとき、何をやっていたのか?」「何が役に立っていたのか?」「今との違いは何か?」を丁寧にみていく「例外探し」の方法です。この例外的にもうまくいったときやマシだったときの経験の中にこそ、その人ならではの「解決の糸口」があるんです。
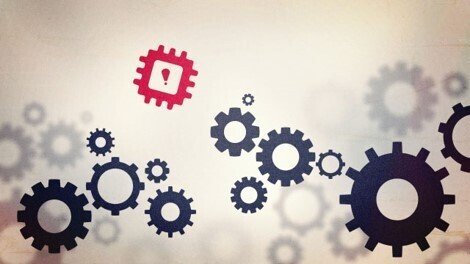
例外的にもうまくいったときを探す
例えば、うつ病を患うクライアントさん。問題を解決するために「なぜうつ病になったのか?」「なぜ気分が落ちるのか?」を探っていってもいいんですが、なんだか、そんな話をしていたら、さらに気分が落ちていきそうな感じがしちゃいます。それよりも大切にしたい視点は、例外的にもうまくいっているときはいつかという視点です。うつ病を患っているといっても、365日24時間、いつも同程度のうつ症状というワケではありません。少し症状が軽い日や気分がマシな時間帯もきっとあるはずなんです。たとえ問題を抱えていても、全部が全部、悪いわけじゃないんです。
「なんで気分が落ちるのか?」ではなく「いつ気分が軽いのか?」
因みに、このうつを患うクライアントさんに「1週間の中でも気持ちが少し軽かったときはいつか?」を伺ってみると、「お昼どきに日が差し込む窓際でゆっくりお茶を飲んでいるときだった」とのことでした。「何が役立っていたのか?」を伺ってみると、「日差しが暖かく気持ちよかったのかもしれない」とのこと。また、「お茶をゆっくり飲むことも、気持ちが落ち着いたのかもしれない」とのことでした。この方にとって、日に当たったり、ゆっくりお茶を飲むことが気分の改善に役立つのであれば、そのような時間を少しずつ増やしていくことって大事ですよね。皆に効果があるかはわかりません。でも、この方にとっては効くんです。このように過去の例外を探し、丁寧に分析していくことで「解決の糸口」が見えてくるケースがあるんです。「なんで気分が落ちるのか?」ではなく「いつ気分が軽いのか?」このポイント、めちゃくちゃ重要です。
僕たちは、どうしてもうまくいかないとき、「なんでうまくいかないんだろう?何が悪いんだろう?」と悪い部分に目が向きがちです。それを続けていると士気まで下がっていくこと、おそらく、皆さんもご経験があるんじゃないでしょうか?
解決の糸口を見つける「例外探し」の質問
今、もし皆さんの中で、問題があったり、うまくいっていないことがあれば、ぜひ以下の問いを大切にしてみてください。きっと、「解決の糸口」がそこにあるはずです。
この問題が無かったときはいつですか?
マシだったときはいつですか?
例外的にもうまくいったときはいつですか?
例外的にもマシだったときはいつですか?
そのとき、今とどんな違いがありますか?
そのときやっていたことで今やっていないことは何ですか?
そのとき、何が役立っていたと思いますか?
他にはいかがですか?
ここでは、解決志向アプローチに必要な3つの力の1つである「自分の強みやリソースに気づき、それを活かす力」について、「例外的にもうまくいったときを丁寧にみること」について一緒に学んできました。また別の記事にて、例外探しの練習やケースなども一緒にやってみたいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。次回は、「例外探し」の応用編として、「勝因分析の重要性」について一緒にみていきたいと思います。(つづく)
【参考文献】
Bannink, F. (2014). Post traumatic success: Positive psychology and solution-focused strategies to help clients survive and thrive. W. W. Norton & Company.
Warner, R. E. (2013). Fast track to beginning practice. In W. E. Ronald (Ed.), Solution-focused interviewing: Applying positive psychology: A manual for practitioners. University of Toronto Press.
