
茶の湯*お稽古の記録をスケッチする時間
絵心なんて全くないのに、絵を描かないと覚えられない頭の作りというビジュアル脳。

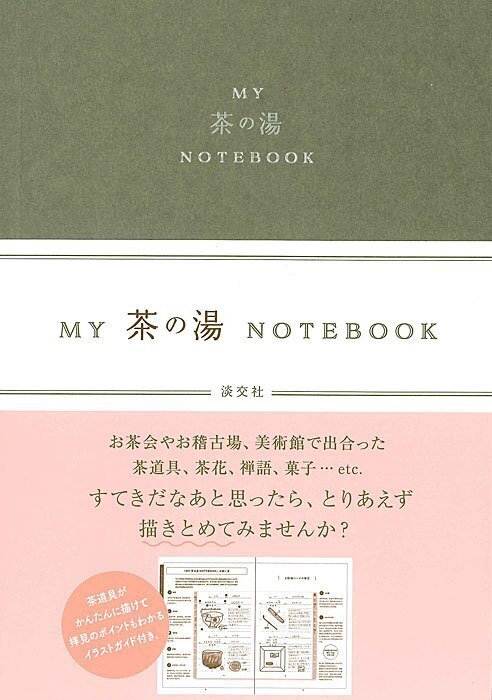
自分の書く字もすごく下手なんだけど、書いた字の形や書いた場所で頭に入ってる。
そしてノートに時系列に順番に書いておけば、時系列に記憶はちゃんとある。
きちんと一度分解してから自分に合った整理の仕方をすると、キッチリ頭に入って忘れないけど、ここの手順を省くとほぼ覚えてない。
ワインの勉強の時も、地図からぶどうの絵から、特徴まで全部絵や字で描いたそのビジュアルを俯瞰したイメージで整理し直して覚えた。
自分に合った方法さえ見つければ誰でもある程度、なにかを覚えることはできると思う。
ただ私はこうやって絵を描くのと、再構築して頭に入れ直すのに時間がかかるから、厄介だ。
お茶を習い始めた当初は意味もわからないまま道具も思い出せず、絵を描くことすら諦めていたけど、10年すぎてやっと今になって描けるようになったことが、すごい進化だと思う。
初志貫徹タイプだから、いつモノになるかわからないような模索の期間が長くなることもあるけど、蓄積されたものが突如大ブレイクすることもある。
だから興味を持ったときになんでも始めておきたいものだと思う。
自分特有の理解の仕方やそれに伴う特技は早く氣づいてよかったと思えるものである。
2月は「旅箪笥(たびだんす)」のお点前を薄茶と濃茶の2パターンしました。野点バージョンのお稽古です。(左ページ)
旅箪笥はたしか年に2回くらいしか出てこない(春とか秋)ので出てきた時に必死に覚えておかないと忘れちゃうから図解!
そして先日のお稽古は「長板」のお点前。(右ページ)
こちらも「小板」「大板」「長板」と中置には3種類ある中の「長板」は台子に準ずる扱いになるので、周りに設えるものもいつもよりちょっと品格が高くて繊細でゴージャス(?)たしかに、磁器の手桶の大きめの水指。

こちらの稽古も素敵な水指を使いたい時とかしか出てこないので、やっぱり後で思い出してメモメモ。
お稽古が終わって、ちょっとカフェに入ってからノートに思い出しながら描いているんだけど、もっと絵も上達したらみんなに見せれるレベルになるかしらん。
私の流派は口伝がベースでお稽古ガイドブック(?)がほぼ無いので、教授になったら自分でちゃんとまとめて教えられるレベルにならないとまずいので、もうわりと必死です♪
そもそもちゃんと通ったからといって、規定の最短の10年で最終免状をいただいたけれど、やはり10年はまだまだひよっこなので、精進あるのみです。
ノートに描くのはとても楽しいので、これもライフワークにしよう。
お稽古は楽しい。それに付随する色々もまたとても興味深い。
ヒカル
