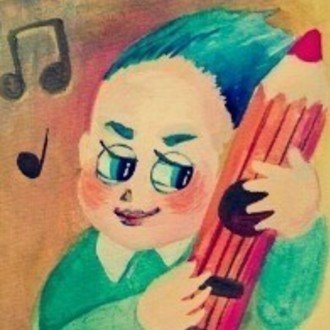【心の詩歌】お気に入りの誤読・柿本人麻呂から前田夕暮へ
きょうの文章は短歌用語・文法用語多めです。
先日、短歌の友達四人で集まって映画を観ました。そのあと、自然に歌会が始まりました。
ある有名な和歌の話題になりました。
あしびきの山どりの尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む/柿本人麻呂
意味合いとしては「長い長い夜をひとりぼっちで寝るんかなあ」みたいな感じです。
「あしびきの」が「山」を連れてくる枕詞(まくらことば)です。
「山どりの尾のしだり尾の」は、一応「山鳥の尾羽、しだれている尾羽のあの感じで……」みたいに解釈はできますが、要は「長い」という印象を与えるための言い回しです。
短歌の世界では「あしびきの山どりの尾のしだり尾の」が、しばしば序詞(じょことば)の例として取り上げられます。
なんとなく長い印象を与えて「ながながし」という語句を引き立てる詞なのですが、歌の情景に直接の関係はありません。山鳥を詠んだ和歌ではないのです。
歌会でこの和歌の話題になったのですが……、そのとき誰かひとりが言いました。自分だったかもしれません。
――「ながながし」って、これ……、終止形ですっけ?
ん? んん?
意味としては「ながーいながーい夜」だから終止形のはずはない。連体形のはずだ。
でも、見た目は終止形だぞ、あれ?
あれか? 過去を表す助動詞「き」とかが何か悪さしてるか?
いやそれも変だ?
一時的に四人が混乱におちいりました。
スマートフォンで検索してわかったのですが、結論を言うと、これは文法上の例外でした。
「ながながし」はシク活用という活用の形容詞で、これを用いて連体修飾をする場合(ながーいながーい夜と言いたい場合)「ながながしき夜」になります。
「ながながし」だと、終止形と思うのは普通です。
さすがに四人ともが初歩でつまづいたわけではなかったようです。
しかし、シク活用の形容詞は、古い時代にはそのまま体言につながって連体修飾する場合があったのだそうです。「ながながし夜」。
四人は「気付かなかった……」「こんなにこすられてるのに……」と顔を見合わせたのでした。
(そして、有名な和歌のことを「こすられてる」と表現した友人に驚きました。)
というこの話は、長い長い前置きです。ここからが本題。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?