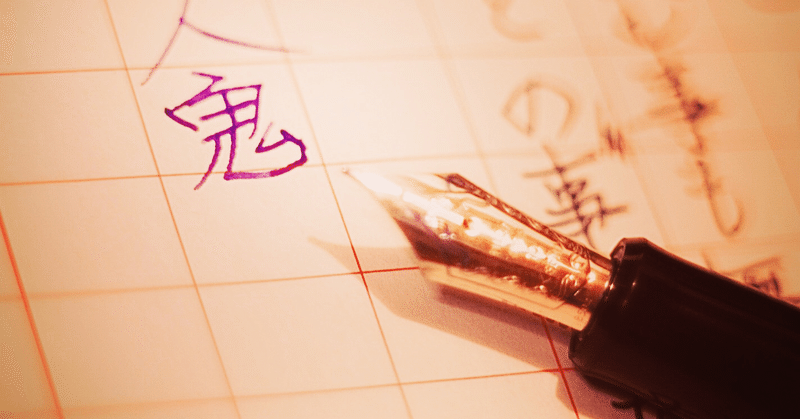2022年8月の記事一覧
牡丹堂、女の執心のこと
『諸国百物語』1677年
中国の寺には、牡丹堂という所がある。
人が死ねば、棺の中に入れる。
棺の外側には牡丹の花の絵を描き、牡丹堂に持ち運ぶ。
そして、他の棺の上に重ねて置く。
ある男が、妻に死なれた。
男は哀しみのあまり夜な夜な牡丹堂へ行き、念仏を唱えることが何日も続いた。
ある夜、その牡丹堂へ若い女がやって来た。
首に円い形の薄い鐘を掛け、念仏を唱えている。
女が来るよう
髑髏(どくろ)、物を言う
『新伽婢子』
今は昔の話である。
現在の兵庫県西宮市、かつての摂州丸橋というところに、たいへん欲深く人の道に外れた男が住んでいた。
ある時、近隣の里にて頼母子(たのもし)があると聞いて、そちらに出向いて行った。
頼母子とは、何人かの人が集まって金を出し合い、そこにいる誰か一人に、その金を貸すという組合の事である。
さて。そこに至る道中に、墓場があった。
男がここを通っ