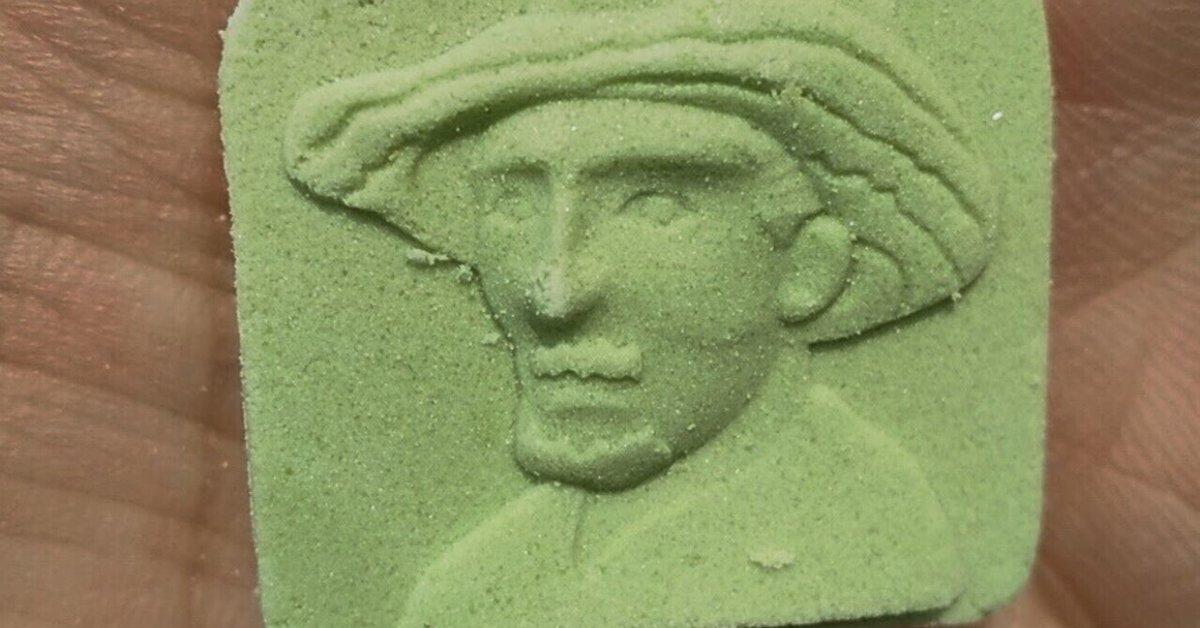
創作において「才能」は本当に必要か? ~北原白秋の一喝~
35歳くらい、遅くとも45歳くらいまでになると、身のほど、「分」というのを意識し始める。
「自分って、『せいぜい』こんなもんだろう、凡人だから」
「自分にできることはこのくらいだろう、凡人だから」
安藤百福、カーネル・サンダース、エイブラハム・リンカーン、伊能忠敬といった、中年から花開いたひとの立志伝を聞かされても、
「まあ、そういうひともいるのでしょうね。ビジネス雑誌の特集記事や自己啓発本なんかで読みましたよ」
とシャットアウトできてしまう。それでいて「それにつけても、この自分の凡庸さ、平凡ぶりはどうか」と複雑な気分になる。
そんなとき、わたしは北原白秋の言葉を思い出す。
白秋の弟子の宮柊二のエッセイから引用する。
ーーー
「才なくて執するは誤り」という言葉がある。私自身そういう思いで自分を振り返ることもあり、友人から同じ意味合いでたずねられることもある。「自分には歌才というものがないのではないか。いつまで勉強していっても、遂に上達するということないのではないか。もし、あんたが私の作を見てくれていて、私に歌才がないと思うならば、そのことをはっきり言ってほしい。才がなくていつまでもやることはさびしい。そして苦しい」など。
(略)
私と同じく北原白秋門下だった友人が、かつて同じことを白秋先生にたずねた。「才があるとかないとかだれがわかるか。質問にも相談にもならない。自分で決めなさい」と一カツされたという。このきびしい言葉は救いである。
(宮柊二「才なくて」『選歌随想[一]』所収 、1966)
ーーー
「才があるとかないとかだれがわかるか。質問にも相談にもならない。自分で決めなさい」
わたしの中の白秋がわたしに一喝する。
自分は何をしたいのか。それをやらずには死んでも死にきれないことは何か。自分は世の中をどう変えたいのか。どんな一つの人生を残して死ぬのかーー
簡単なことだ。
とにかく書けばいい。書き上げればいい。才能を気に病むのは作品が出来てからでも遅くはないーー才能とは作品だからだ。
才能は断じて可能性ではない。目に見えるものである。
才能がなくてもカレーライスは作れる。あとは美味いカレーライス、金を取れるカレーライスを追求するだけだ。小説や詩やエッセイも同じではないか。
恵方とはこの路をただ進むこと 虚子
ーーー
人間一生誠にわずかのことなり。
好いた事をして暮らすべきなり。
夢の間の世の中に、
好かぬ事ばかりして暮らすは愚かなる事なり。
(山本常朝『葉隠』)
(終わり)
※この記事の著作権は本木晋平にあります。無断での引用・複製・転載を禁じます。
