
【1/2エッセイ 】子どもの守り方、間違ってはいないか?
✍️1/2エッセイ とは、エッセイ(実体験、思い)にコラム的要素(リサーチ)を足した私の造語です。勝手解釈なので悪しからず。

さてさて、まず私に湧き起こった疑問から。

そんな文言を見聞きすると
確かにそうだとは思ったのですが、
ちょっと子ども扱いされ過ぎてやしないか?大人が守り過ぎてやしないか?
時に、失敗によって学ぶチャンスからも、
守ってしまっているのではないか?
なんて思ったわけです。
守るタイミングを間違えると、
子どもの成長には繋がりにくいよなぁ。
いつから子どもは、
子ども扱いされるようになったんだろう。
そんな物思いから、次に浮かんだのはこんな疑問。

ほんと、何なんでしょうか、子どもって。
かくいう私たちも子ども時代を過ごしてきました。
でもその子どもが、実は近代以前まで
いなかった、らしいのです。
いやいや、子どもはいるでしょ、今も昔も。
つまり、
「子ども」という概念が存在しなかった、
ということ。

フランスの歴史家、フィリップ・アリエスが著書の「<子ども>の誕生」で述べているこの「小さな大人」とは一体どういうことか。
ここから更に、私の思考の旅は続いていきます。
時は中世ヨーロッパ。
この時代は、なんと多くの子どもたちが働いていたのです。
彼らの年齢は7歳以上。
7歳にもなると、意思疎通がある程度できるので、この辺りの年齢が一つの基準だったようです。
まだ小学校一年生、二年生の子供たちが働いているなんて信じられない!
そうです、その通りです。今の時代、もしそんな事があれば、公的機関の調査も入ります。
けれども別の見方をすれば、早くに子どもは大人の仲間入りができたわけです。
ゆえに大人と一緒になって働くがゆえ、そこに境界線がなく、仕事仲間という仲間意識まであったそう。
また、大人は子どもに混じって一緒に遊んだりもした、というのです。
もしかすると、現代の子どもの扱い方に、当時の人の方が疑問を抱くのではないか、
「なんで子どもは働かないんだ」と。
でも、私たちはきっとこう返します。
「だって子どもたちの仕事は学校に行くことだから」と。

それこそ、学校、だったのです。
時は18世紀後半、イギリスで起こった産業革命の時代です。
ここに、繊維業で成功を収めた実業家のロバート・オーウェンがいました。
彼は、イギリスの哲学者、ジョン・ロックが言う、「習慣が人をつくる」や、哲学者で思想家でもある、ジャン=ジャック・ルソーの言う、「自然に触れる体験こそ、幼少期は大事」という思想に、強く影響を受けていたのです。
そこでオーウェンは、自身がマネジメントする工場で働く子どもの雇用を止めさせたのです。
まず、10歳未満の労働を止めさせ、工場の敷地内に1歳から6歳までの幼児を預けることができる幼児学校を作りました。
そこでは、読み書き、算数、地理、歴史などをできるだけ本を使わずに実体験で学ばせたといいます。
健全な学びの習慣が身につく場所。
まさに、オーウェンとロック、ルソーの想いが融合した教育施設。
やがて、彼らの子どもへの教育に対する思想が人々の注目を浴び、
子どもは「大人社会によって歪められるべきではない存在」となり、
子どもと大人が区別されるようになった、
というわけなんです。
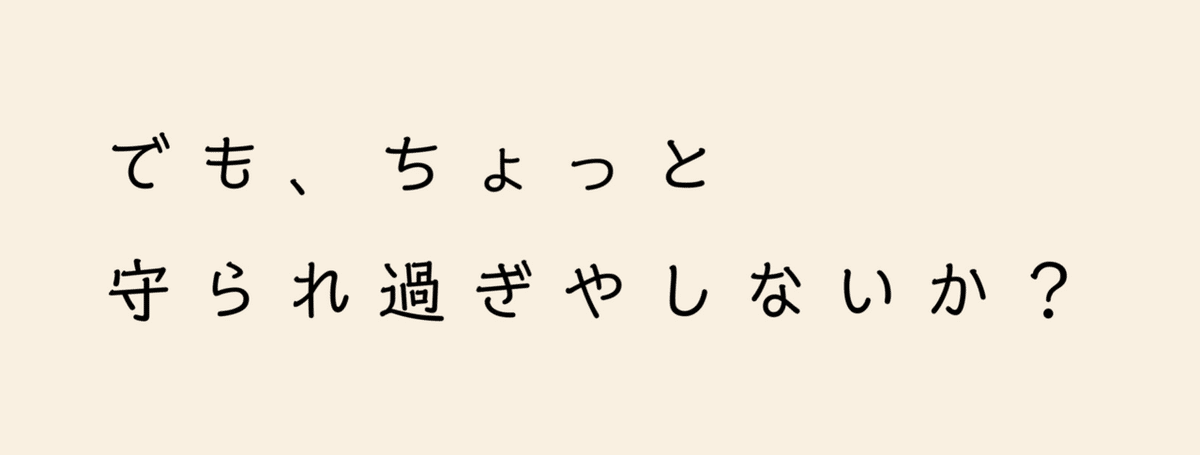
まだ非力な子どもを、悪い人から守るのは大人の役目です。
また、年齢によって、手を離すこともできなければ、目を離すことはできません。ましてや心も。
ですが特別視し過ぎて、時に
チャンスからも守ってしまってはいないだろうか、
なんて思う時があります。
以前、次男の同級生のママ(アメリカの方)と話をしていた時、しつけの話題になりました。
彼女は学校の先生をしていて、親の過干渉について話してくれました。
「過干渉をする親って、ヘリコプターペアレンツって呼ばれてるんでしょ?」
と私が言うと、彼女は
“These days, people call them bulldozer parents.”
(最近はブルドーザーペアレンツって言うのよ)
と。

ブルドーザーってあのブルドーザーです。
土砂をかき起こして、整地してくれる、あの重機です。
つまり、ブルドーザーペアレンツとは、子どもが失敗や困難により、不快な気持ちにならないよう、子どもの進路から、
まるでブルドーザーの如く障害物と判断したものを排除し、スムーズに進めるようにする、子育てのスタイルを表しています。
そんな子育て良くないでしょ。
子どもが何も学べない。
社会に適応できないかも。
そうなんです。
実際、親の過干渉や、失敗から守られた環境で育った子どもというのは、自尊心や適応能力も低くなりがちで、自分で解決する能力も低下する傾向にあるそうです。
でも、当該の親はそんな風にさせようとは微塵も思ってはいません。
むしろ逆で、親としての愛情から、子どもを悪いものから守ろうとしているだけなんです。
なんでそんな守り方になったのか。
その理由こそ、教育と雇用市場における競争の激化から守るため、とも言われています。
皮肉な事ですが、子どもがまだ、「小さな大人」として存在していた頃は、大人に紛れて一緒に働くことが日常であるがゆえ、その中で、自尊心、適応能力、自己解決能力などをきっと今よりも、身に付けていたであろうことは、何となく容易に想像できますね。
ですがだからと言って、まだ小さな子どもを働かせればいい、ということではありません。
そうではなくて、大人が子供から何もかもを守ってしまうのではなく、一歩下がって彼らの挑戦を見守る。
できるだけ手は出さない。
親として、不安だし、もどかしくなりますが、順当に言えば、親の方が先に死ぬわけです。
だから、彼らの自立を支援するのが親の役目、なんですね。

心身に危険が及ばないセーフティネットを大人が用意した上で、時に子どもを子ども扱いしないことこそ、
この不確定な時代を自分で歩めるように、
物事の良し悪しを自分で判断できるように、人を観るチカラを身につけられるように
するための、必要な守り方ではなかろうか、
と、答えを一つ見いだせた気がします。
もちろん、子育てに正解はありません。
これでいいのかな、
ああすれば良かったかな、
なんてしょっちゅう思っています。
子どもは未知の可能性のかたまり。
最近は、息子たちや彼らの友だちに教えてもらうことも色々あって、
親も親扱いされると困る時があるな、
なんて思う時があるくらいです。
大人だからって、何もかも知っているわけではないからなぁ😅
ということで、本日も最後まで読んで下さいましてありがとうございました。
あなたの1日が、素敵なものとなりますよう、シアトルから祈っております😊
しゃろん;

📚ライフログ図書
📘著:孫泰蔵「冒険の書」(日経BP)
📗著:岡本裕一朗「社会学の名著50冊が1冊でざっと学べる」(KADOKAWA)
✍️ライフログ図書とは、ライフログ読書に用いた書物にございます。ライフログ読書に関しては、以下のエッセイをご参照ください。
