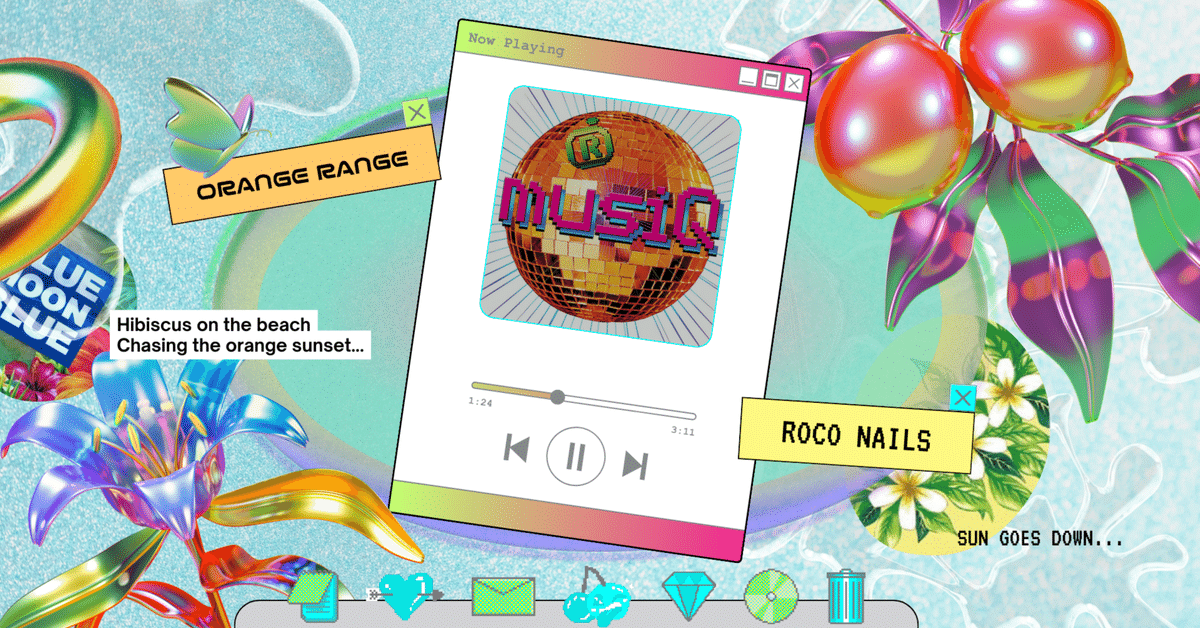
【Ep.4】 Sun goes down... 〜波打ち際のハイビスカスとORANGE RANGEの夕陽を追って〜
🔑Keywords🔑
ピチレモン/nicola(ニコラ)/サーフ系/ハイビスカス/ハイビ/プルメリア/ROCO NAILS/BLUE MOON BLUE/JUNGLE ROCO/COCO BONGO/One* way/Jassie/SUZY Q/SHIBUYA109/SHIBUYA109-②/ショッパー/ショップ袋/ANGEL BLUE /Tommy february⁶/ふたりのシーサイド/サンダーバニー/ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記/プール/家庭科/裁縫箱/裁縫セット/ORANGE RANGE/上海ハニー/ロコローション
前回の続編として、引き続きJUDY AND MARYのことを書こうと思っていたのですが、ANGEL BLUEブームに雲隠れして、重要な出来事を忘れていることに気が付きました。
小学四年生から五年生の頃、ビッグウェーブのごとく一瞬だけ訪れた「サーフ系ブランドとハイビスカスブーム」です。
自分にとっては黒歴史ですが、このブームに触れずして先には進めないため、今回の記事はハイビスカス特集とします。
-イントロダクション-
数日前、日本から届いた船便を整理していた時のことだ。
一年ほど前から趣味で始めた製本の道具一式が入った、大きな段ボール箱を開封した。
三ヶ月ぶりとはいえ、久しぶりに目にする道具たちはなんだか懐かしい感じがした。
白やベージュの落ち着いたトーンの中に、明らかに場違いな見た目をした水色のケースがある。
小学生の家庭科の授業で使っていた、ハイビスカスの柄がプリントされたプラスチックの裁縫箱である。

日常に溶け込む無言の伴走者
この裁縫箱は、かれこれ二十年近く、私の傍らにあった。
大学で上京した時も、ドイツに引っ越す時も、いつも一緒だった。
特に思い入れがあるわけではない。
ただ、コンパクトで使いやすく、ちょっとした手縫いにはもってこいなのだ。
今は、製本の際に糸で紙を綴じたり、布をまとめたりと、意外な活躍を見せている。
にもかかわらず、この裁縫箱を見ると、手に入れた当初のような高揚感は湧いてこない。
遠く離れた家族と久しぶりに再会する感覚とも少し違う。
毎朝飲む水のように、そこに在るのが当たり前な、まるで空気のような存在なのだ。
小学生の頃、ハイビスカスの花は元気で明るい女の子の象徴のような、憧れでまばゆい存在だった。
鮮やかな花びらと黄色の雄しべのコントラストはまるで夏の太陽を連想させ、見ればたちまち常夏気分を味わうことができた。
二十年も経てば、ケースの一部が色褪せたりするものだろうが、手元にあるこのハイビスカスの裁縫箱には、そうした年月をまるで感じさせない、まばゆさと鮮やかさが未だに健在している。
しかし、大人になった今、その花はただの水色のプラスチックケースに印刷された模様でしかなくなっていた。
ハイビスカスの裁縫箱はその見た目に反して、長い年月を経て私の生活にすっかり溶け込み、空気のように馴染みすぎてしまったのだ。
絶望のハイビスカス、
あるいはサンダーバニーへの憧憬
小学五年生になると、学校の授業には「家庭科」という新しい風が吹き込んできた。
それは、同時に裁縫箱という、この先何年もの生活を共にする相棒との出会いでもあった。
小学四年生の終わり頃だろうか。
自分の中のANGEL BLUEブームが終幕し、「モーニング娘。」にも「BoA」にも飽き、まだTommy february⁶には出会っていない空白の時期である。
学校では裁縫箱の注文カタログが配られ、欲しいデザインを親と相談して注文することになっていた。
色とりどりの注文カタログの中から一つの裁縫箱を決めるのに、おそらく一分も掛からなかったと思う。
心の中ではすでに意思決定がなされ、当時の私にハイビスカス以外の選択肢はありえなかった。
注文カタログの画像は見つからなかったが、「あの頃のさいほうセット」という当時の裁縫箱をミニチュアで再現した、ガチャガチャの広告画像を発見した。
ハイビスカスの他に記憶に残るものとしてもう一つ、「サンダーバニー」の裁縫箱があったが、ラインナップは概ねこの感じで合っていた。

当時の私はこのハイビスカスの裁縫箱こそが、これから始まる新しい章を彩るにふさわしいと確信していた。
ところが、小学六年生へと近付くにつれ、その確信は揺らぎ始めた。
自分のハイビスカスの裁縫箱が、急に幼稚に思えてきたのだ。
「なぜ自分はハイビスカスを選んでしまったのだろう」
私は深い絶望に襲われた。
それは、先日家で観た『ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記』(1997年)でのび太が落下する谷底くらい深い絶望と、自分に対する失望だった。

「Tommy february⁶だったら、ハイビスカスではなく絶対にサンダーバニーの方を選んだはずだ…」
学校一のお洒落さんだった友人のMちゃんは「サンダーバニー」の裁縫箱セットを選んでおり、やはり見る目が違うな…と尊敬の念を抱いたのを覚えている。

大人になり、ハイビスカスが日常に溶け込んでいる今となっては、ハイビスカスの裁縫箱を選んだことに対して、当時ほどの絶望感や後悔はない。
しかし、心の奥底では、あの時サンダーバニーを選んでいたら、自分の人生はどのように変わっていたのだろう、と考えることがある。
手に入れる運命になかった、サンダーバニーの裁縫箱。
その面影は今も幻のように、Tommy february⁶の甘い記憶と共に、私の心の片隅に居座り続けている。
ますます焼ける胸に 込み上げる I don't wanna cry
もう届かぬ夢なのに
潮風の中で何度も 幻のようにすれ違う
あなたの面影涙のシールで閉じた ふたりのシーサイド
ロコネとハイビが彩る ひと夏の思い出
当時の私がハイビスカスを絶対に譲らなかったのは、間違いなく「サーフ系ブランドブーム」の熱狂が根底にあったからだ。
以前の記事にも書いたように、小学四年生の頃の私の愛読誌は主に「ピチレモン」と「nicola(ニコラ)」だった。
ANGEL BLUEの影に雲隠れして自分でもすっかり忘れていたのだが、ANGEL BLUEにハマるのと近い時期に、「ROCO NAILS(通称:ロコネ)」や「BLUE MOON BLUE(通称:ブルムン)」、「COCO BONGO」といったサーフ系ブランドにも夢中になっていた。
つまり、ANGEL BLUEの甘い香りに包まれながら、同時に、サーフ系ブランドの爽やかな風にも吹かれていたのだ。
そして、これまでの話の伏線を回収するかのように、2003年8月号の表紙ロゴにはハイビスカスが咲いている。


いかにサーフ系ブランドが流行っていたかが分かる
中でも特に好きだったのが、「ROCO NAILS」だ。

「ROCO NAILS」のこのプルメリア柄(当時はこれもハイビスカスの一種だと勘違いしていた)を見ると、小学生の夏休みの記憶が蘇る。
当時、ブランドのショッパー(ショ袋)をサブバッグとして使うのが流行しており、私は「ROCO NAILS」のビニール素材のショッパーを、プールの水着入れとして使っていた。
ショッパーは丈夫なビニール素材でできていて、手提げ部分は細いストローのように長かった。
プールが好きだったからということもあるが、肩に掛けたそのショッパーは、まるで小さなサーフボードを抱えているようなワクワク感があった。

「ROCO NAILS」の姉妹ブランドである「JUNGLE ROCO」も、冒険心をくすぐるような魅力的なデザインだった。
ジャングルの奥深くへと誘われるような、そんなワクワク感がある。

色とりどりのフルーツが並んでいる
JUNGLE ROCOのコンパクトミラーは、何かのコンパクトミラーの上からシールを貼り付けたお手製品だった。
この柄は結構好きだったので、中学生の時も普通に使っていた。

そういえば当時の雑誌にはよく、ブランドコラボの付録がついていた。
シールや文房具、アクセサリーなど、付録を通していろんなブランドを認知することも多かった気がする。

サーフ系ブランドに加えて、「Jassie」や「SUZY Q」といった109系ブランドを好きになったのもこの頃だった。
当時の聖地、「SHIBUYA109」で買ってもらった「SUZY Q」のパーカーは私の定番アイテムで、古着のような風合いが大人っぽく気に入っていた。

サーフ系の微かな残り香
〜大きな波が打ち寄せた小さな貝殻たち〜
「ANGEL BLUEブーム」は、後に「Tommy february⁶」や 「JUDY AND MARY」といった、自分史を語る上で欠かす事のできない礎を築く功績を残したが、「サーフ系ブランドブーム」がその後の私の人生に継承したものは、おそらく何もない。
文字通り、流行のビッグウェーブに乗っかってしまった、そんな感じである。
しかし、何ももたらさなかったわけではない。
波が消え去った後も、ハイビスカス柄の裁縫箱とJUNGLE ROCOのコンパクトミラーは、私の人生の中に唯一生き残った「サーフ系ブランドブーム」の貴重な財産として、今も糸をかがり、顔面を映し出し、私の生活を支え続けている。
大きな波が打ち寄せた小さな貝殻たちは、日常の中に影を潜め、今も私の人生の中で静かに生き続けているのである。

おまけ:ORANGE RANGEブーム
ハイビスカスブームとはあまり関係のない出来事かもしれないが、この頃、私の通っていた小学校は「ORANGE RANGE」という名の熱帯暴風雨に巻き込まれていた。
ORANGE RANGEは2003年6月4日、1stシングル『キリキリマイ』でデビューした沖縄出身のロックバンドである。
7月16日に2ndシングル『上海ハニー』でブレイクすると、学校の休み時間や給食の時間はもっぱらORANGE RANGEの話題で持ちきりだった。
女子の間ではメンバーの派閥が分かれ、私は強いて言うならYAMATO派だった。
放送係の友人は毎日のようにORANGE RANGEのCDを流し、私たちは給食そっちのけで、まるで自分たちの歌であるかのように大合唱した。
それは単なる音楽の流行にとどまらない、ある種の社会現象だった。
そして、2004年12月1日。
卒業式を迎える三ヶ月前、念願の2ndアルバム『musiQ』が発売された。
中でも『花』や『ミチシルベ〜a road home〜』は感動的なバラード曲で、卒業前の不安や切なさが入り混じる当時の心にとてもよく響いた。

時が経ち、大人になった今、久しぶりに1stアルバム『1st CONTACT』を聴いてみた。
歌詞を読みながら、自然と口が動く自分にとても驚いた。
ちなみに、タイトルに記した「Sun goes down」は『落陽』の歌詞である。
この曲を聴くと、夕暮れ時、友達と遊んだ後の少し寂しいあの帰り道の情景が浮かんでくる。
『ロコローション』、『シティボーイ』、『チェスト』……今聴くと、小学生が聴くには少し刺激が強すぎる歌詞も少なくない。
それでも、私たちは何も考えず「刺激たっぷりの君へエスコートしてぇ」の一心で、そのカッコ良さに夢中になり、無心で歌っていたのだと思う。
翌年、JUDY AND MARYの音楽に出会った時、彼らのパンクロックな音楽に決して戸惑うことなく、すんなりと受け入れることができたのは、ORANGE RANGEを聴いてきた経験があったからかもしれない。
今週は久しぶりに、ORANGE RANGEの2ndアルバム『musiQ』でも聴いてみようと思う。
次回はようやく、JUDY AND MARYの続編へと進もうと思います。
スキ・コメント・フォローなどいただけますと、たいへん励みになります。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
