
【ニッポンの世界史】第13回:現在の世界史教科書のルーツ?—上原専禄と吉田悟郎『日本国民の世界史』(2/2)
一度は検定に合格したものの1958年の検定で不合格となった上原専禄らによる『高校世界史』。前回は、これを1960年に一般書として刊行した『日本国民の世界史』(岩波書店)の構成と特徴について紹介しました。

世界史教育の歴史において「現在の世界史教科書のルーツ」と位置付けられることの多い『日本国民の世界史』ですが、今回はさらにいくつかの視点から「ニッポンの世界史」に対して果たした役割を考えてみたいと思います。

〈にとって〉の世界史:「書かれざる主語」を書く
編者の一人、吉田悟郎は次のように述べています。
〈西洋の近代化〉という。一体それは何なのだろうか。一体それは〈東洋〉にとり、日本にとって、どんな意味をもっているのだろうか。〈アジア・アフリカなどの民族独立〉という。一体それは何なのだろうか。一体それは〈西洋〉にとり、世界にとり、そして日本にとって、いかなる意味があるのだろうか。
この言明の前提にあるのは、〈◯◯にとって〉の◯◯の部分が、ほんとうは「ヨーロッパ」であったにもかかわらず、巧妙に隠されていたことへの問題意識でしょう。
ほかの世界史教科書では「日本国民」は「書かれざる主語」(小川幸司「〈私たち〉の世界史へ」『岩波講座世界歴史1』2021、44頁)となっているところ、『日本国民の世界史』というタイトルは〈日本人にとって〉の世界史というポジショナリティをあえて明言したものといえます。上原らは日本国民にとって必要な世界史観を提示しようとしたわけです。
とはいえ、「日本国民にとっての世界史」だからといって、日本以外の地域の人々のことはどうでもいいというわけではありません。
インドの章末において、インドと日本の国民は課題を共有しているのだと訴えがあったように、上原らは、アジア・アフリカへの純粋な共感の意識を隠しません。
なお、インドの章の末尾には、次のようなくだりがあります。われわれはインドといえば、遠い、あまり縁のない国と思いがちである。しかし、インドの生んだ仏教思想は、日本にも深い影響を与えており、また独立後のインドが、新しいアジア諸国とともに、世界平和のために尽くそうとしているのをみると、同じ課題のもとに努力しようとしている日本人は、インドに対して深い親近感をおぼえざるをえない。(118頁)
敗戦後、昭和20年代を通して、当時の多くの国民には敗戦のもたらした「抑圧」の機制がはたらき、戦前・戦中のアジアが急速に忘却され(大澤真幸『戦後の思想空間』ちくま新書、1998)、「アジアの不在」というべき状況が生み出されていました(吉田裕『日本人の戦争観』岩波現代文庫、70頁)。
1956年にはいわゆる『経済白書』が「もはや「戦後」ではない」と宣言。東京裁判を通して対外的に最小限の戦争責任を認めてアメリカの同盟国となる一方、国内的には戦争責任を事実上不問に付す「ダブル・スタンダード」(吉田裕)のもとで、「戦記もの」の最初のブームを迎えます。
こうした一方で、1955年から1956年頃になると、戦争への協力した経験をもたない世代が戦中派への批判を強めたり、戦争責任意識を自発的に生み出す動きが起こったりするようにもなっています。
1959〜1960年の安保闘争も、日本を(アメリカとともに戦争に参加しうる)加害者として位置付けるか、(アメリカの戦争に巻き込まれうる)被害者として位置付けるかという点が、対立軸の一つでありました。中国文学者の竹内好(1910〜1977)が「近代の超克」で独特な戦争責任論を論じたのも、安保闘争が問題化した1959年のことでした。
たしかに、上原らが「ナショナル・ヒストリー」(一国史的な歴史)の枠組みを前提とし、その限界を指摘することもできるでしょう(成田龍一『方法としての史学史』岩波現代文庫、2021)。
ただいずれにせよ、日本人はまずもってアジアを視野に入れて世界史像をうちたてるべきだとした動機は、こうした同時代的な状況を文脈に置いておく必要があります(上原のアジアへの関心については、戦前の上原の関心からの連続性を指摘する議論もあります(土肥恒之『日本の西洋史学』講談社、2023)。
もう一つ、西洋近代に対する懐疑の眼差しを向けつつも、「近代化」のなりゆき自体を否定するものでなかった点も重要です。そこには西欧の普遍的価値を発展的に継承したアジアによって、ヨーロッパ的「近代」は乗り越えられるとの前提が見え隠れしていますし、その論理は高度経済成長を始動させた日本の雰囲気にもそぐうものでした。小川幸司も「そのヨーロッパ中心主義は日本のナショナリズムと共鳴しながら、現在にまで受け継がれている高校世界史の通奏低音となっている」と指摘しています(小川、上掲、44頁)。
なお、中国に対する課題な評価は「1958年からは、その成果をもとにして、第二次五カ年計画を開始し、中国歴史上いまだかつてない国民経済の全面的な躍進をとげた」とする、最終章「現代の世界」の巻末によくあらわれています。

同時代の事象に世界史的な意義を見出すのは、いまも昔も難しいことではありますが、このいささか冷静さを欠くところも含め、現代に軸足を置きながら世界史を構想しようとした執筆陣の熱気と姿勢をよみとく必要があるでしょう。
***
事実と解釈:ポパーとカー
以上の特徴を踏まえた上で、『日本国民の世界史』にはさらにいくつかの特筆すべき点があると思います。
それは、従来の世界史が客観性をよそおって「悠久な人類の歩み」(人類史)を、歴史的事実を並べ立てて記述しようとしていたのに対し、上原らが歴史的事実を「解釈する主体」の営みの能動性を重視していた点です。
"公式"世界史が掲げる世界史が、不動の歴史的事実として君臨し、大学受験にもそのまま出題され、多くの一般書にそのままの形で扱われている現状に対し、別のかたちの「歴史解釈」がありえることを示そうとしたわけです。
このことは編者の吉田悟郎がのちに「世界史学習の基本的事項・基本的内容といったものをそう容易には設定することができない」と述べていることとも関連しています。
吉田は「旧来の「基本事項」なるものを固定させることがいかに無意味なことであるか」と主張し、たとえば第一次世界大戦期の取り扱い方について次のように述べています。
いわゆる「本通り」の中心からでなく、「本通り」の裏側から、また「裏通り」から第一次大戦をとらえてみたらどういうことになるであろうか。とくに民族革命・社会革命・平和勢力の主体形成の過程として第一次大戦をとらえた場合、「帝国主義」「植民地主義」「封建制」「天皇制」「人民」「民族」といったものは具体的にはどんなものであろうか。
あるいは、授業での生徒の反応を引いて、次のようにも述べています。
たとえば、ある生徒が次のように反応する。「教科書と副読本との照合を先生に指導されてやってみると、歴史には真実が二つも三つもありうるのである!…一つの事実を見るにもその人が上から見るか下から見るか、右側からか左側からか、どの民族からか、どの世界からか、あの時代からか、この時代からか、などによって光も影も形までも全部異なってくる。…歴史とはたんなる年表ではない。事実を知ったり、おぼえることではない。その事実が及ぼした意味を見きわめ、現在の情勢とのつながりを考え、これからの世界のとるべき方向をきめる、羅針盤的なものである。だから、〈第一次世界大戦がはじまった〉ではない(吉田悟郎、20頁)。
吉田はこの後、平成に至るまで旺盛な発言を続け、同時の「世界史学」を構想し続けます。「歴史とは…羅針盤的なものである」——吉田の「世界史学」の根本は、この部分に極まるといってよいでしょう。
吉田のこの文章が刊行されたのは1965年のことですが、こうした吉田の議論を生み出す土壌として見逃せないのが、カール・ポパーの『歴史主義の貧困』(1961)とE.H.カー『歴史とは何か』(1962)の邦訳刊行です。両者ともに、歴史的事実と解釈の関係を問い直す論考で、幅広い支持を集めました。前者は2013年、後者は2022年に新訳版が刊行され、なおも読み継がれています。
このうちポパーの主張は、つまるところ「歴史の記述は科学的理論とはいえない」というものです(歴史の記述は特称命題あるいは単称命題ゆえ反証不能であり、全称命題である科学的理論ではない)。
にもかかわらずヘーゲル、コント、スペンサー、マルクス、トインビーのようになんらかの「法則」によって歴史を記述し、それに基づく未来予測なるものが横行している。この姿勢にポパーは「歴史主義」(ヒストリシズム)と名付け、その未来予測なるものには全く意味がないと主張します。
歴史法則なるものが存在しないのであれば、歴史の記述を演繹的に説明することはできません。
その代わり、歴史家が歴史史料からある「観点」に基づき事項を選択し、ある「観点」に基づき解釈するという、反証不能なアプローチをとらざるをえないことになります。
ですから、歴史学という学問は、それぞれの歴史家の「観点」に基づく営為にすぎないというわけです。ここでポパーが批判しようとしていたのは、進化主義的な歴史観や、トインビーの文明史観、あるいはマルクス主義の唯物史観でありました。
ポパーの批判から生じる帰結として、先ほどの吉田の話に登場する生徒の反応ほどふさわしい例はないように思います。
「一つの事実を見るにもその人が上から見るか下から見るか、右側からか左側からか、どの民族からか、どの世界からか、あの時代からか、この時代からか、などによって光も影も形までも全部異なってくる。」
歴史は理論ではなく「歴史解釈」であるとするポパーに対しては、当然「それじゃあなんでもありになってしまうじゃないか」という批判もありえます。
これに対しポパーはあくまで歴史解釈を、哲学者・野家啓一の言葉を用いれば「われわれが直面している現実諸困難に対する応答である」(野家啓一『歴史を哲学する』岩波現代文庫、2016、79頁)と前向きにとらえます。
事実にはそれ自体単独で意味があるのではなく、われわれ解釈する人間の意味づけに委ねられている。
歴史家の「観点」は、出来事に対応するとみなされた膨大な資料に対して選択的に働く。
ゆえに、「大きな物語」としての歴史哲学をたちあげるのは不可能だ。
これらの見方は、分析哲学や現代思想における言語論的展開の動き、アーサー・C・ダントーやヘイドン・ホワイトの物語り論の議論も相まって、1990年代に入ると歴史と物語との関係をめぐる問題へと一気に「政治化」されていくことになります。
もちろん、上原らの意識は、そのような地点にまで到達していたわけではありません。
『高校世界史』『日本国民の世界史』刊行のための勉強をおこなっていた1950年代という時代において、彼らが「歴史解釈」を全面に打ち出したのは、それほどまでにヨーロッパ中心的な "公式"世界史が、唯一の歴史的法則に裏打ちされた唯一の歴史的事実であるかのような顔をしていたからにほかなりません。
その欺瞞をあぶりだすために、あえて別様の解釈可能性をうちだし、事実に潜む西洋中心的なイデオロギーを解体しようとしたわけです。
先ほど挙げた吉田悟郎は、1921年生まれの戦中派ということもあり、権威に対する徹底的な懐疑心があったとインタビューで回想しています。旧制中学時代には社会主義的な著作に親しみ、軍国少年として少年時代を過ごしたわけではないものの、戦後従事したGHQでの検閲業務をとおして、米国が日本共産党の規定したような「解放軍」ではなかったことに気づいた経験が、公式主義や法則一般への懐疑につながったと述べています(「<インタビュー記録>歴史教育体験を聞く : 吉田悟郎先生」『歴史教育史研究』4、2006、58-85頁)。
そのことが、“公式”世界史の掲げる歴史の記述を、積極的に「相対化」(吉田はこれを「ひっくり返し」と呼びます)し、従来的な世界史を刷新しようとする思いへとつながっていったのでしょう。吉田以外の論者にも、戦中の体験がそれぞれの形で影を落としているはずです(戦中の上原と皇国史観との関わりについては土肥恒之『日本の西洋史学』講談社、2023を参照)。
ただ、「○○にとっての世界史」をつきつめてゆけばゆくほど、新たな問題も生まれます。
しかし、ポパーにならえば、歴史解釈には特定の「観点」が不可欠です。この「観点」の足場いかんによっては、歴史の基本的事項の選定も左右されてしまいます。
たとえばヨーロッパに関する用語と、東南アジアに関する用語のうち、どれをどれだけ世界史の教科書に記載するべきか。この選定にも、なんらかの「観点」は必要となります。
しかも、統一的な法則や理論を排除しようとすれば、「観点」の数だけ世界史が存在する状況を許してしまうことになる。
上原らにしてみれば、これまでの世界史が西洋中心的にすぎたのだし、日本やアジアを抜きにしすぎていたのだから、そっち側ではないアジア的な観点が必要なんだということでしょう。
しかし、それはそれで中心がアジアに移っただけになってしまわないかという問題も生まれます。それこそ「観点」は無限にあるわけですよね。
それらを日本史と世界史を統一的把握のなかで束ねるために、たとえば吉田はベトナム戦争を背景として、日本、朝鮮、中国、ベトナム四者関係を通したベトナム史学習を提案します。「一国、一国のしらみつぶしの学習、その国民史の統一的把握」をすすめるのです(吉田、上掲、1965、25頁)。前年の1964年には上原専禄が、江口朴郎とともに『岩波小辞典 世界史—西洋』を刊行され話題を呼んでおり、各国史を積み重ねていけば、多様な「観点」があらわになって、単数的な西洋史的世界史を突き崩せるのではないかとの期待もあったのでしょう。
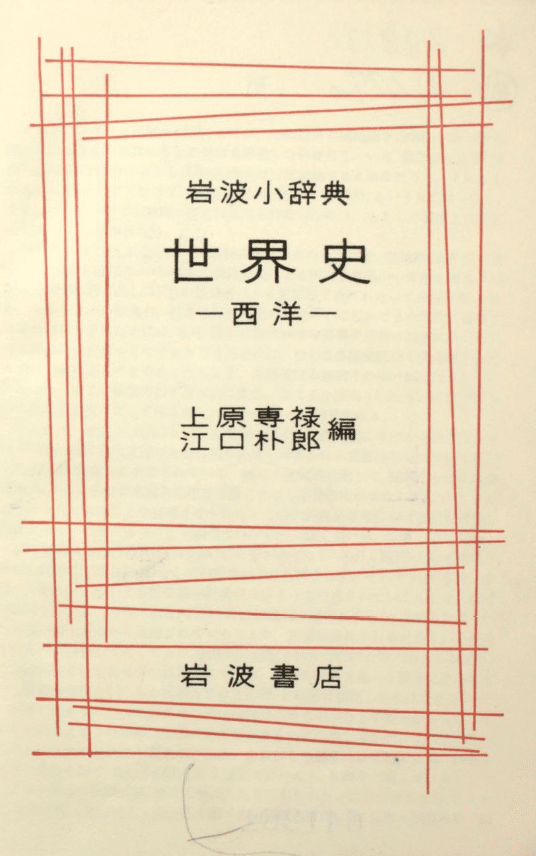
もちろん各国史をたんに記述していくだけで、その総和がそのまま体系的な「世界史」になるとは限りません。同時期に刊行されていた山川出版社の『世界各国史』に対しても、「「世界各国史」でありながら、「世界史」と「各国史」についての深い考察が欠けている」との批判もみられました(小川剛広「指導内容の重点をどこにおくか」『現代の高校教育 世界史の基本的事項と計画』12巻、明治図書出版、1965、107頁)。むろん吉田もそのことを理解した上で、有機的・全体的な各国の連関を構成しようと企図していたわけでしょうが、その連関を浮かび上がらせることもまた「解釈」にすぎないわけですから、西洋中心的ではない何が望ましい世界史か、「観点」をめぐる闘争が必然的に起きてしまう。そのような難しさを抱え込んでいたと思います。
そんな中、西洋中心主義的ではない形の法則や理論が求められることとなるのは時間の問題でした。このことはまたいずれ取り扱うこととしましょう。
『日本国民の世界史』と日本国民とのズレ
以上、上原らの『日本国民の世界史』の「ニッポンの世界史」における位置付けについて考えてきました。
『日本国民の世界史』には、羽田正のいうように、たしかにその後の世界史教科書の一つの範型をつくったといえます。ただ、このシリーズで以前から紹介してきたように、宮崎市定やトインビーのように、前近代におけるいくつかの文明圏の並列によって、ヨーロッパ中心主義をのりこえようとする先行の試みがあったことを忘れてはいけません。
その上で『日本国民の世界史』は、それら先行の試みと課題意識を共にしつつも、「日本の自主独立」と「現代アジアとの共闘」という、一見逆向きにも見える2つの動機に裏支えたものであったといえるでしょう。つまり「ニッポンの世界史」に、日本とアジアの視点を加える役目を果たしたわけです。
戦後における「愛国心」と「民主主義」、あるいは「民族」と「人民」といった用語は、現代の感覚からすると、異なるニュアンスをもつようなイメージがあるかもしれません。逆に「国家」と「民族」は、親和性が高いような気もしますね。
しかし、歴史社会学者の小熊英二の指摘するように、安保闘争における市民派知識人らの多くは当時「愛国心」を称賛し、しかもそこで称賛される「民族」には天皇や国家と対立する意味合いが込められ、民衆とか「ふつうの市民」といった意味合いがあるものでした。前近代においては民族(ドイツ人)が、建設すべき国家(ドイツ)を超えてひろがっていたドイツを研究対象としていた上原にとっても、受け入れやすい感覚であったと思われます(小熊英二『民主と愛国』新曜社、2002、265頁。なお、ドイツ中世史を出発点とする上原の念頭にあったのは、かつてナポレオン戦争に敗れた後に愛国心を鼓舞したプロイセンのフィヒテの唱えた「国民教育」でした。日教組との関係の近かった上原は、ソ連や中国ではなく、フランスやドイツをモデルに近代的個人に支えられたナショナリズム(民族の独立)を唱え、「アメリカ的」な戦後教育を批判しました。西洋化と民族主義の方向性は矛盾するようではありますが、この姿勢は当時の進歩系教育学者に共通する特徴でもありました(小熊、上掲、366頁))。
同時に、中国における中華人民共和国の建国をはじめとするアジアの第二世代は、西洋近代にならった日本の自己反省をせまり、アジアの民族への再評価をもたらします。ここにおいて、「日本の自主独立」と「現代アジアとの共闘」という、一見逆向きにも見える2つの動機が接合をみたわけです。
しかし、当時の日本国民が、果たして上原の想定するような「みな太平洋戦争の苦しさと、戦後の悩みとを深刻に経験している」日本国民であったのかといえば、かなり怪しいと言わざるをえない。ズレが広がっていたことはいなめません。
上原が冒頭に述べているように、たとえば「政治・経済・社会・文化の諸面における日本の主体性と自律性の確立、国民の生活水準の向上」は、日本国民のあり方を、着実を変えつつあったからです(『日本国民の世界史』3頁)。
むしろ、現実的にズレが広がっていたからこそ、『日本国民の世界史』の書きぶりも、歴史家・歴史教育者ら知識人による啓蒙的な書きぶりを備えざるをえなかったともいえます。
1960年代に差しかかり、日本は着実に「大国」へと変容を遂げつつありました。
(続くに)
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
