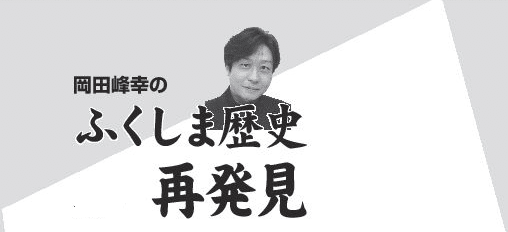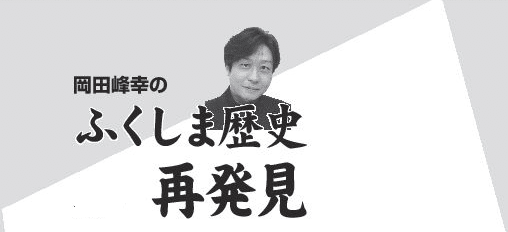南朝の国府奪還|岡田峰幸のふくしま歴史再発見 連載120
南北朝時代の西暦1347年(南朝・正平2/北朝・貞和3)秋、奥州北朝を指揮する奥州管領の吉良貞家と畠山国氏は、陸奥国から南朝勢を一掃。ところが4年後の1351年(南朝・正平6/北朝・観応2)2月、2人の奥州管領が敵対し、吉良が畠山氏を討つという内紛が発生した。この隙に南朝が息を吹き返し、出羽三山(山形県)に逃れていた南朝大将・北畠顕信が同年5月に挙兵する。とはいえ手持ちの兵が少なかった顕信は、すぐに軍事行動を起こせなかった。そのため彼は別の手を打つ。自分に代わって奥州南朝を