
ビジネスの持続的な成長にもはや必須!?『ロイヤルティ』

「ビジネスの持続的な成長にもはや必須!?『ロイヤルティ』」を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
お申込みは上の画像をクリック!
カスタマーサクセスや経営陣だけでなく、マーケティング担当・マーケターも理解が求められ始めている『ロイヤルティ(Loyalty)』。なぜ注目されるようになったか、ロイヤルティの意味や種類、可視化する指標、高めるための方法について解説しています。
■なぜ『ロイヤルティ』が注目されるようになったのか?

『ロイヤルティ』が注目されるようになったのは、社会情勢の変化が大きく影響しています。
人口減少によってマーケットの縮小が進み続け、多種・大量の商品やサービスが溢れている現代では、顧客価値を高めてロイヤルティ(企業ブランドや商品・サービスに対して持つ愛着心や信頼感)を創出することは、どの企業にとっても経営課題の一つとなっています。
そして、短期的な利益重視の経営から、長期的視点に立った「顧客価値重視」の経営へシフトすべく、奮闘する企業が増えています。
とは言っても、「短期的な利益重視の経営」からの脱却は簡単ではありません。

目先の利益を求めるがあまり、値引きによる長期契約や平日昼間の勧誘電話、サービスの複雑な解約手続きといった、「顧客が喜ばない」手法を行ってしまうこともしばしば。
確かにこれらの活動によって収益を生むケースも多くありますが、それはあくまで「短期的」なものであり、その水面下では顧客は静かに離反し、気づいた時には顧客基盤を大きく失うことになってしまいます。
そのため、「長期的な顧客価値重視の経営」へシフトし、ロイヤルティを創出しなければ、顧客から信頼された持続的な成長は見込めません。

つまり、今ではカスタマーサクセスや経営層だけでなく、マーケティング担当・マーケターも『ロイヤルティ』の理解は必須になり始めているのです。
マーケターも知っておきたい『ロイヤルティ』について解説しています。
■『ロイヤルティ』の意味とは?

◆『顧客ロイヤルティ』と『従業員ロイヤルティ』
『ロイヤルティ(Loyalty)』とは、消費者や顧客が企業ブランドや商品・サービスに対して持つ愛着心や信頼感、従業員が持つ愛社精神や忠誠心、帰属意識や組織へのコミットメントを意味しています。

日本では、CS(カスタマーサクセス)やマーケティングにおいて「顧客ロイヤルティ」と用いられ、消費者や顧客が企業や商品・サービスのブランドに対して持つ感情や行動を意味しています。
この「顧客ロイヤルティ」を高めることで、長期的な顧客との関係構築やリピートビジネス、口コミによる新規顧客獲得につながりやすくなるとされています。

一方、企業の人事部門では「従業員ロイヤルティ」と使われ、所属する従業員から企業へ向けられる忠誠といった心理や帰属意識の度合いを指します。

つまり、消費者や顧客を対象として、企業ブランドや商品・サービスに対して持つ愛着心や信頼感の度合いを『顧客ロイヤルティ』、従業員を対象として、愛社精神や忠誠心、帰属意識や組織へのコミットメントの度合いを示す『従業員ロイヤルティ』という、おおまかに2種の対象によって用いられるのが『ロイヤルティ』です。

さらに、「ロイヤルティ経営」という言葉で使われることもあります。
「ロイヤルティ経営」とは、CS(カスタマーサクセス)という部署レベルでの活動ではなく、良い意味で顧客の「期待を裏切る」ために、全社的に「ロイヤルティ」を高める活動を指します。
※混同されがちな『ロイヤリティ』との違いについては、こちらの記事をご覧ください。
■『顧客ロイヤルティ』を可視化する指標

『顧客ロイヤルティ』は顧客の感情であり、それを可能な限り正しく可視化することが、向上させるための第一歩となります。
これまで代表的な『顧客ロイヤルティ』指標は「顧客満足度(CS)」でしたが、現在では『NPS」が主流になってきています。
この『NPS(Net Promoter Score:正味推奨者指数)』は、アメリカのコンサルティング会社Bain & Company社のフレデリック・ライクヘルド 氏が中心となって開発した調査手法で、指標のシンプルさや収益相関の高さなどのメリットによって、急速に広まっています。
◆『NPS調査』とは?

顧客に対するNPS調査の具体例としては、以下のような質問が挙げられます。
「当社(の商品・サービス)を親しい友人やご家族におすすめする可能性はどのくらいありますか? 0点(絶対おすすめしない)~10点(強くおすすめする)でお答えください」
↑上記のような質問を投げかけて、9点・10点をつけた人=「推奨者(Promoter)」、7点~8点をつけた人=「中立者(Passive)」、6点以下をつけた人=「批判者(Detractor)」と定義します。
「推奨者(9点・10点をつけた人)」-「批判者(6点以下をつけた人)」=NPS、とするのが一般的とされています。
ついつい、5点前後を「中立者」と考えてしまいがちですが、NPSを調査する際には思っているよりも「厳しめ」に定義することがポイントになります。
◆『NPS』に当てはまらない企業・事業があることに注意!

顧客ロイヤルティを測る指標として主流になりつつある『NPS』ですが、すべての企業に当てはまる指標ではないということに留意する必要があります。
自社のビジネスや顧客の特性を勘案し、自社に合ったロイヤルティを測る指標を見定め、顧客の「感情」を測り続け、現状と変化を可視化することで活動の是非を判断し、必要に応じて改善を加えるという『PDCAサイクル』の発想で取り組むことが求められます。

そして、ロイヤルティ指標の向上に経営者がコミットすることで企業全体での共通認識となり、会社として目指すべき『ベクトル』が揃うという、文化醸成にも貢献するようになります。
■士気や業務成果に大きく影響する『従業員ロイヤルティ』

従業員を対象として、愛社精神や忠誠心、帰属意識や組織へのコミットメントの度合いを示す『従業員ロイヤルティ』。
この『従業員ロイヤルティ』が低下すると、従業員や社員の士気も下がり、業務成果が出にくくなってしまいます。

反対に高まれば、生産性の向上や離職率が低下(定着率が向上)する可能性が高まり、その結果として顧客満足度や企業・商品・サービスブランドも高まることにつながります。
『従業員ロイヤルティ』を高めることによる、具体的なメリットは以下の通りです。
◆『従業員ロイヤルティ』が高まることによるメリット

離職率が低下する:『従業員ロイヤルティ』が高まれば、所属する組織に対して愛着を持つようになるため、離職率が低下し、平均勤続年数が長くなります。
長期的な人材育成が可能になる:離職率が低下し平均勤続年数が長くなるので、経営陣は離職リスクの懸念が減り、長期的なキャリア形成プランを立てやすくなります。
人材確保が容易に:ロイヤルティが高まれば職場の士気も高まるため、それが求職者にとって魅力的な風土となり、新たな人材が集まりやすくなります。
組織のイメージが向上:『従業員ロイヤルティ』の高い従業員・社員は、自社や取り扱う商品・サービスに強い愛着を持つようになるため、自主的に社外へアピールする可能性が高まります。
顧客満足度アップにつながる:ロイヤルティが高まれば、自社の顧客への対応や商品・サービスといった価値提供の『質』を高めるようになり、結果的に顧客満足度がアップすることに。
リファラル採用をしやすくなる:自社への愛着が高まると商品やサービスだけでなく「自社で働くこと」を推奨するようになるため、知人や友人へ自社を紹介する「リファラル採用」が活発になります(※)。
このように、『従業員ロイヤルティ』が高まると、取り扱う商品やサービス・顧客対応の質にも影響を与えるため、従業員だけでなく自社の新規採用や顧客にもメリットをもたらすことにつながります。

※確かに「リファラル採用」は、自社とのマッチング精度が高くなり、採用コストを削減できるといったメリットがありますが、特に企業規模の小さいベンチャー企業へ入社しようとする側には注意が必要になります。
なぜなら、リファラル採用として声掛けする側は「少人数のベンチャーでみんな仲が良い」「働き方が自由」「インセンティブ制度が充実している」など、どうしても良い点を伝えがちです。
ですが、それらは逆に言えば「コミュニケーションが濃密すぎる」「社内の勤務体制・ルールが定まっていない」「基本給が低い」という可能性があるからです。
紹介される際の「良い点」だけを鵜呑みにして入社を決めるのではなく、同規模の他社の求人情報を調べて比較してみたりヒアリングして曖昧な点を無くすなど、慎重に判断することが必要になります。
↓
この続きでは、『ロイヤルティ』を高める方法について解説しています。
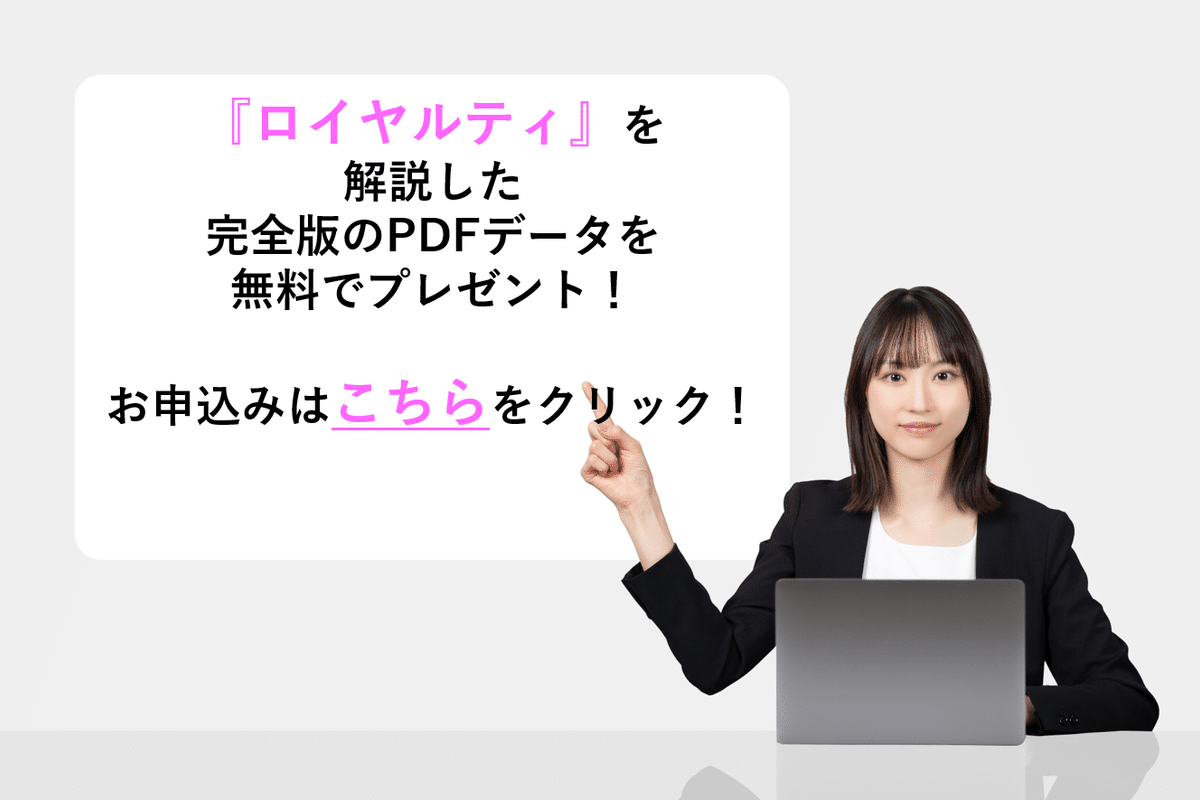
『ロイヤルティ』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
お申込みは上の画像をクリック!

株式会社SBSマーケティングでは、中小規模企業様、個人事業主・フリーランス様向けに集客や販売促進、マーケティングに関連したコンサルティングサービスをご提供しております。

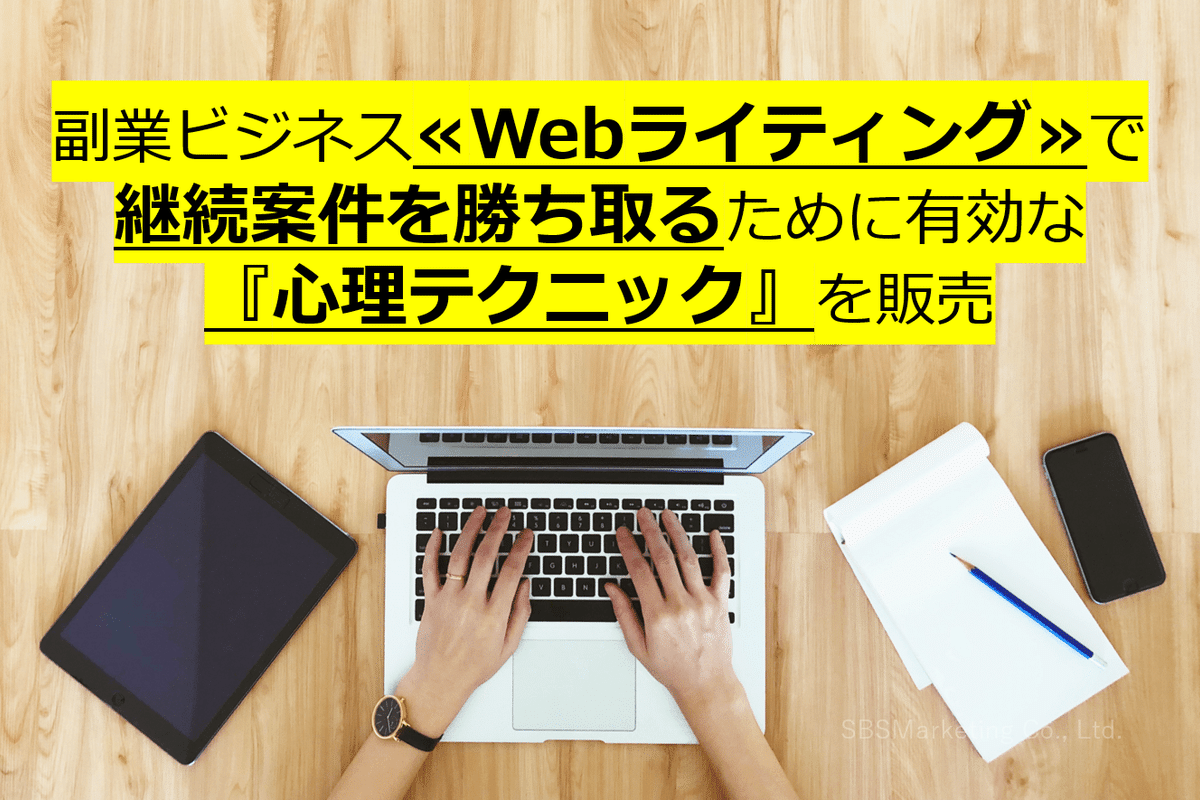
『心理テクニック』を販売中!
■中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
■個人事業主様・フリーランス様向けサービスはこちら
ご興味ありましたら、まずはお問い合わせください。

BtoBマーケターより。
