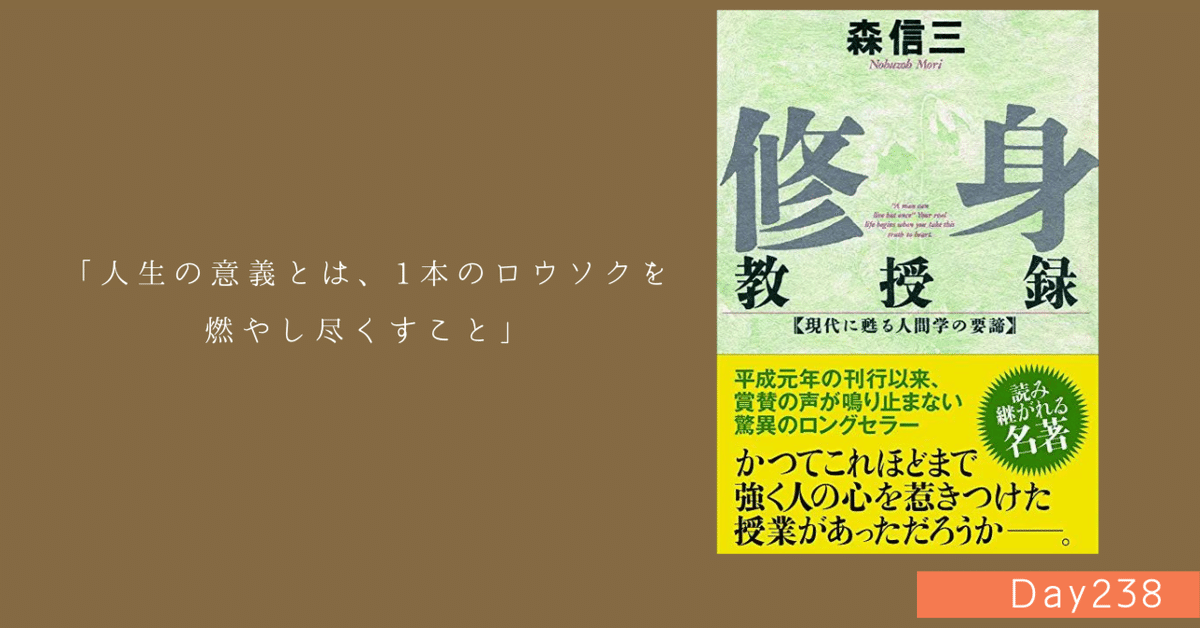
Day 238:『修身教授録』
【本について】
タイトル:修身 教授録
著者:森信三 出版社:到知出版社
Q 人生の意義とは?
A 自分自身、自分の人生について深く知ること
”1本のロウソクを燃やし尽くすこと”
”二度とない人生を全うすること” 無上の喜びを感じながら 人間として生を受けたことに幸せを感じながら
真の人生は志学にはじまる
【WHY】
物事というのは、根本眼目を明らかにしない限り、いかに骨を折ってみても結局、真の効果は上がらない。
【WHAT】
生涯通して学び続けること『修身』
Q何のために学問を?
A 人となる道を明らかにするため
(自分というものを超えた何者かに自己を捧げる気持ちでなければならない)
【HOW】(手段)
読書
Qなぜ読書が大事なのか?
A人間は、読書によって物事の道理を知らないと、真の力は出にくい。
・道理というのは、ひとりその事のみでなく、外の事柄にも通じるもの。
・学問・修養は、読書を抜きにして考えられない。
なぜなら、読書は「心の食べ物」だから。
・読書は、生活の中で最も重要なものである。
・読書によって、必然に偉大な先人たちの歩んだ足跡を辿って、その苦心の跡を探ってみること以外に、その道のないことを知るのが常。
・人間の生活は、読書がその半ばを占むべき読書に費やし、残りの半分は、知り得たところを実践して、それを現実の上に実現していくこと。
『1日読まざれば、1日衰える』
問い:今日は、心の食べ物として、何をとったか?
読書は必要が起こってからはじめたのでは、手遅れ。真の力は得られない。
【響いたメッセージ】
■教育とは、1人の人間の魂を目覚めさすこと
■教育とは、人を植える道(内面より発する心の先を照らす)
ー学校教育は種まき
■真に優れた師は、共に道を歩む
■物事の持続が困難なのは、結局真の目標をはっきり掴んでいないから
■真の確信無くしては、現実の処断を明確に断行することはできない
■偉大な実践家は大いなる読書家である
■将来、ひとかどの人間になろうとしたら、単に学校の教科書だけを勉強していて、それで事すむような姑息低調な考え方でいてはいけない
■何ら自発的な読書をしないということは、すでに心にすが入りかけているということ
■人間の価値は、その人が、この二度とない人生の意義をいかほどまで自覚するか、その近くの深さに比例
■人間は、その外面をつきやぶり、内側に無限の世界を開いて行ってこそ、真に優れた人である
■40になってはじめて人生に対して愛惜の念を起こしているようでは手遅れ
■結局最後は、「世のために」というところがなくては、真の意味で志とは言い難い
■内なる情熱が枯れた時、その進行は止まる(感激や感動ができる間は、まだその魂が死んでいない証拠)
■自分は一歩も踏み出さず、すでに自らを断念する人の言葉→「どうせ」
■真に自己をつくるのは自分以外にない
自己を鍛え、自分というものを一個の人格にまで築き上げていくのは、自己以外にない
■爵の尊さを知って、徳の尊さを知らないものは、その愚かなことを言うまでもないが、徳の尊さを知って齢の尊ぶべきことを知らないものは、未だ真の人物とは言い難いー吉田松蔭
■人間、50を過ぎてから、自分の余生の送り方について迷っているようでは、悲惨
【学び】
■人間というのはただ将来のことばかり考え、そのために現在を疎かにする
■鉄砲は、引き金をひかないということには弾丸は絶対に出ない
■人生は二度なし
■慎独
■一時に没入「一時一事」(今日1日というのは、今日1日に限られている)
■深く考え抜くこと(人生の真の意義は、その長さではなく深さにある)
”朝に道を聞かば、夕に死すとも可なり”ー孔子
■道理を知った上での実行というものは、その実行によって会得した趣を、他の人々にわけ伝えることもできる
学問というのは、ただ実行という土の上に立って、初めてその意義を持つ
■ただ与えられたものをぼーっと受け取っているだけでなく、人生の意義を、人として生まれた意味を意識し、幸せを噛み締めながら人生を全うすること
【アクション】
本の学び、その日のうちに実行
