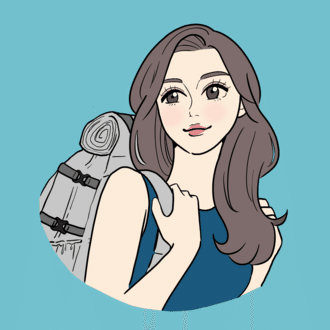【勉強が続かないのは、あなたのせいじゃない】脳科学で毎日の勉強に革命を。
昔から勉強だけは得意だと思えた。
むしろ不器用すぎて、他のことが全くできなくて、唯一、周りより少しだけできた勉強を必死に伸ばしたというかんじだ。
シャトルランは学年ドベを叩き出すわたしにとっては、体育は毎回公開処刑。
美術の授業で作った粘土の作品は、「なにこれ?ドッグフード?」と言われるほどの不器用さ。
手足や身体は思い通りに動いてくれないけど、頭の中では、わたしはとっても自由だった。
勉強だけは、かけた時間だけ、わたしに誠実だったのだ。
そして時は流れ、わたしは社会人になった。
もはやなにかを勉強することは、生涯のライフワークになっていた。
....はずだったんだけど。
さいきんちょっとおかしい。
社会人になって毎日働いているから、時間の捻出は命がけ。
それなのに、せっかく勉強の時間を確保できて「よっしゃあ、勉強できるぞ!」と意気込んでも、座り続けていると無性に尻がむずむずする。
教科書の中も文字が全然頭に入ってこない。文字が脳を泳いでいく。
年齢なのだろうか。
というか働きながら難解な勉強もするなんで無理ゲーなんじゃなかろうか。
「働きながら合格しました!」なんで触れ文句は、選ばれし人間だけなんじゃないか。
悶々としながら、それでも仕方なく勉強をする日々。
そんな中、ある本に出会った。
その本に出会い、わたしは勉強との向き合い方を「社会人」としてアップデートすることに成功した。
さらに学生時代に自分が実践していた勉強法の効果のエビデンスも発見し、「あのときの自分は合ってたんだ」と感動し、人生の伏線回収するような瞬間があった。
▼そんな運命的な本、わたしのファム・ファタルはこちら。
著者は東大卒で脳科学者の中野信子さん。
脳の仕組みを理解・利用することで集中力や記憶力、判断力…果てにはモテ力までコントロールしちゃおうぜという内容だ。
「脳科学」と「勉強」
一見結びつかないようなこの2つのテーマを掛け合わせることで、異常な化学反応が起きる。
脳を騙す工夫を勉強法に散りばめると、勉強が継続できるし、結果も出やすい。
この本を踏まえて、学生時代の勉強法を振り返り、さらに大人になった今のアップデートした勉強法を紹介していきます。
・勉強したいけど、やる気がついてこない。
・毎日仕事があって、勉強が疲れてできない。
・最近、年齢のせいかもの覚えが悪くて…。
こういう悩み、脳科学を毎日の勉強に応用することでずっと楽になる。
「自分なんかやっぱり何やっても続かないダメ人間だ・・・」
と思うのはまだ早い。
だってそれはあなたのせいじゃなくて、脳の仕組みのせいなのだから。
人間は集中できない生き物
歯みがきしないとソワソワする人は多い。
歯がむずむずするし、口臭も気になるし、歯が磨きたくてたまらない。
歯みがきは毎日するものだ。
勉強も歯みがきのように習慣化してしまえば、しないではいられなくなる。
とまあ、ここまではよく聞く話だ。
いやね、習慣化とよく聞くけど、じゃあどうやってやるの?
そもそも勉強できる人が習慣化できるんでしょ?
こうぼやいてた人を一体何人見てきただろう。
まあ、とりあえず机に向かいペンを握ろうよ。
座ると尻がむずむずする
どうしても教科書の文字を見ていられない……
気持ちはわかる。すごく。
さっきまで座っていたソファにもどって、スマホでエックスをチェックしたり、部屋が散らかってるなあ、掃除したいなあって急に思い始めた頃合いのはず。
大丈夫。あなたは決して集中力がないわけじゃない。
人間はそもそも集中が苦手なのだから。
もしここがアフリカのサバンナならば、なにかに集中していたら敵に狙われていても気づけなくて死んでしまう。その本能が残っているのでヒトは簡単には集中できないのだ。
さらに脳には「続けようとする」性質がある。
たとえば、ソファでダラダラしていたら、脳がダラダラを続けてしまおうとする。新しいことを始めるのを脳が嫌がっているのだ。
だからあなたはさっきまていたソファに戻りたくなって、「勉強していなかった状態」に戻ろうとするのだ。
ということはだ、
「机に向かって、教科書を開き、勉強をする」
を物理的にも続けていると、今度は脳がこの状態を継続しようと動き始める。そしていわゆる「集中」状態に入ることができる。
やる気があるから勉強できるのではない。
勉強しているとやる気はあとからついてくる。
この感覚をよくあるド根性論で言われるのと、「脳科学的に~」と根拠があって言われるのとでは、全然納得感がちがう。
「書いて、見て、聞いて」五感で学ぶ
「五感で学ぶ」って「パスタを五感で味わう」と違うんですけど?
って突っ込みが入りそうなんだけど、
見て
聞いて
話して
触って
いろんな感覚を駆使したほうが覚えやすい。
「あなたの脳のしつけ方」Lesson 2 「記憶力のしつけ方」では、人間の記憶方法には「意味記憶」と「エピソード記憶」の2種類あるという。
意味記憶は文字や数字の羅列を記憶すること。
エピソード記憶は経験したことについての記憶を指す。
意味記憶はエピソード記憶よりも忘れやすく、さらに記憶力のピークは若いときだ。
我々、大人は絶対にエピソード記憶で物事を覚えるようにしたほうがいい。
本ではエピソード記憶に変換して覚えるテクニックとして「五感」を駆使して覚える方法を提案している。
これは学生の時にわたしも実践していたテクニックだったので、東大卒で脳科学者である中野信子先生に根拠づけられると脳内でマツケンサンバが流れた(訳:死ぬほどうれしかった)
今回は日々の勉強に取り入れやすく、わたしも実際にやっていた「見る」「聞く」「話す」の方法を紹介していく。
ちょっと脱線するけど、マンガ「左利きのエレン」でおもしろいことが書いてあった。
「自分の集中スイッチをオンにする方法」を設定するというエピソードだ。
たとえば、野球選手だったら、ピッチに入る前にかならず同じ仕草をする選手が多い。
「この動作をする」→「集中」という動線を自分の中であらかじめ設定してあるからだ。
野球の選手は、バッターボックスに入った瞬間に極限の集中状態を求められる。だからすぐに集中状態に入れるようにマインドセットをしておく。
これを応用して、たとえばテスト前に「ハッカ」を嗅ぐと習慣づければ、集中スイッチのONが可能になるのかもしれない。
マンガ「左利きのエレン」は努力・才能がテーマのマンガ(勝手にそう思っている)で、読むと冷めきっていたハートに火が付く。自分を鼓舞したい方は必読の一冊だ。
作者のかっぴー先生はnoteをやっていて、毎月500円で読み放題サブスク販売されている。まさに出血大サービス中。
さて、本題に戻ります。
■「見る」
何回覚えたと思っても、なかなか覚えられないことってある。そんなときは、いろんなやり方で覚えようとするのがいい。
たとえば、「イラストを描く。」
イラストは自己流でどんなイラストでもいい。どう書こうかな~と書く対象について想いを巡らせることが、すでに記憶スイッチを作動させているのだから。
複雑な英単語もイラストを描いてみるといい。
たとえば、「simultaneously」(意味:同時に)(高校生が一番覚えにくい単語1位らしい)は広告のポップのように書いてみる。
■「聞く」
音読をすると「聞く」と「話す」は同時にできる。
英単語や歴史用語はもちろん、教科書も黙読ではなく、とにかく口に出す。
もはや大きい独り言でいい。
たとえば、
「参勤交代」と単語を書く問題を解くときは、
「参勤交代は、豪族を江戸に定期的に集めることで、豪族の力が強まることを防ぎ....」と制度の内容を口に出してみたり。
「家康、こんな制度思いつくなんてすっげー!」と驚嘆してみたり。
黙々とではなく、あえて話すように、心を動かすように、勉強をする。
感情がともなうと、脳が、これは「生きるために必要な情報だ」と判断して記憶に定着しやすくなるのです。
■「話す」
話すのは家族や友人に話すのも効果的だ。
勉強する中で、おもしろいなと思ったことはどんどん周りの人に話す。そうすると経験として記憶される。
「人に話す」行為にはさらに良いことがある。
話していて、繋がりがよくわからなかったり、矛盾点があると「それ、どういうこと?」って相手から突っ込みが入ることがある。
そこが自分でもよくわかっていない、ウィークポイントだと気づくことができる。
学んでいるテーマで自分の日常を埋め尽くす
これはわたしの編み出した勉強法なのだけど、考え方は脳科学と矛盾しないんじゃないかと思う。
そのときに学んでいるもので、自分の世界を埋め尽くすいうものだ。
脳にとっても、普段見慣れているものになってしまうと、頭に入りやすいんじゃないかと思って、実践している。
たとえば、絶対に覚えたいというややこしい言葉や理論、公式は、スマホの待ち受けにする。
トイレや冷蔵庫に貼る。
息抜きに見るドラマや漫画やなるべくもその関連したものにする。
たとえば、歴史を勉強しているなら歴史もの。法律を勉強しているなら裁判や弁護士もの。
あとNetflixで見られるドキュメンタリージャンルもクオリティが高いので、おすすめ。
この勉強法では、そこにある、ということを「普通」の状態にする。ということを目標にしている。
さらにいろんな角度から学ぶと、飽きないし、おもしろい。
極まることで「夢中」になれるのがベストだ。
いったん勉強が楽しい!と「夢中」になったら、もうあなたの勝ちだ。
「夢中」が最強で、夢中のときの脳がいちばん覚えがいい。まさにマリオのスター状態(スターを持っている間のマリオはどんな攻撃を食らっても無敵)
ただ勉強したいだけなのに、回りくどいなあって?
ただ勉強するより、「楽しく」「効率的」に勉強をしたい。
料理もただ洗って焼いて炒めた野菜より、しっかり水気を切って、野菜それぞれに合った切り方と炒め方をした野菜炒めのほうがおいしい。
復習すると記憶の定着率が3~4倍変わる
わたしの勉強は復習から始まる。
1週間前から今日まで学んだことすべてが復習対象になるから、毎日の学習自体は遅々として進まない。
それでも1日の勉強時間の中で、復習にウェイトを置くようにしたら、大学受験の模試の結果が飛躍的によくなった。
復習はそんなに集中する必要がないので、やる気がないときでも始められ、勉強を続けているうちにだんだんとやる気と集中力が出てくる(※一つ目の小見出しで書いたとおり)ので、ウォーミングアップ的な意味でもおすすめだ。
中野信子さんも復習の大切さには触れている。
「覚えていたことが、いざというときに出てこない」
この現象はだれもが遭遇したことがあると思う。
「これが……加齢………?!」ではなく、中野信子さんはこう教えてくれる。
脳の記憶を保管するデータベースを「箱」にたとえるなら、箱の中身がたくさんになってしまったことによって、いざ中身を引っ張り出そうにも見つかりにくくなっている状態です。
これを払しょくするには、なるべくふだんからよく検索にかけておくことに尽きるのです。その記憶と結びついている紐を、しょっちゅう引っ張ることで強化するイメージです。
というわけで、1にも2にも復習が大切。
ある実験によると、一度学習しただけの場合と、学習した後に3回復習した場合では、記憶の定着率が3~4倍も違うという結果が出ている。
働く大人はいつ時間を確保する
では、働きながら具体的にいつ勉強するか。
これもやっぱり脳を味方に決めていきたい。
当時は平日で最低3時間は勉強時間を確保するを目標にしていた。
実は1日の中で「判断ができる回数」には制限がある。
だから朝は頭のリソースを使うもの、理解に時間がかかるものに時間を費やす。仕事を始める前に、まずは1時間を確保する。
昼休憩や日中の隙間時間をかき集めて、もう1時間は暗記。なので参考書や教科書は常に持ち歩いていると良い。
仕事終わりで疲れている夜は、最後に1時間だけ頑張ると決めて、時間を測る。
時間を測るので、過去問や模試を解く時間にしていた。
こうすると3時間は想像していたよりも楽に確保できる。
時間の確保は「できたらする」ではなく、「このタイミングでする」と行動すると意外と確保できる。
おわりに
知性が感じられてストイックな田中みなみさんが好きなので、彼女がMCを務める「グータンヌーボ2」というバラエティ番組を欠かさず見ていた。
そこに中野信子さんが(脳科学者)という「グータンヌーボ2」にはおよそ似合わない肩書で出演されていた。
美しいけれど、発言が浮世離れしていて、ちぐはぐな印象を抱いた。
普段はテレビも見ないし、番組の出演者(おもにモデルや女優)に興味をもつことはないのだけれど、めずらしく調べてみると「なにこのひと、オモシロイ・・・・・」。
気づけば、勉強そっちのけで著作を5冊ほど読んでいた。
勉強したい気持ちはあるのに、うまく行かないと「自分ってダメだな………」と自己肯定感が下がって、情けないと思うことがよくあった(勉強しようとしてる気持ちがすでに偉いのに)。
でも脳科学の知識を身につけた今では、やる気がうまく出ないときは
「やる気無い ならば出そうか いざ脳だまし」(字余り)な精神で脳にアプローチするというやり方を試すようになった。
やる気が出ないとき、覚えが悪いときはだいたい
「あ、これは脳のせいかもしれない!?」
と都合良く脳のせいにするようにしたら、自己肯定感が無闇に下がらなくなったので、メンタル的な意味でも脳科学はおすすめです。
▼めちゃ読みやすい。日常生活に取り入れると人生が変わっていく気がする。
いいなと思ったら応援しよう!