
【ミステリーレビュー】黒いトランク/鮎川哲也(1956)
黒いトランク/鮎川哲也
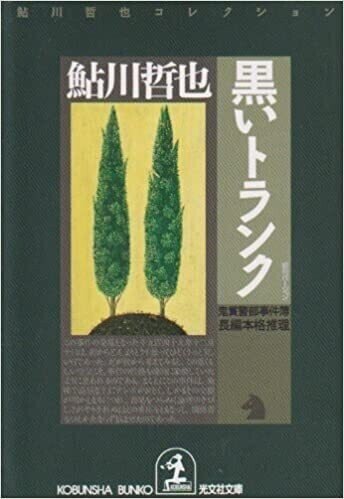
1949年の日本を舞台にした、鮎川哲也による本格ミステリー。
戦後における本格ミステリーの傑作と名高い、鬼貫警部シリーズの代表作。
読んだのは、2002年に初刊当時の形で復刻、文庫化したもの。
なかなか戦後の古典ミステリーを読み返す機会もなかったのだが、たまたま出張が重なったので、移動中の読書にと、これを選ぶことにした。
あまり鮎川作品に触れたことがなかったので、これが時代特有のものか、彼の文体によるものかは判別できないものの、当時の文化、流行がリアルタイムとして描かれていることもあり、さすがにすらすら読むとはいかない。
ただし、じっくり腰を据えて読んでみると、アリバイ崩し1本でこうも読ませるかという緻密な論理パズルが展開されていた。
複雑な事象を紐解いていく、正当派の本格ミステリーを好む読者であれば、鬼貫警部と一緒に右往左往しながら、ひとつずつ真実が明らかになっていく過程を楽しめるだろう。
鉄道ミステリーの要素もあって、食わず嫌いも出てきそうだが、肝となるのはトランクの移動トリック。
時刻表とにらめっこするのは早々に諦めたとしても、最後の謎に挑戦する権利は十分に与えられる。
色々な意味で難解ではあるのだが、ポイントごとに鬼貫警部が頭の整理をしてくれるので、ページを行ったり来たりしなくても置いてきぼりにならないのもありがたかった。
リアリティを重視してしまえば突っ込みどころは多いのかもしれないが、それもまた、古典ミステリー特有の味わいである。
【注意】ここから、ネタバレ強め。
業務日誌の彼がアイスキャンディ食べすぎ問題については、小ネタということになるのだろうか。
登場人物が少ないのもあるが、キャラクターはみな個性的。
特にふたりの容疑者は、イニシャルには遊び心が見られ、人物像も明確だ。
被害者も容疑者も、みんな同期という鬼貫警部の巻き込まれ体質は、既に名探偵の風格。
刑事という職業設定があるのなら、関係者と接点がなくても物語は作れそうなところだが、あえて刑事としてではなく、ひとりの人間としての鬼貫警部を描ききった印象だった。
結局、真犯人は真相がすべて暴かれる前に自殺してしまう。
現代ミステリーであれば、ここから更にどんでん返し、となるところだが、そこから改めて登場人物の人間ドラマが語られて、人情ものっぽく終わっていくのは、いかにも日本の古典ミステリーと言えるだろう。
動機についても、戦後間もなくだからこそ成り立つもので、半世紀経った今となっては、もはや理解に苦しむレベルになってしまった。
そういう古臭さはどうしても感じてしまうものの、トリックの鮮やかさについては、源流だからこその純度。
結果的にではあるが、この時代だからこその設定が活きていて、色褪せていない。
なお、本作はクロフツの「樽」の影響を受けているらしい。
名作を読めば、そのルーツになった作品も読んでみたいと思うのだが、時間が足りないのだよな。
鬼貫警部のその後も気になるし、こうやって読みたい作品が無限に増えていくのである。
