
#53 分析と演奏⑤/ 楽曲を横(モチーフ・メロディ)と縦(ハーモニー、拍)の両面から掘り下げて演奏するポイント
今日のnoteは、曲を「ヨコ」と「タテ」の両側面から掘り下げていく、というお話です。
楽曲を分析したり研究したりする段階で、
「ヨコ」…メロディ、モチーフの形、旋律音程、フレーズの長さ、音の長さ(リズム)など
「タテ」…ハーモニー、縦の調和、音域、声部、拍点など
の両面とも最重要であり、欠かすことができません。
ところが、場合によっては
「メロディを歌うのは得意だけど、タテの意識が甘い」
「テンポに乗って気持ちよく弾いてるつもりだけど、ヨコに聴けていない、歌えていない」
というふうにどちらかに偏ってしまうこともよくあります。
そこでこの note では、具体的にヨコとタテの両面から楽譜を読んで、それを構築していく練習の一例をご紹介します。
※ヨコとタテと単純に分けることは本来はできませんし、どの要素も、タテヨコナナメ、時間空間、あらゆる世界観で成り立っています。ここでは「ザックリわかりやすく」お話しています。ご了承ください。
おもにバッハの平均律、最後に少しだけショパンのエチュードも例にあげています。
平均律は、第2巻2番のプレリュードです。

前半のテキスト部分はオンラインレッスンサロン会員の方以外もご覧いただけますので、あなたの練習のお供にぜひ一度ご覧ください。
★オンラインレッスンサロン会員の方は、計20分の動画だけでも内容がわかるようになっていますので、動画だけご覧頂いても大丈夫です!
【このnoteのポイント】
・音楽をヨコにとらえるポイント
・音楽をタテにとらえるポイント
・ヨコとタテを立体的に構築していく
・その他
【こんなお悩みに】
・歌うのは好きだけど、立体感や構成感が出ないという人に
・雰囲気で弾いちゃう人に
・カッチリ弾けるけど、流れないという人に
・アナリーゼって?理屈はわかるけど曲での実践方法がわからないという人に
【このnoteの構成】
・テキスト
・動画解説・演奏(10分 / 7分 / 2分半の動画)
※動画は vimeo のプライベートリンクを共有しています。
【例に取り上げている曲】
・J.S.バッハ:平均律第2巻 第2番より プレリュード
・ショパン:エチュード Op.10-4
ヨコを意識してみよう!

ヨコ=旋律的、タテ=和声的、ということもできますね(あくまで大まかに)。
まず、ヨコの1番大きな要素は、「歌う」こと。
また、1声のモチーフを取り出して分析していくことも要素のひとつです。
いくつかの要素をピックアップしてみます。
・歌心があること
・音の伸びや響きを聴き続けること
・音価を大事に保つこと
・スルスル…となめらかに流れること
・モチーフの形や音程を見ること
・フレーズの単位、ブレスポイントを考えること
などなど…
練習方法の一例としては、
・片手練習
・1声ずつ練習
・実際に歌ってみる
・スーッと息を繋げるように歌う、弾く
などが一例として挙げられます。
動画では、バッハの平均律のプレリュードの中で片手練習をしながら楽譜の一部を掘り下げて見ていきます。
※実際は、ヨコを見ながらもタテを意識しないと本来の表現や音色は見つかりません。例…和声を理解しながら旋律の各音の色や進行を考えてみる、など。
あくまでここでは、ザックリとしたお話です。
_____
★関連★
旋律の音程を見ていく過程について取り上げている、別の記事です。
________________
タテを意識してみよう!
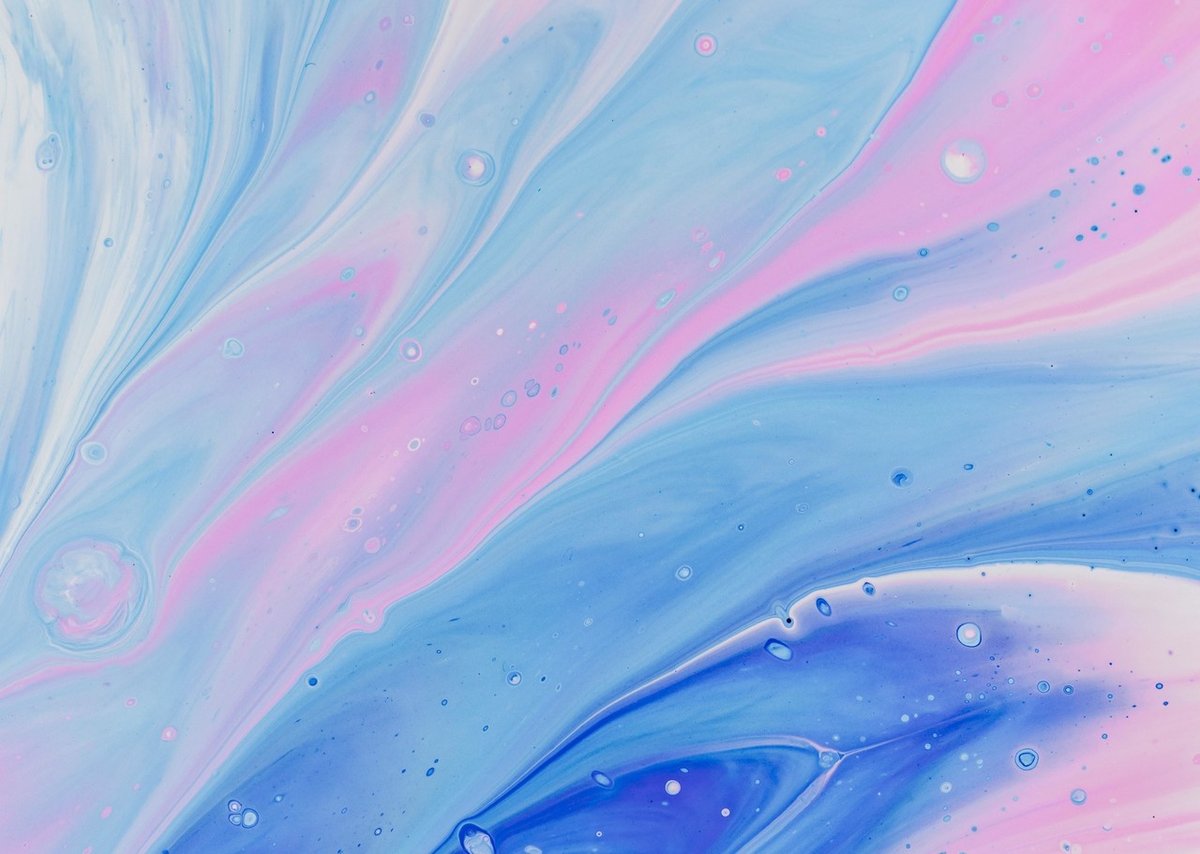
では次は、タテの要素にとくに注目してみましょう。
こちらもいろんな要素がありますね。
・右手と左手の合わさる点とその関係性
・音程、和声の調和
・平行、反行など各ラインの関係性
・和声進行
・カデンツの存在
・拍子感
・音域や声部それぞれの特徴や響き
などなど…
練習のポイントとしては、
両手での練習やポイント練習。
地道な分析。
立ち止まり、バランスや響きを聴くことも大事です。
そこでイメージや計画が得られたら、また片手や一部分の練習に戻すのもひとつですし、その先として、ヨコとタテを分けて考えずに、空気感や空間も含めて総体的に感じ、描いていくこともできます。
_____
★関連★
和声を見ながら曲を理解していくプロセスの一例です。
_____
ここまでの内容を動画で実演&解説します(計20分)
音楽の三要素=リズム、メロディ、ハーモニー ですが、そのトライアングルのバランスが極端に崩れると良くないです。(曲自身が何か特別なバランスを持つ場合をのぞく)
ではなにかのきっかけで、そのことに気づいたとき、どうすれば良いでしょうか?
ここからは実際にバッハの曲を通して、ヨコ、タテ、それぞれのアプローチで順に曲を分析していき、演奏に実際に反映させていくプロセスを動画にしました。
ひとつのアプローチ方法として、ご参考にしていただけると幸いです。
おもな曲は平均律第2巻の、第2番プレリュードです。

最後の動画では、ショパンの練習曲 op.10-4 も例に挙げています。
偏りのあるときに、ご参考にしていただければと思います!
動画①バッハ平均律第2巻2番プレリュードをヨコに見ていく。モチーフ分析や演奏の考察(約10分)
ここから先は

さいりえのオンラインレッスンサロン
ピアニストさいりえによるオンライン講座&小さなコミュニティ。 ピアノ練習やレッスンのポイント、さいりえ自身の練習内容やブログで書かない話…
ここまでお読みいただきありがとうございます!ときどき頂戴するサポートは主に書籍・楽譜の購入・もしくはカフェ時間にありがたく使用させていただいています。もし「とくに役にたったよ」「応援したい!」と思っていただけたらよろしくお願いします。※ご負担のないようにお願いします(^^)
