
「スキルベース組織」とは結局何なのか?そして何ではないのか?
皆さま、スキルベース組織という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
国内企業が「ジョブ型!ジョブ型!」と躍起になり始めたところ、今度は欧米ではスキルベースの組織が話題になりはじめました。
欧米では、ユニリーバやIBMなどがスキルベース組織(の一部)を導入していることで有名です。
人事部門からすると「今ジョブ型検討しているんだよ勘弁してよ」という本音もあるかもしれません。
「日本の職能型人事制度とは違うの?」
「うちはスキル管理もやっているけど、スキルベース組織なの?」
など、いまいち手触り感のないこの概念ですが、本記事ではなるべくかみ砕き、結局このスキルベースなる組織、人事制度とは何であって、何でないのかを解説します。
この記事を開いていただき、ありがとうございます。グローネクサス代表の小出です。元デロイトで14年、最終的にはディレクターで多くの大手企業を支援していました。
現在ではグローネクサス代表として、主に大手企業における人材戦略・人材マネジメント策定やワークスタイル変革、リスキリングのお手伝いしています。
https://grownexus.co.jp/
より細かい「スキル」というメッシュで人と仕事をマネジメント
人と仕事をスキルでマッチングする仕組みである
端的に言うと、仕事と人のそれぞれをスキルに分解して、スキルでマッチングしましょう、という仕組みです。
例えば、ユニリーバでは、部門の仕事が、プロジェクトやタスク 、成果物に細分化されつつあります 。
そして社員は、スキルを持った人材が、柔軟に各プロジェクトやタスクに異動・配置されるような仕組みを導入しています。
出所:Therese Raft,“Unilever is turning the work week towards skills building,” Financial Review April 27 2022

出所:ユニリーバ社 HP
https://www.unilever.com/sustainability/future-of-work/future-workplace/
ん?それって、メンバーシップだろうがジョブだろうが今もやっているのでは?と思われるかもしれませんが、多くの企業(の人事や上司)は「頭の中」でやっています。
例えば、メンバーシップ型では、上司や人事が各人の能力や経験をなんとなく思いを巡らせ、様々な仕事や役割を当たえます(いわゆる適材適所)。
つまり、最初に人があり、その人に「できそうなこと」「成長のためにやらせたいこと」をやらせます。
その過程において、スキルという概念は実はあまり言語化されたり、表出されません。
仕組みやルール上、スキルを管理することは必須とされていないのです。(もちろん、別にスキルセットも管理している企業もあります)
また、ジョブ型は仕事が先にあり、その仕事を実施するために必要なスキルも定義されていますが、そこへのアサインは社員個々人の自律的な手上げであったり、人事や上司からの推薦だったりします。
社員の手上げも、人事や上司からの推薦も、実は厳密に社員本人が保有しているスキルを言語化することは必須ではありません。
(こちらも、もちろん別にスキルセットも管理している企業もあります)
スキルベース組織は、仕事と人をスキルという単位に分解し、それでマッチングをしていくルールです。
といっても仕事や人間が物理的にスキルに分解されて、ミニ人間が仕事をしだす、ということではもちろんありません。
例えば、人事業務の業務マニュアルの作成という仕事がある場合、その仕事に必要なスキルを「人事業務理解」「業務フロー作成」「ドキュメンテーション」の3つに分解します。
また、人側も人事部のAさん(人事オペレーション長い人)、企画部のBさん(業務改革経験あり)、Cさん(やる気のある若手!)のスキルをそれぞれ可視化します。
Aさんは「人事業務理解」「給与計算」などのスキル。
Bさんは「業務フロー作成」「ファシリテーション」などのスキル。
Cさんは「ドキュメンテーション」などのスキル。

そうすると、人事業務マニュアル作成の仕事は、このAさん、Bさん、Cさんをアサインすれば対応できる、となります。
もちろん、3人アサインしますから、工数も分担してやっていくことになります。(ので、Too muchなアサインだな、ということではないです)
メンバーシップ型だと、何となく「Aさんやっとけ!」になりそうですし、ジョブ型だとやる気のあるCさんが手上げで担当して炎上しそうです。
このように、何となく人側、仕事側、ないしは両方のスキルがあいまいな状況でマネジメントしてきた仕組みを、「スキル」という共通言語でやっていこうぜ!というのがスキルベース組織です。
スキルを評価し、処遇する仕組みである
スキルが共通言語化されると、これを基軸とした人材マネジメントに変わります。
いわゆる人材マネジメントの「採用」「配置」「育成」「評価」「処遇」「代謝(退職)」の観点で整理します。

採用:求められるスキルセットに応じた採用。プロジェクト・タスクやスキルの適合性が重視され、柔軟なスキルマッチングが前提。
配置:社員のスキルセットを基にプロジェクトやタスクに柔軟に配置。変化するタスク・プロジェクトに応じて人材が流動的に配置される。
育成:社員が自身のキャリア目標やプロジェクト・タスクに応じて必要なスキルを自主的に強化できる仕組みを整備。リスキリングや学習機会が多い。
評価:プロジェクト・タスクごとの成果やスキルの成長を評価。スキルの習得度やプロジェクトでの貢献(成果)が評価される。
処遇:スキルレベルやプロジェクトへの貢献度に応じた報酬体系。スキルの成長や価値が報酬に反映され、自己成長が処遇にも直結。
代謝(退職):新しいスキル需要に応じてリスキリングが進むが、対応できない場合やスキルの需要がなくなると退職も選択肢に。スキルマッチングの結果、退職が促されることもある。
このマネジメントを行うと、人は会社に求められているスキルをどんどん習得し、できる仕事を増やしたい、そして評価・処遇されたいというインセンティブが働きます。
一方会社では、自社に不足しているスキルや、将来必要なスキルなども明確にできるため、「スキルミスマッチによる人材不足」を解消する方向に向かえます。
更には、タイムリーに人と仕事をマッチングし、より素早く配置を行えます。
環境変化と技術進展により変化する必要スキルに、アジャイルに適応していく人事制度が、スキルベース組織といえます。
メンバーシップ型やジョブ型の延長ではない
スキルという言葉だけを聞くと、何となく職能感(メンバーシップ感)漂う仕組みですが、人材マネジメントについても違いが生じます。特に下記表のオレンジ部分は特徴的です。

また、スキルベース組織を実践するためには、ジョブと人をスキルに分解し、常にそれをアップデートし続ける必要があります。
したがって、運用のイメージもいわゆる職能型・メンバーシップ型や、ジョブ型とは異なります(どっちかというとジョブ型のほうが近いかも)。
詳しくは後述します。
全社に一気にスキルベース導入はかなり困難
運用の大変さとテクノロジーの活用
次世代的な、今風の人事制度にも思えるスキルベース組織ですが、運用はなかなか大変です。
この人材マネジメントの前提になるのは、スキルのみ管理すればよい、というわけではなく、仕事も、人も、タイムリーに管理する必要がある(というかそうしないとスキルを管理できない)、ということです。
欧米にてジョブ型の限界を感じられるようになった1つの要因が環境変化、技術革新であり、ジョブ型よりもっと素早く、流動的に人と仕事のマッチングをしたいというニーズからでした。
この俊敏さ(アジリティ)を担保するためには、常に人(の稼働状況やパフォーマンス)と仕事(のゴールやタスクの内容)を管理し、それぞれをスキルに分解しておく必要があります。
つまり、ジョブ(仕事)をすっ飛ばしてスキルベースで、とはいかないのです。
したがって、純粋にスキルベース組織を実践しようとすると、かなり運用・管理工数がかかります。
ゆえに、スキルベース組織を導入するにあたっては、人、仕事のそれぞれに紐づくスキルを管理するツールやシステム、そしてこれをマッチングするAIなどの技術を活用されることが通常です。
例えば、IBM は、スキル等の人材の属性に基づいて最適な営業チームを提案する AI ツールを開発し、チーム編成に応じた成功率を予測しています。
*出所:IBM,“Building a winning team using AI,” March 16 2018
導入すべき組織を特定する
ということで、このような運用負荷をもってでも導入すべき組織を特定するのが良し、ということになります。
どのような組織がよいか?それは先に述べたような、プロジェクトやタスクが流動的に発生するような組織です。
具体的には、下記のような組織は考えられます。
経営企画部門
DX部門/会社
IT部門/会社
人事企画
エンジニアリング部門/会社 など
こういった組織では、次から次へと新しいプロジェクトや開発が生まれますので、そのプロジェクトごとに必要なタスク・スキルを分解し、人のスキルを見てマッチングする、という形式になります。
なお、筆者も前職では上記に近い運営をやっていました。
週次のアサイン会議なる会議体で、プロジェクトと人をマッチングする、といった感じで、所属組織の全マネジャーが参加して運営していました。

また、昨今は上記のようなプロジェクト型組織へシフトするような事例も多くありますので、これを機にスキルベース組織を導入してみる、というのもよいでしょう。
更に、上記の人材マネジメント全部をスキルベースにするのではなく、例えば評価と処遇以外の仕組みはスキルベースにする、という考え方もあります(というか、本稿執筆時点ではそっちのほうが主流のように思われます)。
このように、まずは対象組織と、スキルベース組織の導入要素を限定しながら進めてみることが現実的かと思います。
なぜジョブ型で騒いでいる間に突如スキルベース型が現れたのか
さて、仕組みの話をしたところで、ここでそもそもなぜこのように注目を浴び始めたのか、についても触れます。
スキルベース組織が注目を集め始めたのは、2010年代後半からのことです。
特にデジタル技術やAIが急速に進化し、企業が従来のジョブ型や役職型の制度だけでは変化に対応できなくなったのがきっかけです。
この流れは、特定の企業が「スキルベース組織」を広めたというよりも、テクノロジー分野の急速な成長に合わせた各企業や研究者の取り組みから広がったものです。
背景と起源
スキルベースの人事制度の原点には、経済学や人材管理の分野での「スキル・マネジメント」や「能力開発」といった概念があり、これらの考え方は長く研究されてきました。
しかし、テクノロジー企業が拡大し、従来の「役割やポジションに基づく評価」が技術革新に対応しづらくなると、スキルそのものを軸とする組織構造への関心が高まります。
特に、企業が求めるスキルが短期間で変わるようになり、職務内容が固定されているジョブ型では、急速な変化に対応しにくいとされるようになったのです。
テックジャイアントの台頭
「スキルベース組織」が企業戦略として明確に語られるようになったのは、Facebook(Meta)、Google、IBM、シスコなどのアメリカの大手テクノロジー企業が「スキル重視の採用」や「スキルセットに基づく社内異動」の導入を始めた時期です。

画像出所:Google HP
たとえば、Googleでは「プロジェクトベースで社員がスキルを発揮できる仕組み」を早い段階で採用し、多様なスキルを持つ社員が異なる部署でも活躍できるような体制を整えてきました。
また、IBMは「SkillsBuild」や「Your Learning」といったスキル開発プログラムを提供し、スキルセットに応じてキャリアが選択できる環境を整えています。
スキルに焦点を当てた学術研究の進展
スキルベース型の組織設計や制度の重要性が学術研究で論じられるようになったのは、2010年代後半のことで、経済学、経営学、人事管理の分野で「スキル主導の人材配置」や「スキルギャップ分析」の概念が強調され始めました。
特に、米国ハーバード大学やMITのビジネススクールが、スキルセットが成果と成長の主要なドライバーであるとする研究を発表しています。
例えば、ハーバードビジネスレビュー(HBR)では、2018年頃から「未来の職場で必要なスキルセット」や「スキルベースのキャリア構築」に関する論文が増え、企業がどのように人材のスキルを管理するかに注目するようになりました。
参考文献:
"Your Workforce Is More Adaptable Than You Think" – Explores how companies can pivot toward skills-based management for resilience (HBR, 2019).
"A New Approach to Building Your Personal Brand" – Focuses on skills-based career advancement (HBR, 2018).
求人プラットフォームの進化
スキルベース型が企業で注目されるようになったきっかけには、LinkedInやIndeedなどの求人プラットフォームの影響も大きいです。

これらのプラットフォームは、職務経験だけでなく具体的なスキルセットを求職者と企業が結びつける手段として提供し、スキル中心の採用や配置がトレンドとなる一助となりました。
さらに、AIやデータサイエンスの需要が高まるにつれて、企業は社員のスキル開発や柔軟なスキル配置を促すようになり、スキルベース型の制度が注目されるに至りました。
一方日本では:ジョブ型機運が高まる
ジョブ型の限界からスキルベースに注目が集まりだしていた欧米に対し、日本では同時期、ジョブ型導入の機運が高まりはじめていました。
ジョブ型雇用導入の流れを生む一つの源になったのは、当時の経団連の意向であったものと思われます。
2019年5月7日の定例記者会見で、「終身雇用を前提に企業運営、事業活動を考えることには限界がきている」と、日本型のメンバーシップ雇用の抜本的な見直しを示唆しています。
この延長線上に、2020年1月に公表された「経労委報告」では「メンバーシップ型」と欧米流の「ジョブ型」の組み合わせの検討が提起されました。
日本は周回遅れなのか
スキルベース組織の注目は、ある特定の企業や論文が一因というより、デジタル化やAIの普及による急速な変化が大きな要因です。
企業が変化に迅速に対応するためには、固定されたジョブ型の考え方よりも、スキルを基にした柔軟な制度が求められるようになり、これがスキルベース型の普及につながりました。
一方で、日本企業はさらにその一歩手前、そもそも日本独特の慣習である終身雇用型の転換が求められているという状況にあります。
「なんだ、欧米はジョブ型の限界を感じて移行しようとしているのに、そのジョブ型を目指しているなんて、周回遅れかいな」と思ってしまいそうですが、そんなに単純な話ではありません。
そもそも日本のメンバーシップ型という人事制度は、日本固有のものであり、グローバルではジョブ型がスタンダードなのです。
そして欧米はそのジョブ型では技術進化に適応しずらい(技術進化に適応するためにスキルベースで仕事を分解したい)という状況であったため、スキルベースに着目している、という文脈です。
一方で、日本はメンバーシップ固有の課題である、「環境変化に合わせて必要なスキルセットを持った人材をタイムリーに確保できない(スキルセットを持っていない人材を外に出せない)」を解消したいのです。
つまり、見えている課題が異なる、という状況にあります。
更に、日本企業はただ単に欧米型の「The Job型」を目指すのではなく、メンバーシップ型のいいとこどりをしようとしている企業もみられます。
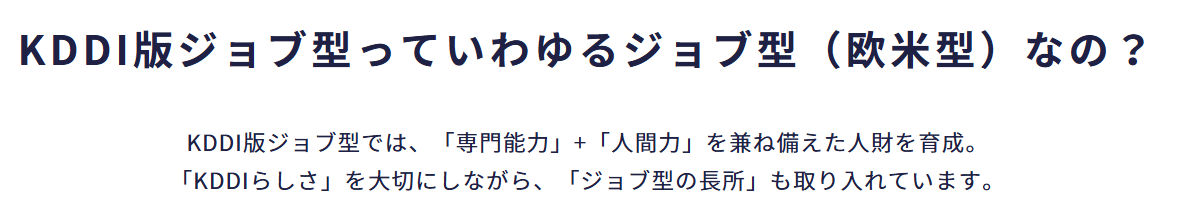
https://career.kddi.com/environment/personal_system.html
ここから示唆されるのは、「ジョブ型やーめた」「ジョブ型導入のモチベーション失ったわ・・・」ではありません。
ジョブ型のいいところと課題、メンバーシップ型のいいところと課題、そしてスキルベース型で解決できる課題を踏まえて、きちんと自社にフィットしたオリジナル制度を作りましょう、ということです。
前述したように、完全なるスキルベース組織導入は難しいので、3つの仕組みのいいとこどりをしつつ、オリジナルな仕組みを作っていくことをお勧めします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
自社でジョブ型含めた人事制度の見直しや、スキルベース組織導入、プロジェクト型組織の導入について、お悩みがある方はお気軽にお問合せくださいませ。
https://grownexus.co.jp/
www.linkedin.com/in/翔-小出-a921642a9
