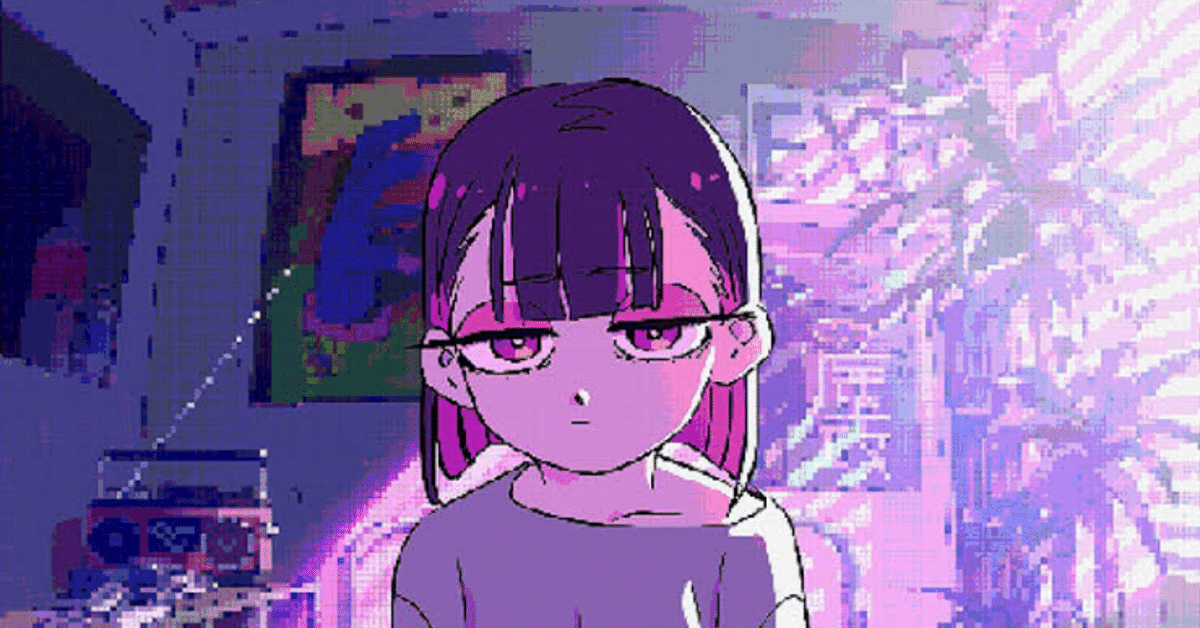
#27 ずとまよを生んだのはボカロではない。
25/02/07: 800 views達成!皆様ありがとうございます!
好評につき一部リニューアルしました。
ずっと真夜中でいいのに。は、(今ではかなり路線が違ってきてはいるものの、)以前の記事で言及したYOASOBIらと同様、YouTube・ボカロ・歌い手世代の影響が強いミュージシャンとして現れた。
「YOASOBIはボカロの影響下以前に、いきものがかり的なグループだ」というのが前述の記事の主張だった。ずとまよも同様に現代的なカルチャーだけでは語れない。ここで比較したいのは、「小林武史」プロデュースの90年代J-POP。特にその根幹を成す、「My Little Lover」の影響だ。
My Little Lover
My Little Loverは95年デビューの3人組。Vocalのakko、Keyboardの小林武史、Guitarの藤井謙二。自分もイマイチ世代ではないのもあり詳しくは語れないグループなのだが、「evergreen」や「topics」といった名盤をサブスクで気軽に聴くことができる。そして「evergreen」が1995年、「topics」が2001年なので、Mr. Childrenの「深海」〜「It's a wonderful world」あたりの活動と共鳴しているというのも興味深い。
なんといっても特徴はオーバーダビングで録られたakkoの透明感ある声と、なぜかその透明感と両立しているちょっと「乱暴な」節回しである。そして、小林武史がMr. Children以上にポップな音色とデジタルな方向に舵を切り、完成度の高い曲が様々残されている。
ずとまよのコバタケ的楽曲
いわゆるずとまよの鉄板的な要素は、デビュー当初の「秒針を噛む」以来変わっていない。ベースとピアノの跳ねるリズムが印象的な、ファンキーなポップス。ちょっと逸れるけど、この時点でYOASOBIとはだいぶ違いますね。
ファンクネスに加え、ストリングスをそこにかなり大胆に加えることで、ポップスとしてのゴージャスさを強化している。
一方で、こんな曲もある。
「マリンブルーの庭園」
3rd EP「朗らかな皮膚とて不服」収録の、ミディアムテンポでメロディアスな進行の一曲。YouTubeのコメント欄を見ると、隠れた名曲として注目している人も多い一曲のようだ。
この曲のアレンジは、デジタル的面を押し出したMy Little Loverの傑作アルバム、「topics」を思わせる。
ボーカルのACAねの歌い方も、My Little Lover的な「乱暴さ」と「透明感」のハイブリッド。そしてそして、歌詞にはMy Little Loverの代表曲、「アリス」が登場するのだ。たまたまかもしれないが、嬉しい偶然である。
この曲も素敵です(「夏枯れ」)
まとめ
ファンクイメージに押されて見過ごされがちだと思うのが、彼らのこういった"90年代女性ボーカルバンド"的な要素である。現代で愛されているミュージシャンは、いずれも90〜2000年代の遺伝子を正統に受け継いでいることをよく表した例である。
