
人材派遣利用マニュアル ~人材派遣利用のルール~ ⑧人材派遣における同一労働同一賃金
人材派遣利用マニュアル ~人材派遣利用のルール~編を解説しています。
人材派遣を利用する際に知っておくと良いルールの紹介です。
今日は、第八弾!「人材派遣における同一労働同一賃金」いってみましょー!
「ひたすら具体的」で「生々しく」人材派遣利用の教科書を作るという狙いなので、僕の独断で、派遣先企業が知っておくべきことについて超実践的に解説していきます。
シリーズのマガジンはコチラ↓
派遣法における2つの選択肢
前回のnoteでお話ししましたが、↓
同一労働同一賃金とは
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの
でした。
当然、派遣労働者は非正規雇用労働者になります。
そこで、不合理な待遇差をなくすために、2020年4月に、派遣法が改正されました。そして、その派遣法には、派遣労働者の待遇決定方式が二通りあります。
・・・・わかります。なぜ、派遣労働者には2つの待遇決定方式があるのか・・・あの派遣会社は労使協定方式とやらのようだが、それはいったい何なんだ・・・ってなりますよね。とてもややこしいですね。
今日は、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2つの待遇決定方式がある理由を解説します。
※この2つの方式のどちらを選択するかは、派遣会社が選びます。派遣先としては、どちらを選んでいる派遣会社に発注するかという考えは出来ても、派遣会社がどちらを選択するか干渉することは原則できません。
派遣における同一企業・団体が特殊
まず、2通りの待遇決定方式がある理由です。それは、ただ一つ。
人材派遣における同一企業・団体が特殊だからです。
ここで、同一労働同一賃金の概念を改めて図にしたものを見てほしいのですが、

このようなイメージで、同一企業・団体の中で、正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇格差を解消していきます。
ところが、派遣労働者が所属している(雇用されている)のは派遣会社です。そこで問題となるのが、同一企業ってなんやねんと言うことで、正確に言うと派遣労働者のイメージは

こんなことになっています。
2つの待遇決定方式がある問題は、この??の部分で
①派遣先企業を同一企業・団体とするのか
②派遣会社が同一企業・団体なのか
という考え方がベースにあります。
派遣先の正社員と比べるか、派遣元の正社員と比べるか
もう少しかみ砕いて表現すると
①派遣先の正社員と待遇を比較するか
②派遣元(派遣会社)の正社員と待遇を比較するか
(ここでは分かりやすく正社員と言う表現にします。厳密には無期雇用の労働者。)
という問題があり、
派遣先均等・均衡方式は①の派遣先の正社員との待遇を比較していて、労使協定方式は②派遣元の正社員と待遇を比較しています。労使協定方式は、派遣元均等・均衡方式と考えても分かりやすいかと思います。
もちろん、派遣先の正社員とも、派遣元との正社員とも不合理な格差がないように待遇を設定するということは無理がありますので、結果として、派遣先均等・均衡方式か、労使協定方式のいづれかを選択するということになっています。
これが2通りの待遇決定方式がある理由です。
労使協定方式は例外規定
次回以降で派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の解説をしていきますが、その前にもう一つだけ知っておくとスッキリするのが、「労使協定方式は例外規定」ということです。
同一労働同一賃金における派遣法改正が議論される過程でもそうだったのですが、まず前提として考えられていた待遇決定の方法は「派遣先均等・均衡方式」です。
いわゆる直接雇用のパートや契約社員と同じ考えで、仕事が同じなら同じ大ぐうとなるので、最も自然だと思われます。

先ほども出てきた↑同一労働同一賃金のイメージそのものです。(いわゆるパートタイム・有期雇用労働法と同じアプローチ)
詳しい解説は、厚生労働省の「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」の36ページ~にあります。↓
そして、この派遣先均等・均衡方式が原則(基本的な考え方)であり、労使協定方式が例外規定なのです。
なぜなのでしょうか。
ガイドラインに以下の通り記載があります。
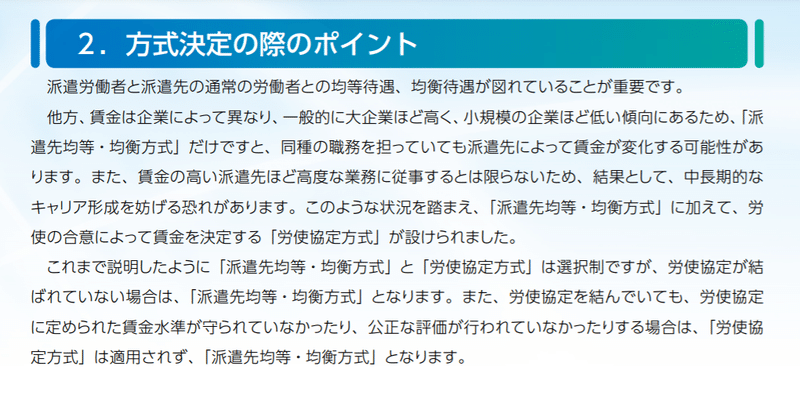
ここでは、A社(従業員数1万人)で経理職として派遣されていた派遣労働者がA社の従業員と均等・均衡を図って待遇を決められているという状況で、そのA社との契約が終了したためにB社(従業員数10名)の会社に派遣されて、B社の従業員と均等・均衡を図ったら、大幅に給料が下がった・・・(ここでは大企業より中小企業のほうが待遇が低かったという偏見ともいえる設定でお送りしています)というような不整合が起こりうるということが書かれています。
本当はB社のほうが、経理部門の立ち上げの業務であり、本人のキャリアにもプラスで、難易度も高かったとしても、「給料が下がるなら、大企業の、簡単で勉強にはならないけど給料高い仕事のほうが良いわぁ」となりかねないということですね。
これは、確かに派遣の現場では頻繁に起こりうるシチュエーションです。
これでは、キャリア形成を妨げてしまう本末転倒な状況になってしまいます。
とはいえ、原則は派遣先均等・均衡方式で、あくまで同じ仕事をする派遣先と比較検討をさせたいという本音も見える話で、労使協定をちゃんとできてなかったら派遣先均等・均衡方式が適応されると言うルールになっています。
そのうえで、派遣労働者のキャリア形成のためであれば、派遣会社内で待遇を決定していく労使協定方式という選択肢を選んでもいいよと言うのが、労使協定方式が誕生した流れなのです。
さて、例外・・・って何かで聞いた覚えはありませんか?
そう!(ってたぶん誰も答えられてない!w)
派遣法は職業安定法44条の例外でした。
そして、銃刀法の例外法である「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(猟師が猟銃を持っていいルールなどが定められている)が厳しいのと同じように、厳しく細かいルールで運用されていました。
同じく、労使協定方式も非常に細かいルールや厳密な運用が必要とされています。ここで覚えておきたいのは、労使協定方式は例外規定なので
①労使間で厳密に運用しなくてはならない必要があるルールがある
②労使協定方式をちゃんと守られていなかったら即、派遣法違反ではなく、原則たる派遣先均等・均衡方式に立ち戻る
ということです。
最後に
今日は、人材派遣には、同一労働同一賃金における派遣労働者の待遇決定の方法が二通りあるという解説をしました。
派遣の同一企業・団体が特殊なので、キャリア形成のために労使協定方式と言う方法が生まれた
と理解いただければ、とりあえずはOKかと思うのですが、もう少し踏み込むなら、そもそも労働者派遣というのは役務の提供(○○の仕事をできる人を派遣する契約をする)であり、地域や職種という市場ごとにそれなりの賃金水準マーケットが確立されている側面がありました。
法改正前から、個社ごとに待遇が異なる正社員と比べると、日本では最も同一労働同一賃金に近い存在であったわけです。
僕なんかは、「人材派遣を参考に制度設計や労働市場を作っていけばいいのでは?」なんて、最初は思っていました。
ただ、前回もお話しましたが、同一労働同一賃金と言っても、正社員という働き方(年功序列、終身雇用、企業内組合)を破壊するような改革を目指すものではないわけです。(終身雇用を前提に職種も地域も異動して転々としてきた正社員とかどうしたらいいの?ってなりますよね)
それによって、逆に人材派遣のほうが、ややこしい制度になっていったという側面もあると捉えても分かりやすいかもしれません。
次回以降では、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式について、それぞれ解説していきます。
最後に、より詳しく知りたい方のために、厚労省HPの派遣労働者の同一労働同一賃金についてのリンクを貼っておきます。↓(前回も貼ったのと同じ)
では、また明日!
転職エージェントや人材派遣会社を利用する中で、不満、不便、不安を感じている方、就職してお悩みがある方、これから転職を考えている方、どちらでもない方、ご質問やご相談はこちら↓へお願いします。
※無料で全力でなんでも答えます。
僕のプロフィール↓
オープンチャット「人材派遣営業の駆け込み寺」を始めました↓
ちょっと、一回勉強してこい!っていう派遣営業がいたら、ご紹介をお願いします!
無料&匿名で相談できますので、ぜひ!(↓関連記事)
いいなと思ったら応援しよう!

