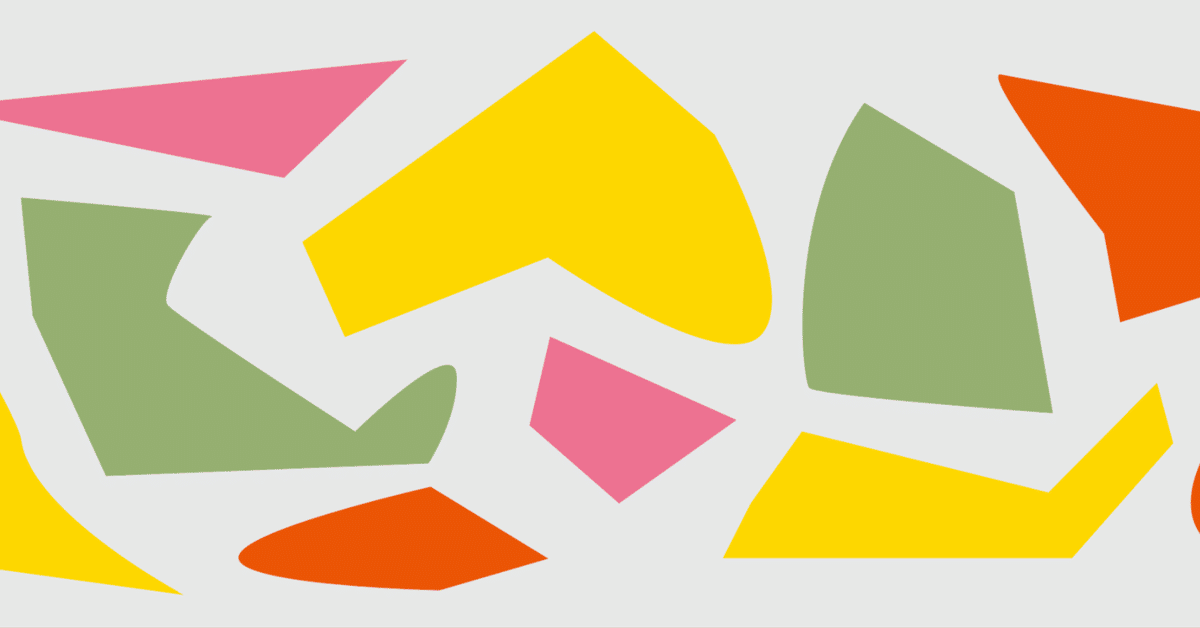
今の自分を育ててくれた絵本20冊(前編)
子供の頃から、大人になった今でも絵本が大好きです。
絵本は知識を、語彙を、感覚を、情緒を、観察眼を、倫理を育ててくれます。
そしてあらゆる表現の幅を許容する、もっともクリエイティブで、表現者や思考者としての人の幅を育てるメディアの一つだと思います。
僕は絵本の専門家ではないですが、絵本というメディアが大好きです。今から思い起こせば、僕にとってものづくりの考え方や視点などを育ててくれた、重要な20冊を振り返りました。
まずは前編として10冊を紹介します。
(現在絶版で手に入りにくいものもあえて紹介します。)
「きょうはなんのひ?」(1979) 瀬田貞二(作)、林 明子(絵)
娘のまみこが学校に行くときに残した「かいだん3だんめ」という謎のワードから始まる謎解きの物語。お母さんと一緒に読者も探索を楽しむことができる、多くの絵本が持つ「連続」の様式を、物語の仕掛けとして見事に生かした作品です。タイトルまでの伏線回収が本当に見事で、暖かい結末に心が温まります。林明子さんの初期の軽快なトーンの作画も、とても魅力的です。
「こんとあき」(1989) 林明子(著)
一人の幼い少女「あき」とぬいぐるみのきつね「こん」の冒険譚。今風にいうと「バディもの」ですね。こんとあきの出会いからの物語、二人の関係性が冒頭に描かれるのですが、この出だしがあるからこそ読者の共感が高まります。そして二人の会話の中から滲み出る、その深い絆におもわずホロリとします。クライマックスで少しショッキングなできごとがあるのですが、それを超えた先にそれを覆す素敵なラストが待っています。共感性能の高い読者は一緒に泣いちゃうかもしれません。
「たろうのばけつ」(1960) 村山桂子(作)、堀内誠一(絵)
デザイナーでもある堀内誠一さんの洒脱な線描の素晴らしさはいうまでもないですが、白眉はその色です。紺色、黄色、オレンジ、グリーン、赤などの限られた原色をうまく配分して、見開き毎に大胆な色彩構成として表現しています。今見てもまったく古びることのない、むしろ今でこそその洒脱さが際立つグラフィカルな作画といえます。
「ぐるんぱのようちえん」(1966) 西内ミナミ(作)、堀内誠一(絵)
堀内誠一さんは絵本作家であると同時に『an・an』や『POPEYE』などのロゴを手がけた日本の雑誌文化を支えた有数のグラフィックデザイナーでもあります。「たろうのばけつ」が堀内誠一さんのドローイングの魅力を表現したものであれば、この「ぐるんぱのようちえん」は氏のペインティングの魅力に溢れています。今でいうと〈ニートのぞう〉が重い腰を上げて職探しの旅に出る絵本。
側面と上面を同時に描くキュビズム的な作画など、イラストレーションの魅力的な技法を多く観測できます。
物語のテーマもスティーブジョブズ曰くの「Connecting the dots」そのもので、あらゆる回り道は、人生の伏線回収となり得る(かもしれない)ことを私たちに教えてくれます。
「くるまはいくつ」(1967) 渡辺茂男(作)、堀内誠一(絵)
「たろうのばけつ」と「ぐるんぱのようちえん」が堀内誠一さんのイラストレーターとしての魅力が詰まったものであれば、こちらは氏の「グラフィックデザイナーとしての実力」がいかんなく発揮された作品です。シンプルな円だけで表現した車輪とゴシック体の日本語、ユーロスタイルの数字書体のバランスが絶妙で、改めて見てみると、レイアウトも配色も完璧で、グラフィックデザインの作品としても一流だと思いました。
「しょうぼうじどうしゃじぷた」(1966) 渡辺茂男(作)、山本忠敬(絵)
コンプレックスをかかえている小型の消防車がその個性を活かして活躍する、今でいうダイバーシティ的な考え方につながる、秀逸なストーリーです。山本忠敬さんはさまざまな乗り物の絵本を描いていますが、乗り物本来のフォルムを大きく崩さず「嘘をつかない」デフォルメが誠実で、そのことが子供の心を掴むのだと思います。そのいっぽうで背景の描写は大胆な色面やテクスチャで表現していたりと、粗密やコントラストがとてもデザイン的な魅力を放っています。
「とこちゃんはどこ」(1970) 松岡享子(作)、 加古里子 (絵)
赤い帽子と青い半ズボンの男の子がさまざまな見開きのシーンで群像の中に隠れています。かこさとしさんの描く集合表現はとにかく楽しく温かい。僕はずっと箱庭的な世界に惹かれ続けてきましたが、原風景の一つはこの絵本にあります。主人公を隠す道具として群像があるのではなく、それぞれの人物が活き活きと生活している様が描かれているんです。何度読んでも発見がある絵本です。
「きみはしっている」(1979) 五味太郎(著)
間違いなく名作ではあるのですが、ネタバレ防止のため多くを語ることができない絵本です。何かのきっかけで読むことができればぜひ、ご自身の目でその斬新な構成に驚いてほしいです(当時にこれを思いついていた五味太郎さんは天才だと思います)。最後まで読むと「やられた!」という気分になり、ページを遡りたくなることうけあいです。多くの人が知る五味太郎さんのタッチとは異なり、太めの輪郭線の強弱など、絵柄的にもレアな本です。残念ながら復刻版も含めて絶版となっており、オークションサイトで1,000円代で出会うことができれば即買いしましょう(笑)。
「はじめてであうすうがくの絵本」(1982) 安野光雅(著)
「1冊」ではなくてずるいですが、計算問題や数字を絵にしましたというような浅薄な内容ではなく、数学の本質、その抽象性の魅力を、子供にもわかるように比喩や物語を駆使し、自然や生活に寄り添って伝えています。「難しいことを誰にでもわかるように説明すること」は非常に難しいことです。安野光雅さんは機知にとんだアイデアと、美しく合理的なイラストレーションを使って、巧みにその解を提示します。理は美を求めることがよくわかります。
大人になって読むと、その情報デザインの技術にも感服します。子供の頃に出会うと「こんなに数学って面白いんだ!」と、その奥深さが大好きになるだろう1冊(ほんとは3冊)です。
「旅の絵本」(1977-) 安野光雅(著)
最後も安野光雅さんの作品です。一人の旅人が俯瞰の箱庭世界の中で、黙々と旅を続ける。文字も説明もいっさいない。でも1枚1枚の絵は実に多弁。芸術的完成度の高さ、画面構成、美しい色彩、世界各国をモチーフにした情景とそこに描かれる物語。淡々と進む世界はときに感傷的でときにユーモラス。世界中から評価されているのは当然というか、まちがいなく絵本というメディアの最高到達点の一つだと思います。
こうやって前半10冊の絵本を見返してみると、いかに絵本が自分の創造性の礎になっていたかわかります。絵と文が対等に融合している絵本というメディアだからこそ、ビジュアルにも言葉にも偏らない、創造性の深いルーツを辿れるのではないでしょうか。
<後編につづきます(後日更新予定)>
