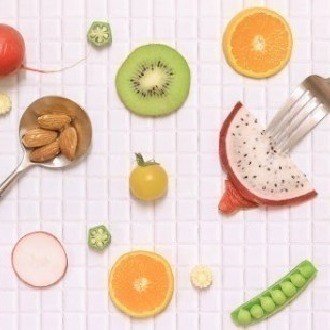2019年10月の記事一覧
White NOise #10
真っ白な夢と真っ黒な夢の間。
そこで、僕達は真っ赫な嘘を吐き出した。
泣き出した子供の頬を滑り落ちていく白銀の雫。
せめて、灰色にしとけばよかったのに。
なんて、君は言うけれど。
僕には、シロかクロかのスイッチしか残されていなかったんだ。
モノローグでモノクロームな世界
第六部 第三章
三、
細胞が徐々に死に向かうように、徐々に壊れていく世界。
そこで暮らす人々の大半は、与えられる安心、安全に満足し、何も望まなくなっていった。やがて、彼らは、生きる希望を失い、明日を夢見なくなった。
止まった世界は、やがて壊れるだけだ。
時間は巻き戻せない。それだけは不可避の絶対的法則。
たとえ、未来がわかっていようとも。
たとえ、過ちがわかっていようとも。
だから、あの時、こ
モノローグでモノクロームな世界
第六部 第三章
二、
アレグロ・バルバロ。
三分間にも満たない曲と同じ題を冠するその作品は、真飛にとっては、李鳥が生きていたという唯一の証だった。
今やどちらも消えてしまったデッドメディアだが。
彼女が、どんな気持ちでこの話を書いたのか。
アレグロとハナを中心に語られる世界は、今、真飛の目の前に見えるこの世界と違い、色鮮やかにその色を彼に伝える。
そして。
嘗ての世界の有様を、彼に伝えた
モノローグでモノクロームな世界
第六部 第三章
一、
ダームシティの特別列車。
それは、いつの頃からか、人々の間でこう噂され、呼ばれていた。
『ダームシティのゴースト・トレイン』
『ゴースト・トレインに乗れば、死んだ人間に会う事が出来る』、と。
噂の真相は、嘘でもあり、また真実でもあった。
無論、現実的に死んだ人間が蘇るわけでも、幽霊として列車に現れるわけでもない。
どこか懐古主義的な装飾が施された黒い列車は、その装飾を除
モノローグでモノクロームな世界
第六部 第二章
三、
ミハラ ケイの名を知ったのは、偶然であり、また、今振り返ると必然であったようにも思える。
いつもこの地下空間まで物資を運んできてくれる馴染みの貿易商人が、 『アレグロ・バルバロ』を探している者が居るとして、彼の名を教えてくれたのだ。
大分前のことだ。
あの作品がナインヘルツの検閲に引っ掛かり、『不適切』の評価を受け、この世界から抹消されたのは。
あれから何年も経ったい
モノローグでモノクロームな世界
第六部 第二章
二、
それからの私の行動は、自分で言うのも難だが狂気じみていただろう。
李鳥と同じ顔の人形を作ると、この世界を創りあげていく過程で得た知識を総動員し、人工知能を与え、李鳥の過去を、記憶を植え付けていった。
壊れたら、また作り、壊れたら、また作る。
その繰り返し。
彼女達に私は、いつも同じ命令を下した。
『世界が壊れた同日同時刻に、私を銃口で狙うこと。』と。
だが、その命
モノローグでモノクロームな世界
第六部 第二章
一、
「本当にこれでよかったのでしょうか。」
私は、ある時、ナインヘルツのやり方に疑問を持ち、一緒に仕事をしていた副島という博士に、そう尋ねた事があった。
思えば、あの時からそうだった。
私達は皆、本当は気づいていたのだ。こんなやり方は間違っていると。
だが、面と向かって、ナインヘルツに歯向かうことが怖かった。
彼等のやり方を知っているが故に。
結局、私もただ、自身の保身に走
モノローグでモノクロームな世界
第六部 第一章
三、
一時期をピークに、次第に自殺の二文字は世間から消えていった。
実際のところは、その数が減少したわけではない。意図的に、それらの報道がされなくなっただけだった。
人々は、そうして与えられる安心、安全に満足し、何も望まなくなっていった。止まった世界の中で人々は次第に真っ白に染まっていく。
町も人も世界も、全てが真っ白だった。
「ようやく復讐が終わったよ。」
狂った箱庭の上で
モノローグでモノクロームな世界
第六部 第一章
二、
世界を新たに構築していく。
地下のシェルターから出た後、そう話す男について、私は新しく作られたナインヘルツという組織へ身を寄せた。
別にこの世界がどうなろうと、知ったことではなかった。むしろ、私は彼女を殺したこの世界を憎んでさえいた。
そんな私が新しい世界を創ることになろうとは、なんと皮肉めいたことだろうか。
男が持ちかけた共感覚を利用したシステムは、思いの外、とん