
厚労省データ「日本人の食事摂取基準2025年版」から見る、日本人の食事改善戦略とは?
トレーニングするあなたを全力応援!
中小企業診断士×パーソナルトレーナーの中村亮太です!
本日は、日本人の食事改善について考えるときに最も参考にすべき資料である、「日本人の食事摂取基準」について紹介いたします。
5年ごとの改訂となっており、2025年版が最近公開となりましたので、その内容を元にしています。
かなりボリュームのある内容ですが、今回は「マクロ栄養素」と「ミクロ栄養素」という切り口で分けて、端的にまとめてみました!
日本人の食事摂取基準とは?
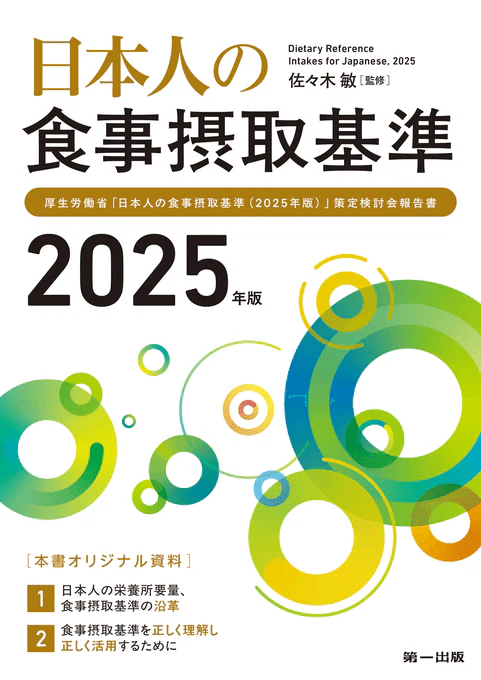
「日本人の食事摂取基準」とは、厚生労働省が策定する栄養摂取の目安で、健康維持や生活習慣病の予防を目的としています。
年齢・性別ごとに、エネルギーや三大栄養素(PFC)、ビタミン・ミネラルなどの適切な摂取量が示されています。
最新の2025年版では、たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスも推奨されており、一般的な理想比率は2:2:6とされています。
あらゆるエビデンスをまとめているので、健康的な食生活を送るための基準としては最も参考になる情報です。
本稿では、「日本人の食事摂取基準」から見えてくる、現代の日本人の食事摂取の現状と課題、そして具体的対応策についてまとめていきたいと思います。
マクロ栄養素についての現状と課題
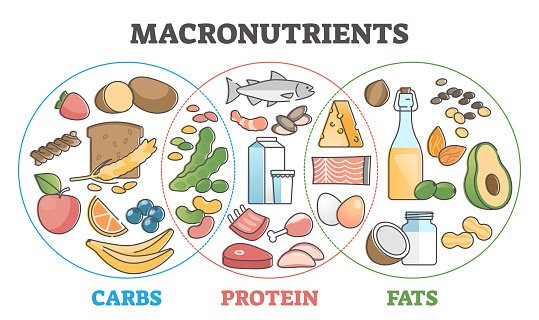
①マクロ栄養素とは?
マクロ栄養素とは三大栄養素(P=たんぱく質、F=脂質、C=炭水化物)のことで、理想的なPFCバランスは 2:2:6 とされています。
現状、日本人の摂取比率はおおむねこの範囲内に収まっていますが、いくつかの課題が以下の通り指摘されています。
②たんぱく質:高齢者にとって不足しがち
一般人にとって、おおむねタンパク質摂取量は範囲内に収まっていますが、高齢者においては、筋肉量低下を防ぐためにたんぱく質摂取の強化が必要な状況です。
なお、これは食事摂取基準に記載はありませんが、筋トレをしている人にとっても十分な摂取が重要になります。
いずれも対策として、脂質の多い肉や加工肉を減らし、タンパク質含有量の多い、赤身肉・大豆製品・卵などの摂取量を増やすことが推奨されます。
③脂質:量は若干過剰。質の改善が大きな課題
脂質の摂取量は成長期の方や活動量の多い人には適正ですが、一部の人にとってはやや過剰になっています。
また、特に加工肉や揚げ物の摂取割合が高く、肉類に偏りがちであり、結果として脂質の質が飽和脂肪酸の摂取に偏っているのが現状です。
オメガ3などの不飽和脂肪酸の摂取量を増やすことで、動脈硬化や心血管疾患を予防していく必要があります。(なお、脂質の質については別項で詳しく解説予定です)
対策として、肉だけでなく、オメガ3を多く含む魚(特に青魚)を1日1食以上取り入れることが推奨されます。
加えて、マーガリンやマクドナルドのフライドポテトなどに含まれるトランス脂肪酸は動脈硬化を強力に促進することがあらゆるエビデンスで判明しているため、極力避けるべきです。
④炭水化物:糖質の質と食物繊維の不足が課題
炭水化物は糖質と食物繊維に分けられます。
糖質については、単糖類(甘いお菓子・清涼飲料水)を摂りすぎず、米・パン・芋などの複合炭水化物から摂ることが重要です。特に砂糖を多く含む飲料は簡単に過剰摂取しやすいため、注意が必要です。
食物繊維は現状平均15g程度と不足しており、女性は18g、男性は20g以上を目指す必要があります。
対策として、白米をもち麦・大麦に置き換える、パンを全粒粉にする、食物繊維の豊富な野菜(ごぼうなど)を増やす、納豆を取り入れるなどの工夫が効果的です。
ミクロ栄養素の現状と課題

①ミクロ栄養素とは?
ミクロ栄養素とはビタミンやミネラルなど、体の機能維持に欠かせない微量栄養素のことです。これらはエネルギー源にはならないものの、代謝や免疫機能の調整、骨や血液の生成などに重要な役割を果たします。
現状、日本人の食事摂取基準によれば、ほとんどのビタミン・ミネラルはバランスの良い食事を心がければ不足しにくいですが、ナトリウム(塩分)の過剰摂取と、ビタミンD・鉄分の不足が課題とされています。
②ビタミンD:昨今、不足傾向にある栄養素
ビタミンDは、日光を浴びることで体内で合成されるほか、魚・卵・キノコ類などの食品からも摂取可能です。
しかし、近年は日焼け防止のため屋外での活動を控える傾向が強まり、また肉中心の食生活の影響もあり、ビタミンDの摂取量が減少傾向にあります。不足すると骨密度の低下や免疫機能の低下を招くため、ビタミンDを多く含む食材である、魚(特に青魚)・卵・キノコ類を積極的に食べることが推奨されます。
③鉄分:女性や成長期の子どもで不足しがち
鉄分は、血液中のヘモグロビンを構成し、酸素を全身に運ぶ役割を果たします。特に女性や成長期の子どもは不足しやすい栄養素です。
鉄分には「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」があり、吸収率の高いヘム鉄は牛肉や赤身の肉に多く含まれるため、豚肉や鶏肉ばかりでなく、牛肉・レバー・魚介類などの摂取を増やすことが有効です。
また、非ヘム鉄が豊富なほうれん草や大豆製品も鉄分補給に役立つため、バランスよく摂取することが重要です。
④ナトリウム(塩分):過剰摂取に注意
ナトリウムの過剰摂取は高血圧の原因となり、動脈硬化や心血管疾患・脳血管疾患のリスクを高めます。
WHOのガイドラインでは成人のナトリウム摂取量を 1日5g未満 に抑えることを推奨している一方、日本人の食事摂取基準では 成人男性7.5g未満、女性6.5g未満 となっており、基準に若干の差があります。
また、特に寒冷地では汗をかきにくくナトリウム不足が起こりにくいにもかかわらず、食品保存のための漬物文化が発達し、塩分過多になりやすい傾向があります。例えば、寒冷地で漬物文化が根付いている地域では高血圧の割合が高く、平均寿命が短いという報告もあります。
ナトリウム摂取量を抑えるためには、加工食品や漬物、ラーメンのスープなどの摂取を減らし、減塩調味料を活用することが効果的です。
まとめ:日本人の食事摂取基準と栄養管理のポイント
✔ 日本人の食事摂取基準とは?
- 厚生労働省が策定する栄養摂取の目安 で、健康維持や生活習慣病の予防を目的とする指標
- 年齢・性別ごとにエネルギーや三大栄養素(PFC)、ビタミン・ミネラルなどの適切な摂取量が示されている
✔ マクロ栄養素(PFCバランス)について
- P=たんぱく質、F=脂質、C=炭水化物 を適切な比率で摂ることが重要
- 理想のPFCバランスは2:2:6(カロリー比)(厚労省「日本人の食事摂取基準2025」参照)
- 筋トレをする人や高齢者は、たんぱく質をやや多めに設定するのが望ましい
✔ マクロ栄養素の現状と課題
- たんぱく質:高齢者やトレーニーは不足しがち → 赤身肉・大豆製品・卵を積極的に摂取
- 脂質:量よりも 質の改善 が課題 → 加工肉・揚げ物を減らし、青魚を1日1食以上摂る
- 炭水化物:糖質の質と 食物繊維の不足 が問題 → 単糖類(甘いお菓子・清涼飲料水)を控え、食物繊維を増やす(もち麦・全粒粉パン・野菜・納豆など)
✔ ミクロ栄養素の現状と課題
- ビタミンD:日焼け防止や肉中心の食習慣で不足しやすい → 魚(特に青魚)・卵・キノコ類を意識的に摂取
- 鉄分:特に女性や成長期の子どもが不足しがち → 牛肉・レバー・ほうれん草・大豆製品をバランスよく摂る
- ナトリウム(塩分):過剰摂取が問題 → 加工食品・漬物・ラーメンのスープを減らし、減塩調味料を活用する
✔ 健康的な食生活のために
- エネルギーだけでなく、PFCバランスやミクロ栄養素を意識する
- バランスの良い食事を心がけ、質の良い食品を選択することが重要
- 食事の改善は継続がカギ!無理のない範囲で実践し、長期的な健康を目指そう!
マクロ栄養素とミクロ栄養素の適切なバランスを意識し、自分に合った健康的な食生活を実践していきましょう!
筋肉は裏切らない。あなたの努力も裏切らない!
読んでいただきありがとうございました!また読みに来てください!
