
自分を知り、チームが変わる|コミュニケーションタイプ論いろいろ
(タイトルに”いろいろ”とつけているので、お空に虹をかけてみました)
なぜ今、MBTIなどのコミュニケーションタイプ診断が注目されるのか?
最近、MBTIがプロフィールの鉄板になっています。
(ちなむと私は主人公です)
「私はENTPだから発想力が得意」「ISTJの慎重さに共感する」といった話題がSNSや職場で飛び交い、MBTIは単なる自己診断を超え、人々の間で共通言語として使われるようになっています。
この現象の背景には、現代社会の働き方や価値観の変化が深く関係しているように感じます。
1. 自己理解への欲求の高まり
情報過多な現代では、自分の個性や価値観を「言語化」し、他者に伝える能力が求められる時代です。特に職場や人間関係において、自分の特性を知り、他者とどう違うのかを明確にすることで、より良い協力関係を築けるようになります。
MBTIをはじめとする診断ツールは、その自己理解を助ける強力なツールです。
2. チームでの多様性理解の必要性
リモートワークやグローバル化が進む現代、異なる価値観や背景を持つメンバーとの協働が当たり前になりつつあります。その中で、コミュニケーションタイプ診断は、チーム内での「相互理解のガイド」として機能します。例えば、「外向型(E)」と「内向型(I)」といったシンプルな分類でも、衝突が起きたときに「相手が間違っている」のではなく「アプローチが異なっている」ことに気づけるのです。
3. SNSによる拡散と親しみやすさ
MBTIが特に若い世代に支持されている理由の一つが、SNSとの親和性の高さです。診断結果がシンプルかつ視覚的に共有しやすいことから、友人や同僚間で「私はこのタイプ!」と気軽に話題にでき、共感や発見の輪が広がりやすくなっています。こうしたライトな広がりが、MBTIをより身近な存在にしています。
4. 科学とエンターテインメントの融合
MBTIは、心理学的タイプ論に基づく信頼性の高いツールでありながら、診断結果がストーリー性を持っている点が特徴です。「自分はこういう性格だ」と理解するだけでなく、「それをどう活かすか」を考えるきっかけを提供してくれるため、個人の自己成長だけでなく、組織のパフォーマンス向上にも貢献できるのです。
だから今、企業研修でも注目されている
このような診断ツールが注目を集めているのは、個人レベルの自己理解だけではありません。企業においても、これらの診断を活用することで、「個人の強みを活かし、チーム全体の成果を最大化する」という目的が達成できるからです。
たとえば、以下のような場面で活用が進んでいます。
相互理解を深めるチームビルディング研修
メンバーがそれぞれの特性やコミュニケーションスタイルを理解し、摩擦を減らし、効率的な協働を実現します。
リーダーシップ研修での応用
上司と部下のタイプを理解することで、部下に「刺さる」コミュニケーションやマネジメントが可能になります。
適材適所の人員配置
診断結果を基に、社員の特性やキャリア志向を把握し、より適切な業務アサインや役割分担を行えます。
これらの診断は、単に「楽しい診断ツール」ではなく、組織全体のコミュニケーション効率やパフォーマンスを向上させる実践的なツールとしても機能しているのです。
本記事の目的
さて、本記事では、流行しているMBTIをはじめ、ストレングスファインダーやFFS理論、PCMなどのコミュニケーション診断について、その特徴、使い方、そして職場や日常での実践方法を解説していきます。
診断ツールは、「自分を知る」「相手を知る」「互いに理解し合う」というプロセスをサポートしてくれます。その結果、人間関係のストレスが減り、協働がスムーズになるだけでなく、組織全体のエンゲージメントやパフォーマンス向上にもつながります。
一部のツールは研修会社の専売特許になっていますが、一部無料でできるツールもあるので、ぜひ気軽に使ってみてください!
目的の異なるコミュニケーション診断がまとまったサイトを見つけられなかったので、新しい診断ツールを発見したら適宜追加していきます!
1. コミュニケーションタイプ診断の目的
改めて、いろいろあるコミュニケーションタイプ診断に共通する目的を定義してみました。それぞれの診断によって特徴はありますが、抽象化すると根っこにある目的は重なる部分が大きいです。
自分の強みを理解し、言語化する
自分の得意分野や行動特性を診断を通じて把握し、具体的な表現で他者に伝えられるようになります。チームでの相互理解を促進する
メンバー間でお互いのタイプを共有し、意見の違いを「異なる」ものとして受け入れ、効果的な協力体制を築きます。適材適所な業務アサインを可能にする
診断結果を活用して社員の強みやキャリア志向を整理し、適切な人員配置や役割分担に役立てます。
2. コミュニケーションタイプ診断の種類と特徴
ここでは、主要な診断ツールについて特徴や活用ポイントを詳しく解説します。詳細はそれぞれのサービスや研修会社のサイトでご確認いただきたいので、情報収集の参考としてお役立てください!
(1) FFS理論
特徴: 人の行動特性を「保全性」「拡散性」「論理性」「感情性」「持続性」の5つの因子で分析
ルーツ: 小林春男博士による行動科学の研究
研究背景: 5つの因子がどの程度自分の中に存在するかを可視化し、ストレスや行動傾向を測定
活用方法:
相手の行動特性に応じたマネジメント:
例えば、保全性が高い部下には「挑戦しよう!」ではなく、「しっかり準備して、安心したら挑戦してみよう」という言葉が効果的。
一方、拡散性が高い上司の場合、「とりあえず試してみよう!」がよく使われますが、保全性が高い部下には通じにくいことがある。

何をしてもらったら嬉しいか」はタイプ次第で、
同じ言葉を使っても、全く違う意味を想像していることすらある。
異なる特性を尊重する:
「自分とは違うタイプだ」と認識し、好奇心を持って相手に向き合うことで、職場でのストレスを減らすことができる。

(参考図書)「宇宙兄弟とFFS理論が教えてくれる あなたの知らないあなたの強み」
(ガチ診断)ヒューマンロジック研究所
(2) ストレングスファインダー
特徴: Gallupが開発した診断ツールで、個人の「強み」を34の資質に分類。特に上位5つの強みを提示
ルーツ: ポジティブ心理学の創始者の一人、ドナルド・クリフトン博士による研究
研究背景: 約200万人以上のデータに基づき、個人の才能を科学的に分析
活用方法:
現在の仕事と強みの接点を探る:
今の仕事が自分の強みをどの程度活かせているかを考える。現在の役割が、自分の得意な領域と一致している場合、成果を最大化するためにさらに強みをどう活かせるかを模索する。強みが原因で起きる衝突を理解する:
強みを持つ人は、その強みが理由で周囲にイライラされる場合がある。例えば、分析力が高い人が「何度も確認しすぎる」と見られることがあるため、周囲との摩擦を避けるために「自分の大事にしたいこと」を共有するのが有効。内省ワークを取り入れる:
強みをもとに、大事にしたい価値観をドリルダウンすることもできる。裏を返すと、自分が本当に大切にしたい価値観を深掘りすることで、強みの使い方をさらに洗練させられる。
豆知識⚡️:
同じ方が2回実施したとき、結果が変わることがある。その場合、1回目の方が正しいと言われる。
なぜなら、2回目は問から類推(この設問はあの回答に繋がっているだろう)することができるから。

ちなみに、私の結果は2024年現在、最上志向、戦略性、着想、未来志向、学習意欲でした。
2018年に実施したときと同一の資質は、最上志向、着想、学習意欲です。
この3資質を生涯かけて育んでいきます。(笑)
(3) PCM (プロセス・コミュニケーション・モデル)
特徴: 個人の認知スタイル(脳で情報を捉えるか、感情で捉えるか)やストレス対処の傾向を分析
ルーツ: NASAが宇宙飛行士の選抜に用いた理論を基に、タウビ・ケーラー博士が開発
研究背景: 認知スタイルは生涯変わらないとされ、合理性・感情性のバランスが異なることで行動の多様性が生まれる
活用方法:
相手の「優しさフィルター」を理解する:
例えば、感情的なタイプの人に「優しい言葉」をかけることが有効だが、合理的なタイプの人には事実に基づいたサポートが響くことがある。ストレスサインを観察:
ストレス時にどのような行動を取るかを予測することで、ストレス環境下に置かれたチームメンバーに効果的なフォローが可能になる。

上記の図で言わんとしていることは、優しさの定義すら人によって異なるということ。
例えば、体調が悪い時に、「大丈夫?熱ある?」と感情的にアプローチする方もいれば「薬は買った?熱何℃?」と合理的にアプローチする方もいる。つまり、私たちのコミュニケーションで生じる行き違いは、世の中を見る認知スタイルが異なるだけということ。
(4) ラブ・ランゲージ
特徴:
自分と他者の「愛情の受け取り方」を知り、関係をより良くするためのフレームワークルーツ:
ゲイリー・チャップマン博士の著書『5つの愛の言語』に基づく研究背景:
愛情表現を「言葉」「時間」「贈り物」「行動」「身体接触」の5つに分類活用方法:
試行錯誤を前提に:
相手がどの愛情表現を好むかは試してみないとわからない。一つの方法が響かなければ、別のアプローチを試してみることが大切

(5) MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)
特徴: 16の性格タイプに分類する心理テストで、行動や考え方の傾向を理解
ルーツ: カール・グスタフ・ユングの心理学的タイプ論に基づき、キャサリン・ブリッグスとイザベル・ブリッグス・マイヤーズ母娘が1940年代に開発した
研究背景: ユングの理論を基にしつつ、長年の研究を経て開発されたツールで、性格傾向を「外向・内向」「感覚・直感」など4つの指標で分類
活用目的:
チーム内でのコミュニケーション改善や個人の適性理解に使用
補足:正確には16personalitysとMBTIは異なります!

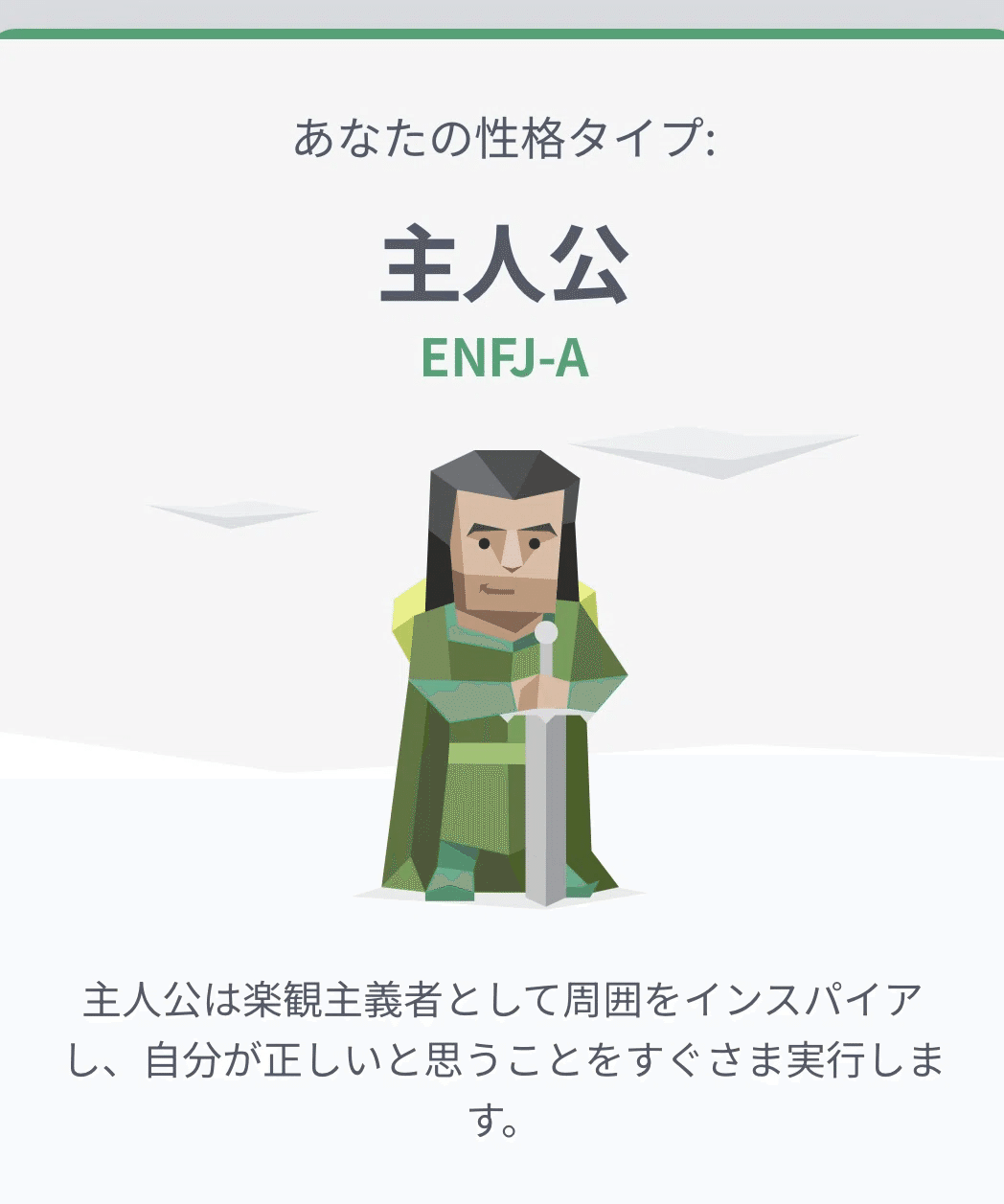
(ということで、詳細は他の方を参照ください)
(6)コミュニケーションタイプ診断
特徴: 「感情表出」と「自己主張」という2つの軸を基に、コミュニケーションのスタイルを4つのタイプ(コントローラー、プロモーター、サポーター、アナライザー)に分類。それぞれの特性に応じたコミュニケーション方法を提案し、相手に合わせた対話を可能に
ルーツ: 「タイプ分け™」は臨床心理学や組織行動学の理論を基に、企業に勤める2万人以上(20歳以上)を対象とした対人関係とリーダーシップに関する調査結果を反映して開発された。「他者とのコミュニケーションが人を最も特徴づける」という考えに基づく
研究背景: 行動科学や心理学の知見を取り入れ、個々のコミュニケーション傾向を測定。特に「感情表出」と「自己主張」の2つの軸を基にした分析は、実践的で直感的な分類方法として評価されている。また、自己認識と他者理解を促すため、個人の傾向を把握するだけでなく、コミュニケーション改善を目指すツールとして設計
活用目的:
自己理解の促進:
自分のコミュニケーションスタイルを認識し、相手に合わせた柔軟な対話を実現職場での応用:
営業や顧客対応、チームビルディング、リーダーシップ開発など対人関係の改善:
自分と異なるタイプを理解し、それに応じたアプローチを取ることで、ストレスや誤解を減らす

(7)エニアグラム診断
特徴:
エニアグラム診断は、人の性格を9つのタイプに分類し、それぞれのタイプが持つ動機や行動パターンを明らかにする診断ツール。性格の根本にある価値観や恐れを理解することで、自己成長や他者理解を促すルーツ:
エニアグラムの起源は古代ギリシャ哲学や中東の宗教的思想にあるとされている。その後、20世紀にオスカー・イチャソやクラウディオ・ナラニョによって、心理学的な要素が取り入れられ、現代的な診断ツールとして発展研究背景:
エニアグラムは心理学の理論を基に、性格や行動を深層的に分析するフレームワークとして広く研究されている。9つのタイプは、特定の「基本的欲求」や「恐れ」に基づいて分類され、それぞれのタイプがどのように他者と関わり、自分を守ろうとするのかを探求される活用目的:
自己理解:
自分の行動や感情の裏にある動機を知り、より健全な自己表現を目指すチームビルディング:
チームメンバーの異なる動機や価値観を理解し、協力関係を築くリーダーシップ開発:
各タイプの特性を活かしたマネジメントを行い、メンバーの成長を支援する対人関係改善:
他者のタイプを理解することで、ストレスや誤解を減らし、円滑なコミュニケーションを実現する

3. 診断結果の活用とコミュニケーション改善
ここまで、複数のコミュニケーション診断の特徴を紹介してきました。
コミュニケーション診断を効果的に活用するためには、結果を単なる自己理解に留めず、日常の職場環境で実践することが重要です。
「異なる」ことを受け入れるスタートにする 意見が合わないとき、「間違っている」ではなく「異なっている」と考えましょう。相手が何を大切にしているかに焦点を当て、違和感をぶつけるのではなく、好奇心を持って向き合います。
役割や状況によるタイプの変化を理解する 職場では「表層的なタイプ」が変化することがあります。例えば、普段は合理的なタイプの人が、友好的な姿勢を意識する場合もあります。
自分の大事にしたいものを明確にする 診断結果を深掘りし、何を重視するのかを内省することが、実際の行動に結びつきます。
4. まとめ
コミュニケーション診断は、自己理解を深めるだけでなく、組織全体のコミュニケーション改善や生産性向上に貢献します。
診断結果を日常の中で活用し、「異なる」ことを受け入れるスタンスを持つことで、チーム全体の相互理解が進みます。
自己理解、他者理解の輪を広げていきましょう!
