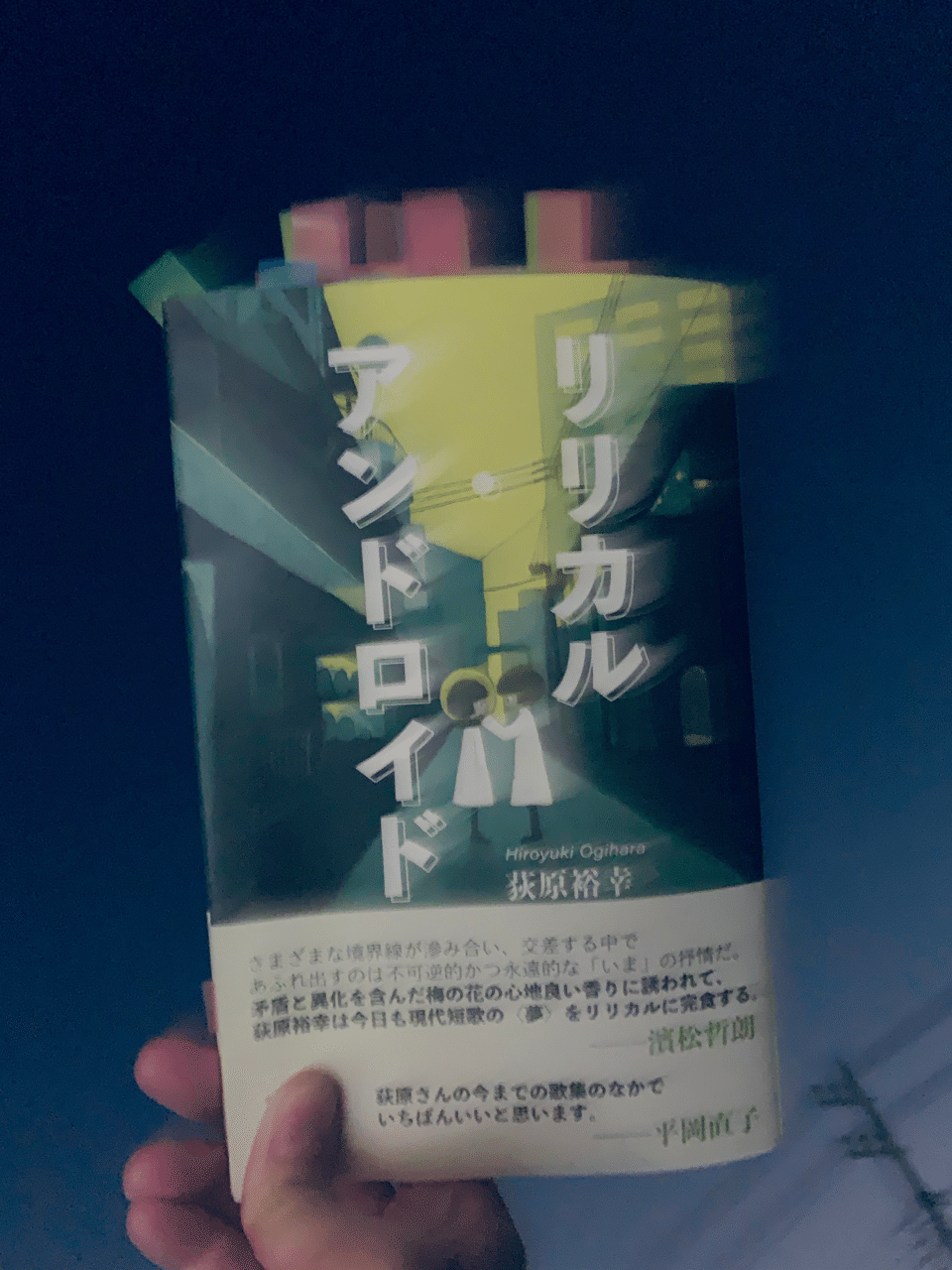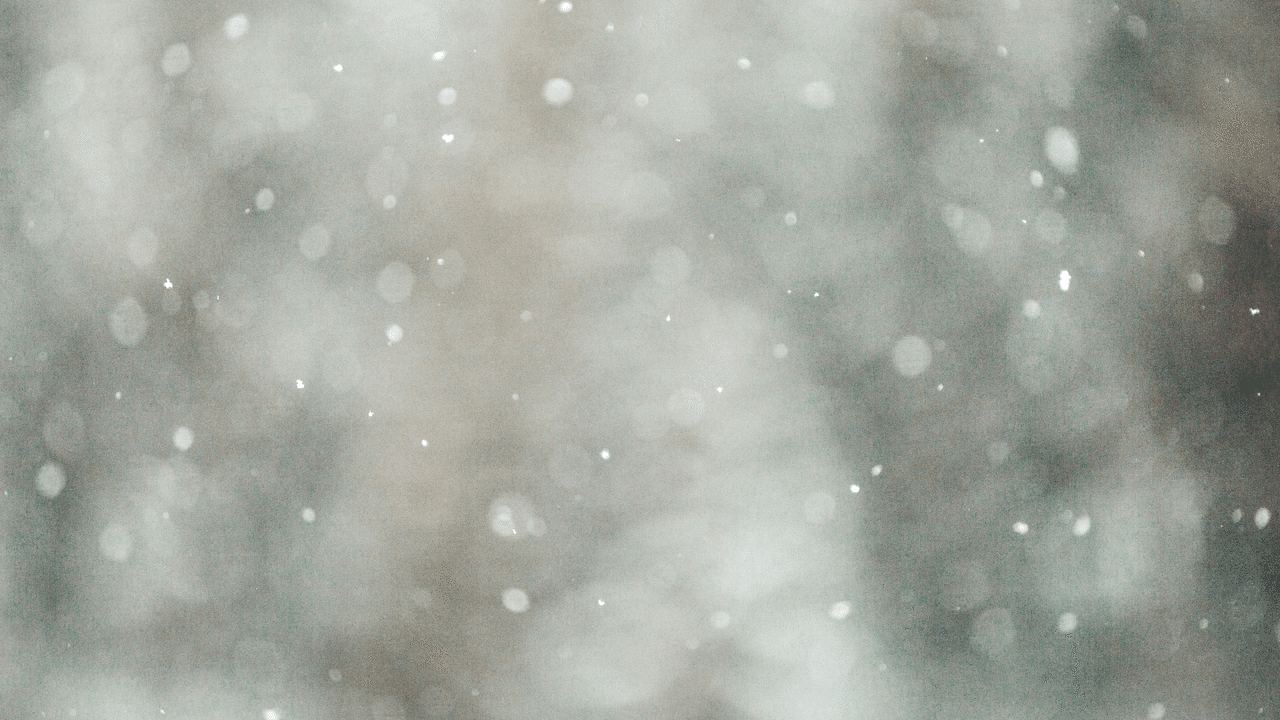読書感想文|荻原裕幸歌集『リリカル・アンドロイド』|亜久津歩
永遠は淡い葉陰のなかに|亜久津歩
荻原裕幸歌集『リリカル・アンドロイド』を読んで
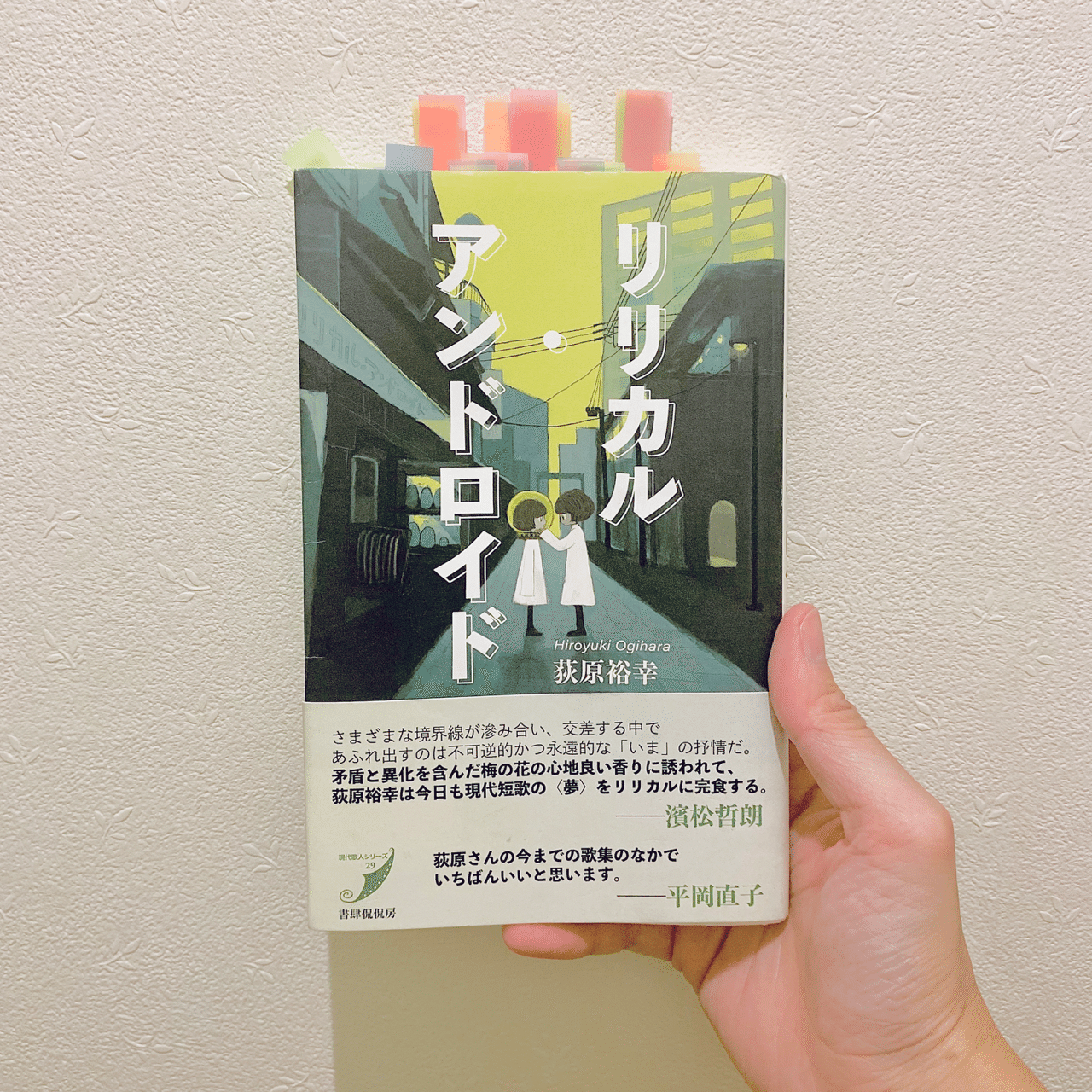
荻原裕幸第六歌集が十九年ぶりに出ると知ったとき、スマホを握り飛び上がった。その名も『リリカル・アンドロイド』! 咄嗟に“荻原裕幸”または作中の“私”の比喩ではと思った。半永久的に叙情する人型装置(『デジタル・ビスケット』を食べそう)、人のようで、人でないもの。わたしはもともと荻原作品にそうした印象を抱いており、愛好しているせいかもしれない。
同書には収録されていない連作について以前、下記の小文を寄せた。ここで書いた「私はもう、この聴力を想像力や表現力などと呼んでいいのかわからない。まるで半神半人の言葉を聞いているようだ」という感触は、今回にも通じている。
実在する名称や季語、耳慣れた口語を用いつつ現実離れしたことをさも当然のように言う。「〜を見てゐる」「〜を聴く」と“ない”ものを指されながら、脳のどこかに生じるひっかかりも、曖昧な共感や77577を始めとする初句七音のなめらかな流れのなかに消えていく。それが妙に心地よいのだ。
(このあたりの技巧を「幻を読者に共有させる」として中本速さんがとても分かりやすく書かれていた。また、榊原紘さんのnoteの「生と死、あるいは現実と夢……その他、のあわい」にある「こわさ」にも強く首肯したので、リンクを貼らせていただきます)
おくすり飲めたね 荻原裕幸『リリカル・アンドロイド』は幻をたぐりよせる(中本速)
共感の向こうへ、輪郭の少し外へ。方向性はきっとそのままに、今回さらに感じられたことを述べてみたい。なお、歌集中の主体はある程度共通するものと解釈し、連作を縦断して記す。
ひかりからゆるやかに淡い陰のなかへ
優先順位がたがひに二番であるやうな間柄にて梅を見にゆく
巻頭歌。そういうものだ、と思う。いくら聞こえのよいことを並べてみてもこの世の多くは、きっとそういうものだ。「一番」は別の誰かや自分自身かもしれないし、短歌かもしれない。だから満開の桜より「梅」が合う。これは妥協や諦めとはちがうんだよと言ったら、若い頃のわたしは信じたろうか。『リリカル・アンドロイド』において、劇的な事象や大仰な言葉は注意深く避けられている。それはこの関係性にも言えるだろう。
こきざみにまばゆきものは炎えつきるときどきかはる玄関の花
常に世界にひかりを望むといふやうな姿勢ゆるめて緑陰をゆく
魂魄その他がやはらかくなるやうな気がして入りゆく桜の葉陰
「まばゆきもの」を追いかけて、「ひかりを望」んできたはずだ。光は自身をも焼き影を濃くし、強いコントラストは淡色を消し去る。そして「こきざみに」「炎えつきる」ところも見てきたのだろう。行き先が緑陰、桜の葉陰であることに安堵を覚える。なお「影ばかりを見て噴水を見てゐないのだと昨夜の非を誹られる」(P85)というときには「影」の字が現れる。陰→影→闇、と暗がりは深まる。ゆるみ、やわらかくなることを許されたい。許してあげてほしいと思う。
もはや手の届かないひかりの奥にいつまでも鳴りつづける電話
菜の花はひかりもみづも奪ふのでできるだけ遠くに挿しなさい
一方で「ひかり」を欲することを否定しない。これは矛盾ではない。こころは複雑なのだ。紋切型の極論、座標軸のあわいに限りなく存在するグラデーションを掬い取る。これは傾向や好みというより、覚悟や信念のように思われる。
生きることの反対は死ぬことぢゃない休むこと夕焼の向うへ
善と悪とのどちらでもないものばかり揺れてわたしの庭の六月
この思惟はかたちくづれて日常の死角に消える水なのだらう
ここと、ここを巡る季節のなかで
爆弾も降らない天使も降りてこないどこまでも梅雨続く昭和区
半生のほぼすべての朝を瑞穂区にめざめてけふはあぢさゐの朝
日常の風景としてそのまま読むこともできるが、「爆弾」も「天使」もこれまでの荻原作品にあるモチーフで、作品あるいは歌人としての道のりを示唆しているようだ(あとがきの言葉を借りれば「暴走と迷走を繰り返した日々を経て」)。劇的なことの起こらない、派手な花も月も雪も特に見頃でない、観光地でもない区内(作中に出てくる昭和区や瑞穂区は名古屋の地名だ)。それでも作り続けていく、作っていけるのだということに感じ入る。外へ遠くへと向かい拡げていくだけでなく、町の中で型の内側で解像度と想像力を上げ細やかに発見を重ねる。「どこまでも梅雨」は単体で読むと閉塞感や憂鬱な印象を受けそうだが、ここでは不思議な心地よさに包まれる。
夏のひざしのほかには特に飾るべきものなく3LDKしづか
春の朝があると思つてカーテンを開いた窓の闇におののく
桜の底はなぜこんなにも明るくて入ると二度と出て行けぬのか
妻がベランダから何か言ふ春の瀬に溺れるひとのやうな身ぶりで
同書は季語や季節的な表現に満ちており四季それぞれが詠われているが、梅雨と秋には主体との穏やかな連結を感じる。陰影が多く、薄淡いせいかもしれない。たとえば「夏のひざし」はそれだけで飾っておけるほど特別なものであるし、春には軋みや人知れず飲みこまれるような仄暗い苦しさがある。冬は白い沈黙と眠りの季節だ。
秋の歌は、恋愛を詠んだものでもしみじみと好きな作品が多い。言葉が過ぎず、嘘のないところが好きだ。
自分ひとりで探し出せない秋からの出口のやうにあなたが笑ふ
デジカメであなたを撮ってほとんどのあなたを消してゐる秋日和
妻のこゑとわたしのこゑがこの家のこゑのすべてである秋の暮
秋のきはみのふたりと思へ果実から果実へわたる軟かなきず
秋は時に、詩神のような他者にもなる。作中、木蓮や山茶花などしばしば花がしゃべるのだが(わたしはこれらは擬人法ではなく“聴こえている”と読んでいる)話す季節は秋だけだ。
秋がもう機能してゐるひだまりに影を踏まれて痛みがはしる
秋がまだ何かをせよと云つてゐるからだの奥で木琴が鳴る
影は自分の一部で痛覚まである。秋の「ひだまり」にさえ、踏まれて痛むほどの。その過敏とも言える感性を想像すると泣きたくなる。歌人としてはすばらしい才能に違いない。わたし自身「人じゃないみたい」と言い、慈雨を仰ぐようにその歌を甘受してきた。けれどその繊細過ぎる知覚を備え、人として人の世界“を行く”意味を、改めて思った。
人の世界を行く、きっと永遠のなかの
新緑を着て新緑のなかを行くどこにもゐないひととして行く
他人には発見されぬひとがたのしろきかたちで三月を行く
機械ではないものとして揺れてゐた天まで熟れる秋の時間に
どんな音かはともかくも音たてて壊れるものに属すると思ふ
リリカル・アンドロイド。しかし「臓器」や「みづ」を痛覚を、感情を宿してしまった人体、それはつまり人間なのだ。
諭したくなる淡雪よひるひなかそんなところに積らなくても
この私はどうしようもなく春の雪どうしようもなく荻原裕幸
「淡雪」「春の雪」ともに春(三春)の季語である。周りより遅れて降り、すぐに溶けてしまう雪。俳句に詳しくなくとも儚さをイメージしやすい言葉だ。儚く淡く、うつくしく寂しい。
その「春の雪」に己が響く。「どうしようもなく」というやるせなさを受けながら、HaRu-ユキ・HaRa-HiRo-ユキとして存在する「この私」。「この私」という言葉に荻原作品らしさがある。他にどの私がいるのか、別の人、別の時間、次元、世界線、存在? 「この私」は「どうしようもなく春の雪」として消えていく(けれど、きっと永遠のなかにある)。
・
卵、枇杷、ベランダの貘、移動後の空間、韻律についてーー話したいことはいくらもあるが、このあたりにしようと思う。ぜひ歌集を手に取り、味わってほしい。
あとがきに「モチーフがメランコリックなものを含むときでも」「私が、短歌をこころから楽しんだ季節の記録として」とあり、ほっとした。新型コロナの流行以降、生活は一変し悲しいニュースも続き、蛇足と思いつつどの立場から言っているのだと恐縮しつつ、こんなことを書き加えてしまう。
荻原さん、この歌集も、わたしにとって特別な本になりました。荻原裕幸「第七歌集」の誕生がまた十九年後でも明日でも、わたしは必ず買い求めますし一首一首を大切に読みます。短歌を始め、続けてくださって、本当にありがとうございます。どうかこれからも、お元気でいてください。