
少し専門的なデザインの話2
前回の続きです。
本ブログでは様々あるデザインを以下のように類別しています。
・視覚・意匠に着目した図案表現型デザイン
・機能・性能に着目した工業型デザイン
・行動・思考に着目した問題解決型デザイン
今回は工業型デザインについて詳しく解説していきます。
工業型デザイン(プロダクトデザイン)とは
デザインと一口に言っても色々あります。外見を彩る意匠的な意味のデザインや、製品によって生活を豊かにするにプロダクトデザイン、他にも行動心理学に基づいた問題解決型のデザイン、、、等々。
プロダクトデザインとは、二次産業である工業との関わりが深いデザインで、当初は商品のスタイリングが対象でした。しかし技術が発展し、ライフスタイルが多様化するとユーザーはさらに心理的・身体的な快適さ、つまり機能面での価値も求めるようになりました。
また近年では情報通信と提携した製品も増え、プロダクトデザインは三次産業との関わりにも足を延ばしています。
では、このプロダクトデザインに求められるもの何でしょうか。
プロダクトデザインの美
プロダクトデザインの本質的な美は「機能美」と「使いやすさ」です。(=用の美 :機能的であると共に手にして初めて心を満たすこと)
「機能美」とは、盛り込みすぎたプロダクトから無駄を削ぎ落とし本来の価値を引きだすプロセスです。
「使いやすさ」は心地良い操作感や誤操作を起こさないデザインを指します。そのためには「人間工学」や「エルゴノミクス」の知識が必要です。
(エルゴノミクス :人と機械の関係を「マン・マシン・システム」として捉え、人と機械の最適な関係づくりを目指すもの)
本記事で説明する様々な考え方から、この2点の理解が深まったらと思います。
それでは本編に入ります。
フィッツの法則
目標物に到達するまでに要する時間は、 目標物の大きさと、目標物までの距離で決まるという法則です。
例えば、コンピュータでカーソルを操作する場合、対象物が大きく近い程すぐに指すことができます。
操作や制御を司る装置を設計する際は、フィッツの法則を適用するべきです。
80対20の法則
2割の要素が事象の8割を生み出している、という考え方です。
例えばある製品の欠陥の80%は、その構成パーツの20%が原因といわれています。この法則を用いることで、 様々な要因から重要な20%を突き止め焦点を絞ることができます。
アクセシビリティ
直訳すると「近づきやすさ」、「利用しやすさ」です。要するに、どれだけ多くの人々が利用できるようデザインされているか、を問う考え方です。
例えば、 反復動作の必要性を減らし身体的負荷を抑えた構造や、例えば、交通案内の標識を多様な言語・アイコン・点字で表現するなどです。
IKEA効果
物を作るという行為が、 作り手に対し、そのものの知覚価値を高める働きをすることです。
例えば家具など、一部を手作りすると作り手はその物に高い価値を認めるようになります。
同じ製品でも人が購入意欲を持つのは、既に組み立てられた完成品ではなく、 自分が手を加えて完成させるものです。
どうぶつの森やマインクラフトといったゲームに人気があるのは、こういった効果ゆえかもしれません。
光沢感バイアス
くすんだ物体よりも、光沢感のある物体が好まれる傾向です。例えばリップ、ジュエリー、塗料などは光沢のある商品の方が好まれます。
ヒックの法則
意思決定に要する時間は、選択肢が増えるほど長くなるという法則です。
ただし、複雑な意思決定(読解や調査など)には当てはまりません。ヒックの法則が当てはまるのは、単純な意思決定の場合です。例えばAが発生したらボタン1を押し、Bが発生したらボタン2を押す、という場合です。
マッピング
操作装置と操作物の位置関係、もしくは動きを関連付けると使いやすくなるという考え方です。
例えば、スイッチを上に持ち上げると車の窓が上向きに閉まる仕組みです。他にも、電子書籍のページめくりを、実際の本のページを指でめくる身体操作に似てるなどがあります。操作がイメージできると、 直感的に利用することができます。
フレキシビリティの二律背反性
機能性を向上させると使いやすさが悪化する現象です。
機能性を追求すると必然的に複雑になります。身近な例で言うとツールナイフです。
特定の機能が繰り返し必要とされる場面では、特化された専用品が向いています。一方で、求められる機能が定まっていない場合は、多用途型の製品が望まれます。
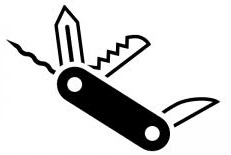
カテドラル効果
高い天井は抽象的思考を活性化し、 低い天井は具体的で細部を掘り下げる思考を活性化するという効果です。
天井の高低が際立っていると、その高さに意識が向き認知機能に影響を及ぼします。
創造性や、常識にとらわれない考えが問われる場面では、広い部屋と高い天井に設定し、反対に手術室など、細部に注意を払わなければならない場面では、こじんまりした天井の低い部屋が望まれます。
また客に長く滞在してほしい場合 (例えばカジノ)は高い天井、客の回転率を高めたい場合 (例えばファーストフード店) は低い天井にすると良いです。
希望線
使用されて傷んだ痕跡のことです。
例えば、沢山の人がショートカットして歩いたことで芝生がすり減り形成された通り道や、パソコンのキーボードで特に傷みが激しいエンターキーなどが希望線にあたります。
広義的には、ユーザーの行動によって刻まれた印もしくは軌跡を意味します。
希望線にはユーザーの強い嗜好・好みが表れ、そこから改善のヒントを得ることができます。
ゲーミフィケーション
ゲーム・デザインの戦略をゲーム以外の分野に応用する手法です。
例えば、ゲームによくある「レベルアップ」や「レイドバトル」を盛り込むことで、参加者を楽しく熱中させ、 学習や目標達成のモチベーションを高めることができます。
主ななゲーミフィケーションは以下の通りです。
・報酬を与え行動を促進させる仕組み
・フィードバックを頻繁に与える仕組み
・目標の達成度合いを可視化する仕組み
・自由に選択できる仕組み
・適切な指導がある仕組み
なお行動を促進させる報酬は、次のように大別されます。これらを上手く盛り込むことで、モチベーションを高めましょう。
・ステータス(Status / 地位)
・アクセス (Access / 入場権、利用権)
・パワー (Power/能力)
・スタッフ (Stuff / 所持品)
KISSの原則
デザインはシンプルな程、より良く機能し信頼性が高いという原則です。keep it simple, stupidの略語で、ソフトウェア開発でよく使われます。
シンプルなデザインは総じて、短期間で安く製作できます。また確実に動作する上、不具合の修理や維持管理が容易です。
費用便益分析
物の価値を次の2つから分析する方法です。
・取得するまでに必要な「費用」
・取得して以降で得られる「利益」
費用が便益を上回る場合は、そのデザインは不適切です。
費用(コスト)の中には
・身体的コスト(労力)
・感情的コスト ( フラストレーション)、
・社会的コスト (ステータス) なども含まれます。
よくある誤解として、様々な機能を付け足せば製品価値が上がるという考えがあります。この考えが当てはまる場面は、 「新しい機能によってもたらされる便益が、使い方が複雑になるという「コスト」を上回る場合」だけです。
MAYA段階
MAYA とは most advanced yet acceptableの略語です。意訳すると「デザインにおいて最も商業的に成功し得る美的段階」のことです。
人は新しいものに惹きつけられる一方で見慣れないものは受け入れにくく、MAYAはその臨界点を指します。
売れる製品は、カテゴリの定義を広げる「目新しさ」を持ちながら、なおかつそのカテゴリの一員として受け入れられる「親近感」も持ち合わせていなければなりません。
一般大衆向けのデザインでは、 MAYAの考え方は効果がありますが、デザインやアート等、専門色の強い場面ではMAYAは当てはまりません。そのような状況では新鮮味が重視されます。
擬態
広く知られている事物の特性を模倣することで、 その特性の利点をもらい受ける手法です。
デザインの擬態には次の3種類「外観、 行動、機能」があります。
・外観の擬態
事物の見た目を真似ること (例えば高価なブランドのコピー商品)。
・行動の擬態
事物の振る舞いを真似ること (例えば人の表情を真似するロボット)。
・機能の擬態
事物の働きを真似ること (例えば計算機のキー配置を見本にした押しボタン電話)。
モジュール方式
大規模なシステムを、独立した小規模なシステムに分割することで扱いやすくする方法です。
システムの様々な機能をグループ分けしたのち、各グループを独立したユニットとして再編成する手法です。このユニットをモジュールと呼びます。
モジュール方式を導入するとシステムの補修、サイズ変更、アップグレードなどが容易になりますが、その分設計は複雑になります。
通常は、初期段階からモジュール方式では設計しません。一連の機能の完成度が高まるにつれて、徐々にモジュール方式へと移行します。
スケーリングの誤解
一定のスケール(規模)で機能するシステムが、 縮小または拡大したスケールでも常に機能すると誤解することです。
代表例として、空を飛ぶ羽ばたき運動があります。羽ばたき運動は、虫程度の中スケールでは上手く機能します。しかし、スケールが極端に小さくなった場合では、空気の分子を効果的に動かすことができず飛べなくなります。 またスケールが大きすぎても、重力の影響が大きくなり飛べません。
スケーリングの誤解は2種類あります。
・荷重に関する誤解
・インタラクションに関する誤解
荷重に関する誤解とは、 システムのスケールが変化しても、負荷される力の大きさは同じであると思い込む誤解です。
インタラクションに関する誤解とは、 システムのスケールが変化しても、人々や他のシステムとの関わり方や影響は同じであると思い込む誤解です。
最弱リンク
重要な要素に被害が及ぶことを防ぐために、真っ先に破損するよう設計された要素のことです。最弱リンクは確実かつ真っ先に、壊れなければなりません。
最弱リンクの使い方は2通りあります。
・不具合発生時に動きを停止させる使い方
(例 電力ヒューズ)
・不具合発生時に被害を軽減させる使い方
(例 消火装置)
最弱リンクは、 障害が段階的に進行するシステムで役立ちます。
例えば自動車安全対策の1つとして、衝突事故の際、乗用車の前部と後部が潰れやすいよう設計されており、それにより乗員スペースに及ぶ衝撃は弱まります。
SN比
Signal-to Noise Ratioの略語です。
意味のある情報と無意味な情報の比を表しています。良いデザインはSN比が高くなります。
情報 (信号) は、時に無関係な外乱が加わり劣化ます。またその情報の表示方法が非効率的な場合も、質が劣化します
例えば曖昧な文章、不適切なグラフ、不必要なアイコンなどです。
デザインのSN比はできるだけ引き上げることが望まれます。そのためにはデザインをシンプルに保つことが重要です。
外乱を減らすには、不要な要素を取り除くだけでなく、 必要な情報に関しても過剰な表現を避けるべきです。
構造形態
建築物の基本的な構造です。マッス(量塊)構造、フレーム構造、 シェル(貝殻) 構造の3つがあります。
・マッス(量塊) 構造とは、 素材の積み上げ、または重ね合わせて作る、中身の詰まったソリッド構造です。この構造の強度は、素材の自重と硬度に応じて決まります。マッス構造が適するのは、防壁や小規模なシェルターなどで特に建築素材が限られている場合に役立ちます。
フレーム構造とは、支柱をつなぎ合わせて作る骨組形式の構造です。この構造の強度は、素材の強度と連結部の強度、 そして骨組の設計に応じて決まります。フレーム構造が適するのは、 大規模な建造物です。
シェル(貝殻) 構造とは、一定の容積を外殻で包み込む中空の構造です。骨組はなく、マッスが内部空間を占めることもなく、一定の形状を保ち、荷重を支えることができます。 外殻全体に荷重を分散させることができれば、強度は高まります。
シェル構造が適するのは、 コンテナ建築、 小規模なプレキャスト式構造物、 シェルター、 大きなスパンが必要とされる建造物などです。
観測者効果
測定作業自体が対象に影響を与え、測定結果や以降の調査が無効になりかねないという原理です。
外的要因に敏感な変数を測定すると、 測定作業自体が変数を変化させ、 測定結果や測定器の有効性を損なう可能性があります。
例えばコンピュータのイベントログは、そのコンピュータの動作状況を確認するのに役立ちますが、それ自体がコンピュータの計算資源を使うため、測定データに影響が及びます。
不確定性の度合いを決めるのは、 測定作業に対する変数の敏感さと、 測定方法の非侵入性です。
ヴェブレン効果
価格の高さが、製品需要を増加させる傾向です。
ある種の状況では、高価な製品ほど需要が増し、安価な製品ほど需要が減ります。
この効果が特に顕著にあらわれるのは、たとえば美術品、 宝飾品、衣類、車、高級ワイン、ホテル、 豪華客船など、ステータスを象徴するようなアイテムやサービスです。価格の高さは、知覚品質を高くします。
引用元
齊藤 勇, 図解 心理学用語大全: 人物と用語でたどる心の学問, 2020, 誠文堂新光社
岸 啓介, 一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 一生使えるシリーズ, 2017, インプレス
William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler,"Design Rule Index 要点で学ぶ、デザインの法則150",2015, ビー・エヌ・エヌ新社
OCHABI Institute, コンセプトが伝わるデザインのロジック, 2020, ビー・エヌ・エヌ新社
森重湧太, 一生使える見やすい資料のデザイン入門, 2016, インプレス
