
俳句のいさらゐ ◬👁◬ 松尾芭蕉『奥の細道』その十六。「涼しさを我宿にしてねまる也」
今回は、尾花沢での芭蕉と曽良の俳句を解釈する。
尾花沢にて清風と云者を尋ぬ。かれは富るものなれども志いやしからず。都にも折々かよひて、さすがに旅の情をも知たれば、日比とヾめて、長途のいたはり、さまざまにもてなし侍る。
涼しさを我宿にしてねまる也
這出よかひやが下のひきの声
まゆはきを俤にして紅粉の花
蚕飼する人は古代のすがた哉 曾良

先ず、芭蕉の最初の俳句「涼しさを我宿にして ねまる也」の「涼しさ」は、宿を提供してくれた人物の名、清風に通わせた言辞である。あなたの名のとおりのすがすがしい宿です、と感謝の意をこめた。芭蕉は、人や土地の名を、俳句の中に生かすという意識が大いにあったと言えるだろう。
例を挙げれば芭蕉の『更科紀行』中の俳句に、
「いざよひもまださらしなの郡( こおり )哉」
があり、その「さらしな」は更科の地名に、去らじな ( 未だ去らず ) の意味を重ねている。
『奥の細道』では、須賀川で雅号、栗斎という俳人のことを
「世の人の見つけぬ花や軒の栗」
と、その雅号の栗を引き合いにした俳句を詠んでいる。
次の俳句、「這出よかひやが下のひきの声」の、ひき ( 蟇 ) は《 かはず 》であるから
朝霞鹿火屋 ( かひや ) が下に鳴くかはづ声だに聞かば我れ恋ひめやも
読み人しらず「万葉集」2265
が、俳句の下にある和歌とほとんどの解説書は説いているが、
草枕旅に物思ひ我が聞けば夕かたまけて鳴くかはづかも
読み人しらず「万葉集」2163
もまた、芭蕉の脳裏に浮かんだ歌としてふさわしかろう。
また、俳句の意味としては、こういう気持ちのよい夕べなのだから、蟇蛙であっても這い出して来て、鳴くがよかろう、という思いと見れば、
今日もかも明日香の川の夕さらずかはづ鳴く瀬のさやけくあるらむ
上古麻呂「万葉集」356
の歌の気分にも通じているだろう。この歌の気分は、翻って初句「涼しさを我宿にしてねまる也」にも通じる。
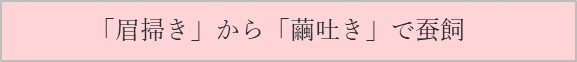
そしてここから、あとの三句は連想で呼び起こしつなげる遊びをしているのではないかというのが、私の解釈である。
注目するのは「ひき」。この音から、かわずとは全く逆の「美姫 ( びき )」あるいは「悲姫」を連想させて、艶麗のイメージにより、次の俳句「まゆはき」( 眉掃き ) につないでゆく。ちなみに広島県では、かわずをビキという方言があり、西日本一帯でビキに似た言い方をするようだ。
そして次の曽良の「蚕飼する人は古代のすがた哉」は、その語音を「繭吐き」と変えて、繭と言えば蚕飼と、持って来たのだろうと思う。
つまり、眉を掃くと、蚕が繭糸を吐くの、異なる「まゆはき」の連想でつないでいる。しかしあくまで、俳句の表は、「古代のすがた哉」と、土俗の、素朴なイメージに収めている。
ただ、「まゆはきを俤にして紅粉の花」の芭蕉の俳句は、尾花沢を出て立石寺へ向かう途中吟であるようだから、曽良が見た「蚕飼 ( こがひ ) する人は古代のすがた哉」の情景も、「まゆはきを俤にして紅粉の花」と芭蕉が詠んで以降の旅中ととらなければ、俳句をつないだ根拠はなくなる。
こういう連想は言葉遊びだから、俳文紀行に格調を与えたい芭蕉が、そういう構成を用いるとは思えないという考えもまた一面正しいとは思うが、芭蕉が生涯情熱的に取り組んだ連句というものに目を向けてみると、前の俳句に対し、連想で場面を転換するのが最大の面白味で、その際、言葉遊びがひとつの手法であるのがわかる。
『奥の細道』においても、同じ考えを以て、俳句を並べていると考えてもおかしくはないだろう。

例を挙げよう。蕉門の連句集「猿蓑集 巻之一砂 冬」から。
砂よけや蜑 ( あま ) のかたへの冬木立 凡兆
棹鹿のかさなり臥る枯野かな 土芳
これは、蜑のかたへが漁師の家を意味し、そこからの連想で続く俳句の「さを鹿 ( 雄の鹿 )」に、船漕ぐ「棹」の字を当てて前句とのつながりを持たせながら、場面を転換しているのである。
この俳句を芭蕉は、半残 ( 門人ー伊賀蕉門 ) 宛て書簡において、「土芳鹿の句、皆々感心申候」と褒めている。そこに連句の興味、面白さを見ている証拠だろう。
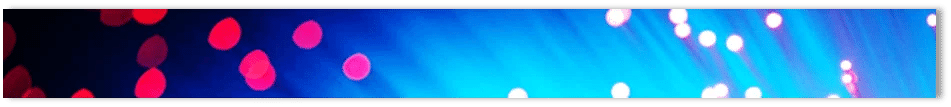
また『奥の細道』の中には、「早苗とる 手もとや昔しのぶ摺り」は、昔をしのぶとしのぶ摺りの掛詞、「蛤のふたみにわかれゆく秋ぞ」の「ふたみ」は、二つの身と、蓋と中身の意味の掛詞を使った俳句があり、この技法を詠句の際に、つねに意識していたのは明解なことである。
令和6年6月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
