
俳句のいさらゐ ⩥⩙⩤ 松尾芭蕉『奥の細道』その四十。「あらたふと青葉若葉の日の光」
芭蕉は、『奥の細道』の日光の章で、
あなたふと青葉若葉の日の光
の初案を推敲して
あらたふと青葉若葉の日の光
にした。
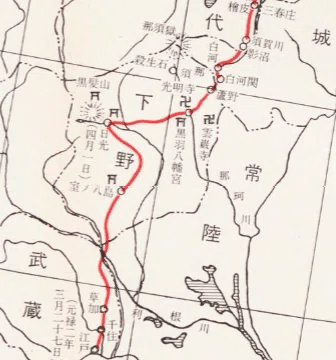
「あな」と「あら」の違いで、句意は変わらない。
今回の考察は、なぜ、「あら」だったのか。そこを考えてみる。
先ず古典和歌と、現代短歌から「あな」の作例を示す。
あな恋し今も見てしか山がつのかきほにさける大和撫子
読人知らず 『古今和歌集』
母が目をしまし離れ来て目守りたりあな悲しもよ蚕のねむり.
斎藤茂吉 歌集『赤光』/「死にたまふ母」連作中一首
「あら」の作例を次に見る。
花ゆゑゆゑに顕れたよなうあら卯の花や卵の花や
『閑吟集』三十番
『閑吟集』俗謡の作例がよく表すように、「あな」と比べれば、一読「あら」の方が、人の生の息遣いを即興で伝える感じが強いのがわかる。
今日においては、「あな」は、おそらく短歌俳句でのみ使われるだけだろう。それも意識して古語を使う場合のみだ。今日においては詩歌だけの特有の語であろう。
「あら」の方は、今日では詩歌においても使う例を見たことがない。「あら」は、日常生活の俗語、口語に変質している。それも頻繁に使われている。その意味では、「あら」の方が歳月の風雨をくぐって生き延び、それゆえに詩歌用語としては絶えたと言える。「あな」はその逆である。


芭蕉が、二荒山 ( ※にこう、の読み方が日光に転じたという説がある ) での感動をより生な印象として表すのに、初案「あな」を、口語調の「あら」に推敲したという解釈は、私の目にした解説諸書のほとんどが述べていることだが、私はその前に、芭蕉がはっと気づいたことがあって、その成果がこの俳句になったと思っている。
先ず、この俳句の前文の一部を示す。
往昔 ( そのかみ ) 此御山を「二荒山 ( ふたらやま ) 」と書きしを、空海大師開基の時、「日光」と改給ふ
芭蕉がこのように前文に書いた意図は、
二荒=ふたら
という音を前もって示すためであったと思う。
前文のふたら=「FUTARA」と、
俳句の、あら=「ARA」の、
ARAの音を重ねる遊びをしているのだ。
俳句の前に二荒山 ―ふたらやま— と先ず声に出して、そのあとで、あらたふと青葉若葉の日の光、と続ければその意図が浮かび上がって来る。
さらには、
「あらたふと」は、「ARA、TAFUTO」で、
その音「FUTO」( ふと ) と、
ふたら=「FUTARA」の ( ふた ) の
語感の近しさも耳に残るように考えているのではないか。
たふとは、尊いの意だから、文字に起こせば、TOFUTOになるのかもしれないが、TAFUTOとTOFUTOどちらにも聞き取れる、つまり「と」と「た」、「う」と「ふ」の中間のニュアンスを持った発語を、当時の人はしていたのだろうと思う。
そして青葉=「AOBA」、
若葉=WAKA「BA」と、
バの響きを重ね、
ひのひかり=「HI、NO、HI、KARI」と、
子音のイ音が後を引くような言葉を選んでいる。
バ音の切れる強さと、イ音の余韻、それを組み合わせている。
そういう言葉の音律の演出は成功していて、若葉という言葉から浮かぶイメージに相応しく、弾んだこころ映えを示す効果を生んでいる。


「日の光」という措辞に、東照大権現家康公崇拝の意をこめたのが、この俳句の核心という定説の解釈があって、その見方が的外れとは思わないが、先ず第一に、音感、ことばの響き合いを、読者に提示して見せようと意図したのがこの俳句であると私は思う。それは『奥の細道』を、読んで面白い紀行にするためである。
以前、松平定知アナウンサー朗読の『奥の細道』を聞いたことがあるが、音で入って来ることばには、ところどころ、はっとする部分があった。読んで知っていても、場面の印象が違って浮かんで来た。その一つが、上に述べた気づきである。
私の一連の『奥の細道』解釈記事で述べてきたように、芭蕉は、読んで面白い紀行にするために、連句仕立て、掛詞、本歌取り、古歌の独自解釈による転用、著名な物語の場面借り、前出俳句と後出俳句の意図的な連鎖、逆意をうたう曽良の俳句あえて並べる対比配置、曽良を教師、自身を学徒にして、名跡案内を語らせる、などなどたいへん手の込んだ演出を全編に施している。
その一環としての演出が、「あらたふと青葉若葉の日の光」にも表れているのである。


二荒は、命名の源は、補陀落 ( ふだらく )=観音菩薩の浄土、 であるという。
ふたら と ふだらく。補陀落山とはさすがに名づけられなかった。
その次の意が「二」にこめられているだろうか。「荒」は、強い・厳か・立派の意味を持つ。
空海の『性霊集』にもその記述はあり、芭蕉は補陀落については触れてはいが、「空海大師開基の時、「日光」と改給ふ」という前文から推し量れば、それは芭蕉の知識のうちにあったわけだ。
元禄の世で、徳川家に恩ある伊賀上野藤堂藩に生まれ、江戸に住まわっていた芭蕉に、自然の情としてあった東照大権現家康公崇拝の思いにとどまらず、さらに心の奥まで見通してみれば、空海の故事から補陀落までを思い浮かべて、あらたふとと詠んだと解釈してみるのも、芭蕉のこの俳句を深く大きく味わう、読者の愉しみ方であろう。
令和6年12月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
