
ワタクシ流☆絵解き館その262 明治生まれ世代の「海の幸」「わだつみのいろこの宮」評
青木繁の二大名作のうち、「海の幸」は、その絵柄の不可思議さと迫力とが現在なお絵の価値を更新し続けていることを、「わだつみのいろこの宮」は、1907年(明治40年)3月20日から7月31日の東京府勧業博覧会においては、情実による三等賞という入選末席の評価しかなかったが、まだまだ調べ尽くされていない青木の修養の末の集大成作であることを、「ワタクシ流☆絵解き館」の記事で何度も触れて来た。
では、東京府勧業博覧会では、鑑賞者にどんな感想を持たれたのか、またその後どのように好まれて、その思いが表現されて来たのかを併せて今回紹介する。発表時には低評価もあり、絵の斬新さを受け入れたかどうかで、評価を大きく分けたのが見て取れる。

上部〇囲いが青木繁 人を食った性格が躍如の一葉だ
⭐ 青木の絵を讃える著名詩人の詩
青木繁の絵画芸術を評価した著名人の顔ぶれを見るとき、小説の自作で触れて褒めた夏目漱石を別格として、蒲原有明、岩野泡鳴の両詩人を筆頭に、
与謝野鉄幹、与謝野晶子、安江不空、前田林外、坂本四方太 ( さかもとしほうだ ) 、河井酔茗、高島宇朗、木下杢太郎、児玉花外、野田宇太郎ら、明治生まれの第一線の歌人俳人詩人などの文学者に、未だ今日ほどの盛名なき時期から、青木を賞賛する者が相当数いるのは特筆すべきことだろう。
上に挙げた名以外で、小説家・詩人佐藤春夫を挙げると、やや意外な思いがするかもしれないが、佐藤春夫には青木繁について書いた詩がある。佐藤春夫が詩の題材に、特定の個人名を出す作例は珍しいと思う。彼は明治25生まれ。青木は明治15年生まれ。
この詩は、青木の遺作展等が話題になって、青木の名が広く知られてからの作である。
青木繁を憶ふ
才 ( ざえ ) あまりあり 青春 ( わかきひ ) の
燃ゆる心は統べがてに
不羈奔放のそのいのち
悲しかりけむ 偉 ( おほい ) なる
明治の盛世 ( みよ ) も現生 ( うつしよ ) も
足ることなしと天平の
とほき昔に 海洋 ( わたつみ ) の
いろこの宮に いみじかる
彩ある夢をかよはせて
僅かに生きし若人が
命ぞ凝れる 高華 ( あや ) に妖しく
佐藤春夫を師と仰いだ1907年(明治40年)生まれの小説家、詩人井上靖にも詩集『遠征路』に「二つの絵」という詩があり、青木の「海の幸」に魅せられる思いが綴られている。ただしこの詩も、青木の名が高まって以降の作である。
「二つの絵」とは、青木の「海の幸」と、富岡鉄斎「梅華書屋図」である。
一読忘れられないいい詩だと思う。

二つの絵
井上 靖
青春の絵では22歳の青木繁が描いた「海の幸」が好きだ。大きな獲物を担
いで波打ち際を歩いて行く漁師たち。金色の空、群青の潮、足もとには白
い波が砕け、魚のうろこは夏の陽光にぎらぎら光っている。そしてそうし
た漁師の群れの中に、作者は己が愛人の白い顔を嵌め込むことを忘れてい
ない。
( 中略 )
深夜眼覚めて、時にこの二つの絵のことを思う。青春は「海の幸」の如く
あるべきであったし、老いは「梅華書屋図」の如くあるべきであるに違い
ない。私は青春への悔恨と、老いへの絶望の中に眠ろうとする。救いは、
悔恨も、絶望も、いささかもじめじめしていないことだ。潮の匂いと、梅
の匂いの中に私は眠る。
🔻 何だかわからない絵だった「わだつみのいろこの宮」
次には、悪評の方に目を向けよう。
以下の文章は、東京府勧業博覧会評で、「わだつみのいろこの宮」について述べている。評者鈍栗翁は、深い教養のありそうな人ではない。面白半分にからかっている口調だ。しかし、発表された当時の、絵についての前知識もなく「わだつみのいろこの宮」を見た率直な感想として貴重だろう。
東京博覧會西洋畫評 / 神話 ( 青木繁氏筆 )
鈍栗翁
氏はいつでも半成の畫を作るのが得意だ。其御得意を棄てゝスツカリ仕上
げた處が一段の御慰み。どうも矢張御得意の方が旨さうだ。神話といふの
は何を描いたのか分らぬが、或る人の説には神話にあらず新話で、青木繁
といふ御自分をかいたのだと云ふ、どうだか知らんが例 ( いつ ) もながら
奇抜な畫なり。惜しい事に掛け場所が悪いので、カンバスの皺が目立て凧
繪のやうに見える。
次の文章は、青木が昵懇の友人森田恒友を介して付き合いのあった画家、山本鼎 ( かなえ ) が、東京府勧業博覧会の展覧会場で耳にした鑑賞者の感想を自身の主催雑誌「方寸」に、雑録として書いているものである。
母君賤より出給ひしか、はた水汲みにおはす路の険しく、いと遠くてか、姫君の御足醜くおはすかな。「わだつみのいろこの宮」仰ぎてかくつぶやける者あり—実にも。
豊玉姫が日本の皇室の皇祖である ( とされている ) ことから、母君と表現している。むき出しの脚が醜いというのは、現代の人の感覚では驚くようなことだが、そう見えたのはやはり、女性の身嗜みに対する明治の世の感覚ゆえだろう。
「賤より出給ひしか」とつぶやいた思いは、青木の絵についての過去の記事で解釈してきたことの繰り返しになるが、貴人は豪華な幾重にも重ね着した衣装で描くのが、神話題材の絵の決まり事であったのだから、羅一枚しか纏わない豊玉姫が、いかにも貧寒とした装いに見えてしまう方が常識的だと言えるだろう。
「実にも」という最後の言葉には、青木を知る山本鼎にしてもなお、( さもあろう。青木のアバンギャルドの芸術性を、すぐに理解するのはむつかしいことだ ) という気持ちが、こぼれ出ているようだ。
✪ 激賞と傑作の烙印
ふたたび、高い評価を綴った文章に戻る。
青木繁の没後最初の遺作展が明治45年に開催された。それを見た感想を雑誌「新公論」に文泉子の筆名で、坂本四方太 ( さかもとしほうだ ) が書いている。坂本四方太は、1873 ( 明治6) 年-1917 ( 大正6 ) 年の俳人、文人。夏目漱石、正岡子規と交友があった人。「孑孑 ( ぼうふら ) は蚊になる紙魚 ( しみ ) は何になる」の句がよく知られる。
この一文は、漱石の青木賞賛に匹敵する激賞と言える。
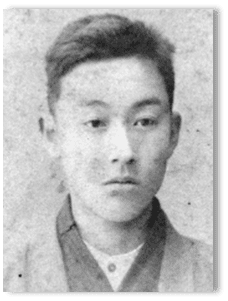
萬年筆
文泉子
◎四月五日。
最近見た絵画展の中で特に記念すべきものが二つある。一つは青木繁氏の
遺作展覧會で、他の一つは菱田春草氏の遺墨展會である。
(中略)
青木氏の方には、四、五年前に見覚えのある「海の幸」と「わだつみのい
ろこの宮」とがあつた。いづれも天才の俤 ( おもかげ ) を窺ふに足るもの
である。
「わだつみのいろこの宮」の方は或る専門家などは、技巧の至らぬものと
して排斥したが、吾々の見るところでは確 ( たしか ) に同氏の傑作であ
る。少なくとも今までに出た日本の油畫 ( あぶらえ ) に一頭地を抜いたも
のである。
若し之を疑ふ人があるならば、青木氏の前にでも後にでも、「わだつみ
のいろこの宮」程の深い感情を表現した油畫 ( あぶらえ ) があるか否か考
へてみるが好い。自分は決して無いといふを断言するに憚 ( はばか ) ら
ぬ。
技巧は兎に角吾々は其點 (てん) 丈 ( だ ) けでも、充分この畫に敬意を表
する価値があると思ふ。同氏の自畫像も亦た軽々に看過すべきものでは
あるまい。
( 白馬会は ) 石井柏亭、満谷国四郎、中川八郎、青木繁らが続出した。ことに青木繁は、日本画界の雅邦、芳崖に匹敵すべき人である。彼の「海の幸」は、雅邦の「竜虎」ととみに特記すべき傑作である。
小川信一は明治35年生まれの評論家。文中、挙げられている雅邦の竜虎が下の図版である。

明治28年(1895)開催の第四回内国勧業博覧会出品 近代絵画最初の重要文化財

明治28年(1895)開催の第四回内国勧業博覧会出品 近代絵画最初の重要文化財
橋本雅邦「龍虎図屏風」が昭和30年、青木繁「海の幸」が昭和42年に、ともに重要文化財に指定されているところからすれば、この評者は戦前昭和10年代において早くも、ピンポイントで絵の真価を言い当ててていることになろう。
令和6年4月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
