
俳句のいさらゐ ❀◌❀ 松尾芭蕉『奥の細道』その二十五。「浪の間や小貝にまじる花の塵」

これは、私独自の見解だろうと思っているが、敦賀の種の浜で詠んだこの俳句は、象潟のおとないをなぞっているようであり、場面の仕立てもいわば双子のようである。
意識した組み立てであり、同じ曲想を持った異曲だと言ってもいい。
比べてみよう。以下、象潟を◉、種の浜を❖で示す。
◉ 「其朝天能霽て、朝日花やかにさし出る程に、象潟に舟をうかぶ」
❖ 「種の浜に舟を走す。海上七里あり」
◉ 「《花の上こぐ》とよまれし桜の老木、西行法師の記念をのこす」
❖ 「ますほの小貝ひろはんと」
◉ 思い浮かべている西行の歌
「 象潟の桜は波に埋れて花の上漕ぐ海士の釣り舟 」
❖ 思い浮かべている西行の歌
「 潮染むるますほの小貝拾ふとて色の浜とは言ふにやあるらん 」
◉ 芭蕉の俳句 象潟や雨に西施が合歓の花
❖ 芭蕉の俳句 波の間や小貝にまじる萩の塵

つまり、
① 西行が歌を詠んだ入り江の景勝地であることに惹かれて、
② 船を仕立てて出かけ、
③ そこでしみじみと西行の歌の世界に浸ったら、
④ 私にはこういう俳句が生まれて来た。
という共通の興趣を詠む構成なのである。
そうして、象潟では、雨にけぶる合歓の花に陶酔し、種の浜ではすでに散ってなお、波間に彩を添える萩の花くずに目を奪われた、という俳句を詠んだ。
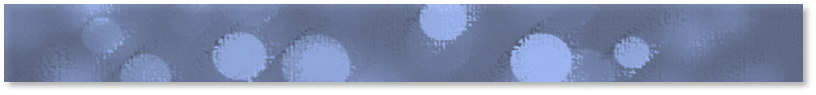
この二つの俳句は、『奥の細道』の旅が深まり、閉じてゆくさまを、花の姿の受け取り方に託して、象徴的に示している。
ひとつは、季節の移り行き、旅の時間の経過である。夏から秋へ、訪れた日は、56日間の隔たりがある。
そしてもうひとつは、『奥の細道』の旅において、それぞれの地で味わった思いであり、ひとつの喩えとして炎のありさまで表現すれば、盛り火を→合歓の花、余熱を→萩の塵、という言葉に置き換えられもするだろう。
そう思う理由は次のようになる。
象潟は、どうしてもそこまでは足を延ばしたいとと念願した地である。そこを訪れるのによい季節 ( 天候の安定期 ) を選んでいる ( 陽暦8月1日に到着2泊3日滞在 ) 感じさえする。

『奥の細道』象潟では、芭蕉曽良ともに二句を載せており、ここに一つのピークが見出せるが、実は載せなかったもう一句
「ゆふ晴や桜に涼む波の華」
も、芭蕉は象潟で詠んでいる。
これは、夕晴れの象潟のきらめく波を、西行が歌に詠んだゆかりの桜の老木越しに見れば、今の時期は桜花はなくとも、あたかもその波が桜花の輝きのように幻想される、という意味の俳句である。
やや観念の色合いが強く、「雨に西施が‥‥」の句との折り合いから、『奥の細道』では採らなかったのだろう。
しかし、とりわけ訪れたいと念じていた地に佇み、思いを達して、盛り火の揺らめきに包まれているような没我の心情を、よく伝える俳句と言える。
対して、種の浜の方を余熱と表現したのは次の意味である。
種の浜へは、『奥の細道』では、「ますほの小貝ひろはんと」して訪れたと書いている。上に掲げた西行の和歌に倣い、同じ行為をしてみる風流を愉しみたかったということだ。
異郷の地の貝は和歌の中では、「つと」の意味を持つ。「つと」とは、平たく言えば土産である。古来、歌に多く詠まれている。一例を引く。
「家づとに貝ぞ拾へる浜波は いやしくしくに高く寄すれど」
万葉集 防人歌
「堀江より朝潮満ちに寄る木屑 ( こつみ ) 貝にありせばつとにせましを」
万葉集 巻二十 4396
「波の間や小貝にまじる萩の塵」は、象潟での俳句「ゆふ晴や桜に涼む波の華」とは対照的な光景として詠まれているのに気づく。
◙ 幻想の「波の華」に対し、手で掬えるほどの目の前にある「萩の塵」
◙「ゆふ晴や」の遠望に対し、「小貝にまじる」のごく手近な視点
象潟では桜花の如く輝いていた波は、種の浜では、小貝を洗う寂寥を描き出すばかりである。しかし芭蕉は、水の底に影を揺らめかせる萩の花くずを、渚の小貝の間に間に見た。

長い旅の果て、帰心にとらわれている芭蕉は、この水底の花影に、江戸を出てからの、彩と苦しみに満ちた漂泊の日々が、未だ旅の帰途にあっても、すでに淡く去りゆかんと瞬いている感を覚えたのではないか。
それはつと ( 土産 ) を求めんとますほの貝を探している自分の姿に、はっとした瞬間であっただろう。
( ああ、もう私はこの旅を終えようとしているのだ )
( 萩の花も散ってゆく季節なのだ。散ってなお、余韻をとどめるように、水の底にその影を行きつ戻りつさせている.。華やぎに包まれていた私の旅の日々もまた同じように・・・・・・ )
計画され、手配され。曽良のお蔭で、ほぼその計画のとうり進んだ旅であれば、計画に沿って終える日がくるのは当然のことである。無事に終わろうとしている安堵心の方が大きい。
なのに、( 終わってしまうのだ )という感傷が胸の内に差し込んでくる。そのひときわの寂しさ。それは、『奥の細道』種の浜でのもう一つの俳句に詠み表した。
寂しさや須磨に勝たる浜の秋 芭蕉

種の浜は、『奥の細道』の旅の最終盤であった。この俳句のあと、「蛤のふたみにわかれ行秋ぞ」をもって、『奥の細道』は終わる。
( 昔、須磨を訪れ俳句も詠んだものだったが、この浜で今味わっている寂しさから思えば、須磨での感懐は何ほどのものでもなかった。真の秋の浜の寂しさを今感じ取っている。須磨では和歌の伝統に即して、須磨の秋の情をなぞったに過ぎなかった )
そういう思いがよぎって、種の浜の寂寥を、「須磨に勝たる」の言辞にこめて用いたのだ。

なお、種の浜と表記し、色の浜の表記をとらなかったのは、貝の種類 ( 種 ) が多い浜の意味から、=貝の色が多彩というつながりで、種を「いろ」と読ませているはずで、芭蕉は、ますほの貝を現実に見て、それが単一の色でなく、またその他の小貝も散見される浜であることを知り、それを示すには、種の浜の表記の方が、文学表現的には勝っている、ととらえたためであろう。
種が多いことが、色を豊かにしている意味を含んだ「いろ」の読みは、自分の創作にもつながると感じていたかもしれない。
地名の持つ情緒を深く味わうのも、『奥の細道』の旅の一つの主題であったのだから。
令和6年7月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
