
俳句のいさらゐ ⦿✤⦿ 芭蕉が『奥の細道』に載せなかった旅中吟④「西か東か先 (まづ) 早苗にも風の音」
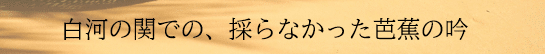
この俳句は、曽良の「俳諧書留」に載り、前後にこういう詞書が添えられている。
しら河の関をこゆるとて、ふるみちをたどるまゝに
西か東か先 ( まづ ) 早苗にも風の音 翁
我色黑きと句をかく被直 ( なおされ ) 候。
※ ( 「と」は 「を」の書き間違いとされている )
直した元の俳句も同じく曽良の「俳諧書留」にこうある。
みちのくの名所名所、こゝろにおもひこめて、先、せき屋の跡なつかしきまゝに、ふる道かゝり、いまの白河もこえぬ
早苗にも我色黒き日数哉 翁
初案、推敲吟、どちらも『奥の細道』では捨てられた。『奥の細道』の白河の関の章では曽良の俳句、
卯の花をかざしに関の晴れ着かな
を採った。この俳句は、曽良の「俳諧書留」にもあり、このような詞書がつく。
しら河
誰人とやらん、衣冠をたゞしてこの關をこえ玉フと云事、清輔が袋草紙に見えたり。 上古の風雅、誠にありがたく覺へ侍て、
卯の花をかざしに関の晴れ着かな
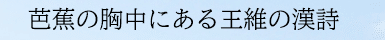
上の引用文に、また『奥の細道』にも「古人冠を正し、衣装を改しことなど」とあるように、芭蕉も曽良も、衣冠をたゞしてこの關を越えて行った文人たちに思いをはせているのだが、芭蕉の俳句、「西か東か先 ( まづ ) 早苗にも風の音」を見れば、「西か東か」という措辞は、王維の著名な漢詩「元二を送る」の中の、「西のかた陽関を出ずれば」が念頭にあって出て来たと思う。
こういう詩である。
元二を送る 王維
渭城の朝雨 軽塵を浥す
客舎青青 柳色新たなり
君に勧む更に尽くせ 一杯の酒
西のかた陽関を出ずれば 故人無からん
王維のうたった状況と、芭蕉の場面とでは全く違うが、いよいよここよりみちのくに入って行く芭蕉の、静かな高揚とでも言うべき思いは、王維に見送られて関を越えてゆく者の気分を重ね合わせるに足るものであって、白河の関越えをうたった ( 多くは想像上の創作 ) 日本の文人たちの、雅趣を味わいとした歌よりも、感覚の近しさがあったのではないだろうか。
「長途のくるしみ、身心つかれ、且つは風景に魂うばはれ」と、須賀川の章で白河の関に至ったときの心境を述べているが、その言葉もまた、王維の漢詩の深い感慨に通い合っていると思える。

ここで思う。『奥の細道』白河の章を構成するにあたって、どのように俳句を選んだのか、3つの考え方があろう。
1. 芭蕉自身の俳句のみを置いたが、それを外して曽良の俳句に置き換えた
2. 初めから自分の俳句は置かず、曽良の俳句のみを置いた(『奥の細道』にあるとうり)
3. 自分と曽良の俳句を並べて置いてみたが、自分の俳句は外した
私は3であろうと思う。つまり、
西か東か先 ( まづ ) 早苗にも風の音
卯の花をかざしに関の晴れ着かな 曾良
と併記してみたが、自身の俳句は、全体の構成を考えて落としたということだ。
しかし白河の関での芭蕉自身の吟を出していない事情を、『奥の細道』の中で、読者への説明のように述べている。
須賀川に着いてから、白河の関をどのような思いで越えて来たかと、世話になった等窮に尋ねられて、次の一句を示した。
風流の初めやおくの田植うた
白河の関というお決まりの雅趣をなぞってうたうのは、先例に埋没して面白みがないという意志からであろう。大きくみちのくの風土をとらえた俳句を詠み、それを須賀川で巻いた歌仙の発句としたのだ。


そこで、「西か東か先 ( まづ ) 早苗にも風の音」を外した理由は何かである。
「風流の初めやおくの田植うた」が示唆していると思うが、紀行のめりはり、起伏として、ここよりみちのくという場面を、パッと明るい、なごやかな雰囲気にしたかったのだろう。それに適うのが、曽良の俳句「卯の花をかざしに関の晴れ着かな」の方だった。
上に述べたように、白河の関に立ち、ここからの茫洋とした先行きにを思って、緊張を覚えているような気分をうたった自身の俳句「西か東か先 ( まづ ) 早苗にも風の音」は、その雰囲気の演出にはそぐわないという判断だろう。
「早苗にも我色黒き日数哉」にしても、「西か東か先 ( まづ ) 早苗にも風の音」にしても、白河の関に立った芭蕉の実感から生まれた俳句である。しかし、芭蕉には『奥の細道』全体の構成で、章ごとの個性を持たせ、陰影をつけてゆくことが、重要な要素であったと思う。
この解釈シリーズ「『奥の細道』その二十六において私は、「『奥の細道』は、人生の節目の行事を題材にしながら、ゆく先々の風物に託して、象徴的に、人生の深まりを追うように表現している一面があると思う。」と述べた。『奥の細道』前半部は、意図して弾んだ気分を前に出していると考える。
「西か東か先 ( まづ ) 早苗にも風の音」では、後半の「あかゝと日は難面もあきの風」や「石山の石より白し秋の風」と相似た感覚を導くのだ。
それが、「西か東か先 ( まづ ) 早苗にも風の音」を、『奥の細道』から外した理由であろう。

令和6年12月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
