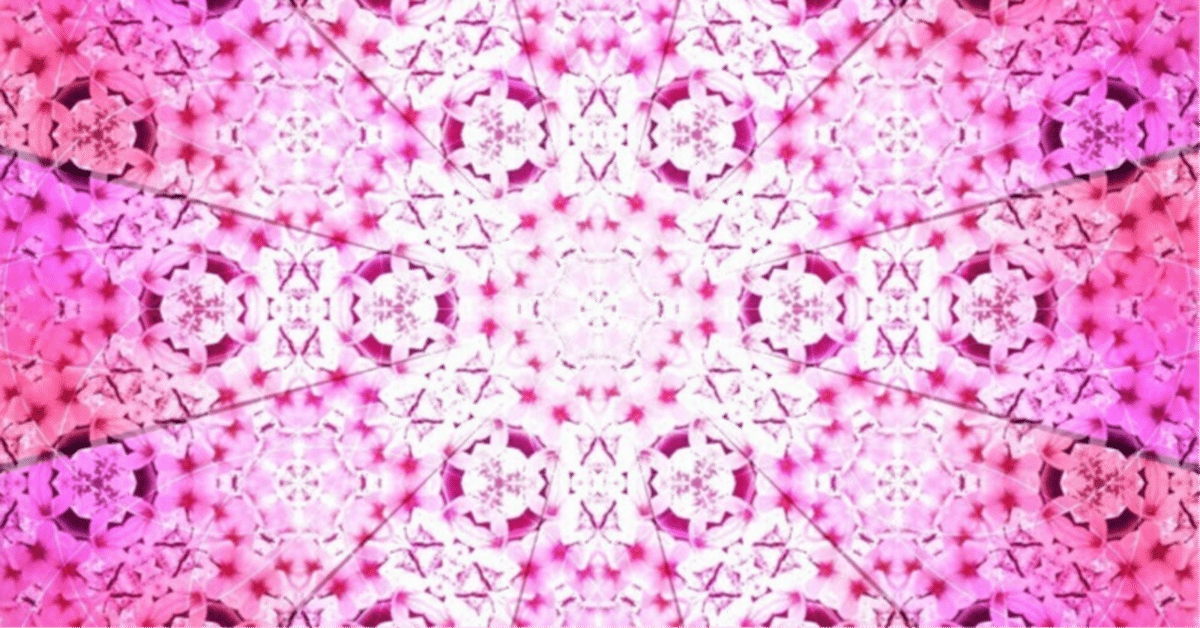
「万の華うつす鏡」に魅せられて
2023年、わたしには大事な人たちとの別れがあった。
どれも急なものではなく、じりじりと音もなく、でも着々とその気配が拭えなくなっていく時期の後、別れのその瞬間と、その後の静寂、遅れてやってくる喪失感の波を経験した。
どれもが長らくじんわりとしんどく、真っ暗闇の中にいるような日々だった。
そんな中、わたしを救ってくれたもののひとつが、『ミュージカル「刀剣乱舞」』だった。
漠然と同シリーズの見せてくれる「生命の景色」に惚れ込んでいる。
もっと細部を知ればもっと夢中になれるのかもしれないのだが、ひとつの文学作品のような気持ちで、ざっくばらんに同シリーズを楽しんでいる。
そして救われている。
いろんな思いを抱えてたどり着いた2023年の暮れは、『ミュージカル「刀剣乱舞」千子村正 蜻蛉切 双騎出陣 ~万の華うつす鏡~』と共にあった。
今回は、その感想を書き記していきたい。
※考察とかではなく、あくまで個人的な感想なので、あしからず。
全体像
今回の双騎出陣では、千子村正と蜻蛉切それぞれのあり様と内面の片鱗、二振りの関係のゆらぎ、強固たる絆、そしてもっともっと広く遠くの視点から眺める精神世界が描かれていたように思う。
第一部は一時間にも満たない公演時間ながら、そこに流れる時間・広がる空間は数字では測れないほど芳醇なものであった。
そして、多くを語らず、観客に託された余白がすばらしかった。
それは作り手の覚悟にも、作品やキャラクターたちへの愛にも、観る側への信頼にも感じられて、それだけでグッとくるものがあった。
昨今のめまぐるしく更新されては流れて消費されていくコンテンツに触れていると、わたし個人的は、わからなさに耐えられなかったり、間を待てなかったり、シェアしないでおけなかったり、そういう効率性の皮をかぶった短絡的なもろさを感じることがある。
だが今回の双騎出陣、そのなんと味わい深く、言葉にしてしまえば解像度が落ちてしまいそうなほど鮮やかなことか。
配信の画面越しではあったが、身も心も重力を忘れて漂うような、すばらしい観劇体験となった。
二振りが見せてくれた、生きるということ
この物語にみたのは、圧倒的な「生の肯定」だった。
なんだかよく分からないのに、どうしようもなくぼろぼろ涙があふれたのは、生きることの苦しみも、そこに差し伸べられる手のあたたかさも、常闇の孤独も、家族の愛も、結局こんなにもうつくしい、わたしたちはまさに今そういう「生」を歩んでいる、ということを見せられたからだ。
刀剣男士は人間ではない、というのは前提にあるとしても、そこに圧倒的な人間を見ずにはいられなかった。
窓を吹きぬける風
時間や運命の「風」が四季をめぐらせるように、「迷い」の夜も、「悟り」の朝も、生命も肉体も、当たり前にそこにあって当たり前にめぐりゆく。
夜と朝・夢と現・内と外・迷いと悟り・こちら側とあちら側……さまざまな「狭間」を行ったり来たり、時に重なって、時にさまよって、時にどちらかがどちらかを包みこんで、時に欠けそして満ちて、それを繰り返しながら地続きでひとつの「形」、ひとつの「季節」、ひとつの「命」つまりはひとつの「華」となってゆく。
その残酷なほどのうつくしさを本作に見て、聴いて、感じた。
そして考えた。
じゃあ、その「華」を揺らし、時に散らせてしまう「風」に、わたしたちは翻弄されるしかないのか、抗うことはできないのか。
いや。
わたしたちは、「吹きかける息」で「かざぐるま」を回すくらいの小さな「風」を起こせる存在でもあるはずだ、とそう思った。
その吐息の「風」は時に文字やことばや歌となり、もし心に「窓」があるとするならばその「窓」を吹き抜け、誰かの心と誰かの心を通わせることもできるんじゃないかと。
それこそが出会い、分かち合い、誰かと共に生きるということなんじゃないか、生命を繋げてゆくということなんじゃないかと。
ほんの少しの言葉、ほんの少しの歩み寄り、ほんの少しの勇気や覚悟、そんな小さな風を、誰かの心の窓に流れ込むような「風」をわたしたちは起こすことができる、そう信じて生きていきたいと思った。
万の華うつす鏡
本作でいう「華」とはきっと「命」そのもののことだろう。
地面に咲く花々もそうだし、夜空に輝く星々、もちろんわたしたち人間だってそうだ。
じゃあそれを「うつす鏡」ってなんなんだろう。
本作を見ながら、たくさんの「鏡」を見た。
太陽の光を受ける「月」、足元に広がる「水面」もしくは「血溜まり」、なんなら「窓」だって夜には鏡のようにわたしたちの姿を映すし、それで言ったら「刀」も鏡だ。
そうしたいろいろ考える中で、本作における「鏡」って「他者」なんじゃないかと思い至った。
というのも、この公演、「見る」「見える」「見えない」という視覚に関する言葉が散りばめられていた。
だから最初は、鏡とは「瞳」「目」のことでもあると思っていた。
数々の「華」を見つめる・愛でるわたしたちの「瞳」こそが鏡なのではと。
でも、見える・見えないは関係ないのだ。
蜻蛉切の瞳に映る千子村正、千子村正の瞳に映る蜻蛉切は、いつしかその視覚がうばわれても互いの存在を確かめられるまでになる。
誰かがいること、誰かが思い出しては思いを馳せ、名前を呼んでくれればそれだけで自分が「在れる」こと、そういう誰かの存在そのものが自分を自分たらしめること。
他者の存在が鏡となって、自分自身を露わにしてくれる。
本公演に、そんな光景を見た。
さいごに
芳醇な広がり
この公演、多くを語らぬ余白の大きい分、観劇後の余韻・後味の広がりもまた大きい。
SNSを見ていると、感想がどんどんと広がり深みを増していくのが印象深い。
それぞれが見た景色や、それぞれが感じたこと、それは十人十色で物語の奥ゆきを押し広げ、それこそ万華鏡を覗いているような鮮やかさがある。
その観客の感想もたずさえて、今となってはこの公演こそが「万華鏡」のように感じられる。
そのうつくしさに、公演からどんなに時間が経っても、うっとりしてしまうのだった。
独りじゃない
わたしたちはどうしようもなく一人で、心細い夜も、圧倒的な自然に抗えない日も、思わぬトラブルに打ちひしがれる日も、先の見えない苦しみに飲み込まれそうになる時もある。
でも本作を見て、良くも悪くも、独りにはなりきれないのだな、と思った。
根拠もなく大丈夫だと、もっと心の窓を開いて生きてみようと、必ず誰かが居てくれるはずだと、生きることはこんなにもうつくしいのだと、この双騎出陣に、そんな希望を見た。
本公演はわたしにとって、始まりの物語であり、人間讃歌であり、鎮魂歌であり、応援歌であった。
あの二振りがどこへ向かったのか、もうその先をわたしは見たことがあるのかもしれないし、まだ知らないのかもしれない。
ただ今は、本作が見せてくれた景色を胸に、二振りに思いを馳せながら、自分の目の前の現実を生き抜いていこうと強く前を向けるのだった。
すばらしい物語と体験を、ありがとうございました。
