
読書 | 安部公房「賭」を再読してみた。
「The Bet」との出会い
10年くらい前、安部公房の作品にハマったことがある。きっかけは、オックスフォード大学出版「Japanese Short Stories」。森鷗外から吉本ばななまで、様々な作家の短編を収めた、日本文学翻訳短編集である。この本の中に、Abe Kobo 'The Bet'が入っていた。英語で読んだが、わかったような分からないような感じだったので、新潮文庫で日本語のオリジナル作品(「賭」)を読んでみた。日本語で読んでも、わかったような分からないような感じは変わらなかった。しかし、とても面白い!と思った。
字面の意味もストーリーも分かる。ではなぜ「わかったような分からない」ような気持ちになるのか?
「賭」の主人公は「設計家」である。主人公が戸惑う様子は、フランツ・カフカ「城」の主人公測量師Kを想起させるが、「賭」の主人公と「城」の主人公とはやはり違う。私の「分からなさ」は、敢えてたとえていうと、三次元空間では絶対にあり得ないものを二次元に現出させたエッシャーの騙し絵を見ているような不安定感にある。
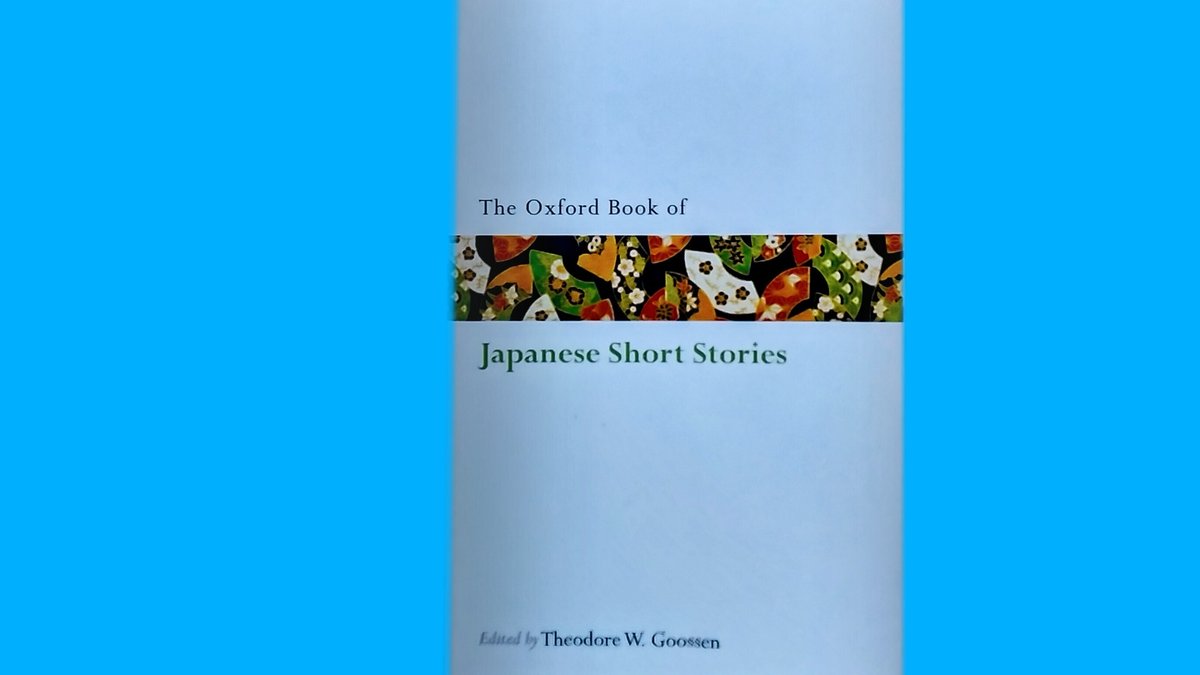
「賭」再読
ふと思い立って、「賭」を再読してみた。それほど長い話ではない。文庫本で50ページ弱の作品である。二回繰り返して読んでみた。今回は以前に読んだときより、「わかった!」と思った。また再々読すれば、また「分からない!」となるかもしれないが、一応、仮説として、今回読みとったことをまとめておく。ネタバレはあるかもしれないが、ネタバレにはならないと思う。というのは、この小説はストーリーが分かったとしても、魅力が損なわれるような作品ではないからだ。
物語は、設計家である私と、依頼主の代理人との商談から始まる。「私」は何度も設計をやり直しさせられている。依頼主の注文が無理難題だからだ。「二階と三階の部屋を隣りあわせにしろ!」のような要望にどう応えればいいのだろう?
今1つ依頼主の気持ちが分からない。そこで、主人公の設計家「私」は、依頼主の会社に商談の翌日、訪問することになった。
「私」が依頼主の会社に行くと不思議なことばかり。社員が出社すると、「お帰りなさい」。それに応えて「ただいま」。
会社の中に入っていくと、「守るな 攻めよ」「欲望に形をあたえよ」「頭はつねに全回転」などの貼り紙がある。途中、赤ランプが光ったり、謎の低い呻き声が聞こえてきたり。
最も不思議なことは、社員全員が午前中に必ず一度「心理分析のテスト」を受けねばならないこと。適当に三枚のカードを選んで「自由連想」しなければならない。
例えば「爪、時計、ペンギン」から次のようなことを連想する。
「爪・・・爪の垢・・・せんじる・・・ペンギンの薬・・・時計。時計の薬は、ねじをまくこと。爪・・・爪に火をともす・・・火の時計・・・温度計・・・温度計とペンギン。ペンギンが体温計を脇の下にはさんでいる。風邪薬のPR」。
主人公の「私」は、最初は奇妙だと思っていたが、次第にこの会社の依頼主の意図が分かるかのような気持ちになっていく。しばらくすると、踵に付けられた金具のことを忘れてしまうまでになっていた!
こんな感じで作品の終わりに近づいていく。この作品を読んでいる「私」は、なんとなく「不条理感」が消えなかったが、依頼主の次の社長の言葉で、この「賭」という作品の主題がわかったような気になった。
「(政治家ではなく)現代の舵をにぎっているのは、われわれ宣伝業者なんだ・・・世論という雌馬と、資本という雄馬を、仲よくならべて走らせる方法を知っているのは、まずわれわれ以外にはないからな。」
「どんなふうにやるのか、教えてやろうか・・・まず、ほんのちょっぴり、欲望という種を腹の中にうえつけてやる。見えないぐらいの、ちっぽけな種だが、これがわれわれの知恵をしぼってつくり上げた、秘伝の品なのだ。くいついたら絶対にはなさない。成長力がまたすばらしい。肥料をほしがって、金切声をあげるのだ。頃合を見はからって、上等のこやしのありかを教えてやる。そうなりゃ財布の底をはたいても、こやしを買いに出掛けていくわけさ・・・」
私の読みが当たっているかどうか自信はないが、この依頼主の会社は、「現代資本主義の表象」なのではないだろうか?貼り紙の標語にしろ、設計の無理難題にしろ、資本主義の本質を表しているように思えた。
先ほど引用した「自由連想」にしても、普通に考えれば何の脈絡もないことを「欲望」に変える訓練なのではないか?
資本主義とは、欲望が渦巻く。そして、利潤を追求し続ける。欲望が希薄になれば、無意味なことにさえ欲望の種をつねに蒔きつづける「システム」である。
P.S.(雑感)
・
細かいことだが、作品の中に「イ列の八番」という人物がいる。行方不明になるのだが、「いの一番」じゃないから、消されてしまったのでは?、なんてことも空想してみた。
・
「賭」とは資本主義の運動原理を表しているのではないか?
・
「システム」とは、資本主義を動かすつかみどころのない「欲望原理」を表しているのではないか?
結び
まだよく分からないことが多い。またしばらく時間が経ったら再読してみたいと思っている。もし、「賭」を読んだ人がいたら、ぜひ感想を聞いてみたい。
#読書感想文 #短編小説
#賭 #ギャンブル
#安部公房 #文学
#資本主義 #学問への愛を語ろう
#新潮文庫 #英語 #オックスフォード
いいなと思ったら応援しよう!

