
🤔文学を科学する | 球体の鏡の中に入ると?
文学と科学。文系と理系。好みがどちらかに偏る傾向があり、文学は文学、科学は科学と別個のもののように考えることが多い。
この記事では文学作品を科学してみようと思う。
(1)江戸川乱歩『鏡地獄』
江戸川乱歩の作品に『鏡地獄』という作品がある。
全面鏡張りにした球体の中へ入ると、どのように見えるだろうか?
作品の中ではハッキリと書かれていないが、再現した動画がある(↓)。
ちょっと想像してから見ると面白いかもしれない。予想通りだろうか?それとも意外に思うだろうか?

(2) 藤原定家「明月記」
藤原定家(1162-1241)は、『新古今集』や『小倉百人一首』などの選者として知られる歌人だが、『明月記』という日記も残している。
以前、新聞(2014.9.15 朝日新聞)で知ったことだが、「明月記」には3個の超新星が登場する。位置などが正確に分かるその記録は、現代の天文学の発展に貢献しているという。
「明月記の功績」
★かに星雲が超新星の残骸だと確かめられた。
→中心に中性子星が残るといったそれまでの超新星の理論が正しいことが裏付けられた。
★超新星が現れてからの年数が正確にわかる。
→爆発のエネルギーが計算できる。
→超新星でばらまかれる元素の比率が計算できる。
→超新星がつくる宇宙線の様子が明らかになる(磁力により電子や陽子が加速する様子)。
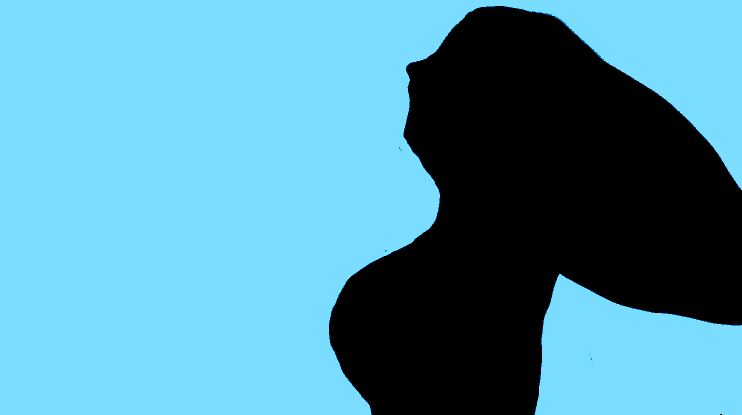
文学が貢献する
こともあるのね💝

(3) 宮沢賢治「銀河鉄道の夜」
宮沢賢治「銀河鉄道の夜」。わたしは全部は読んでいない😱。
図書館で借りたサイエンス・ライターの竹内薫さんの著書で、「銀河鉄道の夜」という物語の描写から、物語の設定となっている日時を特定する考察を読んだ。
おそらく、文学として読むだけでは、こういう発想は出でこない。科学的な読み方をすると、今までに分からなかった謎が解けるかもしれない。
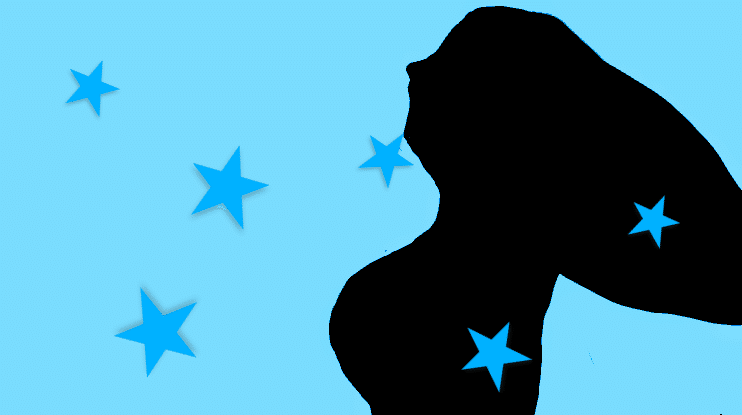
まとめ
その他にも、古典的な作品を科学的に解析するという試みはある。
古典文学には、文学的な価値に加えて、噴火🌋の様子や時期、地震の記録など、データとしての価値があるものも多い。
データベース化していくと、これからも思わぬ発見があるだろう。
そのうち文学評論にも「エビデンス」がないと、評論として不十分だと見なされる日が来るかもしれない。
いいなと思ったら応援しよう!

