
【“寺山修司フェア”(ハルキ文庫)を読みながら】
(初出:2000/04 @ニフティ<詩のフォーラム>●詩歌図書館●)
2000年4月に「寺山修司フェア」と銘打って刊行されたハルキ文庫十数冊のなかの一冊、『われに5月を』。
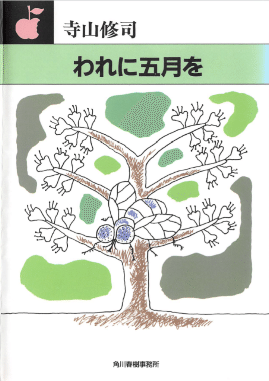
寺山修司、二十二歳のこれが処女作品集です。
収録されるのは俳句、短歌、詩、<ジュリエット・ポエット>と寺山が命名する戯曲のためのエチュードとしての散文詩、友人の山田太一(のち脚本家)等との書簡のやりとりをおさめた日記風のエッセイ・批評などで、のちに「職業、寺山修司」と自称した著者のマルチな才能がすでに存分に発揮されています。
「歌壇も俳壇も詩壇もまったく無視だった。まともな書評も出ずこういう多ジャンルにまたがる本は非常に不利だ」
と寺山は友人に語ったことがあるそうですが、今読むと寺山修司の出発としてこれほどふさわしいカタチはなかったのではないか、と思わされます。
文学は創作性の芸術であり、僕には文学における「まことの花」は考えられない。十代には十代の、三十代には三十代の、六十代には六十代の「時分の花」だけがあるのだ。 (「森での宿題」)
世評定まった感のある短歌はべつとして、詩などは露骨に谷川俊太郎風や北園克衛風であり未完成な印象もうけますが、それも「らしい」といえばらしいのではないでしょうか。
二十才 僕は五月に誕生した
僕は木の葉をふみ若い樹木たちをよんでみる
いまこそ時 僕は僕の季節の入口で
はにかみながら鳥たちへ
手をあげてみる
二十才 僕は五月に誕生した
(『五月の詩・序詞』)
同じ“寺山修司フェア”からもう一冊、『啄木を読む』

寺山修司に言わせれば啄木の歌は『あくまで「人を愛する歌」ではなく「われを愛する歌」であった。そして、啄木にとっては妻も、母も、ただの「生きた玩具」であるにすぎなかったのであった。』ということになります。
たとえば、
友がみなわれよりえらく見ゆる日よ
花を買ひ来て
妻としたしむ
という歌についても『「友がみなわれよりえらく見ゆる日」でさえも、妻だけは「われよりえらく見えない」ということを、どう受けとったらいいのだろうか?』と問いかけ、『固有の人格としてではなく、悲しい玩具の一つとして妻を扱う啄木』とつめより、なかなか手厳しいのです。
でも、そういう寺山の歌人としての出発はじつは啄木の模倣者としてでした。
さらさらとすくえば砂はこぼれ落ち春のゆうべの飽きし時
というのが寺山の中学時代の作品です。
若いころには『オレは「昭和の啄木」と呼ばれてる』と故郷の友人にみずから語ったこともあるそうです。
そういう意味で巻末の小林恭二氏の解説(「反歌作家としての啄木そして寺山」)が興味深いものでした。
啄木と寺山の作品に共通してある、短歌としては自立していないような、つまり一首のワクからはあふれだしておさまりきっていないような「過剰な物語性」を啄木や寺山の個人の資質としてみるのではなく、短歌や俳句が一文芸ジャンルとして確立する以前の日本文学の流れ、つまり連句という物語の発端としての「発句」、長歌というテキストのダイジェストとしての「反歌」という、じつは今も日本文学の地下水脈として脈々とあるものを直感的に感じ取り、それを掘り起こそうというふたりの詩人の試みとして指摘していることでした。
ほかに『歩けメロス』(太宰治)、『さらば青春、さらば中也』(中原中也)、映画監督の篠田正浩との対談『鏡花幻譚』(泉鏡花)、乱歩、織田作之助、夢野久作、西鶴、馬琴、空海についてのエッセイがおさめられています。
寺山ばなし、をつづけたいのですが、『啄木を読む』で出てきた短歌と長歌、俳句と連句のハナシはどっかで読んだことがあるような内容だなあ、と思って本棚の奥からひっぱりだしてきたのが、
山本健吉『古典と現代文学』(新潮文庫)
ちなみに、この新潮文庫版はぼくが高校生のころに買ったもので、絶版。
芭蕉によって、連句の発句として達成された高さにまで、その後俳句は単独で到達したことはなかった。それは人麻呂によって、長歌の反歌として、あるいは叙事詞章のさわりとして達成された高さにまで、その後短歌が単独で到達したことがなかったことと似ている。発句が連句から独立してからは、ただ短い抒情詩という意識による、閉鎖的な世界での完成への道を辿って行く。 (「詩の自覚の歴史」)
五・七・五詩型として方法的に精密化すればするほど、芭蕉の発句が包蔵したカオス(私は比喩的に言うのだが)からは遠ざかってしまうのである。このことは今日の俳句や短歌について言えるばかりでなく、詩についても言えるのだと思っている。
共同社会の法則から解き放たれ、もっぱら作者個人のその場その場の感情や心理や、あるいは思想にしか詩の動機を持たないようになったとき、すなわち孤独の心の告白としてしか意味を持たなくなったとき、それらの詩は避けることのできない一つの症状を露呈する。この世界とその住人たちとをことごとく否認し、詩は人間社会に奉仕することをやめ、象牙の塔における悲劇的孤立のうちに、詩が単に詩であることを目標として、練金の秘術をこらすようになる。
ロマンチズムがこのような詩を合理化したが、創造とはもっぱら個性に帰せられるものの名となり、詩人は天才であり光栄ある孤独者であるという意識を生み、個性の演戯者として社会のおきての外に位置するものとなった。到達するところは、詩人の独善意識、詩の伝達機能の停止とである。 (「抒情詩の運命」)
山本は人麻呂や芭蕉が示した多様な詩の可能性をその後の日本の詩の歴史が切り捨て、作者の「私」という自己閉鎖的なモノローグの世界を磨き上げることに専念することによって、画一化し単調化していったことを指摘します。それはまさに寺山修司も一貫して問題提起しつづけたことでした。
さらに近代演劇が大衆と舞台を切り離して<純粋観客>を作りだし、リアリズムで限定された舞台空間にすべてのできごとを閉じこめてしまっているのに対して、かつての能の舞台が一枚のムシロを敷いただけで村全体を集約的に象徴させていたというような指摘は、そのまま寺山の演劇論にこだましているようにも思います。
寺山修司というと前衛的でとっぴな発想の仕事をしたひとというイメージがあるでしょうが、じつは古典的世界と密接につながっていたりするのだなあ、と今回あらためて思ったのでした。
『古典と現代文学』は読売文学賞受賞。「詩の自覚の歴史」「柿本人麻呂」「抒情詩の運命」「物語における人間像の形成」「源氏物語」「隠者文学」「詩劇の世界」「座の文学」「近松の周辺」「談笑の世界」の十編。
『古典と現代文学』は発表当時も話題になったようで、もちろん批判的意見もあったようです。
遠藤周作のエッセイによると、「壮大にして贅沢な無い物ネダリ」(久保田正文)
などとも言われたようです。
以下、その遠藤のエッセイを少し紹介したいと思います。これは、ぼくの興味をもつところの引用やパロディのありように対する意見としても示唆的に思え、その点からも興味深いのです。
山本健吉氏が文学と共同体について書く時、我々はそれが古典であり現代文学ではないことを、つまり共同体を我々は全く喪っている時代にある以上どうすればいいかという疑問に捉えられる。我々は氏の言う原型善をもった人麿の時代に生きていないからだ。
(遠藤周作「現代文学の義務」)
遠藤は山本の主張の意義を近代文学の無秩序を正そうとするものとして認めながら、一方的な意見でもある、としています。そして
私はまずある作家や芸術家を他の作家や芸術家とのつながりの中でとらえたい。つまり彼が縦のつながりにおいて過去の芸術的遺産からいかなる痕跡をうけたかをまず調べたい。次に横のつながりにおいて同時代の芸術家たちと何が共通したもの、何が異なっているかを考えたい。
この縦、横の芸術的交流体は精神共同体のような我々の時代には既に失われてしまっている不可能な前提ではないのだ。二十世紀の作家といえども、この芸術的交流体にはたえず触れているのであり、またその中で生きているものなのだ。それはもはや過去に失われてしまった現実不在のものではなく現に実在しているものなのである。もし山本健吉氏が古典の世界で人麿に共同体の及ぼした影響を考えるならば、現代文学の世界ではこの共同体に代わるものは芸術的交流体なのである。(同上)
と述べています。この「芸術的交流体」の意識、これは単に批評的態度というものではなく実作者としての遠藤の意見だと思います。なぜなら、
私は一人の作家がまず過去の芸術的遺産から影響をうけながら、それを彼に負わされた状況と時代の神話の中で屈折していく、その屈折度を調べたい。たとえば堀辰雄がプルーストやモーリャックの影響をうけながら『風立ちぬ』や『菜穂子』を書いた時、たしかに彼は知らずしてプルーストやモーリャックを東洋的汎神論の中に屈折していたのである。ここに彼の独自性があるとともに、彼の日本人作家としての状況があるのだ。(同上)
と堀辰雄に仮託して語っていますが、これは日本人でありながらカトリック作家でもありえるか、という遠藤周作の生涯のテーマとも通じるものなのではないでしょうか。
引用したエッセイは講談社の「遠藤周作文庫」の一冊『文学と芸術』におさめられていますが、この文庫自体は二十年以上前のもので絶版。たぶん全集などにはおさめられていると思うのですが。
今回(2024年8月)の追記として
〈参考リンク〉
寺山修司「望郷幻譚ー啄木」(『鉛筆のドラキュラ : 寺山修司の作家論』)
https://dl.ndl.go.jp/pid/12563121/1/81
寺山修司『人間を考えた人間の歴史』
https://dl.ndl.go.jp/pid/12562746/1/1
山本健吉「詩の自覚の歴史」(『古典と現代文学』)
https://dl.ndl.go.jp/pid/12450785/1/11
遠藤周作「芸術交流体について」(『石の声 : 宗教・文学・紀行』)
https://dl.ndl.go.jp/pid/12472185/1/86
