
一流の家庭は知っているー優秀な子を育てる『子育て四訓』令和版|あなたの育て方は大丈夫?
「子どもの未来は親次第」なんて言葉を聞いたことはありませんか?
しかし、いざ子育てをしていると、「本当にこのやり方でいいのだろうか?」「他の家庭はどうしているのだろう?」と、不安になることも多いはず。
実は、優秀な子を育てる家庭には、共通する「法則」 があります。
それが、時代を超えて受け継がれる 『子育て四訓』 です。
そして、令和の時代に合わせて進化した 『令和版・子育て四訓』 を実践することで、子どもはより自主的に学び、成長し、自分の力で未来を切り開くことができるのです。
あなたの育て方は、果たして 「優秀な子を育てる家庭の共通点」 に当てはまるでしょうか?
一流の家庭が実践している「令和版・子育て四訓」、その内容を今すぐチェックしてみましょう!
1.古くから伝わる『子育て四訓』
親という字ですが、「立木を見る」と書きます。立木とはまさに子どものことです。少しずつ成長していく姿を見ていくのがまさに親なんですね。そして親と子の間に少しずつ距離も出てくるのです。 子育てをするには4つのステップがあり、それは親と子の距離を表します。
①乳児は肌身離さず

まず、まだ自分では生きていけない乳児の頃の親と子の距離は、 「肌身離さず」です。乳児の頃は乳房であれ、哺乳瓶であれ、抱っこしてもらい、おっぱいをもらいます。授乳だけでなく愛情表現としてのハグもとても大切なことです。
②幼児は手を離さず
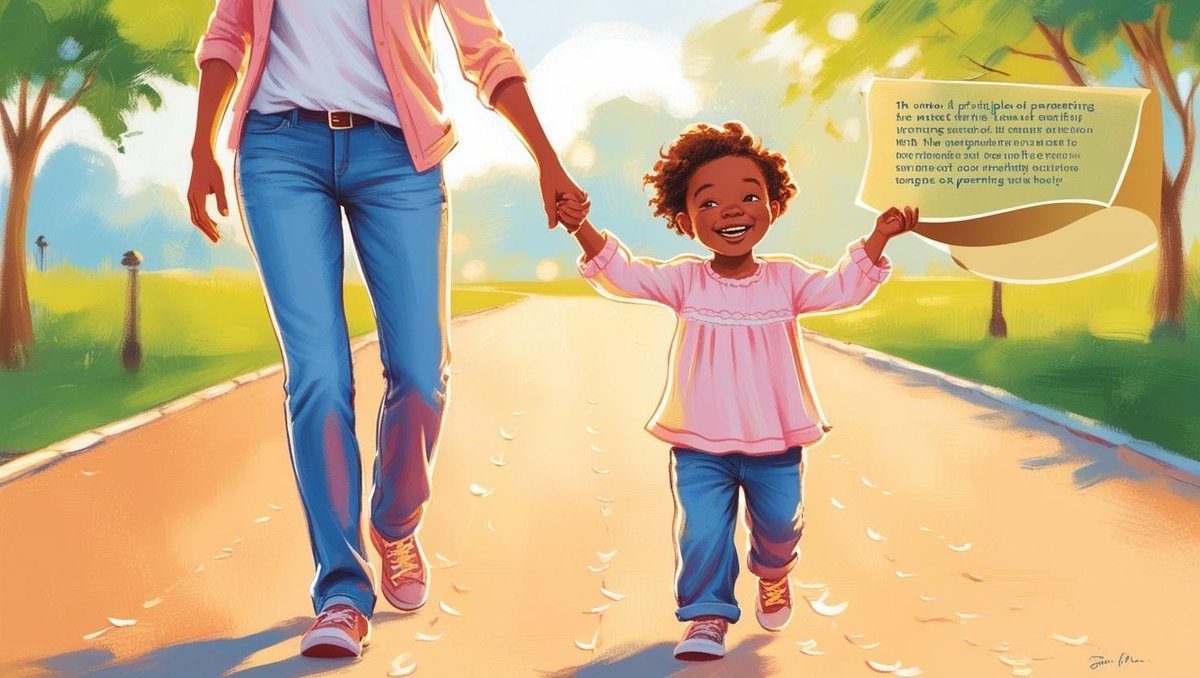
次に、自我が目覚める5歳前後から小学校低学年の頃は、好奇心もでてきて自分でなんでもしようとしますので、 「手を離さず」です。乳児の頃とは違い、もう肌は離しますが、危ないので手をつないでおくという距離になります。
③少年は目を離さず

小学校高学年から中学生の頃までは、 「目を離さず」です。何が危険で安全なのかが大体判断できますので手は離しますが、まだまだ世間がわからないので目は離せない時期です。
④青年は心を離さず

そして、最後は高校生から成人するまでです。ここでの親子の距離はぐっと開きます。 「心を離さず」です。もうそろそろ目も離さなければいけません。立木も随分成長して見えない部分も出てきます。しかし、離してはいけないのは心です。「聞く」ではなく「聴く」という気持ち、心のある「聴く」で相手に接することが肝心
です。
2.令和版 子育て四訓
①乳児は肌身離さず、病気を離せ

「赤ちゃんにとって、肌の温もりは言葉よりも大切なコミュニケーション手段です。」
生まれたばかりの乳児は、視力も未発達で、周囲の世界をはっきりと認識できません。しかし、親の肌の温もりや匂い、心音を感じることで安心し、心の土台を築いていくのです。特に、生後数カ月間は「ママやパパと一緒にいることで安心感を得る」という時期。だからこそ、**「肌身離さず」**という言葉は、この時期の子育ての基本とも言えます。
肌と肌のふれあいがもたらす奇跡
赤ちゃんの脳は、生まれてから飛躍的に発達します。実は、肌と肌の触れ合いが神経回路を活性化し、脳の発達を促すことが科学的にも証明されています。例えば、「カンガルーケア」という育児法があります。これは、未熟児の赤ちゃんを母親や父親の裸の胸に直接抱く方法で、体温調節が安定し、呼吸も整い、ストレスホルモンが減少するというメリットがあります。
実際に、ある病院でカンガルーケアを取り入れたところ、新生児の体重増加が早まり、免疫力も向上したというデータがあります。これは、肌の温もりが、ただの愛情表現ではなく、生命維持に直結する大切な要素であることを示しています。
「病気を離せ」— 乳児期の健康管理のポイント
乳児期は、免疫がまだ未発達なため、感染症にかかりやすい時期です。しかし、「過度な清潔主義」は逆効果になることもあります。
例えば、最近では**「無菌すぎる環境が、アレルギーや免疫力の低下を招く」**という説が注目されています。適度に外の世界に触れさせることが、免疫力を高める要因になるのです。もちろん、病原菌との接触を防ぐための衛生管理は重要ですが、あまりにも過度に除菌ばかりすると、赤ちゃんの免疫システムが正常に発達しにくくなることも知っておくべきです。
「病気を離せ」とは、「免疫力を育てる」こと
風邪をひかせない、菌を寄せ付けないというだけでなく、子ども自身が病気に負けない体を作ることが大切です。
実際に、ある家庭では、第一子のときは除菌スプレーを徹底し、外遊びも最小限にしていたのに対し、第二子は自然の中でのびのびと育てたところ、第二子の方が圧倒的に病気にかかりにくかったというケースがあります。
つまり、「病気を離せ」とは、単に病原菌を遠ざけることではなく、赤ちゃんの身体の強さを育てるという意味でもあるのです。
すぐに実践できる!「肌身離さず・病気を離せ」5つのポイント
毎日、赤ちゃんを抱っこする時間を確保する(特にスキンシップを大切に)
お風呂上がりなど、赤ちゃんの肌に直接触れる時間を増やす
過度に除菌しすぎず、適度に外の環境に触れさせる
自然の中でのびのび過ごす機会を作る(芝生の上でハイハイなど)
親もリラックスし、ストレスを減らす(親の不安は赤ちゃんに伝わる)
まとめ
「乳児は肌身離さず・病気を離せ」という教えは、**「愛情をたっぷり注ぎながら、赤ちゃんの免疫力を自然に育てる」**ということです。
特に、「肌の触れ合い」は、赤ちゃんの情緒の安定や脳の発達に不可欠であり、一方で過度な清潔主義ではなく、自然の力を活かした免疫力の向上も大切です。
「病気にさせたくない!」と思うのは当然ですが、必要以上に菌を恐れるのではなく、「強い身体を作る」という視点で子育てをすることが、将来の健康につながるのです。
今すぐできることから、ぜひ試してみてください!
②幼児は手を離さず、スクリーンを離せ

「幼児期は、子どもが自分の世界を広げていく最も大切な時期です。」
歩けるようになり、言葉を覚え、好奇心旺盛に世界を探検し始めるこの時期。親は「そろそろ自分でできることが増えてきた」と感じるかもしれません。しかし、自立を促す一方で、まだまだ危険が多い年齢でもあります。 だからこそ、幼児期の子どもには 「手を離さず」 が重要なキーワードとなります。
そして、もう一つ現代の子育てで欠かせないのが 「スクリーンを離せ」 という視点。
タブレットやスマホが身近な環境で育つ子どもたちにとって、スクリーンとの距離感は今や親の大きな課題の一つです。
「手を離さず」の本当の意味とは?
多くの親は、「手を離さず」と聞くと「危険だから手をつなぐ」というイメージを持つかもしれません。もちろん、交通量の多い道や高い場所では手をつなぐことが重要です。しかし、それ以上に大切なのは、子どもの心の成長に寄り添い、「精神的な手を離さない」こと です。
エピソード:公園での冒険と親の役割
ある日、公園で遊んでいた3歳の男の子がいました。目の前には、少し高いジャングルジム。彼は登りたいけれど、少し怖そうな顔をしています。すると、お母さんがこう言いました。
「やってみたいなら挑戦してごらん。でも、ママはここにいるから大丈夫。」
男の子はお母さんの言葉に安心しながら、一歩ずつ慎重にジャングルジムを登り始めました。そして、ついに頂上まで到達。満面の笑みで「ママ!できたよ!」と叫びます。お母さんは拍手しながら「すごいね!頑張ったね!」と声をかけました。
これはまさに 「手を離さず」の実践例 です。
親がすべてをサポートするのではなく、子どもが挑戦し、成長できる環境を作ることが大切 なのです。
「スクリーンを離せ」— デジタル時代の新しい課題
一方で、現代の子育てにおいて避けて通れないのが スクリーンとの付き合い方 です。
スマホやタブレットが当たり前になった今、幼児も簡単にYouTubeやゲームに触れられる環境にあります。しかし、長時間のスクリーン視聴がもたらす影響には注意が必要です。
なぜスクリーン時間が問題なのか?
研究によると、2歳〜5歳の子どもが1日2時間以上スクリーンを使用すると、集中力の低下や言語発達の遅れにつながる可能性がある と言われています。
また、スクリーンに夢中になりすぎると、以下のようなデメリットが発生します。
✅ 運動量の低下 → 体を動かす時間が減り、運動能力が発達しにくい
✅ 対面コミュニケーションの減少 → 表情を読み取る力や会話のキャッチボールが育ちにくい
✅ 睡眠の質の低下 → ブルーライトの影響で、寝つきが悪くなる
しかし、デジタル機器を完全に排除するのは現実的ではありません。
大切なのは 「適度に使う」「親がコントロールする」 ことです。
すぐに実践できる!「手を離さず・スクリーンを離せ」5つのポイント
✅ 1. 子どもが挑戦する環境を作る
→ 何でも親が先回りせず、「やってみよう!」と言える環境を整える
✅ 2. 「見守る力」を身につける
→ 手を出しすぎず、子どもが失敗しながら学ぶ機会を与える
✅ 3. スクリーンタイムをルール化する
→ 「平日は30分まで」「週末は1時間まで」など、時間を決めてメリハリをつける
✅ 4. スクリーンの代わりにリアル体験を増やす
→ 絵本の読み聞かせ、公園遊び、おもちゃ遊びなど、実体験を意識的に取り入れる
✅ 5. 親もスマホを手放す時間を作る
→ 親がスマホばかり見ていると、子どもも自然とマネしてしまう
まとめ
「幼児は手を離さず・スクリーンを離せ」という言葉には、「心の成長を支えながら、デジタルとの適切な距離感を保つ」 という重要なメッセージが込められています。
親が常に手を出すのではなく、「見守る力」を身につけ、子どもが安心して挑戦できる環境を作ること が大切です。そして、デジタル社会においては、スクリーンとの付き合い方も親がしっかりとガイドする役割 を果たさなければなりません。
「スマホばかりでいいのかな?」
「子どもが自分で考える力を育てたい」
そんな悩みを持つ親こそ、この考え方を取り入れてみてください。
「親は子どもの一番のコーチ」です。
今すぐできることから始めてみましょう!
③少年は目を離さず、悪情報を離せ

「小学生から中学生にかけての時期は、親の関わり方が大きく変わるタイミングです。」
幼児期を卒業し、親の手を借りずにできることが増えてくる一方で、社会との接点が広がる時期でもあります。
この時期の子どもたちは、友達関係が重要になり、スマホやSNSなどのデジタル世界にも自然と触れる機会が増えていきます。
親として「もう大丈夫だろう」と手を離したくなる気持ちもありますが、実はここが最も慎重に見守るべきタイミングです。
だからこそ、「目を離さず」 そして、「悪情報を離せ」 という考え方が重要になります。
「目を離さず」の本当の意味
「目を離さず」と聞くと、「過保護になれ」という意味に捉えられがちですが、それとは全く異なります。
この時期の親の役割は 「監視する」のではなく「見守る」 こと。
例えば、友達と遊びに行くときに、「どこに行くの?」「何時に帰るの?」と詮索するのではなく、子どもが信頼して自ら報告できる関係を築く ことが大切です。
エピソード:自由を与えたら、子どもはどう変わる?
ある家庭では、10歳の息子が「友達と遠くの公園に遊びに行きたい」と言ったとき、母親は不安を感じました。
しかし、「どこに行くか、何をするか、帰る時間を教えてね」と伝えた上で、あえて自由を与えました。
すると、息子は「ちゃんと帰る時間を守らなきゃ」と考え、途中で親に「今から帰るね」と自主的に連絡をするようになりました。
この経験を積み重ねることで、子どもは自分で責任を持つことを学ぶのです。
目を離さないことは 「干渉すること」ではなく、「子どもが自分で考え、行動できるようサポートすること」 を意味します。
「悪情報を離せ」— 情報過多の時代にどう向き合うか
現代の子どもたちは、親世代とは比べものにならないほど多くの情報に触れています。
特に、スマホ・SNS・YouTube・オンラインゲームなど、インターネット上の情報にさらされる機会が圧倒的に増えています。
「悪情報を離せ」 というのは、単に有害なサイトをブロックすることではなく、
「子ども自身が悪い情報を選ばない力を育てる」ことを意味します。
悪情報が子どもに与える影響
✅ フェイクニュースや陰謀論に影響を受けやすい
✅ SNS上の誹謗中傷や悪口に巻き込まれる
✅ 危険なオンラインゲームや詐欺的な誘いに乗ってしまう
✅ 過度な広告や刺激的な動画に依存してしまう
「うちの子は大丈夫」と思っていても、子どもは知らないうちにこうした情報に影響を受けているかもしれません。
どうすれば「悪情報」を離せるのか?
ここで大切なのは 「情報のリテラシー教育」 です。
単に「その動画見ちゃダメ」「スマホは禁止」とルールで縛るのではなく、「なぜ危険なのか」 を理解させることが重要です。
✅ 1. 「悪情報とは何か」を話し合う
→ SNSの嘘情報、ネット広告の危険性、フェイクニュースなど、実例を使って説明する
✅ 2. 「何を信じるか?」を考えるクセをつける
→ 「この情報、誰が発信してるの?」「根拠はある?」と考えさせる習慣をつける
✅ 3. 「ネットでの発言には責任がある」と教える
→ SNSでのコメントや投稿は、消しても一生残る可能性があることを伝える
✅ 4. 子どもと一緒に情報を調べる時間を作る
→ ニュースや話題の出来事について、親子で一緒にリサーチする
✅ 5. 相談しやすい関係を築く
→ 「何かあったらいつでも話していいんだよ」と伝え、オープンな雰囲気を作る
まとめ
「少年は目を離さず・悪情報を離せ」というのは、
「子どもの行動を監視し、制限する」という意味ではありません。
親が適度に見守り、子どもが自分で「何が正しい情報なのか?」を判断できる力を育てる ことが大切です。
「悪情報を遠ざける」のではなく、正しい情報を見極める力をつけること。
「目を離さず見守る」のではなく、子どもが信頼して相談できる関係を築くこと。
この2つが、これからの時代を生きる子どもにとって最も重要なスキルになるのです。
「スマホを持たせるのが不安」
「ネットの情報に振り回されてほしくない」
そんな悩みを持つ親こそ、この考え方を取り入れてみてください。
「親の目の代わりに、子ども自身の目を鍛える。」
それが、これからの時代に必要な「令和版・子育て四訓」の実践なのです。
④青年は心を離さず、現状維持を離せ

「高校生から成人するまでの時期は、子どもが親の手を完全に離れ、自分の未来を切り拓いていく重要なステージです。」
この時期の親の役割は、もはや「導くこと」ではなく「見守ること」に変わります。
しかし、「もう親の役目は終わりだ」と思ってしまうのは危険です。
子どもが大きくなっても 「心を離さず」 つながり続けることは、青年期において最も重要な親の役割なのです。
さらに、この時代において特に重要なのが 「現状維持を離せ」 という視点です。
今、世界は VUCA(ブーカ)の時代 と呼ばれています。
VUCAとは
Volatility(変動性)
Uncertainty(不確実性)
Complexity(複雑性)
Ambiguity(曖昧性)
これまでの常識が通用せず、未来が予測困難な社会では、安定を求めること自体がリスクになりつつあります。
つまり、「現状維持こそ最大のリスク」 なのです。
だからこそ、青年期の子どもたちに必要なのは、「安定」を目指すのではなく、「変化に適応する力」を育むこと。
これを親がどうサポートするかが、子どもの未来を大きく左右します。
「心を離さず」の本当の意味とは?
多くの親は、「もう高校生だし、自分で決めさせよう」と、急に突き放してしまいがちです。
しかし、青年期は最も迷いやすく、挫折を経験しやすい時期 でもあります。
たとえば、進路選択で悩むとき、部活動や勉強で挫折したとき、人間関係で壁にぶつかったとき――
このときに、親が完全に距離を取ってしまうと、子どもは「自分の居場所がない」と感じてしまいます。
エピソード:進路選択に迷った息子と父親の言葉
大学受験を控えたある男子高校生は、成績はそこそこ良いものの、「本当にこの道でいいのか?」と悩んでいました。
しかし、親に相談するのが怖くて、一人で抱え込んでしまいます。
そんなある日、父親が何気なくこう言いました。
「お前がどの道を選んでも、俺は応援するよ。でも、何か迷ったら、いつでも話してくれ。」
その一言で、息子は「親は自分の選択を否定しない」と安心し、少しずつ進む道を決めていきました。
「心を離さず」とは、何でも口出しすることではなく、「いつでも受け止めるよ」というスタンスを示すことなのです。
「現状維持を離せ」— VUCAの時代に求められる力とは?
「いい大学に入って、いい会社に入れば安心」
かつては、それが「成功の道」でした。
しかし、VUCAの時代には、この方程式がもはや通用しなくなっています。
✅ 企業の寿命が短くなり、終身雇用が崩壊しつつある
✅ AIの発展により、10年後には今の職業の多くがなくなる可能性がある
✅ 国際競争が激化し、日本国内だけでは生き抜けなくなる
そんな時代において、子どもが「このままでいい」と思ってしまうことが、最大のリスクなのです。
親がすべきことは、「挑戦しなさい」と命令するのではなく、挑戦を後押しすること。
「変化を恐れない力」を育てることが、未来の生存戦略につながります。
なぜ「現状維持」が危険なのか?
✅ 挑戦しないことで、成長の機会を逃す
✅ 一度守りに入ると、変化に適応しにくくなる
✅ 「自分はこの程度」と決めつけるクセがつく
✅ 社会に出たとき、困難に立ち向かう力が不足する
特に、「安全な道を選びすぎる」ことが問題です。
どうすれば「現状維持を離せる」のか?
✅ 1. 「変化を楽しむ」マインドを育てる
→ 変化は不安なものではなく、成長のチャンスであると伝える。
✅ 2. 親自身が挑戦する姿を見せる
→ 親が変化を恐れていると、子どもも「挑戦は怖いもの」と思ってしまう。
✅ 3. 「失敗は成長の一部」と伝える
→ 「一度の失敗で終わるわけじゃない」と伝え、何度でも挑戦する価値を示す。
✅ 4. 安全地帯から少しだけ外に出る機会を作る
→ 例えば、海外留学・インターン・ボランティア活動など、新しい環境を経験させる。
✅ 5. 「今のままでいいの?」と問いかける
→ 「現状に満足している?」と穏やかに問いかけるだけで、子どもが自分の未来を考えるきっかけになる。
まとめ
「青年は心を離さず・現状維持を離せ」という言葉には、「心の支えを持ち続けながら、変化を恐れず挑戦する力を育てる」 というメッセージが込められています。
VUCAの時代を生き抜くために必要なのは、安定を求めることではなく、変化に適応する力 です。
子どもが高校生や大学生になったからといって、親が完全に手を引く必要はありません。
むしろ、この時期こそ 「見えない支え」として、そっと背中を押してあげること が求められます。
「うちの子、大人になれるのかな?」
「新しいことに挑戦する勇気を持ってほしい」
そんな悩みを持つ親こそ、この考え方を取り入れてみてください。
「親は最後まで子どもの応援団である。」
そういう関わり方が、子どもの未来を明るく照らすのです。
記事のまとめ
「令和版・子育て四訓」は、時代の変化に対応した新しい子育ての指針です。
私たちの親世代とは異なり、デジタル技術の進化や社会の複雑化により、育児のあり方も大きく変わっています。
そんな今だからこそ、親がどのように子どもと向き合い、支えていくべきかを考えることが重要です。
令和版・子育て四訓のポイント
📌 乳児は肌身離さず・病気を離せ
→ スキンシップは愛情と成長の土台! 免疫力を高めるためにも「適度な外の世界との接触」も意識しよう。
📌 幼児は手を離さず・スクリーンを離せ
→ 親の「見守る力」がカギ! デジタル依存を防ぎ、リアルな体験を増やすことで、子どもの好奇心と成長を促そう。
📌 少年は目を離さず・悪情報を離せ
→ ネットリテラシーが必須の時代! 情報の取捨選択ができるように、親が見守りながら「考える力」を育もう。
📌 青年は心を離さず・現状維持を離せ
→ 変化に強い子を育てる! 「VUCAの時代」を生き抜くために、挑戦を後押しし、親は見えない支えになろう。
今すぐ実践できること
✔ 子どもと触れ合う時間を増やす(特に乳児期)
✔ スクリーン時間をコントロールし、リアル体験を増やす
✔ ネットリテラシーを学び、子どもと情報について話す機会を作る
✔ 「現状維持=安全」ではないことを理解し、挑戦するマインドを育む
親が変われば、子どもの未来は大きく変わります。
「親がすべてを決める時代」から、「子ども自身が未来を創る時代」へ。
だからこそ、子どもが自立しながらも、どんな時でも「安心して帰れる場所」としての親であり続けることが大切です。
この記事が少しでも役に立ったと思ったら…
💖 「スキ」を押して、応援していただけると励みになります!
👥 フォローしていただくと、今後も役立つ情報をお届けします!
🔄 「シェア」して、大切な人にもこの情報を届けてみませんか?
💬 コメントであなたの考えや実践していることを教えてください!
子育ては一人ではできません。
一緒に学び合いながら、より良い子育ての形を模索していきましょう!
あなたの「いいね」や「シェア」が、未来の親たちの支えになります。
いいなと思ったら応援しよう!

