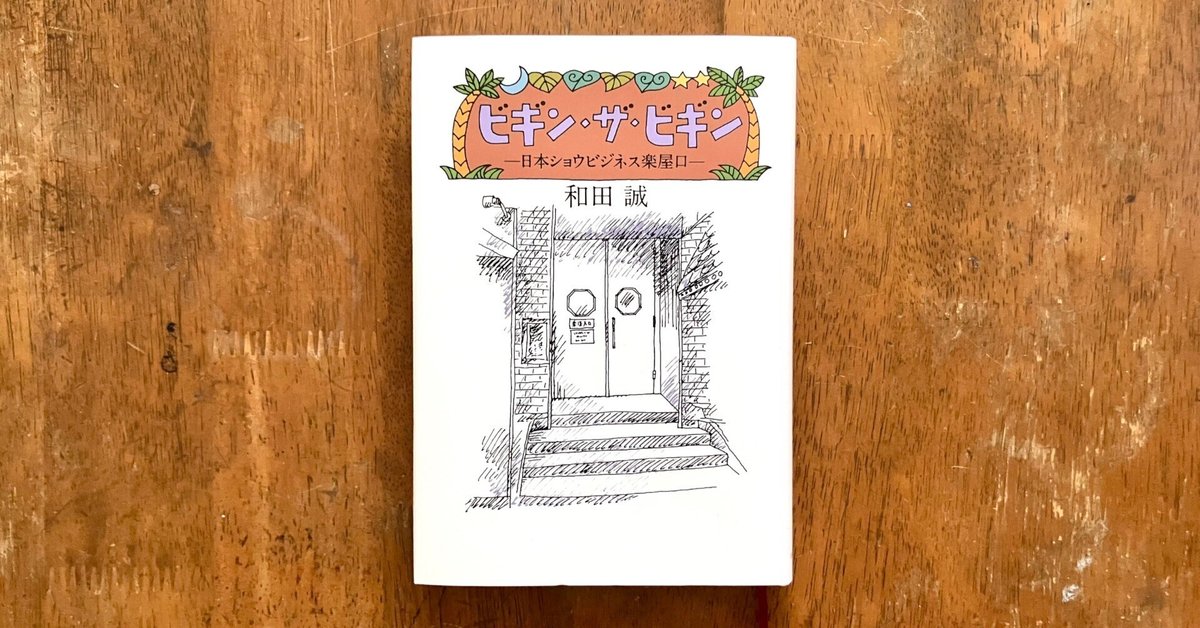
『わたしのつれづれ読書録』 by 秋光つぐみ | #58 『ビギン・ザ・ビギン 日本ショウビジネス楽屋口』 和田誠
PARK GALLERY が発信するカルチャーの「本」担当。2024年の夏、地元・長崎で古書店を開業したパークスタッフ秋光つぐみが、PARK GALLERY へ訪れるみなさんに向けて毎週一冊の「本」を紹介する『わたしのつれづれ読書録』。
本とは出会い。
長崎から、パークに想いを馳せながら、誰かの素敵な出会いのきっかけになる一冊を紹介していきます。
2024年12月5日の一冊
「ビギン・ザ・ビギン 日本ショウビジネス楽屋口」和田誠(中央公論社)
私はこれまでグラフィックデザイナー、フォトグラファー、飲食店やゲストハウスのホールスタッフ、ギャラリースタッフ、古書店員といった基本的に “裏方” に近い仕事に取り組んできた。
そんな自分が生きてきた世界とはかけ離れたものであるからこそ、その距離が憧れの気持ちを募らせる。裏方が性分であり、その世界で生きてきた私が憧れてやまないのが、ミュージカルや演劇などといった "表舞台で輝く人々" である。
今回紹介する本は、イラストレーター和田誠さんによる『ビギン・ザ・ビギン 日本ショウビジネス楽屋口』。

東京・有楽町。ここにかつて存在した「日本劇場」、通称「日劇」。戦前から戦中、戦後の終焉までここで花開いた、歴史的にも誇ることのできるショウ文化を、当時活躍した俳優や演出家、作曲家らのエピソードを交えて生き生きと記録した「日劇を舞台とした芸能史」である。
和田誠さんは大の映画好き・ジャズ好きとしても知られ、その情熱が自身の仕事にも大いに生かされ、映画・音楽業界にも残る業績を今もなお語り継がれていることは皆、承知であろう。
本書は、1982年に単行本、1986年に文庫版が文藝春秋より発刊され、それらを改めて再編集し2024年10月に発刊されたいわゆる『ビギン・ザ・ビギン』完全版なるものである。
昨年度下期の朝の連続テレビ小説『ヴギウギ』ヒロインのモデルとなった笠置シヅ子に始まり、宝塚スターとしてスターダムを駆け上がった越路吹雪など、のちに日劇で活躍したスターたち。
彼女たちの、日劇を舞台として繰り広げられる裏側を、その舞台に立つに至った経緯や、ショウの本番ギリギリまでの演出裏話などを、日劇の主たる演出家・山本紫郎らを通して事細かく取材なされている。

読み進めることで、戦後の芸術活動の厳しさがひしひしと伝わってくるのだけれども、それを越えて、美しい夢を見せなければと情熱を燃やした「日劇人たち」の姿勢も伺うことができる。
豪華絢爛、何百人ものダンサーが大階段に整列し、ラインダンスを繰り広げる。色鮮やかな衣装・小物に身を包み、長いつけまつ毛をたなびかせる。ナマモノの舞台には当然、生演奏。
極端に言えば「なんでもアリ」だった昭和。その場限りのプールを設置してそこに飛び込む演出があったり、宙吊りのブランコに俳優を座らせ10分待機させたりなど、舞台装置も今から考えると超絶トリッキー。
しかし「夢を見せなければ」という執念が、これらの無茶な舞台を許した。そういった時代があったからこそ、俳優、演出家、作曲家、演奏家、大道具、小道具など、それに携わる人間たちとともに舞台芸術は成長し、今日をもって伝説と化しているのかもしれない。
その時代に生まれ、東京に生きて、そんな舞台を観てみたかった。平成に生まれ、長崎に育ち、そんな芸術を目の当たりにしたことのない私には「日劇のショウ」は完全に「夢」でしかない。

『ビギン・ザ・ビギン』はコール・ポーター(1891-1964)の作詞作曲。1935年のミュージカル、『ジュビリー』の中の一曲。
ビギン=beguine は、西インド諸島の一つのマルチックで生まれたリズムの名称。ポール・コーターはこれに英語のビギン= begin を結びつけた。直訳すれば「ビギンを始めよう」。しかし語呂合わせ的な面白さを保とうと「ビギン・ザ・ビギン」と呼んだ。

演出家・山本紫郎との師弟的な縁により、越路吹雪が歌うこととなる。
彼女はこの曲を歌う際に、できるだけ日本語で歌おうという主義があった。英語では日本人に伝わらないし、いくら真似してもアメリカ人のように歌えるわけはない、と。
たのしきは ビギン
あまき恋の しらべよ
椰子のしげる 南国の
想い出の 恋の歌
胸あつき 夜に
声合わせ 歌いし
なつかしの 夜の歌
たのしきは ビギン
胸おどる あの夜の
心ゆするしらべ
ふたりで 愛を誓いて
仰ぎ見る あの空に
神の使いの 歌か
よろこびに 胸もさける想い
はるかにながれゆきし あの歌
忘れられぬリズム
・
・
舞台というものは、言うなれば総合芸術である。
板があり、舞台装置がある。音楽が鳴り、スポットライトが灯る。振付をし、俳優たちが踊る。彼らが纏う衣装がある。詩の世界に浸り、そこで完成する物語がある。客席と一体となった空気がまた舞台を輝かせる。
全てが大切で欠けてはならないものであり、そこで初めて完成する。
1950年代に入ると、次第にテレビの台頭により、ショウビジネスは衰退の一途を辿ることになる。時代の変化には抗えないまま、日劇は消えてしまった。
読み進めるうちに、当時のドラマを思い描いてはドキドキしたりハラハラしたり、知らないのに勝手に寂しくなったり、名残惜しんだり、悔やんだり。
日劇を舞台にショウビジネス界を体現して生きてきた「日劇人」たちの軌跡を、こうして和田誠さんのフィルターを通して堪能することができ、私にとっては当時のエンターテイメントを楽しむことができる貴重な一冊となり得ている。
時代も、世界も、自分とはあまりに距離のある「日劇」はある意味、幻であり、伝説であり、夢である。心の中にそういうものを潜ませているのも、なんだかそれだけで楽しい。唯一、本を通してそれらを味わうことができるのも、ラッキーなのだと思う。
古書堂 うきよい 店主。
グラフィックデザイナーなど。
2022年 夏からPARK GALLERY に木曜のお店番スタッフとして勤務、連載『私のつれづれ読書録』スタート。2024年 4月にパークの木曜レギュラー・古本修行を卒業、活動拠点を地元の長崎に移し、この夏、古書店を開業。パークギャラリーでは「本の人」として活動中。
【Instagram】@ukiyoi_inn
いいなと思ったら応援しよう!

