
「個の力を活かせる組織」が好循環するワケ 1(そもそも編)
マスクが減って表情が見えるこの頃。とはいえ、テレワークも浸透して、コミュニケーションのあり方を改めて考える機会も増えた気がします。
プロジェクトで一緒になるメンバーの考えていること・大切にしてること。もっと深く理解できたら、チームも組織も強くなるのではないかと。
そう思って、今回は創造性や生産性の高める組織経営を学んだので、ご紹介します。
1.注目されてきた「人を資本とする経営」

経産省が発表した「伊藤レポート2.0」
人材を「管理対象」と捉えがちだった日本企業。これから「人材をコストではなく資本」と捉えて、企業理念や経営戦略に合わせて「人」にしっかり投資していこう。というもの
具体的には、人材戦略には「3つの視点」と「5つの共通項目」が求められる。とされてます。
概略は以下ですが、今後組織は「個の力を最大限に発揮できる環境と戦略」が求められるようです

◆3つの視点(経営の大枠)
①「人材戦略」と「経営戦略」が連動してるか
②理想と今のギャップを把握できてるか
③企業文化へ定着してるか
◆5つの共通項目(個別に必要な要素)
①動的な人材ポートフォリオ (多様な人材が活躍)
②知・経験のD&I(個々の能力が活かされる)
③リスキル・学び直し
④従業員エンゲージメント(社員が意欲的)
⑤働き方の多様化
僕自身も、今まで取材させてもらうなかで、
「お客様第一」は大切だけど、「社員を大切にすれば、その社員がお客さんを幸せにしてくれる」という経営を前提にされている方は、結果的に、その企業やお店が周りから愛されているな。という肌感覚がありました。
具体的に社員が大切にされ、エンゲージメントが高いと、どんな効果があるのでしょうか。
2.個の力が活かされる経営論
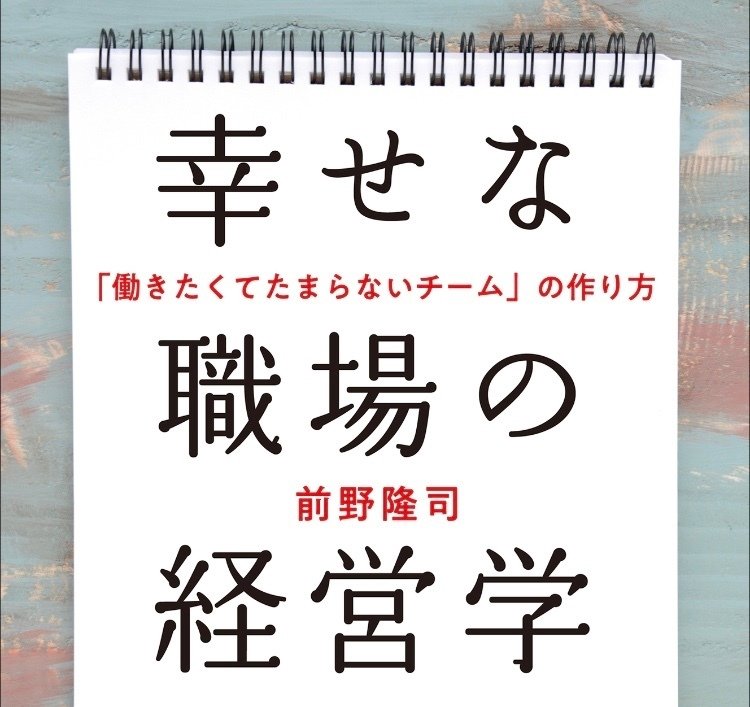
「幸福度」の高い従業員は、そうでない場合より創造性が3倍、生産性が31%、売上が37%高くなるという米心理学者による研究結果があります。
こうした研究を踏まえ、従業員の幸福度を高める経営を提唱されている、慶應義塾大学の前野先生の著書「幸せな職場の経営学」によると
人が幸せになるためには「必要な因子が4つ」あるとされ、経営に当てはまると以下のような状態を指します。
(1)幸せを構成する4つの因子
①やってみよう因子
自分の強みを活かして成長できる
②ありがとう因子
人との繋がりやお互いに感謝を感じられる
③なんとかなる因子
リスクを取った新しいチャレンジが推奨される
④ありのままに因子
他者との比較でなく個々人が尊重される
ちなみに
「地位財(年収や社会的地位など)」より
「非地位財(人との繋がりや趣味など)」の方が幸福が長続きするとの研究結果もあるとのこと。
お金はもちろん大切ですが、まずは、この4因子が満たされているかどうかが重要なのですね。
さらに、「はたらく」を掘り下げたところでは
前野先生がパーソル総合研究所との共同研究で「はたらく人の幸せの7因子・不幸せの7因子」を公開し、その診断ツールを開発されてます。
(2)はたらく人の幸せの7因子
ちなみに、はたらくver.での幸せ因子はこちら
①自己成長因子(学びや能力向上への期待)
②リフレッシュ因子(ワークライフバランス)
③チームワーク因子(仲間とのつながり)
④役割確認因子(自分の仕事 役割を感じる)
⑤他者承認因子(周りから認められてる)
⑥他者貢献因子(人の役に立っていると思える)
⑦自己裁量因子(自分の意思が反映される)
「はたらく幸せの実感が高い人」ほど、個人や組織でのパフォーマンスが高いそうです。こうした研究からも、従業員のエンゲージメントを高めることが組織の成長に繋がることが分かります。
こちら前野先生の書籍です。
3.不幸な組織にある共通点

一方、はたらくうえで不幸な因子も存在します。
(1)はたらく人の不幸せの因子
①自己抑圧因子(自分の強みを活かせない)
②理不尽因子(ハラスメント)
③不快空間因子(視覚や嗅覚など体感的な不快)
④オーバーワーク因子(自分の時間が犠牲に)
⑤協働不全因子(メンバー間が非協力)
⑥疎外感因子(同僚・上司とのコミュニケーション不足)
⑦評価不満因子(努力が報われないと感じる)
②③④はよく目にする項目ですが、①⑤⑥⑦のありがちな項目も、しっかり不幸せの因子です。
たとえ個人の因子でも組織に蓄積されていくとどうなるのか。
そこで、組織を不幸にするマニュアルも確認したいと思います。
(2)米国スパイが推奨した組織の破壊行動
こちらサボタージュ・マニュアル。CIAの前身組織OSSが、組織を弱体化させるために作っもの。暴力とかの破壊行為じゃなく、真面目そうに見える行動が組織を「まわらなく」します。
・形式的な手順をしっかり守る
・とにかく文書で指示を出す、細かく修正させる
・議論を重視して会議をたくさん開く
・十分な準備ができてから行動する
・大切なことをコミュニケーションしない
・組織内の人間関係を悪化させ緊張感をもたせる
・頑張っても報われない環境をつくる。など
特に前半って、真面目な行動に見えますよね^^;
実は度が過ぎるとむしろ組織を破壊するんです。これは肝に銘じておきたいですね。
そして「士気をくじくこと」が組織のサボタージュに重要な位置付けであるとも示唆があります。
なんと、幸せの因子を奪い、不幸せの因子を助長する行為が見事にまとまってる凄いマニュアル…
不幸な組織や、従業員の「やりがい」が奪われた組織は弱体化する。目に見えて弱くなるというより、気づかないうちに少しずつ蝕まれていく印象があって、そこに恐怖を感じますね。
4.やりがいをつくり出す最初の一歩は?

では、個の力を引き出し、従業員がやりがいを感じる組織にするために、まず何ができるのか。
参考となる「組織の成功循環モデル」によると
※MIT組織学習センター共同創始者のダニエルキム氏が提唱
組織は因果関係を持つ4つのサイクルがあります。

そして組織を好循環させるには、まず「関係の質」を高めることが重要とされてます。
関係の質:お互いを理解・尊重して一緒に考える
↓
思考の質:気づきが共有され、良いアイデアが出る
↓
行動の質:自発的・積極的な行動が増える
↓
結果の質:成果が現れてくる
※ただし、ここでいう関係の質は、仲良しグループではなくて、耳の痛いことでも思ったことを伝え合えるという信頼関係を指します。
よい結果へ導くには、当たり前ですが良いチームづくりが基礎となり、そこには「質の高い対話」もすごく重要になります。
前野先生の書籍でも、1on1や対話の重要性に触れられています。
さらに、これまでの取材を通して思うことは
フラットで丁寧な対話を大切にすることはもちろん、経営理念やパーパスがしっかり共有されている組織は、前向きな変化を起こしているということ。
人的資本経営なるものは、対話やチームビルディングも、忙しいからとか、非効率だからといったコストではなく、投資として捉えることが大切で、その基礎ができていれば組織の成長にも繋がっていくのではないでしょうか。
5. 追伸:対話と組織開発にあるメソッド

ちなみに、もっとコミュニケーション増やそう!縦割りなくして横のつながり作ろう…って声かけだけで、組織に変化を起こすのは難しくないでしょうか。
対話やチームビルディングを「投資」と捉えるなら、戦略的に実践することが重要ではないかと思うのです。
そこで、色々な方法論はあるものの、次回紹介したいのが、LEGO® SERIOUS PLAY®です。
企業のビジョン策定やチームビルディングに有効な手法として確立した組織開発のメソッドです。
僕自身、知識を深めたくて「LEGO® SERIOUS PLAY®メソッドと教材活用トレーニング修了認定ファシリテーター」の資格を取得しました。
その経験も踏まえ、後編では組織の成功循環モデルの実践へ向けて一歩踏み出すときに必要なことを紹介します。詳しくはこちらを!
今回もお付き合いくださって、ありがとうございました!!
