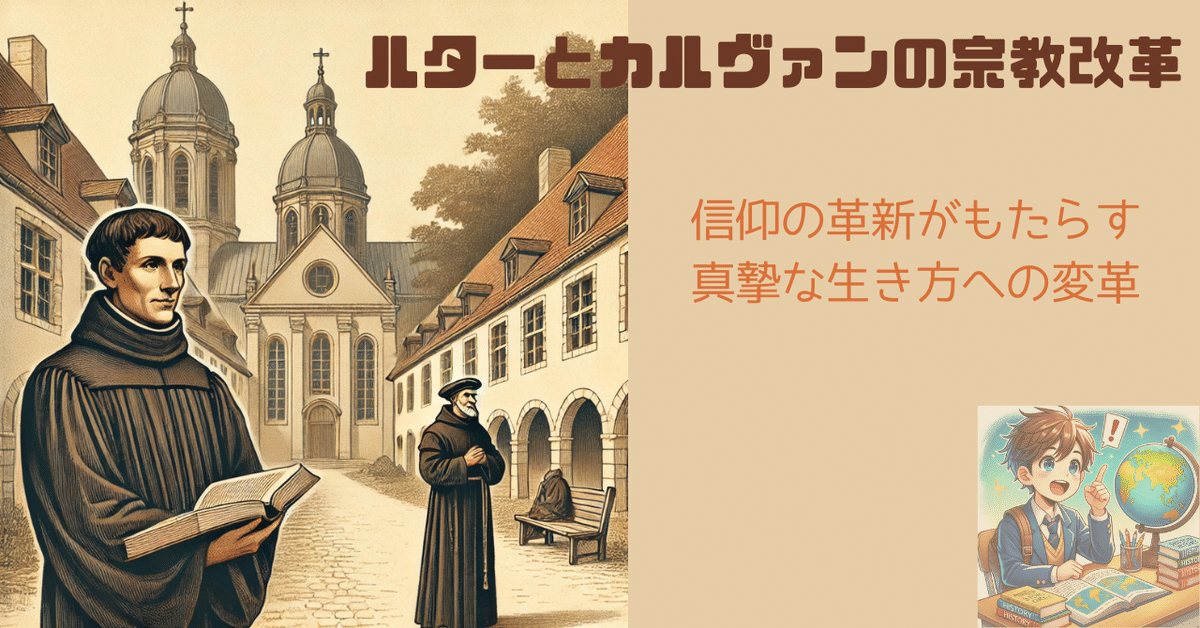
ルターとカルヴァンの宗教改革
近世ヨーロッパにおける宗教改革は、キリスト教内部の動きから政治的な変動に至るまで、多大な影響を与えました。
今回は、このキリスト教の歴史的転換点を理解するために、ルター派、カルヴァン派、カトリックの対抗宗教改革、という点を共有します。
1.近世ヨーロッパ/宗教改革を学ぶ上での教材
今回は、ユーテラ世界史/佐藤幸夫先生のYoutubeから学びました。15分で、重要なポイントを押さえながら、細部を早口で教えて頂けます。後半の地図による解説も面白いです。是非参考にしてみてください。
2.宗教改革が起きた要因と当時の政治的背景
15世紀頃のヨーロッパにおけるカトリック教会は、財政的搾取の手段として、特に神聖ローマ帝国内で免罪符の販売を行っていました。
この時期、ローマ教皇レオ10世は、サン・ピエトロ大聖堂の改築資金を調達するために広範囲にわたる免罪符の販売を推進し、莫大な資金を集めました。このような状況から、当時、神聖ローマ帝国は「ローマの牝牛」と揶揄されていたようです。
また、神聖ローマ帝国は複数の外部的な圧力に直面していました。一つは、イタリア地域でのフランス国王との権力争いであり、もう一つは東部オーストリア地域でのオスマン帝国の脅威でした。これらの外敵との対峙は、帝国内部の政治的、経済的資源を極度に圧迫していました。

3.マルティン・ルター/ルター派の教え
16世紀になると、神聖ローマ帝国において、マルティン・ルターは、このようなカトリック教会の腐敗、特に免罪符の販売に異議を唱えました。そして、彼は「95か条の論題」を発表します。
その後、彼は、カトリック教会からの破門を受けます。当時の神聖ローマ帝国皇帝カール5世の説得にも関わらず自説を曲げず、ルターはザクセン選帝侯の元に逃れます。その後、ドイツ語で新約聖書を翻訳し、広範な支持を得ることで改革を進めました。
※ルターによりドイツ語訳された新約聖書は、活版印刷技術により製本され、同国内に広められます。
彼の教えは、信仰義認説、聖書主義、万人司祭主義に基づいています。
これらの彼らの教えは、同国の反皇帝派の諸侯と農民層に支持されることとなります。
その後、農民による大反乱が起きましたが、これらは諸侯により鎮圧されました。その後、ルターの教えは、諸侯や自由都市の主導により行われました。
最終的には、当時のカール5世も、ルター派の信仰を認めざるを得なくなりました。しかし、ルター派の信仰の選択は、各個人ではなく、その地域の領主(諸侯)が決めることができる。その地域の領民はこれに従わなければならない。これを領邦教会制度と言います。※アウクスブルクの和議(1555年) にて決定。
4.カルヴァンとカルヴァン派の教え
スイスのジュネーブでは、聖書主義、予定説、長老主義といった教えを広めました。これらは、信者に禁欲的な労働を奨励し、経済的蓄財を認めることで、新興の商人階級から広く受け入れられました。
長老主義:司教ではなく各地域の長老が牧師を補佐して教会を運営する
予定説:死後魂が救われるかは、神によってあらかじめ定められている
5.カトリックの対抗宗教改革
プロテスタントの台頭に対抗して、カトリック教会はトリエント公会議を通じて教義を再確認し、内部の革新を図りました。
また、イエズス会の設立により、アジアやアメリカ大陸への積極的なローマ=カトリックの布教活動が行われました。日本にキリスト教を初めて伝えたフランシスコ=ザビエルは、イエズス会の使者です。

6.私が思う宗教改革
この歴史的な学習を通じて、カトリック、ルター派、カルヴァン派の間の教義の違いを理解することが出来ました。特にカルヴァン派の「勤勉であれ!」という教えは、個人的に非常に魅力的に感じます。
これらの宗派の分裂は、その後のヨーロッパの国々の政治と文化に大きな影響を与え、新たな国家の成立や隆盛の要因となっていきます。
7.おまけ
プロテスタントの語源(Protestantio)(抗議する)
当時神聖ローマ帝国/皇帝⁼カール5世は、帝国内でのルター派の信仰を認めざるを得ない状況でした。それは、当時同国が、宗教上の国内での争い・フランスとオスマン帝国の争いを抱えていたからです。しかし、3年後に再弾圧を開始しました(国外からの脅威が減ったため)。これにルター派が抵抗しました。彼らの活動はProtestantio(プロテスタント)と呼ばれたことが、その語源と言われています。
最後まで読んで頂いてありがとうございます。引き続き楽しく世界史を学び続けたいと思います。
