
◆読書日記.《佐藤優『嫉妬と自己愛』》
※本稿は某SNSに2020年6月7日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
佐藤優『嫉妬と自己愛 「負の感情」を制した者だけが生き残れる』読了。
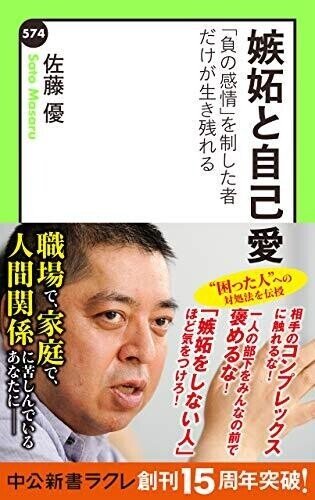
元外務省主任分析官であり現・作家である佐藤優氏が、現代社会に生きる人々の性格特性のうち特に「嫉妬と自己愛」について考える事で、この日本社会の現状と今後を分析していく一冊。
そんな本書は大きく分けて以下、3つのパートに分けられる。
●第1部:「嫉妬と自己愛の時代」では著者が今回の本で何故「嫉妬と自己愛」をテーマとして取り上げたのか、その動機を説明する。それを踏まえて、では現代日本人における「嫉妬と自己愛」は、どういう状態になっているのか「現代文学」をサンプルとして読み解く。
●第2部:「嫉妬と自己愛をめぐる対話」では本書のテーマについて、それぞれの分野の著名人と対話をしながら考える。精神科医の斎藤環氏、ストーカーやDV被害等のあらゆるハラスメントの相談に対処するNPO法人「ヒューマニティ」理事長の小早川明子氏、そして映画監督の井口奈美氏の三名との対談形式の分析だ。
●第3部:以上を踏まえた「まとめ」として行った講義録「人生を失敗しないための『嫉妬と自己愛』講座」である。現代の「嫉妬と自己愛」は、世代によって微妙のその在り方が変化してきている。その変化に戸惑っている者は多いようだが、組織を守るためにそういった変化にどのように対応すれば良いか著者なりの結論を示す。
執筆、対談、講義録、と三種類のアプローチで一冊本を上梓する。
なんてエコで効率的な本の執筆方法だろうかと、ちょっと感心してしまった。これなら一冊丸々原稿用紙を埋めるよりもダンゼン楽だ。そのうえ、まるで「手抜き」感も与えない。それどころか「多角的アプローチ」にさえ見える。
頭のいいやり方だなぁ。
◆◆◆
本書の内容は「嫉妬と自己愛」について、あくまで著者なりの考えと分析を敷衍するため学術的なアプローチというわけではない。
著者の経歴による経験知が大きくモノを言うタイプの論述なので、あくまでその点を踏まえて、適度な距離を置きながら読む事である程度の参考になる知見となるタイプの本だと思う。
まず、著者が本書のテーマである「嫉妬と自己愛」をテーマとしようと思ったきっかけというものの一つが、まず著者がまだ外務省に在籍していた時期に起き、著者自身も有罪判決を受けた「鈴木宗男事件」だったという。
著者自身の主張によればこの事件は「身に覚えがない罪で有罪判決を受けた」と言うが(日本にこういう「濡れ衣」的な話の何と多い事か……)、その原因は鈴木宗男氏に対する周囲の政治家たちによる強烈な嫉妬心にあったと推測している。
2000年4月、その当時脳梗塞で意識不明の状態にあった小渕恵三首相の代わりに、自民党総務局長だった鈴木宗男氏は首相の親書を持ってモスクワでプーチン大統領と会談した。
それの事を当時の外務省東亜局長が当時与党の政治家たちに報告しに行ったところ、ほぼみんなの反応は「憤然とした調子」だったという。
中曽根元総理、橋本元総理、三塚博元大臣、中山太郎元大臣など、それぞれ憤然としている。橋本龍太郎に至っては相槌もせずに席を立って部屋を出てしまったほどだったという。
何か事前の根回しにミスがあったのか?いや、なかったのだ。彼らは怒っていたのではなく鈴木宗男に「強烈に嫉妬」していたのだった。
「嫉妬など女性がするものだ」等という人間もいるようだが、とんでもないことだ。男も嫉妬する。しかも、見苦しいくらいに陰湿で強烈な嫉妬だ。
それは恋人を取られたとか、学校の成績が自分より上だとか言う理由ではなく、「権力」と「地位」に対する権力闘争に結び付く嫉妬が凄まじいのだと著者は言う。
日本の官僚のように仕事のできる人間などは自分の嫉妬心を隠す知恵が身についているというが、著者は外務省時代の経験を踏まえて「同期が一歩先に出世すると、笑いながら「よかったね」と言っても、一瞬、口元がひきつるという形で、嫉妬が表れる」と、官僚たちも確実に持っている嫉妬心の強さを表現している。
特に魑魅魍魎が跋扈して巨大な権力を手に入れるために血みどろの権力闘争が繰り広げられる「政治家」となると、その嫉妬心は凄まじいものとなる。
鈴木宗男氏は政治家には珍しく、さほど嫉妬心は強くないほうだったと言う。だが、彼の「嫉妬心の薄さ」が、彼にとっては命取りになる事となったのだ。
嫉妬心が薄い人間は、他人の妬み、嫉みが分からない、気付きにくいのだという。
鈴木氏の性格は「気配りをよくし、人の先回りをしていろいろ行動する。そして、鈴木さんなしに物事が動かなく」なってしまうという。
「それが相手のためとも思うけど、相手は感謝するよりも嫉妬する。その蓄積があるタイミングで爆発する」
これが日常生活の上でならば、他人に嫉妬する事なく気配りができる人間というのは「寛容で心が広い」という事で美徳ともとれるだろう。
だが、政治家や官僚のように競争の激しい世界では、周囲の嫉妬心を機敏に察知する能力がなければ生きて行けず、それどころか周囲を巻き込んでトラブルを引き起こすのだそうだ。
「鈴木宗男事件」がまさにそれだったと著者は指摘する。
鈴木宗男ープーチン会談によって、政治家たちの鈴木氏に対する認識が変化した。
自分達のライバルになるんじゃないかと危機感を抱いたのだ。
事実、2001年小泉政権が成立した際、外務相の田中真紀子外相は「外務省が鈴木氏に支配されているという認識を一方的に抱き、人事パージを始めたので、外務省は大混乱に陥り、外務省幹部も生き残りに必死になり、外交どころではなくなった」のだという。
「嫉妬心」というのは競争社会の中では必ずしも「悪」ではなく、組織内の各人が上を目指して切磋琢磨するようになるモチベーションとなるものでもある。
だが、これが「足の引っ張り合い」に発展すると組織にとってはマイナスに働く事となる。
特に「能力はないが、意欲だけはある」というタイプが、この場合は嫉妬心に狂い、問題行動を起こして組織にマイナスとなるのだそうだ。
マネジメントする立場としては、このタイプを警戒した方が良いようである。
◆◆◆
さて、本書はテーマを「嫉妬と自己愛」としているように、嫉妬と自己愛というものは隣り合わせの関係にあると著者はいう。
他人に嫉妬するというのは、無論自分の事が大事だからでもある。著者は最近の若い世代の事情は「嫉妬が後退し、代わって歪んだ自己愛が増殖しているのではないか」と見ているようだ。
それは何故なのか?
「結論を言えば、日本で言えば小泉政権くらいから本格的に始まった新自由主義政策が『功を奏し』、いよいよ社会の根っこの部分にまでその仕組みが浸透してきた結果だ」と、著者は考えるのである。
頑張っていればいつかは上にいける年功序列型社会は無くなり、あるのは競争のみとなった。
仮に昇進したとしても、会社自体が倒産したりM&Aで外資に買われたり、リストラにあうといった「事故」の危険性から逃れられるわけではない。
「そういう環境で、ひたすら上を目指して頑張るのは、虚しいものです」と、著者は現代の若者の心理を分析する。
「それよりも、とりあえず身の安全を確保しようという方向に意識が向かうのは、ある意味当然のことなのでしょう。こうして上昇志向が萎え、それが一因となっていた嫉妬の感情も後退しました。先が見えないのでは、出世競争をしても意味がない。そのために嫉妬のエネルギーを費やすだけで無駄、というわけです」
上の世代が持っていたドロドロとした強烈な嫉妬心のエネルギーは、若者にあっては内側に向かう。
自己保身=自己愛へと向かって、その自己愛がこじれる事で歪な自己愛の肥大化につながってしまう。
これが若者世代によく見られる病理の一つなのではないかと著者は考えるのだ。
こういった若者の「歪な自己愛」の好例を著者は柚木麻子の小説『伊藤君AtoZ』の登場人物「伊藤くん」に見る。
伊藤くんの主張はおおむね次のようなものだそうだ。
「傷つくことを恐れるなと言うのは、強者の論理だ。恥をかいたまま起き上がれるのは、限られた特殊な人間だけなのだ。たいていの人間が、夢をかなえないまま死ぬのは、夢と引き換えにしてでも、自分を守りたいから。誰からも下に見られたり、馬鹿にされたり、笑われたりしたくない。傷つける側に立っても、その逆は絶対に嫌なのだ」
伊藤くんは「充実感を得るより、金を稼ぐより、傷つけられないほうが本当は重要なんですよ」とも言う。
フロイト的に言えば、伊藤くんに象徴される若者の心理とは、他人に向けられるべき関心や情動を自分自身に撤収させ、ひたすら自分を守る事に専念するようになったという意味で「歪んだ自己愛」と評価することが出来る。
現代こうした歪んだ自己愛を助長しているのがSNSではないかと著者は見ているらしい。
本書で著者と対談している精神科医の斎藤環氏も、NPO法人「ヒューマニティ」理事長の小早川明子氏も「SNSがこういった歪んだ自己愛を助長しているのではないか?」という著者の意見におおむね賛同している。
SNSはリアルなコミュニケーションではない、あくまで間接的なコミュニケーションでしかない。
だからこそ自己愛が肥大している人物は、一方的に「この子はぼくと心が通じているに違いない」と勘違いするのだし、「自分はこんなにも沢山の人から承認されている!」と勘違いする。
精神科医の斎藤環氏は言う。
「SNSって承認を数量化する仕組みでもありますよね。「いいね!」ボタンが典型ですけど、ネガティブな評価もポジティブに変えてしまう。『こいつアホだからフォローしてやろうぜ』といった悪意のフォローも、『自分を認めてくれた』と誤解できる構図があるわけです」
NPO法人「ヒューマニティ」理事長の小早川明子氏も次の様に指摘する。
「SNSが爆発的に普及して以降、つき合ってもいないのに接近欲求を募らせるケースが、目に見えて増加しています。アイドルのサイトを見に行ったのがきっかけで、ストーカー化した末に事件を起こす、なんていうのは典型です」
こういった若い世代の「自己愛の歪み」とは、新自由主義が縦糸とすれば、SNSが横糸となっていると著者は考えるのである。
そして、その著者が想定する、年代別の組織内メンタリティというのは――今の50歳代以上が「競争原理に晒された嫉妬心が強い世代」であり、30代後半~40代辺りが「自己愛が肥大してこじらせている世代」であり、20代~30代前半辺りが「諦めに入っている世代」といった形でまとめることができそうだ。
◆◆◆
著者の主張としては「歪んだ自己愛」とならないためには「健全な自己愛」をはぐくむ必要があるとしている。
ではこの「健全な自己愛」とは何かというと、キリスト教徒の著者らしい考えを提示している。
キリスト教の「隣人愛」とは単なる利他主義ではない、という事なのだというのだ。
「マタイによる福音書」によると、「隣人を自分のように愛しなさい」とある。
「イエスは、隣人を単に「愛しなさい」と言っているのではなく、「自分のように愛しなさい」と言っていることが重要だ。自分を愛することは、他者を愛することの前提なのである。自分を愛することができない人が、他者を愛することなどできないというのが、キリスト教の愛に対する考え方である。従って、自己愛はとても重要な概念だ。しかし、自己愛を制御することはとても難しい。それは、自己愛が嫉妬と隣り合わせの感情だからだ」
これらの考え方を踏まえて、著者は最後に「嫉妬に対処するための五箇条」と「自己愛に制御するための五箇条」を提示する。
これについて興味がある方は、実際に本書をお読みになったほうが良いだろう。
ぼくからは、最近マイブームのフロイトから学んだ知見からアドヴァイスをすることができそうだ。
フロイトの言う「情動」――無意識から突き上げて来る感情的な動因「エス」を制御する方法は、精神分析的には理性を使うのが有効なのである。人間というのは、生物/動物としてもともと持っている野性的な本能を「理性=自我」によって制御することによって社会に適応できる倫理観を作り上げてきた。
本書の著者も「前に『物事に動じない心は、いろんな知識、教養を身につけることで養われる』と話しました。知識や教養、理性によって感情をマネジメントする事は可能なのです」と言う。
フロイトも、自分の「大きな広場のような空間が怖い」といった恐怖症と戦う際も、理性を働かせて自己分析していたという。
「自己分析」というのは、自分を突き放して、まるで「他人」を見るときのように客観的にその心理を分析してみる事だ。
これは現代の心理学の実証実験でも「有効だ」というデータの出ている立派な自己心理マネジメントの方法でもある。
「嫉妬心」も「自己愛」も、それぞれ必ずしも「悪い感情」というわけではない。これらが「他人の足を引っ張る嫉妬心」となり「歪んだ自己愛」となるからこそ問題なのだ。
ではふり返ってみて「おのれの事」として、改めて周囲を見渡したら、どうなのか。
自分だけでなく、他人や周囲からの嫉妬心にも敏感になる事が重要なのだというのが、本書にあった教訓であった。
本書はそういった現代日本人に漂っているの病理の傾向に気付かせてくれる小さなきっかけとなるだけのアイデアが込められていると考えてみれば、さほど悪くもない一冊だったと言えるかもしれない。
