
◆読書日記.《エラリー・クイーン『ギリシア棺の秘密』》
<2023年3月6日>
エラリー・クイーン『ギリシア棺の秘密』(ハヤカワ・ミステリ文庫版)読了。
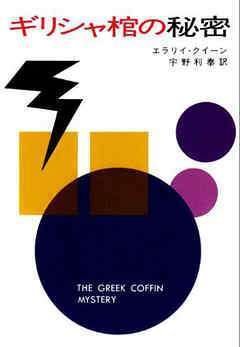
アメリカの20世紀ミステリ文壇を代表する推理作家エラリー・クイーンの有名な「国名シリーズ」のひとつ。
本書はクイーンのミステリの中でも特に分量が多く、内容も多重解解決方式で紆余曲折している。そして、いわゆる「後期クイーン的問題」に関わる作品とも言われている。
ぼくが今回クイーンを読もうと思ったのは、前回ガレス・レン&ロードリ・レン『サイエンス・ファクト 科学的根拠が信頼できない訳』を読んで「ロジック」というものについて考えたくなったからだった。
『サイエンス・ファクト』で提示されていた「科学」という方法論に関する問題は、以前の記事にも書いたように犯罪捜査や刑事裁判にも関わってくる問題だ。
そこで、このテーマをエラリー・クイーンほどロジックにこだわった作家の作品に適用して考えてみるとどうなるだろうか、と思ったのが、本書を手に取るきっかけとなった。
「全ての手がかりは読者の前に提出された」と言って読者へ真相当てを迫る「読者への挑戦状」が付けられているだけに、クイーンの諸作の中でも最も手がかりやロジックといった事にこだわった作品群が「国名シリーズ」であった。
その中でも、ぼくがまだ未読なのはこの『ギリシア棺』と『チャイナ橙』あとは番外編の『ニッポン樫鳥』くらいなものなので、その中で最も分量が多く、読者の評判も良いの『ギリシア棺』に挑戦したという訳であった。
<あらすじ>
ニューヨークで盲目の大富豪ゲオルグ・ハルキスが死去し、葬儀が執り行われたが、葬儀後に遺言書が金庫から消失していることが判明する。リチャード・クイーン警視の指揮するニューヨーク市警が乗り出すが、懸命な捜査にもかかわらず遺言書は見つからない。
クイーン警視の息子で、大学を出たばかりのエラリー・クイーンは捜査に加わり、遺言状のありかはハルキスの棺の中だと主張するが、暴かれたハルキスの棺から発見されたのは、前科者のアルバート・グリムショーの絞殺死体だった。
捜査が行き詰まる中、エラリーは事件が解決したと宣言し、自分の推理を披露する。ハルキスの書斎に残されていた物的証拠と、死亡した日にハルキスが着用していたネクタイの色から、一時的に視力が回復したハルキスがグリムショーを殺害したと結論する。しかし直後、新証言によって推理は根底から覆され、残された証拠が「真犯人による工作」だったことに気づいたエラリーは、誤りを認め推理を最初から立て直す。
※ウィキペディアにはかなり最後のほうまでのストーリーまで書かれているので注意が必要
<感想>
改めて、自分は犯人当てクイズは苦手だなぁと思う。
以前、坂口安吾の記事でも紹介したと思うが、坂口安吾は仲間内での推理小説の真相当てゲームに興じて人一倍熱心に推理し――実によく外れたと言われていた。
彼は考えすぎで、いつも真相をヒネリにヒネって推理し、あさっての方向に結論を持って行ってしまうのだと言われていたが、ぼくもたぶんその傾向がある。
ぼくの場合は、あらゆる可能性を列挙して考えようとしてしまって、その膨大な選択肢の中から妥当な結論を導き出せなくなってしまうという所があるのだ。
たぶん、ぼくが犯罪捜査の指揮を執っていたら、もっと多くの証拠を集めてからでないと結論は導けない、という超慎重派になるんじゃないかと思う。
しかし、実際の犯罪捜査でも、明快に「この人が犯人だろう」という証拠が固まっていなければ、そうそう逮捕に踏み切れるものでもないのではないだろうか。
何しろ、犯罪捜査というものは「逮捕して終わり」ではなく、その先に取り調べやら裁判やらという幾つもの関門が待っているのだから。
捜査員だけが納得する証拠ではなくて、様々な関係者に納得してもらって、最終的に裁判官が納得するだけの証拠がなければ実質的な役には立たないだろう。
だが、推理小説――特に本格推理――の場合はそうもいかない。
あまりにも明確な証拠が揃い過ぎていては簡単すぎてクイズとしての「犯人当て」が成立しないし、かといって、犯人を一人に絞り込めるだけのじゅうぶんな材料が揃っていなくても「犯人当て」は成立しないのである。
情報が揃い過ぎて簡単なクイズになる事なく、かといってクイズが成り立たない程に少ない情報提供にもならないようにする――その間の微妙な分量の「手がかり」を、読者に提供しなければならないのが、犯人当ての難しい所なのだろう。
クイーンの「国名シリーズ」が本格推理史上の傑作シリーズと言われている所以は、その手がかりの提供の仕方が絶妙とさえ言える匙加減だからという事もあるのである。
◆◆◆
しかし、この「手がかり」に関する問題について本作の悩ましい所は、本作の構造が多重構造になっていて、捜査が紆余曲折する点にある。
冒頭にも本作が所謂「後期クイーン的問題」と関わる作品だと紹介した様に、特にクイーンの諸作の中でも本作は、後期クイーン的問題の「第一の問題」に関わってくる問題が現れる作でもあるのだ。
本作では、名探偵役のエラリイが、一度犯人の工作によって「偽の手がかり」に騙されてしまうのである。
第一の問題
「作中で探偵が最終的に提示した解決が、本当に真の解決かどうか作中では証明できないこと」についてである。
つまり“推理小説の中”という閉じられた世界の内側では、どんなに緻密に論理を組み立てたとしても、探偵が唯一の真相を確定することはできない。なぜなら、探偵に与えられた手がかりが完全に揃ったものである、あるいはその中に偽の手がかりが混ざっていないという保証ができない、つまり、「探偵の知らない情報が存在する(かもしれない)ことを探偵は察知できない」からである。
また「偽の手がかり」の問題は、いわゆる「操り(あやつり)」とも結び付く。すなわち、探偵が論理によって「犯人」を突き止めたとしても、その探偵、あるいは名指しされた犯人が、より上位の「犯人」に操られている(上位犯人の想定の中で動いている/動かされている)可能性はつねに存在する。このようにメタ犯人、メタ・メタ犯人、……を想定することで、推理のメタレベルが無限に積み上がっていく(無限階梯化)恐れが生じることがある。
これは「ロジック」や「科学的方法」というものを突き詰めていった末に必然的に突き当たる問題ではなかろうか。
ぼくはそれをガレス・レン&ロードリ・レン『サイエンス・ファクト 科学的根拠が信頼できない訳』を読んでいた時にも感じたし、その他ハイデガーの『存在と時間』やフッサールの『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』を読んでいる時にも同じように感じた問題であった。
思えば20世紀というのは、西洋が信頼を寄せていた「科学的方法」を初めとする様々な学問の「限界」が見えてきた――そういう時代だったのだとしみじみと感じる。
20世紀最大の思想家とも呼ばれたマルティン・ハイデガーは西洋の伝統的思考である形而上学を解体し、古代ギリシアから綿々と受け継がれてきた主知主義を批判してその転覆を試みた。
論理実証主義/科学経験主義の代表者であったアルフレッド・エイヤーは、1972年にテレビでなされたインタビューで論理実証主義の欠陥を「あの運動のほぼすべてが偽であったことだ」とその挫折を決定的に吐露した。
カール・ポパーは「科学は硬い岩盤の上にあるわけではない」と言い、科学が常に批判に対して開かれた「暫定的ドグマ」でしかないと主張した。
こういったポストモダン論的な言説の流れの中の一つとして、推理小説のテーマである後期クイーン的問題も位置付ける事が可能であろう。
しかしながら、そういう後期クイーン的問題に関わるテクストの代表の一つとして挙げられる本作『ギリシア棺の秘密』では、クイーンはどうも「科学的方法」についての信頼を失っている様子はないのである。
それは、本作の第一部と第二部の冒頭に、科学者による「科学的思考」を肯定する内容の文章を引用している事からも伺える。
「諸君の目を用いよ。神に授かった小さな灰色の脳細胞を用いよ。だが、そのさい心すべきは、犯罪行為にパターンはあるが、ロジックがないことを思え。混乱に筋を通し、無秩序を秩序に導くのが、学徒たる諸君の任務であるのを忘れるな。
――フローレンツ・バッハマン教授、ミュンヘン大学
『応用犯罪学』講座の最終講演(一九二〇年)」
「いかなる犯罪現象も解明不能ではない。根気と単純な論理操作こそ、犯罪捜査の核心的な必須要件である。思考をないがしろにする者には謎であるにしても、計量する研究者には自明の真実といえた……犯罪捜査はもはや、水晶球を前にした中世の占い師のたわごとでなく、近代科学のもっとも精緻な一部門なのだ。そしてその根底には、峻厳ながら単純な論理が横たわっている。
――ジョージ・ヒンチクリッフ博士著
『近代科学の傍流』(一四七~八ページ)」
これらの文章を本作のそれぞれのパートの冒頭に掲げている事からも伺わせるし、本作を通読しても分かるように、この時期のクイーンはまだ「後期クイーン的問題」のような科学的方法論に対する問題を提示しているようには到底思えない。
科学やロジックに対する信頼感を失っているようにも思えないのである。
確かに、本作で"読み取れる"問題には興味深いものがある。
探偵役は、犯人が配置した「偽の手がかり」と「本物の手がかり」を見分ける事ができるのか。
そもそも、本物の証拠と偽証拠とを分ける違いをどう判断するのか?
――このように「偽の手がかりに騙される探偵」という興味深い状況を扱っていながらも、本作は「後期クイーン的問題」に見られるような問題にはじゅうぶん意識的に扱われてはいない。「ロジックの正当性」等といったポストモダン的な問題については、本作はほぼ無自覚なのである。
本作での結論はけっきょく、本物の証拠と偽証拠は、ちゃんとしたロジックを辿って行けば見分ける事ができるだろう――という事にしかなっていないからだ。
ここで見られる典型的な誤謬は「論理的に推論を進めていけば、解答は一つに絞られてゆくものである」というものである。
これは笠井潔が長編ミステリ『バイバイ、エンジェル』で指摘していた事でもある。
探偵役の矢吹駆が「僕は探偵の推論がなにも唯一の論理的筋道を辿っているわけではないことを指摘した。探偵の推論と論理的には同等の権利をもつ他の無数の解釈が存在しうることを指摘した」と語るように。
「観察された事実を論理的に配列すれば唯一の道を辿って確実に真実に到達することができるという近代人の確信は、たとえばこんな挿話のなかにも簡潔に示されている。
……部屋のなかで男が死んでいる。妙なのは、被害者が扉に近い場所で襲撃されたのにもかかわらず、おそらく犯人の逃走の後に部屋の中央まで這っていって、テーブルの上の砂糖壺をひっくり返したうえ、その砂糖を固く握りしめて死んでいたという事実だった。探偵はまず、握りしめられた砂糖は、ただ犯人を指示する一種の記号(シーニュ)であると考える。しかし、これがたんなる独断に過ぎないのはあまりにも明らかだ。砂糖を握っていたという事実のなかには、権利上同等な無数の意味(シニフィカシオン)が含まれている。たとえば、被害者が甘党だったので死ぬ前に一度砂糖の甘い味覚を楽しみたかったのかもしれない。たとえば、被害者が雪国の生まれで、死の幻想が彼に砂糖の輝くような白と新雪の汚れない白を結びつけさせ、彼に砂糖を握りしめさせたのかもしれない。けれども探偵は、読者にたいしてどんな根拠を示すことなく、握られた砂糖の多義的な意味を一方的に限定し、それが犯人を支持する記号であることを断定する……」
「観察された事実を論理的に配列」すれば、「唯一の道」が出来上がるという「近代人の確信」は誤謬なのである。
このような誤謬が「偽の手がかり」という状況のすぐ真下に広がっているというのにも関わらず、本作『ギリシア棺の秘密』ではそのような問題意識は表面上、ほぼ現れていない。
ここで指摘されている問題は、「観察された事実を論理的に配列」する方法というものは、権利上同等の道筋が無数に存在しており、その中から「唯一正しい道」を選択する方法というのがそもそも不可能なのだという事である。
自分は今回、本作をガレス・レン&ロードリ・レン『サイエンス・ファクト 科学的根拠が信頼できない訳』で指摘されていた「科学的方法の問題点」を踏まえた上で読んだために、エラリイの推理について、それが「正しい唯一の道」であると主張する理屈に幾度も首をかしげてしまった。
例えば、本作の真犯人はある犯行について共犯者を利用したかどうかという重要な部分の判断について――探偵役のエラリイによる「*********したのに、*******(※ネタバレになるので伏字)共犯者を求めるとは、あまりに知恵の無さすぎる方法です。ぼくは犯人の自信にみちた思考力を考慮に入れて、偽せの手掛かりを作為したのは犯人自身と断定するのに迷いませんでしたね(P.491)」として、犯人がその犯行については共犯を利用しなかったと結論付けている。
ここでは本作で発生した事件を解決するには必要不可欠な「判断」がなされているのだが、この部分は他に比べて証拠とすべき点が少なく、どうにも説得力が乏しいと思えてしまう。
ここでエラリイが証拠としている「犯人の行動パターン」については、例えば単に「犯人の気紛れで共犯を選んだけだった」という事になれば簡単に否定されてしまうからだ。
人間の気紛れによる行動はロジックでは捉えきれない。人間と言うものはしばしば矛盾した行動をするものだし、説明のつかない行動もする。
本作でもP.352で、登場人物の一人が不可解な行動をした事の理由を知ったエラリイが「なるほど、これが殺人捜査の実態なんだな。まあ、いいさ。精神病理学が、気紛れ動機のすべてを究明するまでは、犯罪捜査学も科学の名に値しない幼稚なものだ」と言っている通りだ。
人間の一見矛盾した行動も、何かしら無意識に根差した原因があるのかもしれないが、それを全て究明しつくす事など現代科学には不可能なのである。
このように「同等の権利をもつ他の無数の解釈が存在しうる」中で、エラリイの選んだ「犯人の単独犯説」が真実を得ているとどうして言えるのか? 彼はその説が「最も妥当だろう」と「判断」しただけの事であった。
「観察された事実を論理的に配列すれば唯一の道を辿って確実に真実に到達することができるという近代人の確信」は、けっきょくはその「論理的に配列」する人間の「判断」に依存してしまう。
では、その「判断」の正しさは、どう保証されるのか?――保証される事はないのである。
『バイバイ、エンジェル』では、フィクションとしての名探偵は、解決に至る「判断」を「本質直観」によって選択しているのだというように説明しているのだが、――これは現実の犯罪捜査には当てはまる事ではないし、その説明は現実の「科学的方法」を擁護するものではない。
「観察された事実を論理的に配列すれば唯一の道を辿って確実に真実に到達することができるという近代人の確信」を擁護し祝福する者としての「名探偵」という装置が置かれた――それが近代に至って生まれた、科学的方法を祝福する「本格推理」という文芸ジャンルだったとも言えるのだろう。
だが、その科学的方法に関する限界が見え始め、名探偵の主張するロジックの正当性/万能性と、現実の犯罪捜査とのギャップが明らかになってきたからこそ、本格推理というジャンルもデッドロックに乗り上げてしまった。
現実の犯罪捜査に即した推理とするには、推理小説に出てくる名探偵の推理はあまりに現実離れして「科学的思考法」を高く評価しすぎてしまっていたのである。(だから、という事もあろう。現在よく見かけるラノベ系本格ミステリに登場する名探偵の行う推理はしばしば「超能力」と区別がつかないものになってしまっている。)
やはりポストモダニズムの問題と本格推理の衰退とは無関係ではなかったのだろう。「科学的方法論」を突き詰めていった結果として、推理小説の限界が見えたのも必然的な結果だったのかもしれない。
しかし、本作『ギリシア棺の秘密』は、まだまだ科学的方法に対する無邪気な信頼の揺り籠の中からクイーンが出てきていない、「論理」にとって幸福な時期の作品であって、後期クイーン的問題やポストモダニズムといった問題にまで踏み込んでいるものではない。
本作に於けるクイーンは、本作の第二部に引用されている「いかなる犯罪現象も解明不能ではない。根気と単純な論理操作こそ、犯罪捜査の核心的な必須要件である」というスタンスから一歩も外に出ていない――と、ぼくはそう考えるのである。
◆◆◆
名探偵が推理小説で行っているのは、決して犯人が特定の人物であるという事を「証明」しているわけではない。
真実を解き明かす――という推理小説に託された夢は、現実の科学的方法論の限界によって挫折した。
科学はポパーの主張するように、常に批判に対して開かれた暫定的なドグマでしかない。「真実」を「証明」する事などは永遠に不可能である。
では、推理小説の名探偵が「実際に」やっている事とは、いったい何なのだろう?
ぼくは、名探偵の本当の役割というものは「推理する事」ではなくて、畢竟「人を説得する事」なのではないかと思うのである。
これは、前回読んだガレス・レン&ロードリ・レン『サイエンス・ファクト 科学的根拠が信頼できない訳』で学んだ内容にも絡んでくる事でもある。
科学者も自分の実験によって得られた結論を以てして「真実だ」等と考えている人間はいない。
科学者らがやっている事の意義は、自分たちが行って得られた実験の成果が、暫定的ドグマであったとしても間違いであったとしても、自分の活動の成果を発表して、少しでも科学の知見を前に進める事にある。
実験によって得られた成果が間違いであったとしても「その道はかつて試みて失敗したケースがある」という教訓となり知見になる。
このように科学の知見を前に進めるためには、科学者らが行ってきた研究の成果を、広く科学者たちに知らしめ共有させなければならない。研究成果を他人の目に触れさせ、厳しく吟味され審査され、それを今後の科学発展の礎の一つとさせるには、まずそれが「論文」という体裁として整えられ、発表されなければならない。
「<自分のアイデアと実験の厳密性>に確信をもったとき、科学者は何かしら書き始める。ただし、自らの意図が伝わるように書けるまでは破棄し続けることになる。自らの目で批判的に見直して、「まともなものが書けている」と自信がもてて初めて、同僚に草稿を見せたり、専門部会での講演や会議で議論したりすることになる。そのときに寄せられたコメントや関心の度合いなどに応じて、下書きを修正していく。わかりやすくて影響力の強い、記憶に残る文章になるよう推敲を重ねるのだ」
ガレス・レン&ロードリ・レンが『サイエンス・ファクト』で説明している事によれば、通常科学者は論文を発表しなければ科学者とは言われない。そもそも、論文が発表されなければ「科学者」と認知されないからだ。
自分の研究成果がいくら重要な発見であっとしても、論文が多くの人間に読まれなければ意味がない。その知見が他の科学者の間で吟味検討され発展していく事がないだけでなく、その後その知識が一般化されて活用される事も利用される事も無いから、他人に知られない科学は実際的に何の意味も持たない。
では、書かれた論文が、より多くの人に読まれるにはどうしなければならないのか?その論文を「説得力のあるもの」にしなければならない。
だから、科学者の仕事である「論文執筆」の重要な役割というものは、畢竟「説得」なのである。
研究や実験は重要な事だ。だが、それは真実へ至る唯一の道ではないし、間違いもあれば有害な誤謬を含んでいる事さえある。
だが、それもこれも、研究によって分かった事が発表され、他人に知られなければそれは「実際の科学」には何の貢献もしないのである。
ぼくは、『サイエンス・ファクト』でこのくだりを読んだとき、科学的な捜査法を用いる推理小説の名探偵も、やっている事はだいたい同じなのでは?と思ったのである。
名探偵が行っている仕事も、けっきょくは自らの捜査の結論としての「推理」を発表し、それで関係者を説得する事ではないのか。
何故なら、名探偵の「成果」は推理をする事でなされるのではない、事件を解決する事でなされるのだから。
彼の仕事は、事件の関係者を説得し、捜査関係者を説得し、そして何よりも犯罪を犯した真犯人を説得し、最終的に裁判所を説得する材料に繋がる事で完了する。
探偵が「ロジック」を用いるのは、それが「真実」に至る唯一の道だからではなく、けっきょくそれが最も説得力があるからだ。推理小説におけるロジックの重要性は、そこにこそある。
そして、科学におけるロジックの役割も、それに近いもののように思えるのだ。(無論、その前にちゃんとした研究や実験などが重要である事は大前提だ)
推理小説で犯人が逮捕されるには、警察が名探偵の推理に納得するか、犯人が直接名探偵の説得によって納得し、観念するかにかかっているのではないか。
そして、クイーンの「国名シリーズ」が真に優れているのは、それが最も読者を納得させる説得力に満ちた、魅力的なロジックを持っているから、という事なのではないかと思うのである。
