
◆読書日記.《ジグムント・フロイト『幻想の未来/文化への不満』》
※本稿は某SNSに2020年4月14~16日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
ジグムント・フロイト『幻想の未来/文化への不満』読了。
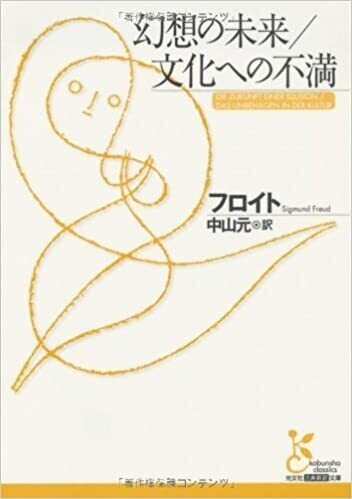
フロイト晩年の壮大な文明論であり宗教論でもある「幻想の未来」「文化への不満」「モーセと一神教(抄)」の3つの論文をまとめた論文集。
いやー、あまりにその思想の射程距離がデカくて壮大なまでに展開して行っているのに圧倒された。
◆◆◆
フロイトはユダヤ人であるにもかかわらずユダヤ教には入信せず学問の道に進み、啓蒙主義の精神で以て迷妄を正そうという意識がけっこう強かったようで、そのために晩年はしばしば宗教を批判する文章を書いていたのだそうだ。それが本書に掲載されている論文となっている。
フロイトはどうも宗教は文明の発展と共に失われていくべきじゃないかと思っていたようなのである。
これはフロイトらしく、人類の精神の発展は、個人の精神の発展段階と同じように「理知によって本能的な幻想を抑圧していく」と捉えていた。
論文「幻想の未来」で言及される「幻想」というのは「宗教」の事を指している。つまりこの論文は「宗教の未来はどうなっていくのか」という事について言及した論文なのだ。
まずフロイトは、人類が宗教を生み出すようになったその心理学的な必然性を、発展史的に分析している。
何故神は生まれたか?
「幼児の頃の寄る辺なさの恐ろしい記憶のために、庇護の欲求が、すなわち愛による庇護の欲求が生まれ、その求めに父親が応じたのだった。そしてこの寄る辺なさが一生を通じてつづくものであることが認識されるようになると、もう一人の父、もっと強い父なる神の存在にすがるようになったのである」――ジグムント・フロイト「幻想の未来」より
この論文でフロイトは、まだ理知よりも本能的な欲求の優っていた段階の古代人が、現代人となるまでの歴史の中で精神的に成長していく過程を、生まれたばかりで本能的な欲求の優っている幼児が、段々と本能を抑圧して理性を備えていく発展プロセスとパラレルの関係だ想定として説明しているのである。
幼児は自分だけでは生きて行かれない寄る辺ない存在であり、そう言った幼児は当初、父親を恐れるべき存在と捉えるが、やがてこの父からの庇護を受ける事で周囲の危険から守られる。
フロイトは、古代人がこの幼児期に経験した「恐怖を和らげるプロセス」を、自分たちを脅かす周囲の自然に対して適用すると説明する。
圧倒的な優位性を持って我々を脅かすものでもあるが、時々はその恩恵を貰う事もできるこの「自然」という不可解なものを、古代人は「擬人化」する事でその恐怖を和らげようとする。
フレイザー卿が多くの古代人らの宗教に存在していたと指摘する「自然神」という「人格」を、古代人は周囲の自然に与えたのである。
フロイトによれば、古代人は自然神を「父親」という人格として捉える事で、幼児期に経験したのと同様の安心感を得ようとするという。
しかし、古代人が段々と文明を発展させていき、理知を働かせられるまで精神と科学知識が発展してくると、自然の規則性と合法則性が理解されるようになってくる。
そう言った形で科学的理知的精神の発展によって「恐怖と憧憬の対象である自然」の価値が下がる。
その代わり相対的に人間中心主義的な「神の父親としての人格」のほうの価値が上がるようになる。かくて宗教から「自然なる神」の要素が後退し、「父なる神」の要素が強調されるようになっていく。
この「神々を創造、発展させていく宗教史」の観点から言えば、神というのは元々は人間の「庇護欲」の願望を充足させるために発明された「社会的な代理父」だ、というのがフロイトの考え方なのである。
だが、精神分析的には人間の欲動は子供から大人になるに従って「父」への欲動を他者へと移行させていかずに、ずっと「父」に固着させてしまうと、それが「神経症」という形で表出する事になってしまう。
人類の欲動もそれと同じく「父なる神」に社会心理的な欲動を固着させてしまうのは良くない。
フロイトはこの根拠の一つとして強迫神経症患者が、内実の伴わない様々な儀礼的な行為を繰り返さないと激しい不安に襲われるという症状を上げて、この症状の宗教儀礼との共通性を指摘した。宗教は「神」という共同幻想に欲動を固着させた集団神経症なのだ、と。
「神経症は個人的な宗教性であり、宗教は普遍的な強迫神経症」だとフロイトは考えるのである。
「人が宗教を信じなければ、道徳を信じずに犯罪を犯したり社会規範を守らない人間が増えてしまうに違いない」と考える者もいるだろう。
だが、人間は宗教がなくとも倫理を守るだけの精神的発展を遂げている。
それが倫理的規範を守らない個人の自我の活動を監視する審級である「超自我」の働きであり、社会的に言えば「超自我」的な働きをする「法律」等の社会的ルールである。
現代人にはこれら宗教に代わる倫理規定がしっかりと整備されている。
これは、宗教のみに頼る必然性が現代人にあるのだろうか?というフロイトの問題提起なのだ。
勿論、心理学的にも「救い」や「癒し」を求める人々の助けとなる場合もあろうが、社会全体が宗教的なものに依存して寄りかかってばかりいては、人類の精神史的な発展にはならないというのがフロイトの宗教批判となるのである。
では、具体的にはどうすればいいのか?
フロイトの執筆当時(20世紀初頭)に支配的だった学校の宗教教育を捨てさせ、理性と科学を中心とした学校教育に変えていくべきだ。社会公共的な部分から「宗教的なものが必須」となる状況から離れていくべきだ。――と、そうフロイトは考えたのである。
勿論、宗教を失くしてしまえ、という話ではなくフロイトは「宗教を学ぶのは必須なのだ」「人類全員に宗教は必要なものなのである」「宗教がなければ道徳はなりたたない」という"状況"を批判していたのだ。
必要な人には信仰があればよい。だか、それは必須のものではなくて、もっと理性的なものを重視していくべきだ。
そうやって、段々と宗教中心主義的な体制を縮小していくのが良かろう、と思っていたのが、フロイトの想定する「幻想(=宗教)の未来」像だったのである。
こういうのを読むと、さすがにフロイトの精神分析は、科学的視点に立脚しているためか随分と柔軟な思想だったんだなと思わされる。
◆◆◆
「幻想の未来」の三年後に書かれたのが「文化への不満」である。
フロイトは「幻想の未来」執筆の時点で既に上顎に癌を発症していて、何年もその痛みに耐えながらも規則正しく診察室に立ち続け、規則正しく時間通りに執筆を行った。
そういう背景もあってか、この論文には論旨を大きく外れて「人生とは?」や「人間にとって幸福とは?不幸とは?」「死とは?」「良心とは?」等のテーマにまで言及している部分がある。
この頃のドイツはナチスがユダヤ人迫害を強めており、フロイトにとっても、癌だけではなく常に死と隣り合わせで生きていたと言って良いだろう。
本論文に出て来る「文化」とは、フロイトの定義によれば「人間の生を動物的な条件から抜け出させる全てのものであり、動物の生との違いを作り出す者の事である。だから私は文化を文明と区別しないつもりである」とあるようにかなり緩い定義づけを行っていて、或いは「文明」と思って読んだほうが早いかもしれない。
人類の歴史とは、動物と違う人間だけの「文化=文明」を発展させてきた歴史だと言えるだろう。では人間は、文明をどのように発展させていったのか。
フロイト的なテーゼでは「幻想の未来」でも書いていたように、人類全体の精神の発展は、個人が子供から大人になるまでの精神の発達プロセスとパラレルの関係にある、という条件がある。
つまり、人類は動物的な本能の欲求を全開にして生きてきた原始人の段階から、徐々に「理性」を獲得し、「理性」を獲得するに従って野放図にしていた動物的本能を抑圧していくようになる。文明の特徴の一つは「人間の持っている欲求を抑制させる事で発展してきた」というのがフロイトの主張としてあるのだ。
そして、文明と同じく、人間の個人個人の精神の発展プロセスも同様なのである。
人は、幼児の頃に持っていた動物的な野放図な欲求を、両親のしつけによって手放さなければならなかったのだ。何故か? 人は独りだけでは寄る辺のない、弱い存在だ。だが、人類は集団となって力を合わせる事で猛獣も撃退し、災害から身を守り、生き延びる力を得てきた。
人間たちは、自分たち同じ種族がそれぞれの欲望に従って殺し合ったり奪い合ったりすると、集団として纏まる事もできず、集団としての強い力を発揮することが出来なくなる。
では人間が「集団」となるには、どうすればよいのか?「自分一人が良ければいい」というエゴを抑制して、協力しあわなければならない。そうしなければ、自然の脅威に立ち向かう事ができなかった。
つまり、人は「集団」としての力を発揮するために、個人個人に「嫌な奴は殺してやる」という攻撃欲求=タナトスを抑え、「食いたい時に食う、ヤりたい時にセックスする」という自分一人だけの欲求も抑えて、集団のルールに従うように要求させられた。
人間は「動物と同じ」時代から、「人間的なもの=文化・文明」を手に入れるために、個人が持っていた欲求を抑圧しなければならなかった。
それが人間が集団的な力を手にする条件であり、現在の文明を発展させるための条件だった。
――この事実を踏まえて、フロイトは「人間の苦悩が発生する三つの源泉」を指摘する。
「1.自然の圧倒的な威力、2.人間の身体の脆さ、3.家族/国家/社会における他者との関係を規制する様々な制度の不十分さ」
これが、人間の苦悩の源泉となるという。
人間はこの苦悩の内「1」と「2」については、文明を発展させていく事でこの苦悩を和らげていく事に成功していった。
だが、こと「3」については、文明が発展すればするほど抉れたり抑圧が強くなったりする。
人間が「社会的生き物」になるためには、人間に元々備わっていた「快感原則」を抑圧し「現実原則」に従わなければならない。
人間は「現実原則」のみでは充足しないので、人が幸福になる条件というのは難しいのだ。これがある種の「文化への不満」となる。
「このように人間が幸福になる可能性というものは、私達の心的な構成のために制約を受けているのだ。所が不幸を経験するのは、はるかにたやすい事なのである」
――ジグムント・フロイト「文化への不満」より
人は快感原則を抑圧しすぎると、それが神経症という形で症状化してしまう。この欲求はどうやって充足すればよいのか?
人類は文明を発展させていく段階で、行き場のないエロスやタナトス等の直接的な動物的欲求を「昇華」という形で充足する事を覚えた。
社会のルールに従って禁欲せねばならなくなり、行き場を失った欲動を、別の方法を持ってして充足させるのである。
その欲動の行き先が芸術であったりスポーツであったり……という各種娯楽や芸術の発展に寄与してきたのだ。
個人の野放図な動物的本能は放っておくと「集団」にとっては危険なのである。
特に破壊衝動であるタナトスをコントロールするのは難しくて、社会の中では犯罪、暴力、差別等々によって解消させられる、つまり「集団の禁を犯す」形で噴出する。果ては戦争や各種紛争といった形で噴出することもある。
フロイトは自我を「エロスと破壊欲動または死の欲動のあいだの永遠の闘い」だと表現した。
フロイトにとって「エロス」とは、他者とのつながりを結んでいたいという「集団形成」に都合の良い欲求である。
よって、文明とはフロイト的に言えば「他者と繋がるエロス的な欲求を保護/抑制しながらも、破壊欲求であるタナトスを安全な方法で昇華させるために「集団」が作ってきたルール」の発展史であり、この「エロスとタナトスの間の永遠の闘い」は、現代もなお継続させていたかなければならない難問なのだと言って良いだろう。
◆◆◆
ぼくは「文化への不満」におけるフロイトの主張「良心は攻撃的な性格をそなえているが、それは外部の権威の攻撃性を引き継いだものだからだ」という考え方に、久々に新鮮な驚きを感じている。
それだけじゃないでしょ?とは思う。だが、面白い見方だし、一定の説得力もあるので、詳しく考えてみたい命題だ。
フロイトはこの論文で「処罰の欲求」とか「自己処罰の欲求」という言葉をしばしば出している。この「処罰欲」という考え方も興味深い。
「処罰の欲求」が外に向かえば安易に正義を振りかざして他人を批判するタイプになるだろうし、逆に内側に向かえば「罪悪感」によって自分を責めてばかりのタイプになるのではなかろうか。
フロイトは次のように良心のシステムを説明している。
「不運のため、すなわち外部の原因のために欲動の充足が拒まれると、超自我における良心の力が強くなるのである。すべてが順調に進んでいる場合には、良心の声も穏やかなものであり、自我に何でも許そうとする。しかし不幸が人間を襲うと、人は自らを反省して、自分の罪深さを認めるようになる。こうして良心の要求は強くなり、禁欲を課して、贖罪で自分を罰するようになるのである」
――ジグムント・フロイト「文化への不満」より
良心から出て来る「罪の意識」とは、精神分析的に言えば超自我が自我の審級として「快感原則」によって自らの倫理観から逸脱してしまう心を抑制する働きから発生するものと言われている。
これをエロスとタナトスの流れの観点で説明すれば、人は自分に不幸な事が起こると「タナトス」の欲動が発生するものと考えられる。
「タナトス」とは「生の欲動=エロス」と逆の立場の欲動で、つまりは「死の欲動」であり破壊衝動や攻撃欲のようなものである。
フロイトによれば「充足が放棄された攻撃のエネルギーは全て超自我が受け継ぐ事になり(自我に対する)超自我の攻撃が始まる」と説明する。
この「攻撃エネルギー=タナトス」が自我=内側に向かって流れる事で「自分が悪いからこんな事が起きたんだ」と自分を責めるようになる。これが「罪の意識」となる。
逆にタナトスが外側に向かって流れると「〇〇のせいに違いない」「私が不幸なのは〇〇が××したせいに違いない」と他人に対する「義憤」に駆られる事となるのではなかろうか。
このタナトスが外側に流れ易いタイプが誰のせいでもない天災にあうと、欲動は行き場を失って「どうにもやりきれない」という心理となる。
つまり「他人が許せない人」というのは、タナトスの欲動を外に向ける傾向にある人に多いのではないだろうか。
このタナトスの欲動は、行き場を失えば「ガス抜き」したがって様々な「悪人」を探してバッシングするようになる。
要は最近もちらほらと話題に上がった「他人を激しくバッシングする正義マン」というのが誕生する事となる。
逆に、タナトスが内側に向かう傾向のある人に多いのは、不幸が重なった原因を自分の責任に帰してしまう傾向になり易いのではないかと思われる。
タナトス的な欲動を内側に向けるという事は、逆にエロス的な欲動を抑制する事に繋がって来る。攻撃欲は治まるが、今度はエロス的な欲求が抑圧されることとなる。
「エロス的な欲動の充足を抑えて抑圧しなければならなくなる」という事態はフロイトが「神経症の原因」の典型的なものとしてみなしている状態だ。
つまりこれが現代では「鬱病」という症状として顕在化しているのではないかと思う。(以上、あくまでぼくなりの理解なのだが)
……で、ここまで書いていて気づいたのは、フロイトがここで言っている「良心」というのは、どちらかと言えば「倫理観」のニュアンスに近いかもしれない、という事だ。
フロイトのテーゼを「倫理観は攻撃的な性格をそなえている」という命題に読み替えれば、少しだけぼくの感覚に近づいてくる。
◆◆◆
ところで、皆さんはフロイトの最期は「安楽死」だったのをご存知だっただろうか?
彼は67歳の時に上顎に癌を発症させ、83歳で亡くなるまでこの癌と付き合いながら生きてきた。
フロイトは、鎮痛剤を飲むと集中力が落ちて執筆の仕事が出来ないからと言って、鎮痛剤も飲まずに痛みに耐えながら執筆していた。
更に晩年はナチス政権に追われ、82歳の時にドイツからイギリスに渡ってさえも、執筆は相変わらず続けていた。
彼は癌の進行のために疲弊が酷くなって遂にショーアという医師に自分の意向を伝えたという。
「私は貴方が不必要に私を苦しめる事は無かろうと信じていますよ」と、フロイトは告げた。
フロイトはショーアの三度にわたるモルヒネ注射によって安らかに息を引き取った。
これはどこか無宗教で無神論者だったフロイトらしいと思わされる。自らの判断によって自らの死も決めたかったのかもしれない。
感情ではなく、「理性」によって物事を判断すべきだ、というフロイト的な意識を感じてしまうのである。
「人間が幸福になる可能性というものは、私達の心的な構成のために制約を受けているのだ。所が不幸を経験するのは、はるかにたやすい事なのである」
――ジグムント・フロイト「文化への不満」より
――この言葉からも、フロイトは人間が幸福になるというのは非情に難しい事なのだと考えていたのではないかと思ってしまうのだ。
フロイト晩年の論考「文化への不満」で、この論文の論旨とは大きく外れて「人の幸福とは何なのか?」というテーマについて論じているのを読むと、この論文を書いていた当時のフロイトの状況が思いやられて悲しい気持ちになってしまう。
フロイトは「私の死」という人生最大の事態を前にして、必死に理性を使ってこの「不幸」について考え、理性によって自分を抑えていたのだろうと思うのだ。
