
◆読書日記.《山田風太郎『修羅維新牢』》
<2023年1月23日>
山田風太郎『修羅維新牢』読了。
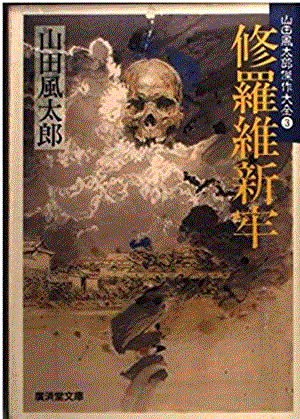
山田風太郎による連鎖短編方式で描く長編幕末小説。
新年からなかなかいい作品を読んだ。去年はハズレを引く事が多かったので、これは新年から縁起がいい。
幕末、江戸城が官軍に明け渡された激動の時期に人生を翻弄された人間たちのドラマ。本作は山風の死生観が色濃く反映された「死の哲学」であった。
<あらすじ>
慶応4年(明治元年)、江戸城は官軍に明け渡された。
官軍兵は我が物顔で江戸中を闊歩し、中には市民に乱暴狼藉を働く者も出てきていた。
だが、庶民も武士も彼らには逆らえず、江戸は混乱の渦の中にあった。
そんな中、何者かが官軍の兵士を惨殺し、鼻を削ぐという事件が続発する。既に二十人以上もの兵士が犠牲になっていたにもかかわらず、下手人はあがらない。
更には薩摩軍の中でもある程度身分のある人物を含む3名が晒首になるという事件が起こり、遂に薩摩軍の東海道先鋒隊長・中村半次郎(のちの桐野利秋)は激怒した。
「薩摩兵が暗殺されたら一人につき、罪なき旗本十人を斬る!」
中村半次郎の命に従い、官軍兵はたまたま目についた旗本侍を片っ端から十人捕まえて牢屋に閉じ込めた。
――これは何の脈絡もなく、何の理由もなく突然死の運命を宣告された侍10名の人生を描いた物語である。
<感想>
本作は山田風太郎お得意の「連鎖短編方式の長編小説」である。
このタイプの作品の形式というのは、世界観は同一の短編を連ねた連作短編集なのだが、各短編に張られた伏線が最後の短編で全て一つに繋がってラストで数珠繋ぎのように一つの話にまとまるというタイプである。
これは山田風太郎が、自分は長編を書きたいのに依頼が来るのは短編小説なので、苦肉の策として思いついたのがこの方式だったと記憶している。つまり、それぞれ独立した短編小説として楽しむ事も可能だが、全部通して読むと長編作品になる、という形式である。
山田風太郎はこの形式で幾つもの名作・傑作を生みだしている。『明治断頭台』『棺の中の悦楽』『妖異金瓶梅』『誰にも出来る殺人』等々。
本書もこの形式を採っているのだが、『誰にも出来る殺人』や『明治断頭台』のようなミステリではない。
かといって『棺の中の悦楽』のように派手などんでん返しを仕掛けているわけでもないし、『白波五人帖』のようなアクションシーンがあるわけでもない。
まず冒頭の一編として<あらすじ>に書かれたくだりが説明されると、次の一編は「一人目」と題してその当時江戸で生活していた一人の旗本侍の人生が描かれる。
次いで「二人目」、「三人目」……といった形で、一人一人の侍の人生が描写されていく。
各短編の結末では、全てその侍が突然、何の脈絡もなく官軍兵に捕まる事で終える、というパターンが貫かれる。
そして「十人目」の旗本が捕らえられると、最後の短編として官軍の屯所で旗本が捕らえている牢獄の中と、屯所の外で、いったいどんなドラマが展開していたのか……という事が描かれて幕が閉じる事となる。
以上の様に、本書は山田風太郎作品の中でも珍しく派手などんでん返しや奇想やアクションシーンといった分かり易いエンタテイメント要素は抑え気味に、それよりも著者の死生観を前面に出した内容となっているのである。
ここに描かれる幕末の侍の人間模様と言うものは、たいそう滑稽でもあり、たいそう悲惨なものでもある。
当人からしてみれば大真面目に自分だけの代えがたい人生を懸命に生きているのだろうが、それを「神の視点」である三人称視点で俯瞰して見ると、表ではすまし顔をしながらも裏では見るに堪えない醜態をさらしていたりするものだ(山田風太郎はしばしば、人間のそういう面を暴き出すのを好んだものだった)。
本書の本筋である「突然の死の宣告」というものは、そういった人間の裏面をさらけ出してしまうものなのかもしれない。
山田風太郎の作品の三人称視点は、彼特有の他人を突き放したような淡々とした書き方が、こういう重苦しい内容にドライな悲喜劇の味わいを帯びさせるのである。
彼はこの大地震(※安政の大地震)で、おびただしい人間が虫ケラみたいに死んでゆくのを見た。いい人間、尊敬すべき人間が、この世の地獄の中にのたうちまわって死ぬのをまざまざと見た。
人間は、その値打ちとは全然無関係な死にかたをするものだ。
と、彼は考えた。
それどころか、気のせいか、悪いやつ、ろくでもないやつ、醜悪なやつばかりがつつがなく生き残った気がする。
ぼくは本書を読みながら、山田風太郎の晩年の奇書『人間臨終図鑑』を思い浮かべた。これも、実在した人物の死に際のドラマを、非常に乾いた筆致で描いたものだった。

「人間は、その値打ちとは全然無関係な死にかたをするものだ」とは、まさに『人間臨終図鑑』に掲載されている死に関するエピグラムそのものといった感がある。
もしかしたら、本作は山風が小説の形式で、フィクションとして『人間臨終図鑑』的なものを書きたかったという事なのかもしれない。
◆◆◆
本書は著者の「死」に関する考え方が色濃く反映された作品だが、それだけでなく著者の「人間論」であり「日本人論」ともなっているのが面白い。
本書では冒頭で、この幕末の時期と、第二次世界大戦で日本が敗戦を迎えた時期との状況が比較されている。ちょっと長いが以下に引用してみよう。
このとき(※明治元年、江戸に官軍が入ってきた時)のさまざまの記録を見ると、七十七年後の米軍の東京進駐当時の政府や軍人や市民の様相とあまりに似ているので驚く。
いや、驚くには当たらないかも知れない。人間というものは、相似た外部的条件には相似た反応を示すのがあたりまえで、そもそも太平洋戦争で、日本が果たして降伏するか、という懐疑を抱いたアメリカが、明治元年のこの歴史を調べて、その可能性のあることに確信を持ったといわれているほどである。
三月六日、東海道鎮撫大総督は通告した。
「江戸城を明け渡すこと。兵器軍艦一切相渡すこと。将軍の暴挙を助けた面々は厳重に取り調べ、断罪すること。
玉石倶に砕く意志はないが、もし抵抗する者があって手に余れば、力をもって断乎鎮圧する」
あたかもこれはポツダムからの連合国の左の意味の通告にひとしい。
「日本国内の諸地点は占領される。日本国軍隊は完全に武装を解除される。一切の戦争犯罪人に対しては厳重に処罰を加える。
日本国民を奴隷化しようという意図はないが、右以外の日本国の選択は、迅速かつ完全な滅亡のみである」
これに対して幕臣有志は哀訴した。
「神祖の基地たる江戸城、皇国守衛の根本である兵器、関八州及び駿遠参の保持、この三か条のみは格外無比の恩典をもってお許し相成りたい」
これが、昭和二十年八月の陸軍少壮将校たちの阿南陸相に対する涙ながらの主張と何とまあ同じであることか。
「天皇制護持、国軍みずからによる武装解除、日本本土と朝鮮台湾の保持、この三条件が容認されないならば、ポツダム宣言を拒否されたい」
阿南といえば――官軍が進駐を開始した三月十五日、「ただ落涙のほかなし」と記して自決した幕末切っての名官吏川路聖謨は、「いい遺すべき片言もなし」と詠んで、割腹した阿南惟幾にあたるものといえようか。
また将軍江戸を去らんとして、「この際、主公の御心中、いうにたえず、見るに忍びず」と記した勝海舟の日記は、「陛下の白い手袋の指はしばしば頬を撫でられ、私たちは正視するに耐えなかった」と書いた下村海南の記録と照応する。
以下、しばらく著者による明治元年と昭和二十年との比較が続く事となる。少々強引なこじつけかな、と思う部分も見受けられるが、興味深い意見だと思う。
確かに、この両者は日本の近現代史の中でも時代が激変したきっかけとなった時期だったからこそ、共通点も様々に見られただろうし、昭和二十年については、やはり山田風太郎は実際に経験した人間として比較し易い素材だったのだろう。
山田風太郎の考え方として、この手の日本人の愚かさというのは今も昔もそう変わらなくて、死に際にその人間性が現れる、というのがあるらしい。
前節に引用した描写にあった「気のせいか、悪いやつ、ろくでもないやつ、醜悪なやつばかりがつつがなく生き残った気がする」というのは本作に出てくる旗本侍の考え方を記したものだったが、これは著者が終戦の時期に見聞きした事態の意味も含ませているのだろう。
以前の記事で紹介した山田風太郎の終戦時期の日記『戦中派不戦日記』において、陸軍元帥であり軍事参議官であった皇族の梨本宮守正王が、戦後に戦犯として逮捕令状が出された際に、外人記者に「自分は戦争とは何の関係もなかったし、政治問題について相談も受けた事はない」と語った記事を読んで「愕然とせざるを得ない」と書いていた事が思いだされる。
丸山真男の『超国家主義の論理と心理』には、極東裁判において、当時の役人や政治家が見苦しく互いに責任を擦り付け合っている様を見て、連合国軍側の裁判関係者らは唖然としたと書かれていた。
太平洋戦争の終戦間際ロシア軍が満州国に侵入してきた時期、関東軍の軍人らが日本国民を置き去りにして真っ先に逃げ帰ってきたという話も良く聞く事だ。
「突然の死の宣告」というものが、人間の裏面をさらけ出してしまう。
「何とかを見なけりゃ、人間ってわからねえもんだとよくいう。その何とかはいろいろあるだろうが、首を斬られるときのざま、というのが一番鑑定になるかも知れねえ。……明日は、だれかなあ?」
本書のラストも、まさに『人間臨終図鑑』の様相を呈するのである。
考えてみれば、終戦当時にも極東裁判だけでなく、世界各地で日本軍将校らが戦犯として「突然の死の宣告」を受けて牢に捕えられていた。
無論、その中には戦争犯罪には関わらなかった将校もいて、本書で描かれる旗本侍と同じように、当人自身の罪状や普段の行状とは無関係に捕らえられ、裁判にかけられた者もいただろう。
まったく、「人間は、その値打ちとは全然無関係な死にかたをするもの」である。
本書は、このように明治維新という当時の状況を、太平洋戦争終戦当時の状況と暗に照応して見せる事で、日本人の変わらぬ愚かさ、人間自体の変わらぬ愚かさを浮き彫りにした作品であった。
日本はこの明治期に急速に西洋かぶれになり、戦後にはアメリカ文化を雨あられとばかりに浴びせられ、たかだか百数十年の間にその文化形態を急激に変化させてきた。
だが、そういった表向きに見える文化的な変化の裏側で、どうやら変わりなく継続させているある種の傾向だとか構造だとかを確実に持ってきていたようなのである。
その一つが、先日も紹介した中根千枝の『タテ社会の人間関係』に出てくる【「場」の中の「タテ」型の組織】という社会構造であった。
とにかく、痛感することは、「権威主義」が悪の源でもなく、「民主主義」が混乱を生むのでもなく、それよりも、もっと根底にある日本人の習性である、「人」には従ったり(人を従えたり)、影響され(影響を与え)ても、「ルール」を設定したり、それに従う、という伝統がない社会であるということが、最も大きなガンになっているようである。
――これなども恐らく、日本人の「変わらぬ愚かさ」の一つであろう。
