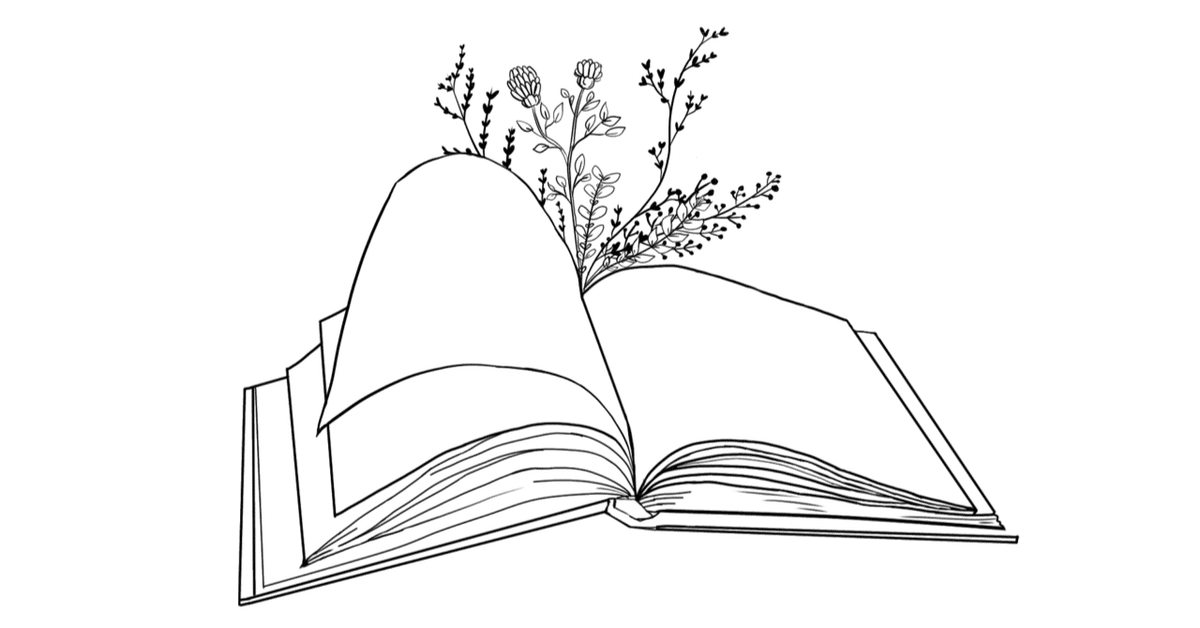
「読書論」(小泉信三著、岩波文庫)
ある本について、結論が普通だし、当たり前のことしか言っていないからという理由で、それを読まないというのはもったいないというときがある。
本書の著者である小泉信三(1888~1966)は、明治~昭和にかけての経済学者で、慶應義塾の学長を務めた方でもある。
「結論が普通だし、当たり前のことしかいっていない、だからといって読まないのはもったいない」とはどういうことか?
その一見当たり前の結論は、どうして書かれたのか?どうやって書かれたのか?あるいは誰が書いたのか?それによって、結論が奇をてらったものではないとしても、その内容は、重みと深みを増し、解釈と創造の幅を広げてくれるはずである。
では、本書に書かれている「読書論」。書かれている内容が、普通で当たり前のことなのだとしたら、本書を読む価値は一体どこにあるのか。
例えば、こういった側面からみてみたらどうだろう?
本書は、福沢諭吉や、夏目漱石や森鴎外といった明治時代の文豪たちの文献を当時ほぼリアルタイムで読んだ体験をもとに「読書論」を書いているのである。
読んでみないともったいない気がしてきませんか(笑)
※Amazon のアソシエイトとして、この記事は適格販売により収入を得ています。
どんな本をどう読むか
ここにはさしあたり一般方針だけを言う。一般方針として私は心がけて古典的名著を読むことを勧めたい。
著者は、古典的名著を読むことを勧める。
それぞれの分野において、流行浮き沈みを超越した標準的著作を読むことを勧める。
しかし、人は意外に古典的名著を読まない。
著者は、古典的名著が人にある畏怖の念を抱かせ、圧迫を感じさせるからではなかろうかという。
あーわかる。名著には畏怖がある。なかなか読めない。
本書でよく引用される部分を引用します。
先年私が慶応義塾長在任中、今日の同大学工学部が始めて藤原工業大学として創立せられ、私は一時その学長を兼任したことがある。時の学部長は工学博士谷村豊太郎氏であったが、識見ある同氏は、よく世間の実業家方面から申し出される、すぐ役に立つ人間を造ってもらいたいという註文に対し、すぐ役に立つ人間はすぐ役に立たなくなる人間だ、と応酬して、同大学において基本的理論をしっかり教え込む方針を確立した。すぐ役に立つ人間はすぐ役に立たなくなるとは至言である。同様の意味において、すぐ役に立つ本はすぐ役に立たなくなる本であるといえる。人を眼界広き思想の山頂に登らしめ、精神を飛翔せしめ、人に思索と省察とを促して、人類の運命に影響を与えてきた古典というものは、右にいう卑近の意味では、寧ろ役に立たない本であろう。しかしこの、すぐには役に立たない本によって、今日まで人間の精神は養われ、人類の文化は進められて来たのである。
この論旨の引き合いに、福沢諭吉の「学問のすゝめ」「文明論之概略」あるいは「福翁自伝」、森鴎外の「ヰタ・セクスアリス」の一場面が出てくる。
著者は、難解の書と称せられるものは必ずしも難解でない。恐れずに再読三読すれば、意外によく解るという。古典的名著に対する故なき畏怖を去ることは、読書論の第一に力説しなければならないところと著者は言う。
書籍もまた同様で、再三反覆して読むことにより、人は始めてよく著者の真意を会し、また再読三読することによってその真価を判ずることが出来る。
読んだ本を自分のものにするにはどうするか
読者として他人から受動的に受け入れたものを、今度は逆に自分のものとして外に出してみるが第一であると思う。別言すれば、読んで頭に入れたものを、今度は自分の口から人に話してみるか、或いは自分の筆で書き留めてみるのである。
これも、当たり前っちゃあ当たり前である。
しかし、その引き合いのエピソードがこれ。
・慶応義塾には、福沢諭吉が好んで書入れをした、ミル(ジョンスチュアートミル)の「功利主義」(1874)が、貴重本として保存されている。
・欄外の書入れがとくに面白いのは漱石。彼がいかに注意深い読者であり、いちいち分析し批判しつつ進んだかは、全集に収められた「蔵書の余白記入されたる短評並みに雑感」に示されている。
・鴎外は、読むとすぐ本の梗概(=あらすじ・あらまし)を書いた。
これを引き合いに、本を読んだら読みっぱなしにしないで、少なくとも大切な本は、「読んだことについて何か書いておこう」とこれまたよく言われる当たり前のことをいう。しかし、重みが違う(笑)
本を読むだけではだめ
読書についてだんだん語って来たが、次に私は、書籍に囚われるなということを言いたい。
(中略)
物を見たら必ず書籍によってその名を学べ、書籍によって名を知ったら必ず物そのものを見よ、
ここでも鴎外の小品文の「名を知って物を知らぬ片羽」が引き合いに出される。
読書とともに如何に観察し、思考するか。
著者は、福沢諭吉は、優れた観察力をもっていた。また、読みかつ考える読書家の最も立派な一例は漱石だろうという。
これらを模範にせよという。
もう何も言えない(笑)
文章論
本書は、第8章で文章論にも触れている。
結論は、一言で言ってしまうのであれば
畢竟推敲がいかに大切であるかというに帰着する。
ここも当たり前だからと言って読まないのはもったいないような気がする。
ここでも福沢、鴎外、漱石が引き合いに出される。
どう料理して、「ちゃんと推敲しよう」なのか、そこがこの本の面白いところなんじゃないかと思う。
ホントにすぐには役にたたねえなぁ(笑)
第9章、第10章はちょっとかわいい
読書論、文章論ぽいのは8章までで、そのあとはコラムっぽい。
第9章とか、要は、理想の書斎がほしいということを言っている(笑)
後半はエピソードを楽しむ感じではないかと思う。
本書は、一見「読んでいない本について堂々と語る方法」とは真逆のことが書いてあるように思える。
一方は「本を読んでいない方がいい」という本であり、もう一方は「本をちゃんと読んだ方がいい」という本である(笑)。
しかし、私は、両者は共通していると思う。
いずれも「本」を通して、私たちは、何を学び、何を観察し、何を考え、何を創造したらいいのかを論じている。
いずれにも共通するのは、本に対する「故なき畏怖を去る」こと。
違う点は、本を読んだ方がいいのか、読まない方がいいのかという点だけである(笑)。
誰にも創造の世界は開かれている。
そんな本を通したコミュニケーションの可能性をまた違う視点から取り入れて、また次の本を読んでみよう。まあ、私には、古典的名著はどうしてもなかなか読むのが大変なんですけどね(笑)
そんなわけで「今日一日を最高の一日に」
