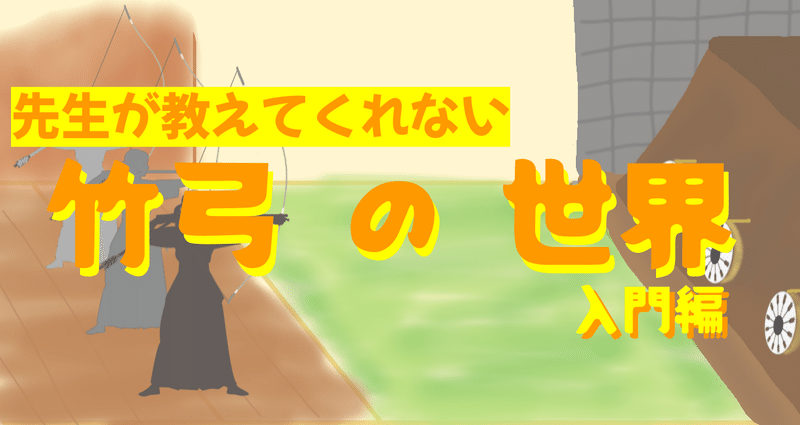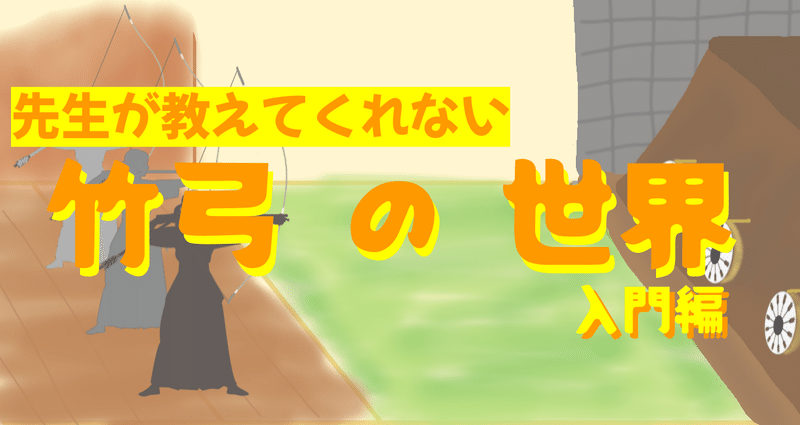012_弓が矢を飛ばす仕組み
小さい頃に弓矢を作った経験はないですか?
長めの木の棒とタコ糸を使って弓を作って、矢を飛ばす。
そんな子供時代を過ごしたことがある人は今では少なくなってしまったでしょう。
あれって全然飛びませんよね!!
太い木を使えるようになってることには別の遊びに夢中で、、、次第に弓矢に興味がわかなくなっていくという。。。
より遠くに飛ばす、速く飛ばす、を追求していった昔の人が射たからこそ、今の弓矢があることに感謝をします。
というわけで、今回は弓が矢をより強く飛ばす仕組みについて紹介して