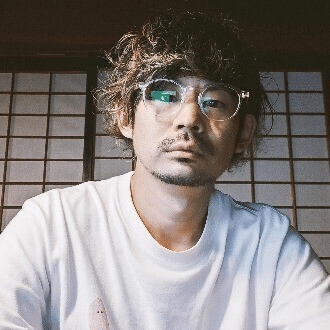オールナイトニッポー0728
水木しげるにちなんで、水・木(曜日)はお休みにしてます。そして、休(み)はQ(uestion)について考えたい日でもあります。
猫と暮らしてると、ふと思う。「こいつら、勝手だよなぁ」と。人がやることがあるときにこすり付いてきて「なでろ」「遊べ」と訴え、構ってると急に態度を変えひょろ~っとどっかに行ってしまう。夏の昼寝は風が通る一番心地のいい場所で、餌がなくなればちゃっかり鳴いてアラームする。”自由気ままに”の形容詞がこんなにも似合う生き物がいるのか、と日々教えられている。
ときどきふと考える。そんな猫たちは働いているのだろうか? この「働く」をまた「労働(labor)」と「仕事(work)」の視点で考えてみたい。前回の続きとして。
一言でいえば、「猫は、労働はしているが、仕事はしていない」とぼくは思っている。何かをつくる/生み出すという行為がないので、仕事は当然のようにしていない。
しかし、労働はちゃっかりしている。あらためて労働について。『学びのきほん 考える教室 大人のための哲学入門』の解説がわかりやすかったので、そこから引用していく。
労働は、生命活動と深く結びつく営みだとアレントは考えました。ここで「労働」と訳されている言葉は、英語で”labor”と書きます。
この言葉には、単に労働という意味だけではなく、「陣痛」あるいは「分娩」という意味もあります。つまり、女性が子どもを産む過程にも”labor”という言葉を使うのですアレントはここに注目しました。
労働(labor)は仕事(work)と語源的にも異なることにも彼女は言及しています。"labor”は、いわば「いのち」の営みであり、"work”は、何かを作ることを意味しているというのです。(p65)
アレントがいう「労働」という言葉には、人間の根源的な尊厳のようなものが含まれています。ですから人は、生きている限り労働から離れることはできません。万人が、つねに「生きる」という労働に従事している、ということになります。そこに動かない意味を見出すことからアレントの哲学は出発しています。
現代では、アレントがいう労働の意味が見失われたまま、「仕事」をすることを強いられることがある。彼女のいう「労働」を忘れたまま、仕事の評価によって人の生き方や人の在り方を評価する世の中になっています。
しかし、よく考えてみましょう。仕事なしに労働は成立するのですが、労働なき仕事は成立しないのです。仕事のうえに労働があるのではありません。いのちと直結した労働のうえにこそ、真の意味での「仕事」が開花するのです。(p66)
ただ息を吸って吐いては繰り返すことそのもの(とそのための作業)が労働であり、仕事がなくても労働は成立するし、むしろ労働こそが仕事の基盤になるよね。そのことを現代の人間はちょっと忘れがちなんじゃ? というのがアレントの見解ということだろう。
そして、これを猫たちに当てはめてみると、寝て、食べて、採って、じゃれて、とどんな過ごし方をしていようと、紛れもなく、彼らは自分たちが生きるために必要なことを素直に行っているだけあり、それが労働そのものということになる。
仕事をしないぶん、自由気ままに労働だけをしている姿に、ぼくはグッとくるし、生物としての深い学びがあり、現代社会の構造へのパンクな魂を日々見せつけられていると気づく。
だからこそ、余計に、まず大事なのは、仕事よりも労働であって、仕事を支える労働をちゃんとしよう、なのである。ぼくにとって「家事は、労働を取り戻すための作業」であり、食べる・寝る・心地よい環境を整えるための家事をやり切ることは、猫に近づくための方法であると信じている。
仕事をするための前提条件、ここの意味を見失っていたり、忘れていたり、間違っていたり、そもそも意識が薄かったり、そんなとき、やはり猫が家でくつろぐ様をみてると宗教画のように映る。猫様様である。
「働く」を考えるための「アレント」と「猫」は、引き続き、深めていきたい。
いいなと思ったら応援しよう!