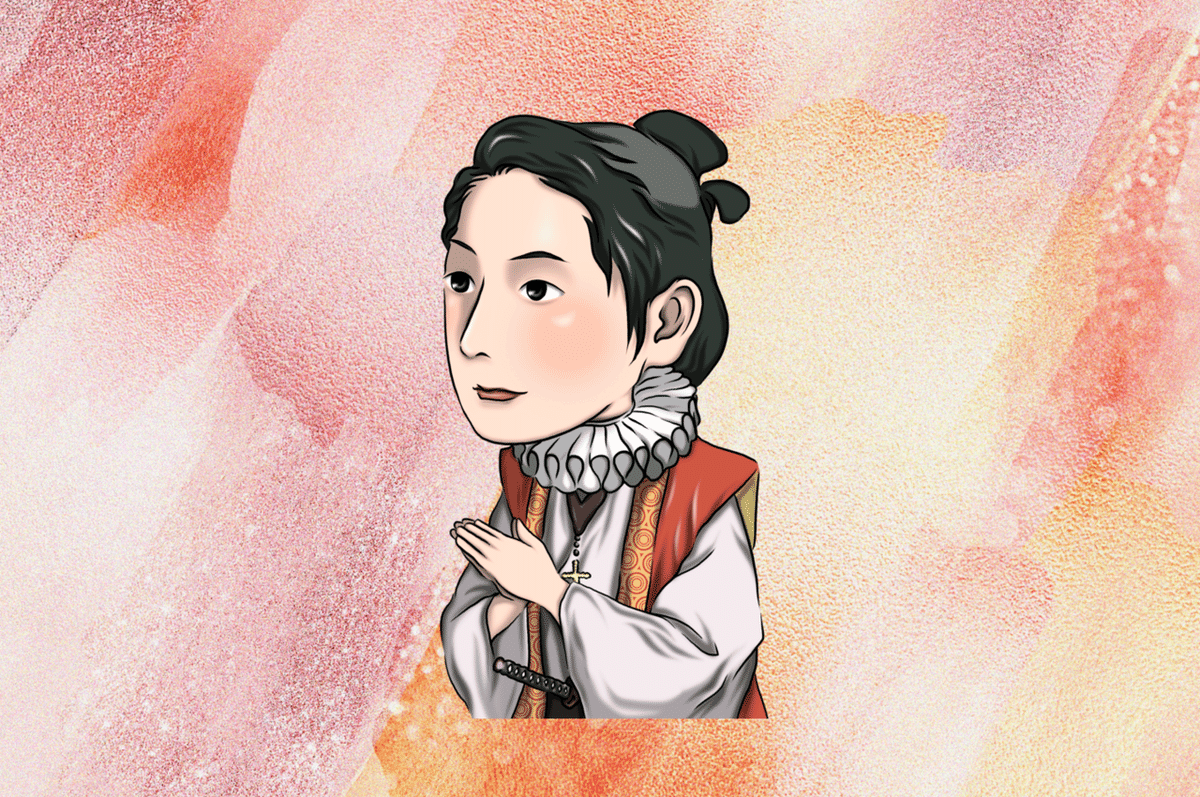【戦国時代の暮らし②】ルイス・フロイス日本史から安土桃山時代の日本人の文化や習慣を紹介【茶の湯・おもてなし】古陶磁鑑定美術館
こんにちは、古備前鑑定の古陶磁鑑定美術館です。
私たちは、何百年以上も前に使われた陶磁器の分析・調査・研究・蒐集・展示しています。
突然ですが、みなさんは、戦国時代の生活をイメージしたことはありますか?
織田信長や、明智光秀や、豊臣秀吉が活躍していた頃の日本の暮らしは、一体どんな様子だったのでしょうか。
そんな安土桃山時代の文化や生活が伺える貴重な記録が、宣教師ルイス・フロイスが残した『日本史』の中に残されています。
ルイス・フロイスは、フランシスコ・ザビエルらの後継として、イエズス会から日本に派遣された宣教師です。
織田信長に気に入られ、豊臣秀吉にも謁見するなど、戦国時代の日本の権力者たちと交友があった人物です。
そのルイス・フロイスが布教活動の傍ら残した記録からは、当時の日本の風土や、文化や、生活を鮮明に伺うことができます。
このコラムにて、その一端を紹介して参りますので、安土桃山時代の日本の暮らしを、肌で感じてイメージしてみましょう。
-----------------------------------------------------------------------
今回紹介する記録(逸話)は、「堺商人のおもてなし」です。
戦国時代の堺(大阪)は、諸外国から物資が集まる貿易港として、大きく発展しました。
当時の茶の湯で活躍した千利休や今井宗久や津田宗及らは、堺商人としても代表的な人物です。
ルイス・フロイスの記録の中に、そんな堺商人らとの交友にまつわる記載が残っていますので、その表記から、当時の生活のワンシーンを探ってみたいと思います。
------------------------------------------------------------------------
『私(フロイス)は日比屋了珪(洗礼名ディオゴ)に、明日出かけたいと申しました。彼(ディオゴ)は答えて、私がもうそのように決心しているのなら致し方なく、まず自分が所持している幾つかの財宝をお見せしよう、と言いました。
身分ある富裕な日本人のもとでは、大いに好意を示そうとする来客がある場合には、別離に際して、親愛の証として自ら所蔵する財宝を見せる習慣があるのです。おれらは、彼らがある粉末にした草を飲むために用いるすべての茶碗とそれに必要とする道具です。それは茶と呼ばれ・・・』
(完訳フロイス日本史1から引用、()内注釈は当館追記)
------------------------------------------------------------------------
この記録からは、戦国時代の日本人が、親しい知人や友人をどのようにおもてなしたかが分かります。
仲の言い証として所蔵している財宝を特別に見せたという風習からは、当時の人たちが、二人の間の信頼関係を重視していたことが伺え、とても素敵な習慣と言えますね。
当時の人達が大事にしていた財宝が、金銀などではなく、茶碗や茶道具であったことも、茶碗一つで国が買えてしまうと言われた当時の逸話通りで、興味がそそられます。
また、宣教師(外国人)視点で見たお茶の表記も初々しさがあって新鮮です。
安土桃山時代の日本人は、茶の湯を、ただのしきたりや礼儀作法の一環ではなく、コミュニケーションの手段として、身近に楽しんでいたのでしょう。
いわゆる茶の湯とは、戦国時代の「社交の場」といったところでしょうか!?
安土桃山時代から、私たち日本人は、人と人との交流を大事にしていたのですね。
その心遣いから生まれたのが、一期一会などの美意識なのかもしれません。
古陶磁鑑定美術館は、古陶磁が使われた時代や文化の背景を、当時の一時記録や伝来品を通して紹介しています。
安土桃山時代の日本の文化が知れる貴重な逸品を公開していますので、ホームページもぜひご覧ください!