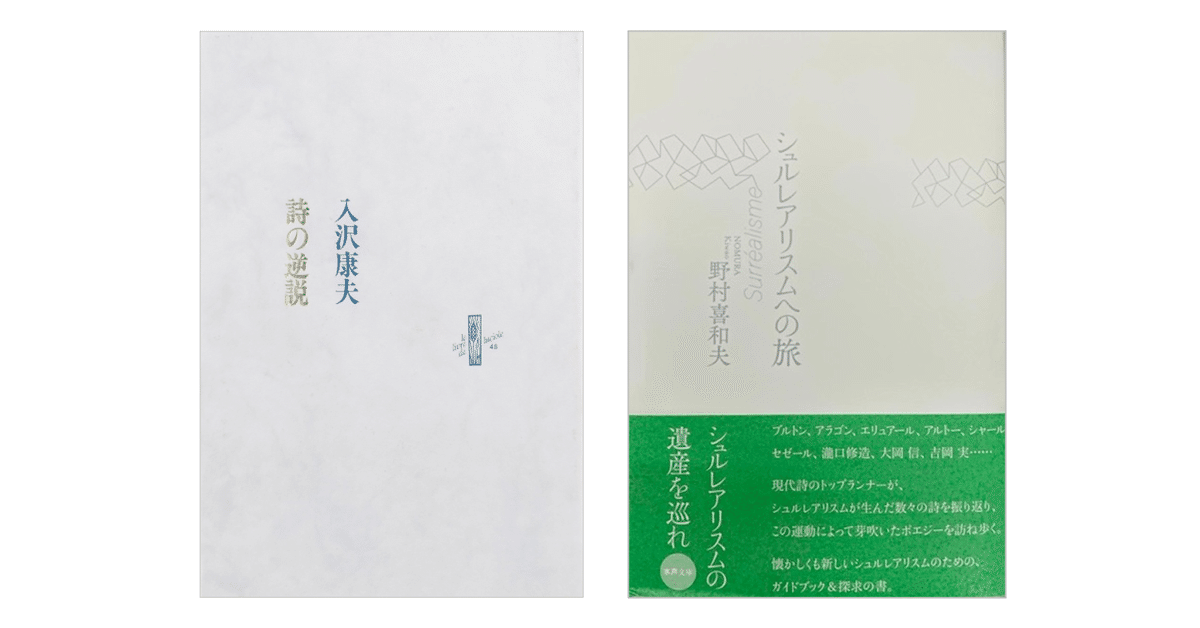
入沢康夫『詩の逆説』/野村喜和夫『シュルレアリスムへの旅』
☆mediopos2920 2022.11.15
詩作は地獄下りにほかならない
そのことを示唆した入沢康夫は
〈詩は表現ではない〉
という逆説を生きた詩人だった
「現代詩の地獄下り」と題された詩論が
熱く書かれたのはすでに六〇年以上前
その入沢康夫もすでに亡き今
はたして「地獄下り」へと向かう詩人が
どれだけいるだろう
おそらくいまだ挑戦的であり続けている
詩人・高橋睦郎は「死者」を召喚し
みずからがその依代となることを試みているが
それもまた稀有の「地獄下り」となっている
「地獄下り」とは
詩を詩として支える意識の深みから
ポエジーを展開させようとする営為である
かつてそれを試みたネルヴァルは狂気に赴き
ランボーは詩から出奔してアフリカに赴く
「地獄下り」の困難さは
「無意識の世界への、意識的主体的な挑戦」である
という逆説に「われとわが身の存在理由をかける」ことが
「永遠の詩の基礎条件」として要求されるからだ
シュールレアリスムという試みもまた
「地獄下り」にほかならなかった
そこで使われる言語には
「言葉のいわばプラズマ経験が潜在している」
それは夢であり無意識であり狂気であり
「社会の約束事としての冷めたラング」からの自由を求め
「いつまでもかたちをなしていない力でありつづける」
「未知の卵」としての「プラズマ経験」に
激しく身を委ねなければならない
詩と詩人を自称する者の多くは
詩を「自己表現」としてとらえ
「安易な知的遊戯の詩や、
ひとりよがりの日常的な印象の詩や、
名目だけの社会参加の詩」で
「甘えとなれ合いの安全地帯にねそべ」っている
詩は「自己表現」ではありえない
「自己表現」などという
意識世界に安住することはできない
けれども同時に「自己」を超えた「自己」において
「地獄下り」に挑み続けなければならない
詩人であるということはそういうことだ
現代において詩作すること
そして詩人であることはどこまで可能だろうか
少なくともわたしは決して詩人などにはなり得ない
勿論たとえ詩のような言葉を使ったとしても
それが詩であるはずもない
少なくとも「地獄下り」へと赴き得るときまでは
■入沢康夫『詩の逆説』
(Le livre de luciole 書肆山田 2004/4)
■野村喜和夫『シュルレアリスムへの旅』
(水声文庫 水声社 2022/9)
(入沢康夫『詩の逆説』〜「現代詩の地獄下り」(一九六〇年)より)
「詩とはなにか。それはポエジーで裏付けられた一連の言語の配置から成る文学作品のことだ。では、そのポエジーとはなにか。詩を内側から支えて、それを詩として成り立たせるものだ・・・・・・。これでは問題はぐるぐるまわりで、いつまでたっても終わることがないだろう。」
「詩を詩として支えるもの、詩的発想とその言語を裏うちする独特の秩序、詩人を仲介者として詩に作用するもあるもの、その存在を確信し、そしてその実体を更に明らかにしようとする意図を持つひとは、やがて、一つの新しい考え方(・・・)、C・G・ユンクやG・バシュラールなどによる集合無意識、あるいは神話的類型という観念に立脚する考え方の有効性の問題の前に、いやおうなしに直面させられるであろう。
人間には、太古以来蓄積されてきた巨大な無意識の層が(・・・)存在し、これは個人や民族を超えた人類共通の心的基盤であり、芸術的発想と芸術的感動の母胎であること(・・・)
このようなユンクの説は、当面の問題にとって、かなりうまく適合する一つの鍵となるものであることをぼくは感じる。ぼくたちの文学精神のかてとなり栄養となった近代から現代に到る偉大な作家たち、フランス象徴派からシュルレアリストに至る詩人たちや、イエーツ、ジョイス、ロレンス、エリオットなど英国の作家たちの作品の魅力の秘密を、このユンクの見解はきわめてよく解明していると言えよう。
(・・・)
詩は文学作品の中でも、おそらく、もっとも多く無意識に(その根源も、その形成も)依存しているジャンルであり、喚起されるべき対象のためには、表面的な論理性や、描写性を犠牲にしても省みないジャンルであるだけに、「ポエジー=集合的無意識の展開」という図式をもっともよく体現できるにちがいない。
(・・・)
ユンクの考え方は、はなはだ普遍的な有効性をもつだけに、それが、弱い精神にとっては現実逃避の口実や、神話のパターンの安易なひきうつしの口実になる可能性をもっていることに常に留意すべきである。詩人の、詩人としての主体性の問題が、その次元において、あらためてはっきりとうかび上がって来る。おそらく詩は、詩人の一生の意義となる全想像力を賭けた真剣な探求からしか、絶対に生まれてはこないであろう。」
「ここでぼくたちは、十九世紀のフランスの偉大な詩人を思い起こすこともできる。夢と狂気の幻想を、小説『オーレリア』や詩集『レ・シメール』に定着したネルヴァルと、言葉の錬金術の成果である『地獄の一季節』『イリュミナシオン』をあとにのこしてアフリカに出奔したランボオと。二人とも、この世界と他の生秋との間をへだてる扉を侵して、フランス文学にそれまでなかった新しい戦慄をもたらした詩人たちである。そしてこの二人のもたらしたものには、往々、はなはだ共通する多くの神話的象徴がちりばめられていることも、すでによく知られていて、この点、ユンクの学説に一つの適切な例を提供しているとも言えるであろう。」
「神秘主義的なもの、あるいは超自然的なもの、つまりは、ユンク流に言えば原型の世界への彼らの関心が単なる知的な好奇心や詩法としてだけの興味に由来するものではなかったこと、自己の生の意義を全的に認識するための手がかり、生を意義づける至高のヴィジョンをそこに見出そうとしたのだということを、ぼくたちはここではっきりと確認しておこう。
それにしても、このようなヴィジョンをわがものとし、それを高度の完成度をもった作品として定着するために、彼らが、どのように激しい努力を集中したかを見れば、思いなかばにすぎるものがあると言わねばならない。
個人的なものを、超個人的なヴィジョンに昇華させ、自己の詩に汎人類的な地盤から発する戦慄的な力を付与するためには、詩人は自己をあえて危地においやり、自ら、灼熱の原イメージの炉、あるいはるつぼと化する覚悟をもたなくてはならないであろう。詩に一生を賭けるなんて言い方は、時代錯誤だとひとは言うだろうか。本当にそうだろうか。
無意識の世界への、意識的主体的な挑戦、この一種逆接めいた探求に、われとわが身の存在理由をかけることに、おそらく永遠の詩の基礎条件がある。そして、その決意が安易な知的遊戯の詩や、ひとりよがりの日常的な印象の詩や、名目だけの社会参加の詩が、人の心をとらえる力もないままに、甘えとなれ合いの安全地帯にねそべる数知れぬ自由詩人によって大量生産されている状況下に詩を求めるぼくたちにとって、今ほど要請されている時期はないとぼくは信じている。
真の生の賛歌、人間のための、人間をまもる詩は、この地獄下りの決意と実行の結果としてでなければ、決して実現されないであろう。」
(野村喜和夫『シュルレアリスムへの旅』より)
「言語は社会の約束事としての冷めたラングであるが、その下には、言葉の自由が、言葉のいわばプラズマ経験が潜在している。「プラズマ」を辞書で引くと、「超高温下で、原子の原子核と電子が分離し、激しく動き回っているガス状態」とある。それは夢と呼ぼうと、無意識と呼ぼうと、狂気と呼ぼうと、要するにシュルレアリスム的な何かである。ブルトンは、「言語はシュルレアリスム的に使用するように出来ている」と断言してはばからなかったが、それは全くその通りなのだ。一度はプラズマを潜らなければ、私たちは冷めたラングに支配されたままであり、いや、支配されていることにすら気づかない。
あるいは、吉岡実にならって、ひとつの卵を想像してもらってもいい。球体への嗜好をもつこの詩人にとって卵とは、固体と液体、硬く無機質な外皮と柔らかい生命の塊である内部という両面性が、危うい均衡のうちに実現されているオブジェであった。しかし卵の特性はそれだけではない。ここからは吉岡実を離れるが、卵とは、さまざまな分化ぶ向かう力線にあふれている、その潜勢的なあふれそのもののことである。言葉の卵。いずれ何にでもなりうるが、いまはしかし安住すべき拠点もなく、あらかじめ定められた目的もなく。そうした状態のまま、いつまでもかたちをなしていない力でありつづけること。それが自由ということだ。というのも、一方で今日、私たちの生は、その内面も含めてくまなく管理され、監視され、等質化され、苛烈な経済原則へと方向づけられている。そのような時代状況下では、一度は卵という未決定的な力のうごめきになにごとかを託すというのも、考えられうるひとつの有効な抵抗のアクションであるように思われるのだ。シュルレアリスムは、今日なお、私にとってひとつの無視し得ぬ卵、なつかしい未知の卵でありつづけている。」
